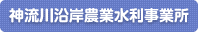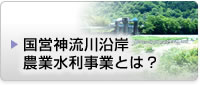さらに詳しく竪岩くり抜き工事
明治時代、九郷(くごう)用水では洪水の度に堰が流出し、これを、修復・復旧する費用と人件費に手を焼いていました。
ちょうど川の流れがぶつかるところに大きな竪岩(たていわ)があることから、この竪岩をくり抜いて頑強な堰として利用できないかと考えた人がいます。児玉村の野沢昭三郎です。この時は、話し合いがまとまらす、実現しませんでしたが、9年後、堀越弥三郎という実業家が私財を投げ打ち、工事を行いました。当時は機械のない時代、全てが人の手によって行われ、約1年半の歳月と4,000人の人たちが力を合わせて、ようやく堰が完成しました(1872年)。
この事業を推進したのは九郷堰側、通水にあたっては九郷堰の分水率を45%対55%と従来の比率と逆転するまで譲歩し、事業に賭けましたが、増水時や渇水時には取水が不安定で、紛争が絶えず、一触即発の危機の中、協議に協議を重ね、竪岩の穴を埋めては戻しの試行錯誤が重ねられました。
この問題に決着が付くのは、左岸藤岡側の三名川貯水池(さんながわちょすいち)と、神流川筋6堰合口事業が完成するのを待たねばなりませんでした。
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-740-0541