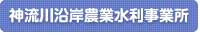さらに詳しく座繰製糸業
江戸時代の養蚕(ようさん)農家は、養蚕から製糸、機織りに至るまで一連の作業を行っていました。繭から糸を取り出しやすくするために、繭を釜で煮ますが、片方の手で糸を繰りながら、反対の手で巻き取る作業のことを座繰製糸(ざぐりせいし)といいます。江戸時代からは、繭を煮る釜と糸巻き枠が一緒になった繰糸機が使われはじめ、主に農家で用いられていました。
明治に入って、生糸が輸出品として需要が伸びると、農家は繭だけを生産し、製糸工場で糸を作る分業化が進みました。
お問合せ先
農村振興部設計課
ダイヤルイン:048-740-0541