食品ロス・食品リサイクル・フードバンク関連
食品ロス
 東北地方食品ロス削減・食品アクセス確保連絡会
東北地方食品ロス削減・食品アクセス確保連絡会
東北地方食品ロス削減・食品アクセス確保連絡会について
国連の持続可能な開発目標(SDGs)のターゲットの一つである「食品ロス削減」を効果的に進めるためには、幅広い関係者が協調し取り組むことが重要であり、食品リサイクル法の基本方針では、事業系食品ロスを2030年までに2000年度比で60パーセント削減する目標を定めています。また、国民一人一人の食品アクセスの観点からも、食品ロス削減に関する取組のうち、フードバンク等への食品提供の取組の重要性が高まっています。こうした状況を踏まえ、東北農政局では、東北地方の食に関する幅広い関係者間の有機的なつながりを構築し、食品産業で発生する食品ロスの削減及びフードバンク活動等の推進を目的とした東北地方食品ロス削減等情報連絡会を令和6年5月に設立しました。その後、本連絡会の目的をより明確にするため、令和7年6月に「東北地方食品ロス削減・食品アクセス確保連絡会」に名称変更しました。
本連絡会への入会を希望される方(食品関連事業者、一般企業、フードバンク団体、子ども食堂、農林水産物生産者・団体、地方自治体、社会福祉協議会等)は、下記入力フォームからお申し込みください。
- 会員一覧(PDF : 72KB)
- 規約(PDF : 93KB)
- 入会を希望される方 → 入力フォームはこちら
令和7年12月11日、コープ東北サンネット事業連合コープフードバンクにおいて食品等倉庫の見学会を開催しました。
コープ東北サンネット事業連合コープフードバンク(宮城県富谷市)において、東北地方食品ロス削減・食品アクセス確保連絡会の現地見学会を行い、食品製造業者、食品卸売業者、物流業者、行政機関等10名が参加しました。
現地見学会では、みやぎ生活協同組合参与小澤義春氏からコープフードバンクの取組についてご説明をいただいた後、食品等倉庫において寄附食品の受入れや管理状況等を見学し、意見交換を行いました。
意見交換では、食品提供事業者とフードバンク団体等とのマッチング、寄附食品の在庫管理のシステム化、寄附食品の安全性、フードバンク団体等の人手不足、企業における寄附行為のインセンティブなどについて意見が交わされました。
 |
 |
|
| 東北農政局荻野次長の冒頭あいさつ | みやぎ生活協同組合小澤参与による コープフードバンクの取組の説明 |
 |
 |
 |
| 食品等倉庫の見学の様子 | 食品等の保管状況 | 意見交換の様子 |
令和7年9月29日、仙台合同庁舎(オンライン併用)において第6回連絡会を開催しました。
東北農政局において、オンライン併用で開催した「第6回東北地方食品ロス削減・食品アクセス確保連絡会」には、食品関連事業者、フードバンク関連団体、物流業者、行政関係者など37名が参加し、物流の現状と商慣習の見直しをテーマに、専門家を講師にお招きし勉強会を行いました。
勉強会では、株式会社時事通信社経済部長川村豊氏から「物流問題の現状~2024年問題で浮かぶ課題~」について、公益財団法人流通経済研究所上席研究員石川友博氏から「商慣習の見直し」についてご講演をいただきました。
また、東北農政局からは、令和8年度予算概算要求における食品ロス削減及び食品アクセス確保に関する事業について情報提供を行いました。
質疑応答では、専門家のお二人からフードバンク活動に対する提言をいただきたい、フードバンク運営費に係る支援はないか、フードバンク団体に対する寄付に係る損金算入計算方法の適否の確認窓口があれば知りたい、賞味期限表示の大くくり化の広がりの状況を知りたい等の質問・意見が出されました。
 |
 |
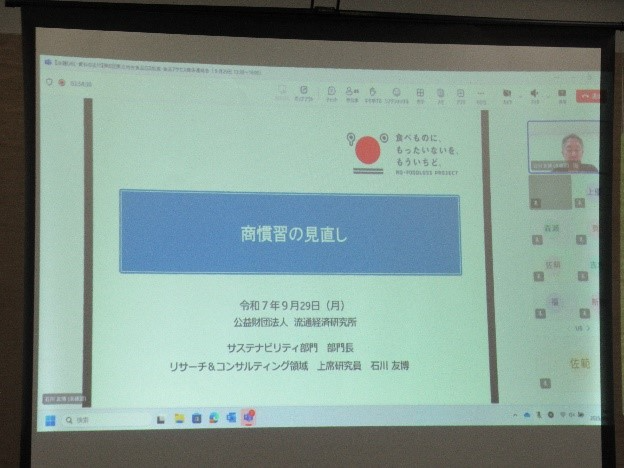 |
| 東北農政局小山内経営・事業支援部長の 冒頭あいさつ |
株式会社時事通信社川村経済部長による 「物流問題の現状」の講演 |
公益財団法人流通経済研究所石川上席研究員による「商慣習の見直し」の講演 |
 |
 |
 |
| 東北農政局による「令和8年度予算概算要求」の説明 | 質疑応答の様子 | 会場の様子 |
令和7年6月10日、仙台合同庁舎(オンライン併用)において第5回連絡会を開催しました。
 |
 |
 |
| 清野東北農政局次長の冒頭あいさつ | 消費者庁食品表示課による 「食品期限表示ガイドラインの改定について」 の説明 |
消費者庁消費者教育推進課による 「食べ残し持ち帰り促進ガイドラインについて」 の説明 |
 |
 |
 |
| 厚生労働省食品監視安全課による 「食べ残し持ち帰り促進ガイドラインについて」 の説明 |
農林水産省外食・食文化課による 「食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」の説明 |
農林水産省消費者行政・食育課による 「食品アクセスの確保について」の説明 |
 |
 |
 |
| 株式会社ユニバースによる事例発表 |
モガミフーズ株式会社、一般社団法人 やまがた福わたしによる事例発表 |
多くの会員の皆様にご参加いただきました |
令和7年1月21日、仙台合同庁舎(オンライン併用)において第4回連絡会を開催しました。
 |
 |
 |
| 原東北農政局次長の冒頭あいさつ | 消費者庁消費者教育推進課による 「食品ロス削減基本方針改定について」の説明 |
農林水産省外食・食文化課による「食品リサイクル基本方針等の見直し及び食品ロス削減政策支援予算について」の説明 |
 |
 |
 |
| 農林水産省消費行政・食育課による 「食品アクセス関連予算について」の説明 |
山崎製パン(株)仙台工場 三浦総務課長による事例発表 |
(株)稲庭うどん小川 小川専務取締役による事例発表 |
 |
 |
 |
| 宮城県循環型社会推進課による 「フードロスクーポンミニアプリ」の紹介 |
(一社)東北フードバンク連携センター 林理事による閉会の挨拶 |
多くの会員の皆様にご参加いただきました |
令和6年11月22日、特定非営利活動法人フードバンク岩手(岩手県盛岡市)において第3回連絡会を開催しました。
 |
 |
 |
| 渡辺東北農政局経営・事業支援部長の 冒頭あいさつ |
特定非営利活動法人フードバンク岩手阿部副理事長兼 事務局長による概要説明 |
熱心に耳を傾ける参加者の皆さん |
 |
 |
| 食料品保管状況の見学 | 質疑応答の様子 |
令和6年9月12日、株式会社盛功流通(仙台市宮城野区)において第2回連絡会を開催しました。
 |
 |
 |
| 特定非営利活動法人フードバンク仙台に寄附 された食品が保管されている倉庫の見学会を 行いました |
ドライ(常温)倉庫見学 | 冷凍倉庫見学 |
 |
 |
 |
| 活発な意見交換がされました | 特定非営利活動法人フードバンク仙台による 活動報告等の説明 |
(株)盛功流通糸川取締役副社長にフードバンク 活動を取り組むきっかけ等をお話いただきました |
令和6年5月17日、仙台合同庁舎(オンライン併用)において第1回連絡会を開催しました。
 |
 |
 |
| 原東北農政局次長の冒頭あいさつ | 農林水産省外食・食文化課による「食品ロス削減等をめぐる最近の情勢について」の説明 | 多くの会員の皆様にご参加いただきました |
 |
 |
| 認定NPO法人自立生活サポートセンター・ もやい大西連理事長による御講演 |
イオン東北株式会社赤田総務部長による事例発表 |
 令和6年度「全国一斉商慣習見直しの日」について
令和6年度「全国一斉商慣習見直しの日」について
令和6年10月30日に食品ロス削減に向けた商慣習見直しに取り組む事業者について公表しました。
10月30日の「全国一斉商慣習見直しの日」にあわせ、農林水産省では、商慣習見直しに取り組む事業者名と取組内容を公表しました。
全国の情報や詳細は、農林水産省のホームページをご覧ください。
- 東北農政局管内の取組事業者
〇納品期限を緩和している小売業一覧【令和6(2024)年10月31日現在】
:緩和実施済(全店舗)
注:掲載は50音順
〇賞味期限表示を大括り化した食品製造業者【令和6(2024)年9月30日現在】
注:掲載は50音順
〇平成24(2012)年以降に賞味期限を延長した食品製造業者【令和6(2024)年9月30日現在】
注:掲載は50音順
〇フードバンクや子ども食堂に食品を提供している食品製造業者【2024年9月30日現在】
- 全国の食品関連事業者の取組事例はこちらからご覧いただけます。
 恵方巻シーズンにおける食品ロス削減の取組について (取組実施事業者の公表)
恵方巻シーズンにおける食品ロス削減の取組について (取組実施事業者の公表)
近年、節分後の恵方巻きの廃棄が社会的な話題となったことから、農林水産省では、食品小売業者の方々に対して恵方巻きの需要に見合った販売を呼びかけ、恵方巻きのロス削減に取り組む小売店である旨を消費者に PR するための資材の提供や、その資材を活用して恵方巻きのロス削減に取り組む事業者名及び取組内容の公表を行ってきました。令和6年は、東北では、14事業者からのご応募をいただきました。
全国の情報や詳細は、農林水産省のホームページをご覧ください。
東北農政局管内で実施している取組事業者(五十音順)
- イオン東北株式会社、株式会社伊藤チェーン、株式会社おーばん、株式会社PLANT、
株式会社ベルジョイス(ビッグハウス・ジョイス・スーパーアークス・ベルプラス・スーパーロッキー・ロッキー)、
株式会社マイヤ、株式会社丸江、株式会社ヤマザワ、株式会社ユニバース、株式会社よこまち(よこまちストア)、
株式会社リオン・ドールコーポレーション、生活協同組合コープあいづ、
本間物産株式会社(マルホンカウボーイ/マルホンプラス)、有限会社中央市場 ビフレ新庄店
東北地区を含む全国各エリアで実施している取組事業者(五十音順)
- 株式会社イトーヨーカ堂、株式会社セブン-イレブン・ジャパン(セブン-イレブン)、
株式会社ファミリーマート、株式会社ローソン、ミニストップ株式会社、
山崎製パン株式会社デイリーヤマザキ事業統括本部(コンビニ:デイリーヤマザキ)
また、令和6年取組事業者のうち全国10事業者について、取組事例を公表しています。
詳細はこちらから!(東北地区からは株式会社ベルジョイスの取組事例がご紹介されています。)
 NO-FOODLOSS PROJECT
NO-FOODLOSS PROJECT
食品ロス削減国民運動のロゴマーク「ろすのん」の申請はこちらから![農林水産省へリンク]
食品リサイクル
 食品リサイクル法関連 (農林水産省へリンク)
食品リサイクル法関連 (農林水産省へリンク)
食品リサイクル法は、廃棄物の減量化と再生利用を推進し、循環型社会の形成を目指して制定されました。
- 食品リサイクル法の概要
- 食品リサイクル法の仕組み
- 食品廃棄物等の再生利用等の目標について←(農林水産省へリンク)
- 食品リサイクル法における廃棄物処理法の特例(PDF:131KB)
- 食品リサイクル法に基づく新たな基本方針の概要について(PDF : 290KB)
 定期報告書について (農林水産省へリンク)
定期報告書について (農林水産省へリンク)
平成21年度から、食品廃棄物等多量発生事業者(食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者)は、毎年度、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられました。
対象事業者は毎年6月末までに提出することになっています。
主たる事務所(本社等)の所在地を管轄する地方農政局に、必要部数(農林水産大臣あて1部、環境大臣あて1部、その他事業所管大臣があれば当該大臣あての部数)を送付して下さい。(農林水産省から他省庁へ回付致します)
また、郵送の際は、報告書のエクセルファイルをCD-R等の電子記録媒体に保存して、書面による報告書の提出時に同封していただくと、後日、修正があった場合、書面での再提出が最小限ですみますので、磁気媒体の提出に御協力をお願いします。なお、事前に作成した報告書を電子メール等で提出前に確認したい場合は、下記の問合せ先にご連絡ください。
※令和2年度以降に提出する、定期報告の主な変更点について
(2019年4月~2020年4月の実績報告)
令和2年度以降、定期報告の様式が変わりますので、今後の作成にあたりご留意ください
◇主な変更点(PDF : 340KB)
〇食品廃棄物等の発生量・再生利用実施量について、「市町村毎の把握」が必要となります。
〇「きのこ菌床」が新たに再生利用手法となり、市町村毎の再生利用実施量が必要となります。
〇定期報告内容が拡大します。
食品リサイクル法に基づく新たな基本方針等について(PDF : 297KB)
 登録再生利用事業者制度について (農林水産省へリンク)
登録再生利用事業者制度について (農林水産省へリンク)
登録再生利用事業者制度とは、優良な再生利用事業者を育成することを目的として、再生利用事業を的確に実施できる
一定の要件を満たすものを登録する制度です。
登録された場合のメリット
食品関連事業者にとって ・優良な再生利用事業者の選択が容易になります。
再生利用事業者にとって ・登録されることにより、受託先の拡大等が期待できます。
・肥料取締法・飼料安全法の特例が受けられます。製造、販売等の届出を重ねて行うことは
不要になります。
・廃棄物処理法の特例が受けられます。荷卸し地における一般廃棄物の運搬にかかる
業許可が不要になります。 (荷積み地における市町村からの業許可は必要)
東北管内の登録再生利用事業者マップ
詳細はこちら(PDF : 543KB)をご覧ください。
 再生利用事業計画認定制度について (農林水産省へリンク)
再生利用事業計画認定制度について (農林水産省へリンク)
再生利用事業計画認定制度とは、食品循環資源の発生者である食品関連事業者、これらの食品循環資源について
リサイクルを実施するリサイクル業者、また、製造されたリサイクル製品を利用する農林漁業者等の3者が連携し、再生利用についての計画を作成し、認定を受ける制度です。
認定を受けた場合に適用される廃棄物処理法の特例
1. 一般廃棄物収集運搬業の許可に係る特例
廃棄物処理法においては、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合にあっては、市町村長の許可を受けることが必要であり、この場合、例えば、A市で発生した一般廃棄物に該当する食品循環資源を別のB市に運んでリサイクルする場合にあっては、これを運ぶ一般廃棄物の収集運搬業者は、A市とB市の両市において、許可を取得することが必要です。
上記の場合、食品リサイクル法においては、認定を受けた再生利用事業計画に従った再生利用事業を行う場合について、計画の参加者である食品関連事業者からの委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬を実施する事業者に対して、A市及びB市のいずれの一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可も不要とする特例を設けています。
なお、産業廃棄物の収集運搬業の許可に関する特例はありません。
2. 一般廃棄物処分業に係る料金の上限規制の特例
廃棄物処理法においては、一般廃棄物処分業を行う場合、その料金の認定については、市町村の条例で定める手数料の上限を超えてはならないと定められています。
しかしながら、再生利用は焼却等の処分と比較してコスト増となりことも多いことから、食品リサイクル法においては、認定を受けた再生利用事業計画に参加しているリサイクル業者が行う再生利用事業について、この料金の上限規制を適用しない特例が設けられています。
フードバンク関連
 フードバンク活動の推進
フードバンク活動の推進
東北農政局では、備蓄の役割を終えた災害時⽤備蓄⾷料について有効活⽤を図り、食品ロスを削減するため、令和2年度よりフードバンク活動団体等に提供を行っております。
TOPICS
令和6年度は、6月又は7月に賞味期限を迎えるアルファ米の田舎ご飯及びドライカレー(ともに100g×50袋/1箱)、缶入りパン (100g×24缶/1箱)、飲料水(500ml×24本/1箱)の提供を行いました。
ご多忙の中、取りに来てくださったフードバンク団体の皆様ありがとうございました。
今年度の提供の様子をお届けします!
〇2024年6月20日 「フードバンク仙台」のスタッフが東北農政局まで受け取りにこられました。 ![]()
7月に賞味期限を迎える缶入りパン計25箱を提供しました。

〇2024年6月13日 福島県拠点から「特定非営利活動法人真善美」へ提供を行いました。![]()
7月に賞味期限を迎える飲料水計10箱を提供しました。


〇2024年6月4日 青森県拠点から「あおもりフードバンク(青森県社会福祉協議会)」へ提供を行いました。![]()
7月に賞味期限を迎える缶入りパン計5箱を提供しました。




- 令和元年度フードバンク活動促進情報交換会の概要について
開催日:令和元年11月14日(木曜日)
開催場所:仙台合同庁舎A棟7階会議室 - 平成30年度フードバンク活動促進情報交換会の概要について
・開催日:平成30年9月26日(水曜日)
・開催場所:仙台合同庁舎B棟2階 共用第一会議室
 東北のフードバンク団体情報
東北のフードバンク団体情報
農林水産省が、現在情報を入手している東北6県のフードバンク団体についてご紹介しています。
 補助事業等のご案内 (農林水産省へリンク)
補助事業等のご案内 (農林水産省へリンク)
このページでは、食品ロス削減・リサイクル推進に関する補助事業等について掲載しています。
 関係法令 (農林水産省へリンク)
関係法令 (農林水産省へリンク)
食品リサイクル法、同法に基づく政令、省令、告示、登録及び認定事務等、取扱要領を掲載しています。
 関連リンク
関連リンク
- 食べもののムダをなくそうプロジェクト(食品ロス削減に向けた取組) ←消費者庁HP〔外部リンク〕
- 環境省食品リサイクル関連 ←環境省HP〔外部リンク〕
- (財)食品産業センター ←食品リサイクルに係る認証制度〔外部リンク〕
- 食品産業の環境対策 ←(農林水産省へリンク)
- 容器包装リサイクル関連 ←(農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課担当者:食品産業環境指導官
食品リサイクル係
代表:022-263-1111(内線4375、4368)
ダイヤルイン:022-221-6146



























