 『食料自給率』は、その国で消費される食料がどのくらい国内で生産されているか(自給の度合い)を示す指標です。 『食料自給率』は、その国で消費される食料がどのくらい国内で生産されているか(自給の度合い)を示す指標です。
令和2年度の日本の総合食料自給率は、カロリーベースで37%、生産額ベースで67%となりました。
担当:企画調整室
|
 消費者展示コーナー、消費者相談、食に関するコミュニケーション、食の安全に関する講師派遣について掲載しています。 消費者展示コーナー、消費者相談、食に関するコミュニケーション、食の安全に関する講師派遣について掲載しています。
消費者相談は窓口を設け、皆様から寄せられる各種のご相談を承っております。
【消費者展示コーナー】
【消費者相談】
【食に関するコミュニケーション】
【食の安全に関する講師派遣】
担当:消費・安全部消費生活課
|
 「食育」は様々な経験を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を養うことにより、健全な食生活を実践することが出来る人間を育てることを目的としています。 「食育」は様々な経験を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を養うことにより、健全な食生活を実践することが出来る人間を育てることを目的としています。
こちらのページでは、各方面の取り組みや情報をご紹介します。
担当:消費・安全部消費生活課
|
 日常の「食」について、見たり聞いたりしたこと、『食』に対する思いやちょっとした出来事などを、食生活のヒントになればとつづるブログ「食(ク)リックひろば」です。 日常の「食」について、見たり聞いたりしたこと、『食』に対する思いやちょっとした出来事などを、食生活のヒントになればとつづるブログ「食(ク)リックひろば」です。
担当:消費・安全部消費生活課
|
| |
食の安全等、食に関して、関係府省が公表した情報や農政局の取組について掲載しています。 |
 |
担当:消費・安全部消費生活課
|
 食品の表示の基本の一つとなるJAS制度は、食品全体に係る横断的な規格・規準の他、特定の品目を対象とした個別の規格・規準が制定されています。 食品の表示の基本の一つとなるJAS制度は、食品全体に係る横断的な規格・規準の他、特定の品目を対象とした個別の規格・規準が制定されています。
担当:(表示)消費・安全部米穀流通・食品表示監視課
(JAS規格)経営・事業支援部食品企業課
|
 食品の偽装表示、JAS法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法、食糧法、農産物検査法及び水産流通適正化法に関する疑義情報など、幅広い情報を受け付けています。 食品の偽装表示、JAS法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法、食糧法、農産物検査法及び水産流通適正化法に関する疑義情報など、幅広い情報を受け付けています。
担当:消費・安全部米穀流通・食品表示監視課
|
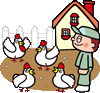 伝染性疾病などのまん延防止に向けた家畜及び水産の防疫体制の強化、飼料及びペットフードの安全性を確保することとしております。 伝染性疾病などのまん延防止に向けた家畜及び水産の防疫体制の強化、飼料及びペットフードの安全性を確保することとしております。
担当:消費・安全部畜水産安全管理課
|
 食品のトレーサビリティとは、食品の出荷、流通、販売に関する記録を作成・保存することによって、生産から小売までの食品の移動経路の把握を可能とする仕組みで、食品事故が発生した際は迅速な回収等に役立ちます。 食品のトレーサビリティとは、食品の出荷、流通、販売に関する記録を作成・保存することによって、生産から小売までの食品の移動経路の把握を可能とする仕組みで、食品事故が発生した際は迅速な回収等に役立ちます。
現在、牛肉及び米・米加工品については、法令によりトレーサビリティ制度が整備されていますが、その他の食品についてもトレーサビリティに対する取組みを推進しています。
担当:消費・安全部消費生活課
|
 病害虫の発生予防、まん延防止に向けた取組、農薬・肥料の安全確保への支援等を行っています。 病害虫の発生予防、まん延防止に向けた取組、農薬・肥料の安全確保への支援等を行っています。
担当:消費・安全部農産安全管理課
|
 『地産地消』に関する関係法令、補助事業、地産地消促進計画の策定状況、優良事例やメニューコンテストの表彰団体を紹介しています。 『地産地消』に関する関係法令、補助事業、地産地消促進計画の策定状況、優良事例やメニューコンテストの表彰団体を紹介しています。
担当:農村振興部都市農村交流課
|
 農林水産省では、食料自給率向上に資するため、米の消費拡大を目的とした「めざましごはんキャンペーン(朝ごはんの習慣化の促進や米を中心とした日本型食生活の普及・啓発)」や、「米粉の利用拡大」などに取り組んでいます。 農林水産省では、食料自給率向上に資するため、米の消費拡大を目的とした「めざましごはんキャンペーン(朝ごはんの習慣化の促進や米を中心とした日本型食生活の普及・啓発)」や、「米粉の利用拡大」などに取り組んでいます。
米粉情報はこちらから
担当:生産部生産振興課
|
 現在は農業をしていないけれど、将来、農業をやりたい。そんなあなたにきっと役立つサイト、情報を紹介するページです。 現在は農業をしていないけれど、将来、農業をやりたい。そんなあなたにきっと役立つサイト、情報を紹介するページです。
国、県及び市町村などでは、これから自分で農業を始めたい方、農業生産法人等に雇われて農業を始めたい方に向けて、様々な事業や制度を設けております。
また、就農相談窓口を開設して、新規就農を応援しています。
担当:経営・事業支援部経営支援課
|
 グリーン・ツーリズム(GT)とは、田舎で楽しむ余暇活動のことです。 グリーン・ツーリズム(GT)とは、田舎で楽しむ余暇活動のことです。
ここでは、田舎の自然、文化、人々との交流事例や各種情報の紹介をしています。
また、こうした取組をバックアップする各種支援の紹介をしています。
担当:農村振興部農村計画課
|
 一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、自治体、農協、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。 一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、自治体、農協、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。
担当:農村振興部農村計画課
|





 『食料自給率』は、その国で消費される食料がどのくらい国内で生産されているか(自給の度合い)を示す指標です。
『食料自給率』は、その国で消費される食料がどのくらい国内で生産されているか(自給の度合い)を示す指標です。 消費者展示コーナー、消費者相談、食に関するコミュニケーション、食の安全に関する講師派遣について掲載しています。
消費者展示コーナー、消費者相談、食に関するコミュニケーション、食の安全に関する講師派遣について掲載しています。 「食育」は様々な経験を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を養うことにより、健全な食生活を実践することが出来る人間を育てることを目的としています。
「食育」は様々な経験を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を養うことにより、健全な食生活を実践することが出来る人間を育てることを目的としています。 日常の「食」について、見たり聞いたりしたこと、『食』に対する思いやちょっとした出来事などを、食生活のヒントになればとつづるブログ「食(ク)リックひろば」です。
日常の「食」について、見たり聞いたりしたこと、『食』に対する思いやちょっとした出来事などを、食生活のヒントになればとつづるブログ「食(ク)リックひろば」です。
 食品の表示の基本の一つとなるJAS制度は、食品全体に係る横断的な規格・規準の他、特定の品目を対象とした個別の規格・規準が制定されています。
食品の表示の基本の一つとなるJAS制度は、食品全体に係る横断的な規格・規準の他、特定の品目を対象とした個別の規格・規準が制定されています。 食品の偽装表示、JAS法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法、食糧法、農産物検査法及び水産流通適正化法に関する疑義情報など、幅広い情報を受け付けています。
食品の偽装表示、JAS法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法、食糧法、農産物検査法及び水産流通適正化法に関する疑義情報など、幅広い情報を受け付けています。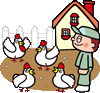 伝染性疾病などのまん延防止に向けた家畜及び水産の防疫体制の強化、飼料及びペットフードの安全性を確保することとしております。
伝染性疾病などのまん延防止に向けた家畜及び水産の防疫体制の強化、飼料及びペットフードの安全性を確保することとしております。 食品のトレーサビリティとは、食品の出荷、流通、販売に関する記録を作成・保存することによって、生産から小売までの食品の移動経路の把握を可能とする仕組みで、食品事故が発生した際は迅速な回収等に役立ちます。
食品のトレーサビリティとは、食品の出荷、流通、販売に関する記録を作成・保存することによって、生産から小売までの食品の移動経路の把握を可能とする仕組みで、食品事故が発生した際は迅速な回収等に役立ちます。 病害虫の発生予防、まん延防止に向けた取組、農薬・肥料の安全確保への支援等を行っています。
病害虫の発生予防、まん延防止に向けた取組、農薬・肥料の安全確保への支援等を行っています。 『地産地消』に関する関係法令、補助事業、地産地消促進計画の策定状況、優良事例やメニューコンテストの表彰団体を紹介しています。
『地産地消』に関する関係法令、補助事業、地産地消促進計画の策定状況、優良事例やメニューコンテストの表彰団体を紹介しています。 農林水産省では、食料自給率向上に資するため、米の消費拡大を目的とした「めざましごはんキャンペーン(朝ごはんの習慣化の促進や米を中心とした日本型食生活の普及・啓発)」や、「米粉の利用拡大」などに取り組んでいます。
農林水産省では、食料自給率向上に資するため、米の消費拡大を目的とした「めざましごはんキャンペーン(朝ごはんの習慣化の促進や米を中心とした日本型食生活の普及・啓発)」や、「米粉の利用拡大」などに取り組んでいます。 現在は農業をしていないけれど、将来、農業をやりたい。そんなあなたにきっと役立つサイト、情報を紹介するページです。
現在は農業をしていないけれど、将来、農業をやりたい。そんなあなたにきっと役立つサイト、情報を紹介するページです。 グリーン・ツーリズム(GT)とは、田舎で楽しむ余暇活動のことです。
グリーン・ツーリズム(GT)とは、田舎で楽しむ余暇活動のことです。 一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、自治体、農協、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。
一般に市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、自治体、農協、個人など多くの方々が市民農園を開設できるようになっています。