フォトレポート(奈良県拠点) 2023
※ほかの年のフォトレポートはこちら→ 2022年 2023年 2024年 2025年

特別栽培農産物、土耕栽培いちご ~Odamaki農園~
Odamaki農園(おだまきのうえん)は、奈良県桜井市の三輪山のふもとにあるいちご農園です。
同農園では自家製たい肥を活用した土耕栽培にこだわり、さらに害虫が嫌うハーブ液の散布や天敵虫を放つ等、化学農薬に頼らない栽培に取り組んでいます。
栽培された土耕いちごは、奈良県唯一の特別栽培農産物として、桜井市の「大和桜井ブランド」にも認定されています。
(取材・撮影:令和5年12月)
詳しくはこちら>>>
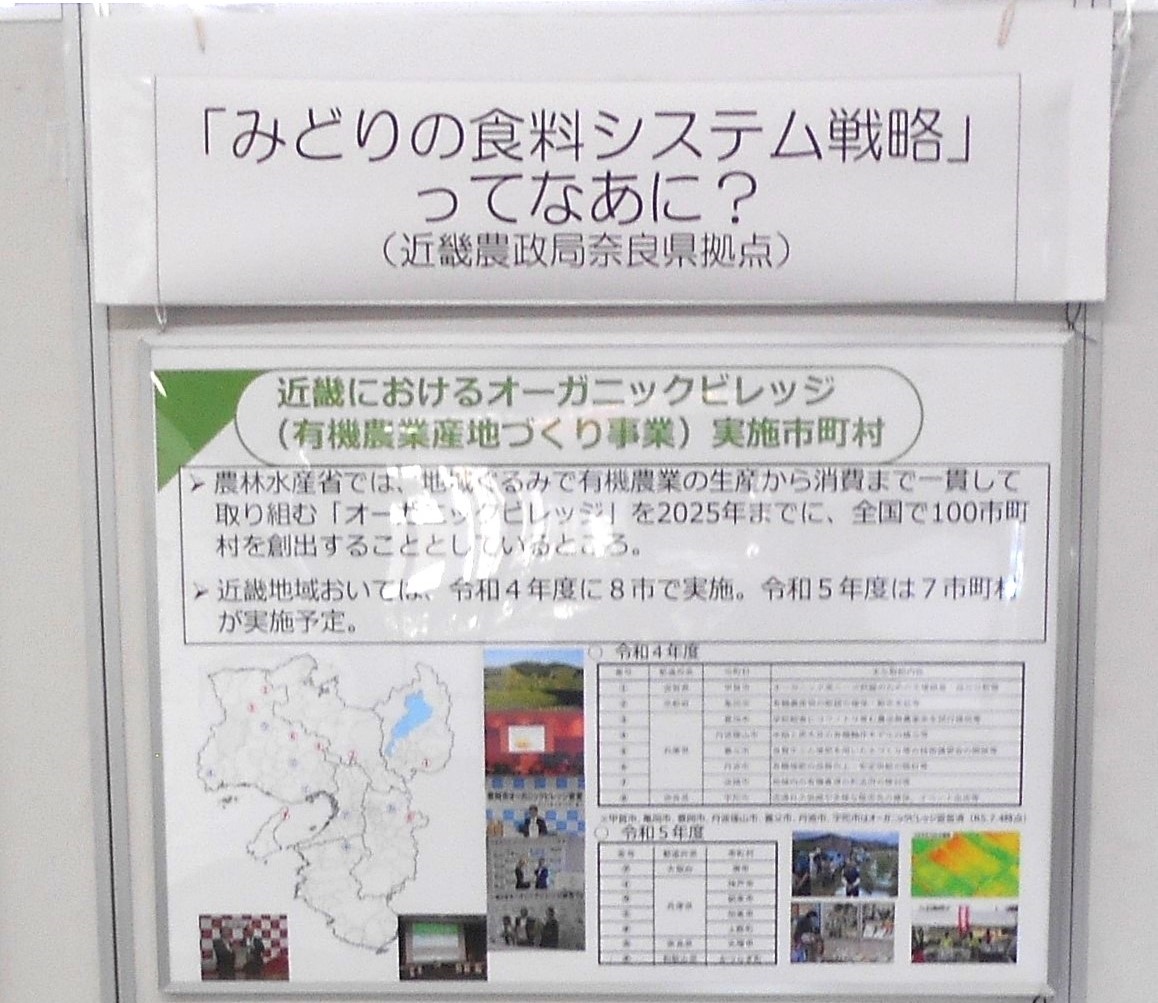
「宇陀オーガニックビレッジフェス2023」が開催されました
宇陀市は、奈良県内で有機農業に取り組む生産者が多い地域で、昨年全国で初めて「オーガニックビレッジ宣言」を行いました。その1周年を記念して、11月18日から26日にかけて「宇陀オーガニックビレッジフェス2023」が開催されました。有機農業セミナー・相談会や有機農産物・その加工品の販売、体験型イベントなどが行われ、有機農業に関心のある人を始め多くの来場者がありました。
(取材・撮影:令和5年11月)
詳しくはこちら>>>

「富有(ふゆう)柿」の最盛期を迎えています ~JAならけん西吉野柿選果場~
奈良県は全国有数の柿の産地で、中でも五條市は柿の栽培が盛んな地域です。7月のハウス柿の出荷に始まり、9月からは露地柿の刀根早生(とねわせ)柿、平核無(ひらたねなし)柿、そして今は富有柿が最盛期を迎えています。今年は天候にも恵まれ、14000~15000トンの出荷を予定しています。
(取材・撮影:令和5年10月)
詳しくはこちら>>>

女性農業者の立場から農業の楽しさを伝えたい ~なら起業ネットワーク「和母(わはは)」~
令和5年10月3日、奈良県拠点は「なら起業ネットワーク『和母』」(以下「和母」という。)と意見交換を行いました。
「和母」は奈良県内で活躍している女性農業者13名の集まりで、取り扱う品目は、野菜、果物、お茶、卵、豚肉など様々ですが、毎月の情報交換や勉強会のほか、互いの理解を深めるための農園訪問、マルシェの開催など楽しく活動しています。
メンバーそれぞれ扱う品目は違っていても各々の課題を知ることができるとともに、年代の違いもあって意見交換では新たな発見があるなど、活動にも活かされているそうです。
(取材・撮影:令和5年10月)
詳しくはこちら>>>

環境にやさしい栽培にこだわり、レモングラスを栽培しています ~平原区自治会むらづくり委員会(下市町)~
平原地域は、奈良県吉野郡下市町の西部に位置し、現在の人口は50名に満たない小さな集落です。
地域の活性化を目指し、平成26年に「平原区自治会むらづくり委員会」を発足し、レモングラスの栽培を始め今年で10年目を迎えます。
現在、栽培期間中に農薬を使用しない等の環境にやさしい栽培にこだわり、地域住民でレモングラスの栽培、加工、販売に取り組んでいます。
(取材・撮影:令和5年8月)
詳しくはこちら>>>

「食」と「農」の未来を拓く担い手を育てる ~奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校(NAFIC)~
奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校は、平成28年に既設の奈良県立農業大学校を改組して設立され、全国に先駆けて「食」と「農」の担い手を育てる「フードクリエイティブ学科」と「アグリマネジメント学科」が設けられました。
アグリマネジメント学科は、栽培技術と消費者ニーズに対応できる販売力、そして奈良らしい地域ブランドの強みを知ることができるカリキュラムとなっています。特に、フードクリエイティブ学科と協力しあって取り組む「食材活用ワーキング」は、農産物の特徴やそれを活かす調理法などをともに学び考えるカリキュラムで、食と農のつながりと理解を深める機会となっています。
(取材・撮影:令和5年5月・6月)
詳しくはこちら>>>

荒廃農地を利用して楽しく農作業体験 ~たんぼの楽耕(がっこう)奈良県河合町~
奈良県河合町では、荒廃農地を活用しようと平成27年から「たんぼの楽耕(がっこう)」事業を開始し、今年で9年目を迎えます。
この取組は、河合町内外の住民や就農希望者を対象に、水稲や野菜の植え付けから収穫まで共同作業を行うもので、農作業を通じて荒廃農地の解消と参加者の交流の場が広がっています。
参加コースは、参加者が共同で作業する入門編の「一般体験コース」、一般体験コースを経験した方が個人で好きな野菜を栽培する「独立畑コース」、米作りを本格的に学びたい「本格的な米コース」の3つのコースがあり、農業に興味のある方がステップアップできる体制を整えています。
(取材・撮影:令和5年6月)
詳しくはこちら>>>

集落一丸で地域の農地を守る ~農事組合法人 ひがしとよ営農組合~
ひがしとよ営農組合は山添村岩屋地区、毛原地区の農地を守るために令和2年10月に設立され、令和5年5月に法人化されました。
現在は、両地区合わせて約25haある農地の半分以上を当組合に集積し、43人の組合員が農作業に従事し、主食用米に加え、小麦や飼料用米を栽培していますが、小麦収穫後の農地を有効に活用するため、新たに大豆の栽培にも挑戦する予定とのことです。
(撮影・取材:令和5年5月、6月)
詳しくはこちら>>>

「花は観光、根は生薬に」シャクヤク栽培で地域農業を活性化~奈良県下市町栃原地区~
平成25年から、農事組合法人 旭ヶ丘農業生産販売協同組合と株式会社大紀(農園部)が薬用作物の栽培を始めました。薬用作物のシャクヤクは、根を薬の原料にするために花を摘み取る必要がありますが、その花の美しさを観光資源として活かしたいという思いから、毎年開花シーズンには「シャクヤクガーデン」としてほ場を一般に開放しています。
(取材・撮影:令和5年5月)
詳しくはこちら>>>

曽爾村の自然と風土を活かしたオンリーワン商品をめざして~山浦農園~
山浦農園(代表 山浦康二氏)は、化学農薬や化学肥料に頼らない環境に配慮した栽培方法で、サラノバレタス(リーフレタス)やベビーリーフを中心に、少量多品種の彩り野菜等を飲食店向けに販売しています。
代表の山浦康二氏は、「未来につなぐ食育倶楽部」の会員として長年にわたり小中学校での体験学習に取り組まれ、また、奈良県指導農業士として農業後継者や農業技術者をめざす学生等の指導にも尽力されてきました。
(撮影・取材:令和5年3月)
詳しくはこちら>>>

農作業体験で里山の魅力を知ってもらいたい ~杉浦農園Gamba Farm~
御所市にある杉浦農園Gamba Farmの代表 杉浦英二氏は、約20年前に大阪から御所市に移住し、里山の復興活動をしながら農業を始めました。現在は山際にある約70筆の棚田と段々畑で農業経営を行っています。
耕作する農地が増えたことから、1人で管理することが難しくなり、ボランティア制度を利用して、外国人や国内の自然や農業に興味がある人達を呼び込み、地域の魅力を紹介しながら、一緒に農作業を行っています。今では年間400~500人のボランティアの人達が訪れています。
(撮影・取材:令和5年2月)
詳しくはこちら>>>

近畿「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第6回)選定証授与式を開催 ~宇陀市古民家活用地域活性化協議会(宇陀市)~
奈良県拠点は令和4年12月20日に「うだ薬湯の宿 やたきや」において、近畿「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第6回)選定証授与式を開催し、ビジネス・イノベーション部門で選ばれた宇陀市古民家活用地域活性化協議会に対して宮本地方参事官から選定証を授与しました。
近畿「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより、地域の活性化や所得向上に取り組んでいる近畿独自の特徴ある優れた事例を選定しました。
(撮影・取材:令和4年12月)
詳しくはこちら>>>

食卓に笑顔を届けたい~藤原京菜園~
橿原市でランドセルの製造・販売を行う(株)鞄工房山本は、かつて藤原京があったこの地で「藤原京菜園」として、令和4年3月から農業を始めました。ランドセルづくりの目的のひとつでもある「お子様とそのご家族を笑顔にする」ことを農業の分野でも実現させたいという思いで、トマトづくりに取り組んでいます。
ハウス内では、環境制御システムと土耕栽培を組み合わせた栽培方法が行われています。
(取材・撮影:令和4年12月)
詳しくはこちら>>>

近畿「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第6回)選定証授与式を開催しました
奈良県拠点は令和4年12月13日に九果園直売所において、近畿「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第6回)選定証授与式を開催し、代表 谷尾 薫氏に対し宮本地方参事官から選定証を授与しました。
代表からは、「優良事例として選定頂いたことが終わりではなく、これを機に周りの地域において同じような想いの仲間を増やし、農事組合法人の設立を目指したい。
この地においていちじくが産地ブランドになるよう取組み、農地の集約や雇用の創出など地域の活性化に汗をかきたい」と語られました。
詳しくはこちら>>>
お問合せ先
奈良県拠点
電話:0742-32-1870




