フォトレポート(奈良県拠点) 2024
※ほかの年のフォトレポートはこちら→ 2022年 2023年 2024年 2025年

奈良市4Hクラブとの意見交換を開催しました
令和6年11月28日、近畿農政局奈良県拠点は、奈良市4Hクラブのメンバー5名と意見交換を行いました。
奈良市4Hクラブは現在19名が在籍し、毎月定例会を開き、メンバー間で情報交換等を行っています。
当日は、地域農業との関わりや環境負荷低減の取組、地球温暖化による農産物への影響、新規就農に当たって苦労した点など様々なテーマについて意見交換を行いました。
(取材・撮影:令和6年11月)
詳しくはこちら>>>
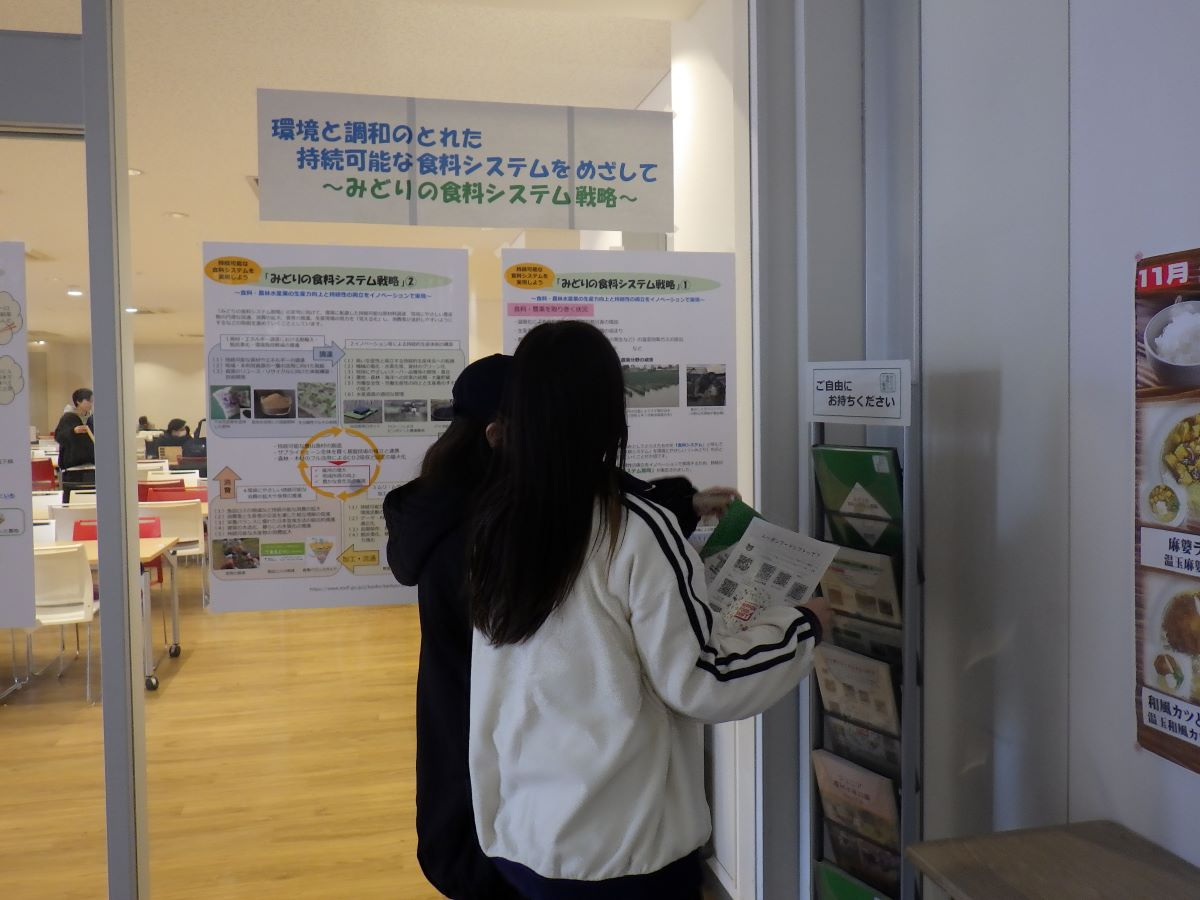
畿央大学で「みどりの食料システム戦略」パネル展を開催しました ~畿央大学(広陵町)~
農林水産省では、資材の調達から生産、流通・加工、消費までの各段階で環境負荷低減の取組を行い、将来に向けた持続可能な食料システムの構築をめざして、「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という。)を策定し、その取組に理解と関心を持っていただくことで、具体的な行動につながるきっかけとなることを期待し、畿央大学においてパネル展示を行いました。パネル展示期間中には「食」と「農」に対する考えなどを今後の若い世代に向けた取組の参考となるよう、「みどり戦略」に関するアンケートを実施しました。
(取材・撮影:令和6年11月)
詳しくはこちら>>>

太陽の恵みと柿本来の力を生かした栽培で樹上完熟の柿を届ける ~西吉野 柿と梨の平井農園(五條市)~
平井農園は、全国有数の柿の産地である奈良県五條市で柿や梨などの果樹を栽培しています。元気な土づくりや草生栽培、農薬の使用を減らすなど環境に配慮したこだわりの栽培方法で柿づくりに取り組んでいます。また、大切に育ててきた園地を次の世代に引き継ぐために、第三者継承の準備も進めています。
(取材・撮影:令和6年11月)
詳しくはこちら>>>

「大和の黒豆“KAWAI BLACK”」収穫体験 ~JAF奈良支部・河合町役場(河合町)~
河合町では昔から黒豆を栽培し、枝豆として食べてきたという歴史があります。町制50周年となった令和3年に、このおいしさを広く知ってもらいたいという思いから特産品として、「大和の黒豆“KAWAI BLACK”」の取組が始まりました。この取組を知ったJAF奈良支部が地域貢献の取組の一環として河合町と連携し、会員向け参加型イベント「JAFデーin河合町黒豆&さつまいも収穫体験」を開催し、たくさんの人でにぎわいました。
(取材・撮影:令和6年10月)
詳しくはこちら>>>

環境に優しい栽培方法で「三橋トマト」を新たなブランドに ~中西農園(大和郡山市)~
中西農園代表の中西昭仁さんは、大和郡山市で奈良県の伝統野菜「大和丸なす」の出荷組合(丸三出荷組合)の代表として「大和丸なす」の生産・普及に尽力されています。
中西さんは、「地域の農業を守るため、環境に配慮し低コストで誰もが取組むことができる作物として、ミニトマトを試験的に栽培している。栽培方法が確立できれば、新たなブランド「三橋トマト」として広めていきたい。」と中西さんは抱負を語られました。
(取材・撮影:令和6年9月)
詳しくはこちら>>>

棚田の生物多様性を保全し、都市と農村の交流を図る ~忍辱山(にんにくせん)の棚田自然観察会(奈良市)~
忍辱山の棚田(旧大柳生村)は、ヤゴ、カイエビ、カエル、イモリ、ドジョウ等様々な生物の生息場所となっています。
こうした生物多様性を保全し、棚田を核とした棚田地域の振興を図るため、地域活動の実施主体である忍辱山地内中山間組織が地元の興東公民館との共催により、奈良市内等の小学生と保護者を対象に、専門家を講師に招いて自然観察会を開催しました。
(取材・撮影:令和6年7月)
詳しくはこちら>>>

下市町の新たなブランドをめざしてメロン栽培に取り組む~美吉野ファーム(下市町)~
美吉野ファーム代表の佐々岡浩子さんは、奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校を卒業し、令和2年に下市町で就農しました。下市町の新たなブランドになることをめざしてメロンの栽培に取り組んでいます。
(取材・撮影:令和6年7月)
詳しくはこちら>>>

あすか夢耕社で働きながら農業を学び就農をめざす ~(一財)明日香村地域振興公社(明日香村)~
明日香村では、農業者の高齢化が進む中、持続可能な力強い農業を実現するため、一般財団法人明日香村地域振興公社をプラットフォームに、将来の農業を担う新たな人材の育成と就農支援を行っています。
「あすか夢耕社農業実習生研修プログラム」は、将来的に明日香村に定住し、就農を希望する方を対象に、公社がパート職員として雇用し、実習生は収入を得ながら農業の基礎知識、栽培技術等を学ぶ仕組みとなっています。
(取材・撮影:令和6年7月)
詳しくはこちら>>>

大和郡山市4Hクラブとの意見交換を開催しました
令和6年6月21日、近畿農政局奈良県拠点は、大和郡山市4Hクラブと意見交換を行い「近隣の高齢農業者から農地の引受けの依頼について、引き受けたい気持ちはあるが、家族経営なので作業量に限界があり引き受けられない」、「将来を担う子どもたちに少しでも農業に興味を持ってもらえるように、小学校で農業体験や出前授業を行っている」、「子どものために、できるだけ環境に負荷がかからない農作物を提供したいとの思いで、農薬等を使用しないようにしている」、「4Hクラブでは身近な農業者であるメンバーに助けてもらったり相談に乗ってもらったりして、仲間づくりができるので、新規就農者には是非加入してほしい」など活発な発言があり、有意義な意見交換となりました。
(取材・撮影:令和6年6月)
詳しくはこちら>>>

棚田オーナーで「稲渕の棚田」の美しい景観を守る ~NPO法人明日香の未来を創る会(明日香村)~
6月23日、明日香村「稲渕の棚田」で棚田オーナーの田植えが行われました。
棚田オーナー制度は、明日香村「稲渕の棚田」の景観を守るために、地域住民で組織するNPO法人明日香の未来を創る会が運営しており、今年で29年目を迎えます。インストラクターの指導を受けながら米作りを体験する内容で、籾まき、代かき、田植え、稲刈り、脱穀作業のほか、案山子づくりや伝統行事への参加など1年を通して行われています。奈良県内外から多くの方々が参加し、都市と農村の交流が図られています。
毎年参加している方も多く、和気あいあいと参加者同士が協力しあって取り組む姿が見られました。
(取材・撮影:令和6年6月)
詳しくはこちら>>>

多様な農業人材を育て、農地の保全と農業振興に取り組むまち ~いこまファーマーズスクール(奈良県生駒市)~
生駒市は、隣接する大阪の中心部へのアクセスの良さから住宅都市として発展してきたまちです。人口は大きく伸びる一方で、農業者の高齢化のため担い手が不足し、遊休農地の増加が課題となっていました。
生駒市はこの課題解決に向けて、新たに農業を始めたい方や別の仕事をしながら農業をする「半農半X」などを支援し、多様な農業人材を育て、農業への参画を促すことにより、農地の保全と農業振興を図ることを目的として「いこまファーマーズスクール」を開講しています。
(取材・撮影:令和6年6月)
詳しくはこちら>>>

「国の担い手施策について」をテーマに出張講座を行いました ~奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校(NAFIC)~
令和6年6月20日(木曜日)、奈良県拠点大澤地方参事官が講師となり、奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校アグリマネジメント学科の学生に「国の担い手施策について」をテーマに出張講座を実施しました。
今回受講した学生は、同校で農業経営に必要な知識と技術を実践的に学び、卒業後は新規就農や農業法人・農業関連企業への就職を希望している2年生です。
(撮影:令和6年6月)
詳しくはこちら>>>

地元の新鮮な野菜を子育て世代に食べてほしい ~ Sakayama farm(五條市)~
Sakayama farmの代表の坂上由起子さんと義妹の山田幸子さんは、「新鮮でおいしい野菜を子どもたちに食べさせたい。農地を荒らしてはいけない」という思いから10年前に就農し、五條市北宇智地区で長年作られてきたサラダごぼう、やまのいも、なす等を栽培しています。
同年代で気心が知れた二人は、子どもの成長等のライフステージにあわせた経営を行うことで、無理をしすぎない農業を行っています。
(取材・撮影:令和6年5月)
詳しくはこちら>>>

災害用備蓄食料をフードバンクへ提供しました
近畿農政局奈良県拠点では、備蓄の役割を終えた災害時用備蓄食料について有効活用を図り、食品ロスを削減するため、フードバンク活動団体等に提供することとし、今回、特定非営利活動法人フードバンク奈良へ食品の提供を行いました。
(撮影:令和6年5月)
詳しくはこちら>>>

いちご栽培から新たな事業展開 ~直営店「Very Berry Café」をオープン
株式会社明日香園芸は、大阪市内で生花・鉢物・観葉植物の販売やレンタルサービス事業の他にフラワーアレンジメントスクールを運営し、事業エリアは京都府や奈良県へと広がっています。
2022(令和4)年、いちご栽培での観光農園とカフェ経営による新たな事業展開を目指し、農地中間管理機構から同市中町の農地を借受け、奈良市の認定農業者となり、農園「Aska Strawberry Field」を開設し、2024(令和6)年2月に農園から少し離れた場所でカフェ「Very Berry Café」をグランドオープンしました。
(取材・撮影:令和6年4月)
詳しくはこちら>>>

大和茶の産地である奈良市月ヶ瀬からお茶の魅力を伝えたい ~上久保(うえくぼ)茶園~
奈良市月ヶ瀬で茶の生産を行う上久保 淳一氏は、機械による製茶が一般的となっている現代において、お茶の魅力を伝えたいとの思いから、「手もみ製茶」の実演や体験を楽しむことができるティーサロン「TEA UEKUBO」を令和5年11月にオープンされました。
上久保さんは手もみ茶の技術と文化を伝える活動に取り組んでおり、第25回全国手もみ茶品評会において農林水産大臣賞を受賞され、全国手もみ茶振興会から関西で初の「茶聖(ちゃせい)」の称号を贈られています。
(取材・撮影:令和6年4月)
詳しくはこちら>>>

天敵農法にこだわり、完熟で新鮮ないちごをお届け(奈良県橿原市)
つがわ農園代表の津川 正直さんは、サラリーマンから農業に転職し今年で10年目。
農地を農地中間管理機構から借地し、ビニールハウスでの土耕栽培から始め、その後、高設栽培の施設を拡張し、完熟で新鮮ないちごを生産しています。
(令和6年3月撮影)
詳しくはこちら>>>

れんこんを愛しすぎて! ~自然派農場しもかわ(山添村)~
山と川に囲まれた奈良県山添村の畑で農業を営む「自然派農場しもかわ」の下川麻紀さんは、野菜嫌いの子どもが「お母さんの野菜は世界一おいしいね」と言ってくれた言葉に励まされ、化学農薬や化学肥料の使用を控え、環境に優しい農法を実践しています。
収穫したれんこんやマコモダケ、パパイヤ、生姜など多種多様な野菜は、県内の直売所で販売しています。
(取材・撮影:令和5年12月、令和6年3月)
詳しくはこちら>>>

品質にこだわり高級いちごで輸出を拡大 ~奈良いちごラボ~
「奈良いちごラボ」は、奈良県内のいちご農家5名で組織されたグループです。奈良県の育成品種「古都華(ことか)」を始め、「淡雪(あわゆき)」「パールホワイト」「真珠姫(しんじゅひめ)」を栽培し、年々海外への輸出を増やしています。
今シーズンは、日本貿易振興機構(JETRO)のほか販売関係者などの協力を得て、新たにイギリスの高級百貨店へ輸出の販路を拡げました。
(取材・撮影:令和6年3月)
詳しくはこちら>>>

~天理市がオーガニックビレッジを宣言しました~
令和6年3月10日(日曜日)、循環型社会を目指す「大和高原『福住村』プロジェクト」の三月市(さんがついち)が旧天理市立福住中学校で開催され、その中で、天理市長が「オーガニックビレッジ」を宣言しました。
オーガニックビレッジとは、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組を進める市町村のことをいいます。
(取材・撮影:令和6年3月)
詳しくはこちら>>>

これからも立派なイチゴを作り続けたい! ~こしお農園(奈良県大和郡山市)~
大和郡山市でイチゴの養液土耕栽培に取り組む小塩 大策さんは、サラリーマンをされていましたが、農業は自分の裁量で決められることが多いという点に魅力を感じ、転職を決意されました。
2人の子供を育てるパパの顔もお持ちで、「子供にも喜んでもらえるように、これからも立派なイチゴを作り続けたい」と語られました。
(取材・撮影:令和6年3月)
詳しくはこちら>>>

若手生産者との意見交換を開催しました
令和6年2月26日(月曜日)、近畿農政局奈良県拠点は、「奈良県若手生産者との意見交換」を開催し、県北部の2市から4名の若手生産者(20~30代)にご参加いただきました。
この意見交換は、昨年末に意見交換を行った若手生産者の方から、知人の生産者たちの話も聞いて欲しいとの要望を受け、ぜひとも実施したいと準備を進めてきたものです。
(撮影:令和6年2月)
詳しくはこちら>>>

リーフレタスの水耕栽培で安定出荷を実践 ~森島ファーム(奈良県天理市)~
森島ファーム代表の森島 秀浩さんは、サラリーマンをされていましたが、自分で何かをしてみたいとの思いがあり、また、農業に興味があったことから、実家の農地を受け継ぐ形で平成30年8月に就農しました。
森島さんは、「水耕栽培は、年間を通して安定して収穫できることが魅力であり、1年を通して安定的に出荷できるように、計画的な生産を心がけています」と語られました。
(取材・撮影:令和6年2月)
詳しくはこちら>>>

栽培技術を磨いて品質と味の良いいちご「古都華(ことか)」を届けたい
~雇用就農を経て独立就農松尾農園~
橿原市でいちごの高設栽培に取り組む松尾匡章さんは、奈良県立なら食と農の魅力創造国際大学校(以下「NAFIC」という。)で農業の基礎を学び、いちご農家での雇用就農を経て令和4年に独立就農しました。
在学中のインターンシップ実践実習では、明日香村のいちご農家で生産技術の奥深さや産地の協力体制などを学び、卒業後は奈良市のいちご農家に雇用就農して3年間の経験を積みました。お世話になった方々はいずれもNAFICの前身「奈良県立農業大学校」の卒業生で、松尾さんの就農をサポートしてくれています。
(取材・撮影:令和6年2月)
詳しくはこちら>>>
山村地域を元気にするために ~農事組合法人上湯川きのこ生産組合(奈良県吉野郡十津川村)~
農事組合法人上湯川きのこ生産組合は、奈良県の最南端に位置する十津川村上湯川地域で、ナメコやブナシメジ、エリンギ、ヒマラヤ茸等の菌床栽培に取り組んでいます。
現在、20名を超える従業員は全員が近隣地域の村民で、20代から80代の幅広い世代が栽培に取り組んでいます。
(取材・撮影:令和5年12月)
詳しくはこちら>>>

近畿の若手農家が集い、奈良で新鮮農作物マルシェを開催 ~奈良県4Hクラブ連絡協議会~
12月17日、奈良公園バスターミナルにおいて、近畿農業青年クラブ連絡協議会主催の「農家直送!新鮮農作物マルシェ」が開催されました。近畿府県の農業の魅力を発信し、4Hクラブの活動を広く知ってもらおうと企画されたものです。
近畿農業青年クラブは、近畿地域の若手農業者を会員とする組織で、様々な活動を通じて会員の栽培技術を高め、高品質の農産物の栽培等に取り組んでいます。
古都奈良でのマルシェには県内外からの観光客が立ち寄り、こだわりの農産物の説明に聞き入り購入する姿が見られました。
詳しくはこちら>>>

近畿農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝(第7回)選定証授与式を開催しました(奈良県)
奈良県拠点は、令和5年12月14日御所市役所において、近畿農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第7回)選定証授与式を開催し、御所市6次産業化・地産地消推進協議会 会長 壷井和子氏に対し大澤地方参事官から選定証を授与しました。
壷井会長からは、「御所芋は希少品であり引き続き御所芋を用いた焼酎の販売を進めていきたい。また、御所柿を使った柿蜜など、地域のすぐれた農産物をブランド化することで産業間の連携や販路拡大を図り、地域経済を活性化し、農家所得の向上を図りたい」と語られました。
(取材・撮影:令和5年12月)
詳しくはこちら>>>
お問合せ先
奈良県拠点
電話:0742-32-1870





