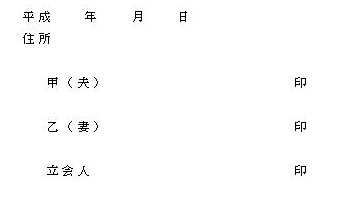家族経営協定の普及推進による家族農業経営の近代化について
|
本通知には機種依存文字が含まれているため、当該文字は変換して表示しています。 |
7構改B第103号
平成7年2月7日
各地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて
(農林水産省)構造改善局長
農蚕園芸局長
ウルグァイ・ラウンド農業合意等国際化の急速な進展の中で、効率的かつ安定的な経営体が地域における農業生産の大宗を担うような農業構造を実現するためには、農業生産基盤の整備、農地の流動化の促進等と併せ、農業経営体の大宗を占める家族農業経営をはじめ経営体の経営管理能力の向上等その近代化の一層の促進を図ることが重要となっている。しかしながら、家族農業経営は家族で営まれているため、世帯員個々の意欲と能力が顕在化しにくい側面もあり、これを顕在化するための方策について、国、地方公共団体、関係機関が連携し、全国的に推進することが求められている。
このため、今般、下記のとおり、近代的な家族農業経営を実現するための手法の一つとして家族経営協定の一層の普及推進を図ることとしたので、御了知の上、貴職におかれても関係機関との連携・協力の下に、これらの一層の推進に努めるようお願いする。
なお、貴局管内各都府県知事には、貴職から通知するとともに、これらの推進につき適切な指導をお願いする。
おって、全国農業会議所会長、全国農業協同組合中央会会長、(社)全国農業改良普及協会会長及び(社)農山漁家生活改善研究会会長に対しては、本日付けをもって本通達写しを送付し、協力を依頼しているので念のため申し添える。
記
第1 趣旨
農業経営の近代化を促進するためには、農地等生産基盤の整備、機械・施設等資本装備の高度化、新品種・新技術の導入等生産方式の改善・合理化の推進と併せ、経営を担う者の経営に関する諸活動が適切に行われることが必要であり、この意味で意欲と能力のある者が十分にその力を発揮し得るよう経営内における個人の地位及び役割が明確化されることが重要である。この観点を含め、体質の強い農業経営の育成を図るため、熟度の高いものについてその法人化を推進してきたところであるが、法人化を選択しない家族農業経営においても、女性、後継者等農業に従事する世帯員の個人の地位及び役割を明確化していくこと、すなわち世帯員がそれぞれ個人としてその地位や役割が尊重され、経営のパートナーとして位置づけられるよう関係者の認識醸成を図り、具体的対応につなげていくことは極めて重要な課題である。
この場合、家族農業経営内での個人の地位及び役割を明確化し近代的な家族農業経営を実現するための手段としては、これまでも先進的農家等での実践例があり、世帯員相互間のルールづくりの意義を有する家族経営協定が極めて有効であると考えられる。家族経営協定の締結を通じ、経営内における世帯員の役割分担、労働時間・休日・休暇等の就業条件、収益の分配、経営の円滑な継承等に関するルールの明確化が図られ、これにより、農業経営に参画する各世帯員の農業経営に対する意欲の増進と能力の向上、さらには生活運営の近代化が期待される。このことは、意欲と能力のある者の農業への参入の促進と、後継者及びその配偶者の確保に資するものであり、今後一層その普及推進を図る必要がある。
第2 家族経営協定の内容
家族経営協定の現実の内容は、営農計画の作成、収益の分配、労働時間・休日等就業条件、経営移譲に関する取決め等様々なものがあるが、女性の地位向上や世帯員の個人としての地位の確立等の観点から、今後普及推進すべきものは、家族農業経営を構成する個々の世帯員が対等の立場で共同して経営体づくりとその運営に参画することを基本とするものである。世帯員の参画の仕方は必ずしも一様ではないが、これにより、各人が意欲と責任感を持って経営に参画するようになり、その能力の十分な発揮によって近代的な家族農業経営の実現が可能になるものと考えられる。
もとより、いかなる内容の家族経営協定を締結するかは、その家族農業経営の発展状況をはじめ実情に応じて当事者間の話合いに基づき決定されるものであり、画一的性格のものではないが、以上の観点から近代的な家族農業経営を実現するために家族経営協定に盛り込まれることが適当な事項として考えられるものを掲記すれば、別紙1のとおりである。
また、具体的な家族経営協定の内容は、これらの事項に留意しつつ、当事者間の話合いの下にその熟度に応じて作成されることとなるものであり、もとより、画一的性格のものではないが、現実の諸例を参考にした成熟した段階の家族農業経営における望ましい家族経営協定の具体例としては、別紙2のようなものが想定される。
さらに、締結された家族経営協定が社会的認知を受け実効性を増すよう、地域の実情に応じ、適切な第三者を立会人とすることが望ましい。また、その内容は、家族農業経営の変化、社会経済情勢等農業をめぐる状況の変化等により見直すことが必要となるため、家族経営協定の有効期間を定めるとともに、併せてその更新方法について定めることが望ましい。
なお、世帯員が家族経営協定に基づき耕作する場合であっても、その耕作が農地法上許容されたものである必要があるが、各世帯員(住居及び生計を一にする者)が農地の権利を有する場合のほか、ある世帯員が権利を有する農地を他の世帯員が耕作する場合も含まれるので申し添える。
第3 推進方策
家族経営協定については、これまで、農業経営基盤強化促進対策事業、新しい家族経営推進運動事業等によりその普及推進を図ってきたところであるが、今後、関係機関との一層の連携・協力の下に、次のとおり積極的に実施していくこととする。
(1)農業経営基盤強化促進対策事業
農業経営基盤強化促進法に基づいて、効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るに当たっては、家族経営協定が農業経営の改善に資することを踏まえ、構造政策推進会議等において家族経営協定の推進を周知させるとともに、経営改善支援活動事業等により、農業経営改善計画の事項に家族経営協定による農業経営の改善が含まれることに留意しつつ、計画策定の支援に努める。
(2)協同農業普及事業
協同農業普及事業の実施に関する方針の策定に当たっては、協同農業普及事業の運営に関する指針における普及指導活動の基本的な課題を踏まえ、普及指導活動の課題として、家族経営協定の普及推進についても盛り込むよう努めるとともに、効率的かつ安定的な経営体の育成、青年農業者の育成確保、農業経営における女性の能力発揮等のための普及活動の一環として、家族経営協定の普及推進を図るよう努める。
(3)新しい家族経営推進運動事業
都道府県推進会議において、事業の推進方向、推進体制等について検討を行うとともに、啓発資料及び家族経営協定の事例集を作成し、その効果的な活用に努める。また、地域農業改良普及センター段階に設けられる地区推進会議において、企画専門家会議で作成した指導マニュアル等を踏まえて事業の推進方策を検討し、新しい家族経営体の育成に関する夫婦セミナー、情報交換会を積極的に開催する。
(別紙1)
家族経営協定に盛り込まれることが適当と考えられる事項
1.目 的
農業経営の目指す方向、協定を締結する目的等
2.経営計画の策定
家族のライフステージに留意しつつ、中長期の資金計画、施設・農業機械の更新・導入、就業条件の改善等を内容とする「長期農業経営改善計画」、当該計画に基づく毎年度の具体的な行動を内容とする「年度別農業経営計画」等の策定等についての取決め
3.経営の役割分担
農業経営における個人の責任を明確にするため、経営部門の分担等農業経営における役割分担についての取決め
4.収益分配
農業経営から得られる収益の分配方法等についての取決め
5.就業条件
農作業における就業時間、休日・休暇等についての取決め
6.将来の経営移譲
農業後継者への経営移譲の時期・方法等の取決め
7.その他
経営の発展段階等に応じた次の事項等についての取決め
・簿記記帳、青色申告の実施
・労働日誌の記帳
・後継者等の養成、教育
・経営体構成員が新規部門へ経営展開する場合の支援方法
・家族のライフステージを踏まえた中長期の生活設計
・家計費に繰り入れる金額の分担、家事分担等生活面についての取決め
・経営者夫婦の引退後の扶養方法
・その他協定で規定していない事項の決定方法
(別紙2)
家族経営協定書(例1)
(夫婦及び後継者夫婦の4者による場合)
(目的)
第1条 この協定書は、甲(夫) 、乙(妻) 、丙(後継者) 及び丁(後継者の配偶者)が、相互に責任ある経営への参画を通じて、近代的な農業経営を確立するとともに、健康で明るい家庭の建設を目的とする。
(経営計画の策定)
第2条 甲、乙、丙及び丁は協議の上、今後の資金計画、作付計画、施設の導入、就業条件の改善等を内容とする長期農業経営改善計画及び毎年の具体的事項を内容とする年度別経営計画を作成する。
(経営の役割分担)
第3条 経営の部門のうち、○○に係るものについては丙及び丁が、○○以外に係るものについては甲及び乙が主体となり、他の2者と相談の上行うものとする。
(また、簿記記帳については○が、労働日誌の記帳については○が行うものとする。)
(収益分配)
第4条 農業経営から生じた収益について、下記の額を毎月○○日に甲、乙、丙及び丁の個人名義の口座へ振り込むものとする。
甲 ○○万円 乙 ○○万円 丙 ○○万円 丁 ○○万円
また、収益が予想を上回った場合には、賞与として、甲、乙、丙及び丁で協議の上定めた額を臨時に振り込むことができるものとする。
なお、配分額については、農業収益、経営計画に基づく企画労働、農作業労働等の従事状況等を勘案し、毎年1回見直しを行うものとする。
(就業条件)
第5条 就業条件は次のとおりとする。
[1] 1日の労働時間は、甲及び丙は○時間、乙及び丁は○時間を原則とし、農作業の繁閑により甲、乙、丙及び丁で協議の上延長又は短縮する。
[2] 休日は、甲、乙、丙及び丁各々につき原則として月○回とするが、農作業の繁閑、健康状態、他の仕事への従事状況等を踏まえ、甲、乙、丙及び丁で協議の上変更することができるものとする。
また、正月、盆等の休日については、甲、乙、丙及び丁で協議の上定めるものとする。
(将来の経営移譲)
第6条 甲及び乙が有する経営権及び経営用資産については、将来、甲及び乙の合意に基づき丙及び丁に移譲する。
移譲の時期及び方法は、丙及び丁の意向を踏まえながら甲及び乙が十分協議の上定めるものとする。
(その他)
第7条 この協定書に規定されている以外の事項で、決定すべき事項が生じた場合は、その都度甲、乙、丙及び丁で協議の上決定するとともに、必要に応じて立会人に相談の上改訂を行う。
(附則)
[1] この協定書は、平成 年 月 日より実施する。
[2] この協定書の有効期限は、実施の日より○年間とし、当事者から申立てがない限り自動的に更新されるものとする。
[3] この協定書は、5通作成し、甲、乙、丙、丁及び立会人が各1通を保有する。

家族経営協定書(例2)
(夫婦及び後継者の3者による場合)
(目的)
第1条 この協定書は、甲(夫) 、乙(妻) 及び丙(後継者)が、相互に責任ある経営への参画を通じて、近代的な農業経営を確立するとともに、健康で明るい家庭の建設を目的とする。
(経営計画の策定)
第2条 甲、乙及び丙は協議の上、今後の資金計画、作付計画、施設の導入、就業条件の改善等を内容とする長期農業経営改善計画及び毎年の具体的事項を内容とする年度別経営計画を作成する。
(経営の役割分担)
第3条 経営の部門のうち、○○に係るものについては丙が、○○以外に係るものについては甲及び乙が主体となり、他の者と相談の上行うものとする。
(また、簿記記帳については○が、労働日誌の記帳については○が行うものとする。)
(収益分配)
第4条 農業経営から生じた収益について、下記の額を毎月○○日に甲、乙及び丙の個人名義の口座へ振り込むものとする。
甲 ○○万円 乙 ○○万円 丙 ○○万円
また、賞与として、甲、乙及び丙で協議の上定めた額を臨時に振り込むことができるものとする。
なお、配分額については、農業収益、経営計画に基づく企画労働、農作業労働等の従事状況等を勘案し、毎年1回見直しを行うものとする。
(就業条件)
第5条 就業条件は次のとおりとする。
[1] 1日の労働時間は、甲及び丙は○時間、乙は○時間を原則とし、農作業の繁閑により甲、乙及び丙で協議の上延長又は短縮する。
[2] 休日は、甲、乙及び丙各々につき原則として月○回とするが、農作業の繁閑、健康状態、他の仕事への従事状況等を踏まえ、甲、乙及び丙で協議の上変更することができるものとする。
また、正月、盆等の休日については、甲、乙及び丙で協議の上定めるものとする。
(将来の経営移譲)
第6条 甲及び乙が有する経営権及び経営用資産については、将来、甲及び乙の合意に基づき丙に移譲する。
移譲の時期及び方法は、丙の意向を踏まえながら甲及び乙が十分協議の上定めるものとする。
(その他)
第7条 この協定書に規定されている以外の事項で、決定すべき事項が生じた場合は、
その都度甲、乙及び丙で協議の上決定するとともに、必要に応じて立会人に相談の上改訂を行う。
(附則)
[1] この協定書は、平成 年 月 日より実施する。
[2] この協定書の有効期限は、実施の日より○年間とし、当事者から申立てがない限り自動的に更新されるものとする。
[3] この協定書は、4通作成し、甲、乙、丙及び立会人が各1通を保有する。
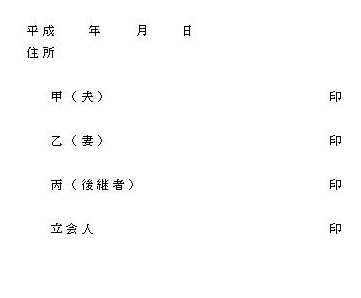
家族経営協定書(例3)
(夫婦の2者による場合)
(目的)
第1条 この協定書は、甲(夫) 及び乙(妻) が、相互に責任ある経営への参画を通じて、近代的な農業経営を確立するとともに、健康で明るい家庭の建設を目的とする。
(経営計画の策定)
第2条 甲及び乙は協議の上、今後の資金計画、作付計画、施設の導入、就業条件の改善等を内容とする長期農業経営改善計画及び毎年の具体的事項を内容とする年度別経営計画を作成する。
(経営の役割分担)
第3条 前条の経営計画に基づく具体的な行動のうち、○○○に係るものについては甲が、○○○に係るものについては乙が主体となり行うものとする。
(また、簿記記帳については○が、労働日誌の記帳については○が行うものとする。)
(収益分配)
第4条 農業経営から生じた収益について、下記の額を毎月○○日に甲及び乙の個人名義の口座へ振り込むものとする。
甲 ○○万円 乙 ○○万円
また、賞与として、甲及び乙で協議の上定めた額を臨時に振り込むことができるものとする。
なお、配分額については、農業収益、経営計画に基づく企画労働、農作業労働等の従事状況等を勘案し、毎年1回見直しを行うものとする。
(就業条件)
第5条 就業条件は次のとおりとする。
[1] 1日の労働時間は、甲は○時間、乙は○時間を原則とし、農作業の繁閑により甲、及び乙で協議の上延長又は短縮する。
[2] 休日は、甲及び乙各々につき原則として月○回とするが、農作業の繁閑、健康状態、他の仕事への従事状況等を踏まえ、甲及び乙で協議の上変更することができるものとする。
また、正月、盆等の休日については、甲、乙及び丙で協議の上定めるものとする。
(将来の経営移譲)
第6条 甲及び乙が有する経営権及び経営用資産を将来移譲するに当たっては、甲及び乙の合意に基づき行うものとする。
(その他)
第7条 この協定書に規定されている以外の事項で、決定すべき事項が生じた場合は、その都度甲及び乙で協議の上定めるとともに、必要に応じて立会人に相談の上改訂を行う。
(附則)
[1] この協定書は、平成 年 月 日より実施する。
[2] この協定書の有効期限は、実施の日より○年間とし、当事者から申立てがない限り自動的に更新されるものとする。
[3] この協定書は、3通作成し、甲、乙及び立会人が各1通を保有する。