水産業協同組合法の一部を改正する法律の運用について
|
本通知の第1の2(2)、4(1)及び6には機種依存文字が含まれているため、当該文字は変換して表示しています。 |
5水漁第3323号
平成5年10月15日
都道府県知事あて
水産庁長官
水産業協同組合法の一部を改正する法律(平成5年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行については、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行について(平成5年10月15日付け水漁第3322号農林水産事務次官依命通達。以下「次官通達」という。)により通達されたところであるが、それらの運用については、下記事項に留意し、遺憾なきを期されたい。
記
第1 資源管理規程制度
1 資源管理規程の内容
(1)対象となる水面の区域
資源管理規程の対象となる水面の区域は、組合員が対象となる水産資源を通常採捕している区域であることが必要である。したがって、管理の対象となる水面の区域は、水産資源の分布域又は産卵場・幼稚仔の生育場とほぼ重なる場合もあり、また、通常採捕されている水面の区域の一部の場合もあるなど水産資源の生物学的特性、利用の方法等により異なる。
(2)対象となる水産資源
資源管理の対象となる水産資源は、漁獲量が以前と比較して減少若しくは減少傾向にある水産資源又は当該漁協等、隣接漁協等が種苗の放流等の増殖行為を行っている水産資源が適当である。
(3)対象となる漁業の種類
資源管理を適切かつ有効に実施するためには、対象となる水面の区域において対象となる水産資源の漁獲努力量が相対的に大きい漁業の種類のすべてが対象となっていることが必要である。したがって、漁業権漁業、知事等許可・認可・承認漁業に限らずいわゆる自由漁業であっても、漁獲努力量が相対的に大きいものは対象とする必要がある。
なお、資源管理規程は「水産動植物の採補の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行う」ために制定されるものであるので、水産動植物の採捕でない養殖は、資源管理規程の対象とはならない。
ただし、第3種区画漁業については、実体上第1種共同漁業と相違ない場合には、資源管理規程の対象として差し支えない。
また、漁業権漁業のみを対象とする場合は、漁業権行使規則で対応が可能であると考えられるので資源管理規程を定める必要はない。
(4)水産資源の管理の方法
水産資源の管理は、網目規制等の漁具、漁法の制限、禁止期間の設定、操業区域の制限、禁止区域の設定、体長制限その他対象漁業の種類及び地域の実情に応じた方法により行うものとする。
なお、資源管理は、資源の利用の合理化に資するために行うものであり、需給・価格の調整を図るために行うものではない。このため、漁獲量の制限、漁船の隻数の縮減等需給又は価格の調整に結びつくおそれのある方法は用いないこととする。
また、資源管理の方法には、ブイ、漁網、魚礁等の施設の設置は含まれない。
(5)資源管理規程の有効期間
資源管理はある程度の期間継続して行わなければ効果は現れないので、漁況、海況等の変化を考慮しても、少なくとも3年から5年間を有効期間とすることが適当である。
(6)過怠金の賦課
過怠金については、その金額等を毎年の総会の議決に委ねることは、資源管理規程が関係組合員の3分の2以上の同意を要することとなっている趣旨から適当ではないので、資源管理規程において定めるよう指導されたい。
2 資源管理規程と資源管理協定、漁業権行使規則又は入漁権行使規則との関係
(1)資源管理協定は、水産資源の自主的な管理を図るという目的は共通するものの、資源管理協定が漁協を含む複数の漁業者団体等の間で締結されるものであるのに対し、資源管理規程は漁協等内部の申合わせであるという点で異なっている。
(2)また、漁業権行使規則又は入漁権行使規則は、漁業法に基づき漁協等が管理する漁業権又は入漁権に基づき、組合員が当該漁業権又は入漁権の内容となっている漁業を営むことに関して漁協等が定める規則であり、その内容は漁業権又は入漁権を行使する者の資格及び漁業の方法その他遵守すべき事項を定めることとされている。これに対して、資源管理規程は、漁協等による水産資源の自主的な管理を図るための制度であり、[1]漁業法に基づく公的な規制措置ではなく、自主的に設けられたものであること、[2]水産資源の管理を目的とすること、[3]漁業権漁業に限らず、組合員の営むすべての漁業が対象となることという点において、漁業権行使規則とは異なる。
(3)資源管理規程は、これらの資源管理協定、漁業権行使規則又は入漁権行使規則が存する場合にあっては、これらの協定等に従った内容のものでなければならないこととなっており、例えば、漁業権行使規則により規制されている事項について、その規制の内容を緩和するような内容のものはこれに従った内容のものとはいえない。
なお、これらの協定等が存する場合とは、設定しようとする資源管理規程の対象となる水面の区域の全部又は一部の水面において、漁業者団体等又は当該組合によって協定等が締結又は設定されている場合をいう。従って、当該組合が協定等を締結又は設定していなくても、漁業者団体等が当該資源管理規程の対象となる水面の区域の全部又は一部の水面において協定等を締結又は設定している場合は、当該協定等の内容に従わなければならない。
また、既に設定されている資源管理規程の水面の区域を含む水面において、新たに、協定等が締結又は設定された場合において、当該協定等の内容が当該資源管理規程の内容より規制が強化される場合にあっては、当該協定等の内容に従うために資源管理規程の変更等の手続が必要となるので留意されたい。
3 遊漁者と資源管理規程
漁協等は、従来から、水産資源の保護培養のために、種苗の放流や漁場の整備など積極的な増殖行為を行ってきたことに加え、今後は、資源管理規程を定め、組合員の行う漁業についての自主規制を行うこととなったが、このような努力が遊漁者にも理解され、その協力の下に資源管理を進めていくことが重要である。
このためには、漁業者側の活動を遊漁者にも十分認識してもらうことが必要であるので、市町村の広報等による遊漁者に対する協力要請を推進するとともに、漁協等においても遊漁者の理解を求める取組を促進するよう指導されたい。
4 資源管理規程の認可等
(1)認可又は変更の認可の申請
認可の申請に当たっては、申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
[1] 資源管理規程
[2] 資源管理規程の設定又は変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
[3] 関係組合員の同意を得たことを証する書面
[4] 資源管理規程が、資源管理協定又は漁業権行使規則等が存する場合にあっては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従った内容のものであることを証する書面
[5] 資源管理規程の変更の場合にあっては、資源管理規程に記載された資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続に従って行われたことを証する書面
[6] その他行政庁が必要と認める事項を記載した書面
(2)認可の基準
「関係法令に違反するものでないこと」で、特に注意を要するものは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)との関係であり、漁獲量の制限、漁船の隻数の縮減等需給又は価格の調整に結びつくおそれのある方法は、同法に違反するおそれがあるので、認可することは適当ではない。
また、行政指導や海区漁業調整委員会の指示に違反する場合は、関係法令に違反するものとはいえないが、認可することは妥当ではないので、これらに違反することのないよう適切に指導されたい。
(3)資源管理規程の認可の取消
資源管理規程が認可の基準に該当しないと認められるときは、行政庁は、認可を取り消すことができる。認可の取消は、資源管理規程が認可の基準に該当しなくなったときに直ちに行うものではなく、基準に適合するよう指導を行ってもなお該当しない場合に行うものとする。
(4)資源管理規程の変更又は廃止
資源管理規程の変更又は廃止については、その手続を資源管理規程に記載しなければならないこととされているが、この場合の手続は、例えば、変更又は廃止する場合には、関係組合員の同意を得る前に学識経験者等の意見を聞くものとする旨の規定、漁業種類ごとの協議会を開催して意見を聴取する旨の規定などが考えられる。
これらの手続を経た上で、認可時と同様の手続により変更の認可を受けるものとされており、この場合の変更の認可の基準は、当初の認可の基準と同様である。
また、資源管理規程を廃止するときは、資源管理規程に記載された廃止の手続によって行われたことを証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5 資源管理規程例について
資源管理規程の具体的な例については、別紙資源管理規程例を参照されたい。
資源管理規程の内容は、疑義が生じないように、正確に定める必要がある。特に、漁業種類ごとに規制の内容が異なる場合には、正確を期すよう指導されたい。
6 次の事項について、漁協等に対し周知徹底するとともに、必要な指導を行われたい。
[1] 改正法により新たに漁協等の事業として位置づけられた「水産資源の管理に関する事業」は何ら施設の整備を伴うものではなく、また、組合員以外の者の行う各種の海洋における活動(海洋性レクリエーション活動を含む。)に何ら制約を及ぼすものではないこと。
[2] 資源管理規程は、漁協等内部の規定であって、組合員又は所属員以外の者に対しては何ら制約を及ぼさないものであること。
[3] 資源管理規程の設定によって、漁業に関する新たな権利が生ずるものではなく、また、港湾法その他の法律による諸規制、事業の実施、海洋レクリエーション活動の振興その他の漁業以外の水面の利用を妨げるものではないこと。
[4] 資源管理規程の認可を受けることによって、従来からの漁業を営む権利等のほか、新たな財産上の価値、評価を漁協等に帰属させるものではないこと。
第2 信用事業実施権能の拡充
1 有価証券の貸付け、金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い、保護預り、両替の業務が新たに行えることとなったが、その実施に当たっては、別に改正される模範定款例の規定するところにより定款に明記し、適正な実施に努めるよう指導されたい。
なお、有価証券貸付については、漁協及び水産加工業協同組合にあっては、特定組合に限り、これらの事業を行えることとしたので、定款変更の認可に当たっては十分留意されたい。
2 員外利用制限の撤廃
今回拡充された信用事業に係る員外利用については、組合員の利用分量と同量という制限が適用されないこととなったが、その運用に当たっては、員外の利用が組合員の利用を妨げることのないよう指導されたい。
3 両替業務について
両替業務を行う場合は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第14条第1項の規定により大蔵大臣の認可が必要であるので、定款変更の認可に当たっては十分留意されたい。
4 農林中金等金融機関の業務代理の範囲の拡大について
今回の法施行と併せて、漁協等が行う農林中金等金融機関の業務代理として、新たに、信託業務を行う銀行の業務代理を行うことができることとされたところである(水産業協同組合法の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関を定める件(昭和48年9月3日大蔵省・農林水産省告示第12号)の一部改正)が、これは、本体業務として信託業務を行う能力のない漁協又は信漁連が、組合員をはじめ地域住民等の信託ニーズに対応するため、信託業務を営む銀行(具体的には農林中金の子会社が考えられる。)の業務代理を行うことができることとされたものである。
第3 事業譲渡規定の整備
事業譲渡の具体的手続については、平成2年水協法改正運用通達(水産業協同組合法の一部を改正する法律の運用について(平成2年12月25日付け2水漁第4737号水産庁長官通達))第6の2に準じて適正に事業譲渡が行われるよう十分指導されたい。
また、漁協事業基盤強化総合対策要綱の制定について(平成4年7月10日付け4水漁第1882号農林水産事務次官依命通達)にも即しつつ、適切な指導に努められたい。
マ ア ナ ゴ 資 源 管 理 規 程 (例)
○○漁業協同組合は、水産業協同組合法第15条の2の規定に基づき、次のとおりマアナゴに関する資源管理規程を定める。
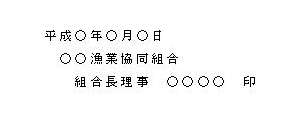
1 資源管理規程の対象となる水面の区域
(例1)
○○町××灯台から正東の線と△△灯台から正東の線との間の海域のうち沖合1km以内の水面の区域
(例2)
次のアからエまでの点を順次に結んだ線により囲まれた区域
ア ○○岬突端から□□□度××分、◇◇◇mの点
イ ○○岬突端から□□□度××分、◇◇◇mの点
ウ ○○岬突端から□□□度××分、◇◇◇mの点
エ ○○岬突端から□□□度××分、◇◇◇mの点
2 資源管理規程の対象となる水産資源
マアナゴ
3 資源管理規程の対象となる漁業の種類
アナゴ篭漁業、○○漁業、××漁業、・・・・
4 水産資源の管理の方法
(1)網目の規制
(2)漁法の制限
(3)禁止期間
(4)操業区域の制限
(5)禁止区域
(6)体長制限
(7)その他の制限
(注)対象となる漁業種類ごとに定めること。
5 資源管理規程の有効期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
6 資源管理規程に違反した組合員に対する過怠金に関する事項
この資源管理規程に違反した組合員については、違反した当日のアナゴ水揚げ金額の全額を過怠金として徴収する。
7 資源管理規程の変更又は廃止の手続
この資源管理規程を変更、又は廃止する場合には、法令に定める手続のほか、総会の議決の前に、3の漁業を営む組合員以外の組合員であって、2の水産資源を採捕する組合員の2分の1以上の同意を得なければならない。
8 その他
この資源管理規定に違反した組合員については、6の過怠金を課するほか、4の各号に掲げる事項の種類に応じて次の期間について停船又は出漁の停止とする。
4の(1)に違反した場合・・・ 日間




