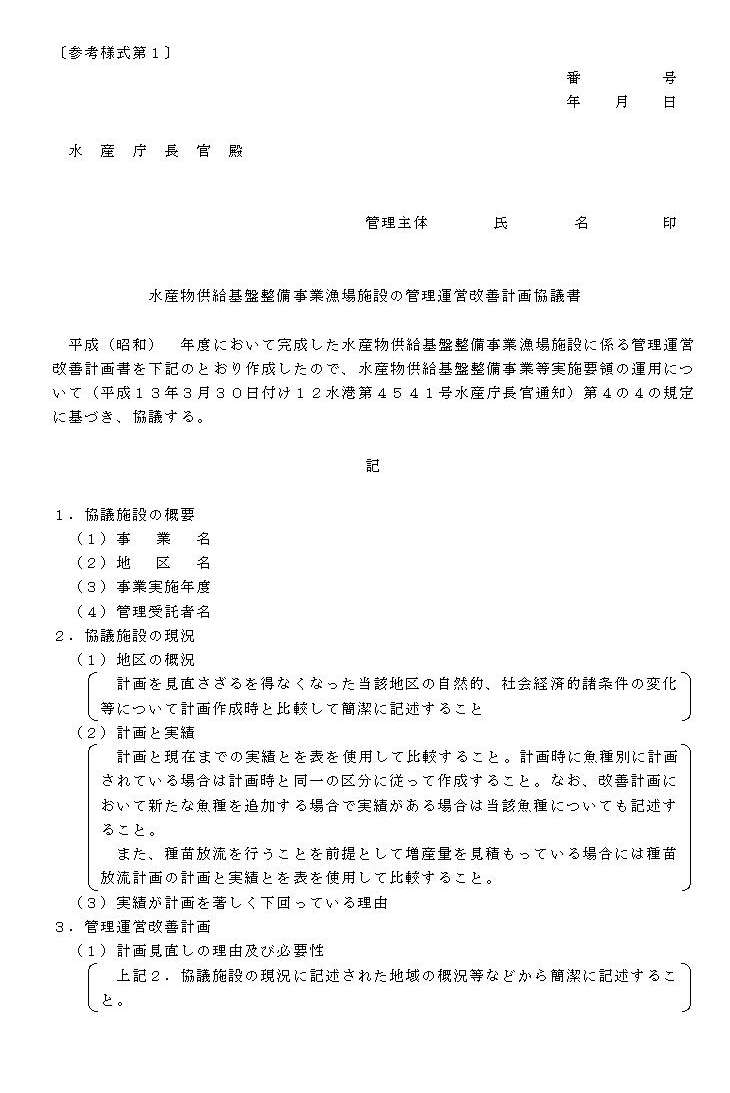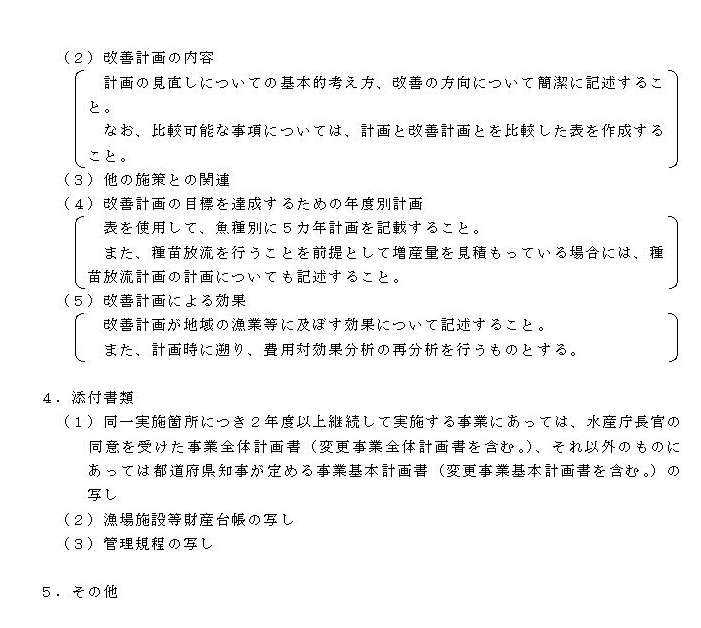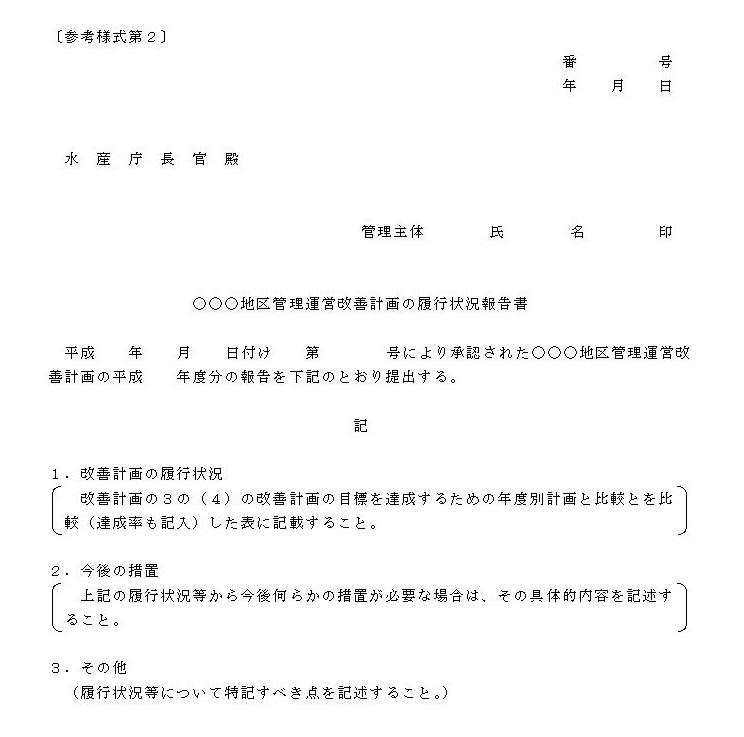水産物供給基盤整備事業漁場施設の管理運営改善計画について
12水港第4711号
平成13年3月30日
都道府県水産基盤関係主務部長あて
水産庁漁港漁場整備部長
「水産物供給基盤整備事業等実施要領の運用について」(平成13年3月30日付け12水港第4541号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)第5の4管理運営の変更の取り扱いについて下記のとおり定めたので、その取扱について遺憾のないようにされたい。
なお、「沿岸漁場整備開発事業施設の管理運営改善計画について」(平成10年4月8日付け10-3216水産庁資源生産推進部長通知)は廃止されたので、併せて通知する。
なお、貴管下関係市町村への通知については、貴職からお願いする。
12水港第4711号
平成13年3月30日
瀬戸内海漁業調整事務所長
九州漁業調整事務所長 あて
沖縄総合事務局農林水産部長
社団法人 全国沿岸漁業振興開発協会会長
水産庁漁港漁場整備部長
水産物供給基盤整備事業漁場施設の管理運営改善計画について
このことについて、水産物供給基盤整備事業等実施要領の運用について(平成13年3月30日付け12水港第4541号水産庁長官通知)第5の4の管理運営の変更の取扱について別添のとおり定め、関係都道府県水産基盤関係主務部長あて通知したので御了知願いたい。
水産物供給基盤整備事業漁場施設等の管理運営改善計画について
平成13年3月30日付け12水港第4711号
水産基盤関係主務部長あて(水産庁漁港漁場整備部長通知)
一部改正 平成14年4月1日付け13水港第4270号
1.管理主体(実施主体)の長は、その管理する漁場施設(水産物供給基盤整備事業等実施要領(平成13年3月30日付け12水港第4457号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第2の漁場の施設をいう。)及び漁場環境保全創造事業により設置又は造成された施設について、自然的・社会経済的な諸条件の変化等のため著しく低利用になっているもの、未利用に至っているもの等やむを得ない場合にあっては、漁場施設の効率的な利用を図るため、対象魚種又は種苗放流計画の変更等管理運営計画の見直しを行い、参考様式第1により5年を目途に目標の達成を図ろうとする管理運営改善計画(以下「改善計画」という。)を作成して水産庁長官に協議(事業主体が都道府県知事以外の者については、都道府県知事を経由して)するものとする。
この場合の著しく低利用になっているものとは、生産計画数量の計画に対する実績の割合が50%以下のものとする。また、管理運営計画とは実施要領第4により水産庁長官が承認した事業基本計画又は同意を得た全体事業計画及び運用通知第4の3の(2)に定める管理規程に定められた施設の管理運営に関するものをいう。
2.改善計画の作成に当たっては、施設の基本的な規模・能力に沿ったままで見直すことを原則とするが、一層効率的な利用を図るための増築、改築、移築、移転又は改良はやむを得ないものとする。この場合、改善計画の中にその旨を記入すれば、運用通知第4の5の(3)に規定する漁場施設等増設(又は改築、移築、移転、改良)届は必要ないものとする。
3.なお、自然的・社会経済的な諸条件の変化等が著しく、改善の目途がたたない等やむを得ない事情により改善計画を作成することが困難な場合については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号、以下「適正化法」という。)第22条の規定に基づき、農林水産大臣の承認を得て、それぞれの場合に応じ最も適当と考えられる処分を行うこととする。
4.管理主体の長は、毎年度(改善計画作成後5年間)、参考様式第2により水産庁長官に改善計画の履行状況を報告(事業主体の長が都道府県知事以外の者については、都道府県知事を経由して)するものとする。
5.都道府県知事は、改善計画期間中に改善計画に沿った利用が期待しがたい場合は、現地調査等更に適切な指導を行うこととする。
6.管理主体の長は、改善計画終了後も低利用等についての改善の目途がたたない場合については、上記3に準じて「適正化法」第22条の規定に基づき、農林水産大臣の承認を得て、それぞれの場合に応じ最も適当と考えられる処分を行うこととする。
附則
沿岸漁場整備開発事業施設の管理運営計画について(平成10年4月8日付け10ー3216水産庁資源生産推進部長通知、以下「旧通知」という。)は廃止する。ただし、この通知の施行前に旧通知の規定により行われることとされている報告については、なお、従前の例による。