みなみまぐろの採捕を目的として遠洋かつお・まぐろ漁業を行う際の遵守事項について
本通知の6の(4)には機種依存文字が含まれているため、当該文字は変換して表示しています。
変換前の文字をご確認される場合はこちらをご覧下さい。(PDF:126KB)
16水管第3657号
平成17年3月11日
関係都道府県 水産主務部長あて
水産庁資源管理部長
我が国における、平成17年漁期(平成17年3月1日~平成18年2月28日)のみなみまぐろの採捕を目的とした遠洋かつお・まぐろ漁業の操業については、別紙写しのとおり業界団体及び漁業者あて通知したので、御了知ありたい。
16水管第3657号
平成17年3月11日
関係漁業者 あて
水産庁資源管理部長
みなみまぐろの採捕を目的として遠洋かつお・まぐろ漁業を行う際の遵守事項について
平成16年10月に開催された、みなみまぐろ保存委員会第11回年次会合において、平成17年3月1日から平成18年2月28日までの間の我が国のみなみまぐろの国別漁獲割当量は、6,065トンとされたところである。ついては、我が国における平成17年漁期(平成17年3月1日~平成18年2月28日)のみなみまぐろの操業に当たっては、関係法令を遵守するとともに、別途指示を行った場合を除き、別添の「みなみまぐろの採捕を目的として遠洋かつお・まぐろ漁業を行う際の遵守事項」に記載した事項を遵守されたい。
16水管第3657号
平成17年3月11日
社団法人 全国近海かつお・まぐろ漁業協会会長理事 あて
水産庁資源管理部長
みなみまぐろの採捕を目的として遠洋かつお・まぐろ漁業を行う際の遵守事項について
平成16年10月に開催された、みなみまぐろ保存委員会第11回年次会合において、平成17年3月1日から平成18年2月28日までの間の我が国のみなみまぐろの国別漁獲割当量は、6,065トンとされたところである。ついては、我が国における平成17年漁期(平成17年3月1日~平成18年2月28日)のみなみまぐろの操業に当たっては、関係法令を遵守するとともに、別途指示を行った場合を除き、別添の「みなみまぐろの採捕を目的として遠洋かつお・まぐろ漁業を行う際の遵守事項」に記載した事項を遵守するよう、貴傘下漁業者に対し指導の徹底方よろしくお願いする。
みなみまぐろの採捕を目的として遠洋かつお・まぐろ漁業を行う際の遵守事項
1. みなみまぐろ操業の届出
みなみまぐろの採捕を目的として操業する場合には、業界が定めた操業開始日までに、所属業界団体を通じて「みなみまぐろ操業届出書」(別紙様式1)を水産庁資源管理部遠洋課かつお・まぐろ漁業班(以下「かつお・まぐろ漁業班」という。)に届け出ること。また、届出の内容に変更すべき事項が生じた場合も同様に届け出ること。なお、業界団体に所属している場合には、所属業界団体を通じて届け出ること。
2. 入・出域報告
「遠洋かつお・まぐろ漁業につき報告すべき事項及び方法を定める件」(平成3年2月15日農林水産省告示第197号)で定めた海域(以下「指定海域」という。)(別添1)に操業を目的として入域又は出域した場合は、「遠洋かつお・まぐろ漁業によるみなみまぐろの漁獲数量等の報告について」(平成3年2月21日付け3-2225 水産庁海洋漁業部長通達)に定められている「遠洋かつお・まぐろ漁業によるみなみまぐろの漁獲数量等の報告要領」に従い、3日以内にかつお・まぐろ漁業班あて、入・出域報告を行うこと。
3. みなみまぐろ操業禁止の海域
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第17条別表第2の遠洋かつお・まぐろ漁業の項第24号の規定に基づき、農林水産大臣が定める日(以下「操業終了日」という。)以降は、同省令で定める操業禁止の海域(別添2)から速やかに退去すること。
4. 衛星通信を利用した船位通報システム(VMS)による報告
上記2の指定海域(別添1)で操業を行う場合は、衛星通信(インマルサット)を利用した船位通報システムにより確認される漁船の位置を「船位通報システムによる位置報告について」(別添3)に定める方法により、かつお・まぐろ漁業班あて報告すること。
5. 漁獲報告
(1)旬別の漁獲数量報告
上記2の指定海域(別添1)において操業する場合及び指定海域以外の海域においてみなみまぐろを採捕した場合には、「遠洋かつお・まぐろ漁業によるみなみまぐろの漁獲数量等の報告について」(平成3年2月21日付け3-2225 水産庁海洋漁業部長通達)に定められている「遠洋かつお・まぐろ漁業によるみなみまぐろの漁獲数量等の報告要領」に従い、旬別のみなみまぐろ漁獲数量を当該の旬末から3日以内に、かつお・まぐろ漁業班あて報告すること。なお、みなみまぐろの採捕を目的としない操業においても報告しなければならない。
報告の遅延及び漁獲数量の誤りについては、いずれも行政処分の対象となるので十分留意すること。
(2)即時漁獲情報調査計画(RTMP)
上記1の操業開始日から上記3の操業終了日までの間に、上記2の指定海域(別添1)において操業を行う場合は、船舶の概要(別紙様式2-1)を提出するとともに、ミナミマグロRTMP報告書(別紙様式2-2)を毎日ファクシミリによりに送信すること。
なお、外国200海里内において操業する場合も、RTMP報告書を提出しなければならないことに留意すること。
ただし、外国の現地法人に貸し渡された遠洋まぐろはえ縄漁船が、貸し渡し期間中に行う操業については、この限りではない。
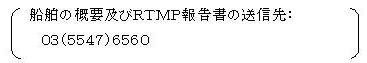
(3)漁獲成績報告書
「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」(昭和38年農林省令第5号)第28条第1項の規定に基づき、日本又は外国の港に寄港した場合には、寄港後30日以内に漁獲成績報告書をかつお・まぐろ漁業班あて提出すること。
(4)まぐろはえ縄漁業における混獲生物等調査
操業中の混獲実態を把握するため、「かつお・まぐろ漁業における混獲生物等調査について」(平成10年3月30日付け10-2606 水産庁資源管理部長通達)で定められている「かつお・まぐろ漁業混獲生物調査票」を作成の上、漁獲成績報告書に添付してかつお・まぐろ漁業班あて提出すること。
6. 操業上の留意事項
(1) 漁獲枠の有効利用及び操業秩序の安定を図るため、業界が自主的に定めた規制措置を遵守すること。
(2) みなみまぐろの親魚資源の回復を図るため、小型のみなみまぐろの漁獲を回避するように努めること。ただし、小型のみなみまぐろを漁獲した場合は、これを船体に取り込むこと。
(3) 水産庁の漁業監督官から漁船の位置報告等の指示を受けた場合は、速やかに従うこと。
(4) 海鳥の偶発的捕獲の回避
- [1] みなみまぐろの採捕を目的として操業する場合は、遠洋かつお・まぐろ漁業の許可の制限条件とされている海鳥の捕獲を回避するための吹き流し装置(トリポールストリーマー)を使用すること。
- [2] 「はえなわ漁業における海鳥の偶発的捕獲の削減のための措置について」(平成13年2月23日付け12水管第3385号 水産庁長官通知)で通知した、海鳥の混獲回避のための措置の実施に努めること。
- [3] 外国の200海里水域内で操業する場合には当該沿岸国の規定に従うこと。
7. 漁獲物の取扱い
(1) 平成17年3月1日から平成18年2月28日までに漁獲されるみなみまぐろについては、外国200海里水域内での漁獲物と公海での漁獲物が識別できるカラーテープを一尾毎に装着すること。なお、装着部位は当該各船の判断によることとするが、日本での陸揚げの際に確実に識別できる状態にしておくこと。
(2) 平成17年2月28日現在で、みなみまぐろを積載していた漁船は、同日までの積載状況を「みなみまぐろ積載状況報告書」(別紙様式3)により、平成17年3月25日までに水産庁資源管理部遠洋課清水漁港駐在官事務所(以下「清水駐在官事務所」という。)あて報告すること。
(3) 漁獲物(クロマグロ、ミナミマグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、メカジキに限る。)の陸揚げ又は転載を行うにあたっては、当該陸揚げ又は転載を行う10日前までに、必要な届出を行うこと(指定省令第60条の2)。
8. 漁獲物の数量検査
みなみまぐろの陸揚げを行う際には、(社)日本海事検定協会又は(財)新日本検定協会による漁獲物の数量検査を受け、同機関が発行する検査証明書を陸揚げ終了後10日以内に、清水駐在官事務所あて報告すること。
なお、水産庁は、陸揚げする漁船又は冷凍運搬船を無作為に指定して、漁業監督官による陸揚漁獲物の数量検査を行うので、検査を受ける際には当該漁業監督官の指示に従い、求めに応じて操業日誌等の必要書類を提出すること。
9. 外国200海里内操業上の留意事項
外国の漁業に関する管轄権が及ぶ水域内で操業する場合には、当該国の入漁許可を受けるとともに、当該国の発給する許可証に記載されている制限又は条件を遵守すること。当該操業条件の違反は、日本国内においても行政処分の対象となるので十分留意すること。
〔連絡先〕
水産庁資源管理部遠洋課 かつお・まぐろ漁業班
住所:東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話番号:03-3591-6582 ファクシミリ番号:03-3595-7332
水産庁資源管理部遠洋課 清水漁港駐在官事務所
住所:静岡県静岡市清水区入船町4番18号(海事ビル)
電話番号:0543-51-0186 ファクシミリ番号:0543-51-0187




