特集1 緑茶(1)
|
日本人にとって親しみやすい飲み物である緑茶は、茶葉を摘んでから発酵させないでつくられます。
多種多様で幅が広く、奥の深い緑茶の世界をご案内します。 |
味わいや香りもさまざま 緑茶の種類
|
緑茶は、栽培や製造方法などによって、さまざまな種類に分かれ、味や香り、淹れ方も異なってきます。
代表的な緑茶をご紹介しましょう。 |
 |
煎茶 日本でもっとも一般的に飲まれている緑茶。細く丸くよれていて、針のような形状が特徴。嗜好に応じてブレンドされ、種類も豊富。うまみと苦みのバランスを重視したものが多い。 |
| 深蒸し煎茶 通常の煎茶より、生葉の蒸し時間を2~3倍長くしたもので形状が細かい。淹れると濃い緑色の茶となり、渋みがなく、濃厚な甘みが特徴。 |
 |
 |
玉露 日光をさえぎった茶園で栽培された茶葉を使った高級茶。渋みが少なく、お茶本来のうまみを存分に味わえる。独特の青海苔のような「覆い香」も特徴。 |
| 抹茶 鮮やかな緑色が特徴的な粉末状のお茶。てん茶を石うすで挽いたもの。最近は抹茶を使ったお菓子や料理も人気で、海外でも食材としても親しまれている。 |
 |
 |
ほうじ茶 煎茶や番茶などを強火で煎じてつくる。香ばしい香りとともに、スッキリとした飲み口となっている。カフェインが少なめで刺激が抑えられた、やさしい口当たり。 |
| 番茶 新芽が伸びて硬くなった茶葉や夏以降の茶葉から作られる。煎茶より渋みが少なく、あっさりとした飲みやすい味。食後の口直しとして出されることも多い。 |
 |
 |
茎茶 茎の部分のみを集めたお茶。独特の甘みがあり飲みやすく、お茶の初心者でも淹れやすい。 |
| 玄米茶 煎茶や番茶に炒った玄米を混ぜているため、独特の香ばしい香りや味が特徴。渋みが少ないので、高温で淹れて、香りを引き出す飲み方がおすすめ。 |
 |
 |
釜炒り製玉緑茶 生葉を蒸さず、釜で炒って作る。釜炒りならではの甘い香りがあり、すっきりとした味わい。 |
| てん茶 日光をさえぎった茶園で栽培された柔らかい新芽を揉まずに乾燥して作られる。これを粉末状にしたものが抹茶。 |
|
粉末茶 機械などで煎茶を細かく粉末状にしたもの。寿司屋などで出る「上がり」でおなじみ。お湯に溶けやすく、茶殻も出ないため簡単に飲める。 |
|
蒸し製玉緑茶 茶葉が丸まった形から、釜炒り製玉緑茶とともに「ぐり茶」とも呼ばれる。じっくりと蒸しているため、渋みが少ない。 |
|
緑茶(煎茶)の作り方は3工程
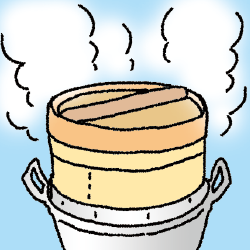 |
蒸す 摘んだ茶葉や茎を蒸気で蒸し、発酵を止めます。この蒸し時間によって、味や香りなどが変わります。 |
 |
揉む 揉む工程では、「粗揉(そじゅう)」、「揉捻(じゅうねん)」、「中揉(ちゅうじゅう)」を経て、最後に形を整える「精揉(せいじゅう)」を行います。 |
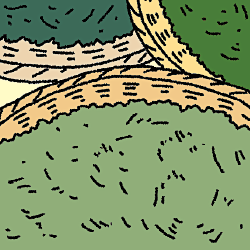 |
乾かす 熱風で乾燥させ、水分を5パーセントほどに。この状態を「荒茶」といい、仕上げ加工を経て製品化されます。 |
取材・文/相川いずみ
撮影/野口雅裕、船津祐太朗
イラスト/あべかよこ
撮影/野口雅裕、船津祐太朗
イラスト/あべかよこ




