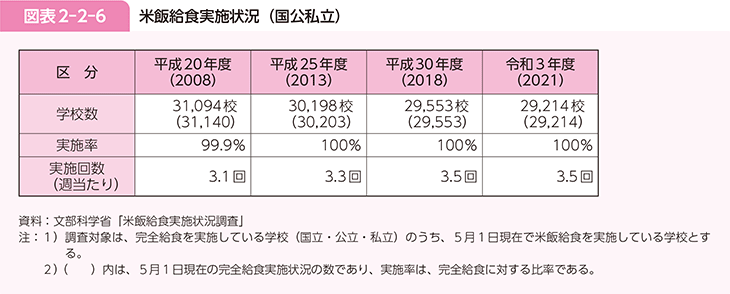3 米飯給食の着実な実施に向けた取組
米飯給食は、子供が伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を身に付けることや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めること等の教育的意義を持つものです。令和3(2021)年度には、完全給食を実施している学校の100%に当たる29,214校で米飯給食が実施されており、約922万人が米飯給食を食べています。また、週当たりの米飯給食の回数は3.5回となっています(図表2-2-6)。
農林水産省では、次世代の米消費の主体となる子供たちに、米飯を中心とした「日本型食生活(*1)」を受け継いでもらうため、米飯給食のより一層の推進を図っています。令和5(2023)年度は、令和4(2022)年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援として、各学校が米飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付を実施しました。
なお、献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ様々な食に触れることができるように配慮することが大切です。
*1 ごはん(主食)を中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、お茶など多様な副食(主菜・副菜)等を組み合わせた、栄養バランスに優れた食生活
事例:学校給食における地場産物の活用について
福井県若狭町(わかさちょう)
福井県若狭町では、地域の農林水産物の有効活用、生産者の所得向上、地域内のネットワークづくり等を目標に、学校給食における地場産物の活用を検討していました。一方、若狭町は中小規模の農業・漁業者が中心で収量が不安定なため、必要量の安定的な確保が難しく、学校給食における地場産物の活用を進めることが困難でした。
そこで、令和4(2022)年度に地産地消コーディネーター派遣事業を活用し、課題の解決に向けた取組を行いました。
具体的には、町広報誌上で、学校給食の特集を組み、給食での地場産物活用への理解と納入に協力できる農業者・漁業者への呼びかけを行うとともに、農業者・漁業者、小売店、JA、県農林部、福祉事業者、栄養士等を集め、地場産物の活用に向けた意見交換会を実施し、新規食材の掘り起こしや地場産給食推進の組織づくり等について話合いを行いました。
取組の結果、新たに4品目の地場産物の使用開始、3者の納入事業者の増加等、学校給食での地場産物の活用推進につながる結果となりました。さらに、令和5(2023)年度は新たに1品目が追加される等、地産地消コーディネーターの派遣を契機に地場産物活用の取組がより一層広がっています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4551)
ダイヤルイン:03-3502-1320