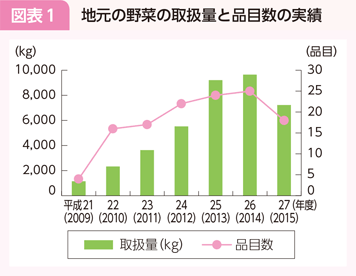3 米飯給食の着実な実施に向けた取組
米飯給食は、子供が伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を身に付けることや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めることなどの教育的意義を持つものです。
平成27(2015)年度には、完全給食(*1)を実施している学校のほぼ100%にあたる29,925校で米飯給食が実施されており、約930万人が米飯給食を食べています。また、週当たりの米飯給食の回数は3.4回となっています(図表2-2-4)。
なお、文部科学省では、平成21(2009)年に通知(*2)を発出し、米飯給食の実施回数が週3回未満の地域・学校については週3回程度、週3回以上の地域・学校については週4回程度など新たな目標を設定し、実施回数の増加を図ることを促すなど、国全体として週3回以上とすることを目標としています。
また、農林水産省では次世代の米消費の主体となる子供たちに、米飯を中心とした日本型食生活やその味覚を受け継いでもらうため、米飯学校給食のより一層の推進を図っています。
平成28(2016)年度は、昨年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援として、各学校が米飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付を実施しました。また、小中学校の学校給食関係者に対し、米飯給食の実態調査を行うとともに献立作りに役立つ事例集を作成・配付しました。
*1 給食内容がパン又は米飯(これに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食のこと
*2 「学校における米飯給食の推進について(通知)」(平成21年3月31日20文科ス第8023号文部科学省スポーツ・青少年局長)
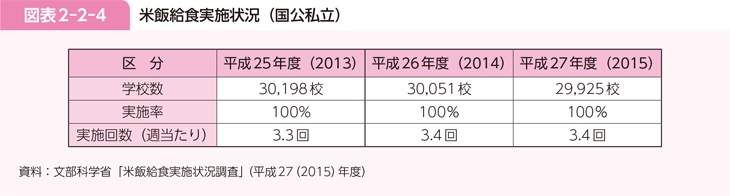
事例:社会的課題に対応するための学校給食の活用事業について
山形県
文部科学省では、食品ロスの削減、地産地消の推進及び食文化の継承といった食をめぐる諸課題に対し、学校給食の活用を通して課題の解決に資する取組を推進するため、平成28(2016)年度から「社会的課題に対応するための学校給食の活用事業」を開始しました。
山形県では、文部科学省から本事業の委託を受け、「地産地消の推進」と「食品ロスの削減」をテーマに事業を実施しました。実施に当たっては、平成28(2016)年4月に町内の中学校が統合し、新たに自校給食方式の大規模校として開校した高畠町立高畠中学校において取り組みました。
【地産地消の推進】
大規模校においても、可能なものは全て地元農産物を学校給食に活用できるよう、新たに地元生産者による農産物供給組織を立ち上げ、地区単位に設定した集荷所に農産物を搬入してもらい、それを集荷して回り学校に納入する仕組みを構築しました。成果としては、近くに搬入できることで生産者が農産物を納入しやすくなり、大規模校の学校給食でも多くの地元農産物を使用することができました。今後は、供給組織の組合員の更なる確保や、より多様な品目の栽培等により、更に地産地消が推進できるものと考えられます。
【食品ロスの削減】
農産物供給組織の生産者から、販売ができない「規格外」の農産物も納入してもらい、学校給食に活用しました。活用したものは、サイズの小さい玉ねぎやじゃがいも、形や大きさが不揃いな人参など様々で、その使用量は8月~12月で200kgを超えました。また、中学校の生徒が「食品ロス削減レシピ」の開発に取り組みました。人参やごぼうを皮ごと入れた「冬野菜カレー」や、大根を余すことなく使用した「大根菜飯・大根のそぼろあん煮」など、生徒のアイディアからいくつかの献立が実現しました。成果としては、廃棄せざるを得なかった規格外の農産物を学校給食で活用したことで、食品ロス削減に貢献できました。さらに、食品ロス削減レシピの開発や献立としての提供を通じ、生徒の食品ロス削減への意識が高まり、生産者が栽培した大切な農産物を余さず食べることで食や生産者に感謝する心が育まれました。一方、調理効率が落ちる食材の使用には調理員の理解が不可欠であるため、日頃からの協力体制づくりが重要であることが分かりました。
山形県としては、今回の事業をモデルケースとして、県内に事業成果を普及していきたいと考えています。
事例:地域一体となって取り組む学校給食の取組
枕崎市立学校給食センター

鹿児島県の薩摩半島の南端に位置する枕崎市には、本土最南端の始発・終着駅「枕崎駅」があり、友好都市である本土最北端の稚内市「稚内駅」とレール一本でつながっています。この縁がきっかけとなり、お互いの特産品である「かつお節」と「昆布」をテーマにした交流事業「コンカツプロジェクト」において、「和だし」を生かした献立づくりと地元食材を活用した学校給食の充実に取り組んでいます。
1 学校給食センターにおける地産地消の取組
枕崎市立学校給食センターでは、現在、小学校4校、中学校4校の約1,730食を提供しています。地元で栽培された野菜や果物、米をはじめ、かつお、かつお節、枕崎牛、枕崎茶、鹿籠豚(かごぶた)など、地産地消を生かした学校給食の提供に努めています。

平成27(2015)年度 納入実績
給食センターでは、献立計画に沿った食材調達を実現するために、納入業者と連携した納入体制を構築しています。中でも地元の野菜や果物については、地元納入業者と地域の生産者グループ(給食検討部会)から納入しています。「次世代を担う子供たちに地元で作ったおいしい新鮮な野菜を食べてもらいたい」との思いから、平成21(2009)年、地元の高齢者で結成された桜馬場地区農産物生産出荷協議会が、地産地消の一環として給食検討部会を設立しました。ここでは市農政課が窓口となって開催される月1回の野菜供給検討会で、給食センターから翌月の使用野菜の予定表を示し、納入可能な食材について検討を行っています。例年の納入実績を参考にしながら、収穫時期に合わせて献立を作成しています。
2 「ふしの日」の取組
枕崎市では、「枕崎鰹節の良さをもっと広げたい」と、平成24(2012)年に、毎月24日を「ふしの日」、11月24日を「いいふしの日」として制定しました。枕崎が誇るべき食材「かつお節」を枕崎の子供たちが大切にしてほしいとの願いから、給食でもかつおだしを味わうすまし汁やポテトのおかかチーズ焼きなど、かつお節を使った様々なメニューを提供しています。
3 地元の野菜を生かした食育の取組
各学校で地元の野菜について子供たちの理解を深めるため、生産者の協力を得て交流授業や交流給食を行っています。栄養教諭が仲介役となり、学級担任と生産者との連携を図った上で、生産者から食材等の実物を使って講話を行っています。生産者から直接話を聞くことで、子供たちが食べ物を大事にし、食材の生産に関わる人々への感謝の心が育まれるなど、食に関する意識を高めることができていると感じています。
4 取組の成果と課題
枕崎市が地産地消の取組に力を入れていることもあり、学校給食への地元の野菜の使用割合は増加傾向にあります。また、野菜生産者以外の地元業者の方々からも、かつお節を作る工程で廃棄される腹皮(はらがわ)(かつおの腹身の部分)を活用したコロッケや、希少価値の高い鹿籠豚など、新しい食材を紹介していただくこともあり、地元の食材を使用した献立も多様化してきました。給食センターが地域と連携することで、子供たちはもちろん、学校、家庭、地域が一体となったつながりのある食育が取り組まれてきていると感じています。
課題としては、野菜を納入する給食検討部会の高齢化が進み、今後も継続していくためには後継者の育成が必要です。また、台風の影響を受けやすい地域であるため、安定した野菜の供給を行うことは難しく、平成27(2015)年度の取扱量は減少する結果となりました。自然と向き合いながら、常に柔軟な対応ができるよう、生産者と密に連携を図る必要があります。
今後更に、未来ある子供たちが地域食材の素晴らしさに気付き、地元を誇れるような豊かな人間性を育むことが、枕崎の食文化の継承へとつながっていくと考えます。給食センターが地産地消の拠点となれるよう、地域と一体となった学校給食の充実に取り組んでまいります。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974