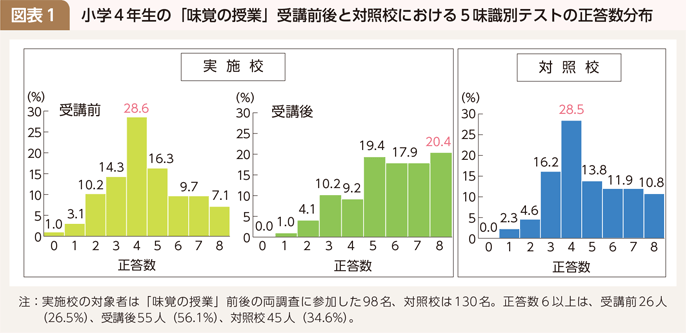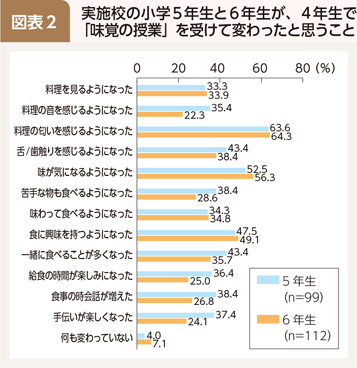第3節 食育推進の取組等に対する表彰の実施
食育に関して、特に優れた取組を表彰し、その内容を情報提供することにより、食育が国民運動として、一層推進されることが期待されます。
農林水産省では、他の地域においても参考となり得るような若い世代の食生活の改善に取り組んだボランティアについて、「食育推進ボランティア表彰」を実施しました。平成28(2016)年度は、44団体と2個人、大学生等を主体にした12団体の総計58件の推薦があり、10の優秀事例に対し、第11回食育推進全国大会において農林水産大臣から表彰を行いました。また、平成29(2017)年度には「食育推進ボランティア表彰」の対象を拡大した新たな表彰として、農林漁業、食品製造・販売等その他の事業活動、教育活動又はボランティア活動を通じ、食育の推進に取り組む者による取組が全国で展開していくことを目的として、食育活動表彰を行うこととしており、これに向けた実施要領を平成28(2016)年度に定めました。
さらに、学校給食等における地場産物の活用の促進を図るため、「地産地消給食等メニューコンテスト」を実施し、学校給食・社員食堂、外食・弁当等において地場産物を活用したメニューの内容の工夫、生産者との交流、年間を通じた地場産農林水産物の活用の継続等を行っている者(11件)を農林水産大臣賞等として選定・表彰しました。
文部科学省では、学校給食の普及と充実に優秀な成果を挙げた学校、共同調理場、学校給食関係者、学校給食関係団体について、文部科学大臣表彰を実施しています。平成28(2016)年度は、学校25校、共同調理場2場が「学校給食優良学校等」として、また、23名の学校給食関係者が「学校給食功労者」として表彰されました。
また、基本的な生活習慣の定着に向けた取組の一層の推進を図るため、「早寝早起き朝ごはん」運動などの子供の生活習慣づくりに関する活動のうち、特色ある優れた実践を行い、地域全体への普及効果が高いと認められるものに対し、文部科学大臣による表彰を行いました。
厚生労働省では、栄養改善と食生活改善事業の普及向上等に功労のあった個人、地区組織等について、栄養関係功労者厚生労働大臣表彰を実施しています。平成28(2016)年度は、功労者として271名、功労団体として49団体が表彰されました。また、国民の生活習慣を改善し、健康寿命をのばすための運動「スマート・ライフ・プロジェクト」が掲げる4つのテーマ(適度な運動、適切な食生活、禁煙、健診・検診の受診)を中心に、従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための優れた取組等をしている企業、団体、地方公共団体を表彰する「第5回 健康寿命をのばそう!アワード」の生活習慣病予防分野では、応募のあった108件の中から18の企業、団体、地方公共団体が表彰されました。さらに、平成27(2015)年度より、「健やか親子21(第2次)」のスタートに合わせ、母子保健分野を加え、食育を含む母子の健康増進を目的とする優れた取組を行う企業・団体・地方公共団体を表彰しています。平成28(2016)年度は、応募のあった34件のうち、10の企業、団体、地方公共団体が表彰されました。
事例:奈良県内の4つの大学サークルが連携 ~「ヘルスチーム菜良(なら)」~
(平成28(2016)年度食育推進ボランティア表彰 受賞)
ヘルスチーム菜良協議会(奈良県)

「ヘルスチーム菜良」は、奈良県内の4大学(畿央大学・近畿大学・帝塚山大学・奈良女子大学)の200名を超える管理栄養士養成課程の学生で構成する食育ボランティアサークルです。若い世代や地域住民に向けて食生活改善や健康づくりを応援するため、平成21(2009)年10月に結成しました。
協議会結成前は大学ごとに活動を行っていましたが、せっかく同じ目的を持った仲間がいるのだから、もっと幅広く地域資源を活用し、地域の食育関係者との関係・連携を活かした活動ができないかと考え、4大学連携の協議会が生まれました。4大学連携で、県・市町村や関係団体が実施するイベントに参加するほか、企業との連携による奈良県産の材料にこだわったお弁当等の開発、県と連携した若い世代向けの啓発媒体の作成など、幅広い活動を展開しています。また、毎年実施する4大学での交流・発表会は、お互いの取組を情報交換することにより、新たな活動への刺激につながっています。このように、協議会を結成することで、それぞれ主体的な活動をしてきた4大学がつながって大きなパワーを発揮できるようになりました。
特にチーム結成当初から続いている活動の一つに、高校生への食育があります。高校の文化祭へ出向いて実施する展示では、クイズやゲーム形式など、高校生が楽しく学べるよう工夫しています。また、オープンキャンパスの際に大学を訪れる高校生へ向けて、食事のバランスチェックやその結果に基づく栄養相談を行うなど、食を振り返ってもらう機会を提供しています。高校生とは年齢が近いこともあり、親しみを持って聴いてもらえていると感じています。
さらに、奈良県が実施する「県内大学生が創る奈良の未来事業」に応募した政策提案が採択・事業化され、野菜を摂取することの大切さについての課外授業を高校生に向けて行うなど、行政との連携も積極的に行っています。大学生自身が県の担当者や関係者等と連絡調整を行い、準備を主体的に行うことで、卒業後に管理栄養士として活躍するために必要な企画提案力を身に付けることにもつながっています。
これらの活動が評価されることで、管理栄養士を目指す他の学生の意識向上や、地域全体の食育に対する機運の醸成にも貢献しています。今後も、管理栄養士養成施設で得た知識や技術と大学生ならではのアイディアをいかして、行政・企業・各種団体と連携した食育の実践活動に取り組んで行きたいと考えています。
事例:五感を育み、食べる楽しさを伝える ~「味覚の一週間」®~
「味覚の一週間」事務局

「味覚の一週間」は、フランスで行われてきた27年にも及ぶ味覚教育の活動であり、日本でも平成23(2011)年から同様の取組が始まりました。6年目となる平成28(2016)年は、10月17日から23日までの一週間に、日本各地の小学校やレストラン等において、五感を使って味わうことの大切さや食の楽しみを体感できる様々な取組を展開しました。
活動の中心である「味覚の授業」は、和・洋・中の料理人や生産者等が講師としてボランティアで小学校を訪れるものであり、平成28(2016)年には約300人の講師が全国189校、約1万4千人の児童に向けて実施しました。以下の要素で構成することを基本としつつ、講師はそれぞれの専門分野や個性をいかした体験型学習を展開しています。
「味覚の授業」の基本構成
- 五感の働きと5つの基本の味(甘味・塩味・酸味・苦味・うま味)を教えること
- 五感で味わうことによって広がる食の豊かさを教えること
- 食品の産地や生産方法について情報を伝えること
- 仲間と「おいしさ」を共有することの楽しさを教えること
- 講師自身の経験や料理に対する思いを伝え、「食」に興味を持つきっかけを作ること
新宿区立四谷小学校では、5年生の2クラスに向けて「味覚の授業」を開催しました。始めに5つの味について「しょっぱい食べ物ってどんなものがあるかな?」などとシェフが児童に問いかけながら、味の基本について説明し、児童たちの味に対する興味を引き出します。そして実際に塩、米酢、砂糖、チョコレートの味や香り、食感を確認してもらい、児童たちの味覚を研ぎ澄ませます。
味の基本を学んだ後は、シェフから配られた3種(たまねぎ、レモン、チョコレート)の小さなタルトを、児童たちが目で観察し、香りを嗅ぎ、ゆっくりと噛みしめ、それぞれの味の違いや食材の特徴を五感を使って感じ取っていました。また、児童同士で味の感想を伝え合うことにより、食べる楽しみを広げるのに欠かせない表現力も磨かれます。
続いて次の時間には、フランス料理のシェフが野菜スープの調理実演を行いました。ガスコンロの炎を見ながら火加減をコントロールすること、野菜を炒めたり煮たりする時の香りや音の変化を感じ取ることなど、料理をする時にも五感が大切であることを児童たちに伝えました。
また、東京学芸大学附属世田谷小学校では、5年生の1クラスと3年生の3クラスに向けて「味覚の授業」を開催しました。和食の料理人が訪れたクラスでは、教室でかつお節を削り、出汁をとる実演が行われました。児童たちは、堅いかつお節に触れ、削り節の香りを嗅ぎ、出汁のうま味を味わいました。この授業の中では、食べ物の生産や調理などに携わった人に感謝して食べることの大切さも伝えています。
さらに、公立大学法人福岡女子大学と連携して「味覚の授業」の効果を把握するための調査を行っています。福岡県篠栗(ささぐり)町立北勢門(きたせと)小学校では、平成24(2012)年から毎年4年生に「味覚の授業」を実施しています。平成27(2015)年には「味覚の授業」前後に調査を行いました。5味識別テスト(甘味・塩味・酸味・苦味・うま味の低濃度溶液と水3、計8検体を識別)の結果、受講前における正答数の最頻値は4、受講後には8(満点)で、正答数6以上の児童が約2倍に増え、味の識別能力が向上したことがわかりました。なお、隣接する未実施校(対照校)4年生の正答数の最頻値は4であり、北勢門小学校(実施校)における「味覚の授業」受講前と同様の結果となり、受講後の結果との間に有意差が認められました。
また、北勢門小学校の5・6年生が、4年生の時に受けた「味覚の授業」後に変わったと思うことについて調査した結果、嗅覚や味覚、触覚、視覚、聴覚を使うようになったと答えた児童が多く、「味覚の授業」が五感を使って料理を味わうきっかけになったことが分かりました。また、その他の食行動に関しても、“食に興味を持つようになった”、“一緒に食べることが多くなった”、“会話が増えた”、“手伝いが楽しくなった”など、「味覚の授業」が食への関心を高め、食行動に好影響を与えたことが分かりました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974