1 管理栄養士・栄養士の養成・活用
厚生労働省等では、食生活や健康づくりに関する専門的な知識を有し、食育を推進する上で重要な役割を担う者として管理栄養士等の養成を行っています。管理栄養士等は、「栄養士法」(昭和22 年法律第245号)に基づく資格であり、栄養士は都道府県知事から、管理栄養士は厚生労働大臣から免許が交付されています。
平成31(2019)年4月1日現在、栄養士養成施設数は300 校(平成30(2018)年度302校)であり、そのうち管理栄養士養成施設数は149校(平成30(2018)年度148校)です。栄養士免許は、平成30(2018)年度18,037件(平成29(2017)年度18,551件)、管理栄養士免許は令和元(2019)年12月現在で10,291件(平成30(2018)年12月現在10,119件)交付されています。管理栄養士等は、学校、保育所、病院、社会福祉施設、介護保険施設、保健所、市町村保健センター、食品産業、大学、研究機関等の様々な場において食生活に関する支援を行っています。
特に、都道府県や市町村においては、地域での食育の推進が着実に図られるよう、行政栄養士の配置を推進しており、令和元(2019)年度においては、6,877人(平成30(2018)年度6,610人)となっています。行政栄養士は、都道府県や市町村の食育推進計画の策定や食育に関する事業の企画・立案・評価、食生活改善推進員などのボランティアの育成、国民運動としての食育の推進が図られるよう関係団体や関係者との調整等を行っています。
公益社団法人日本栄養士会では、会員である約5万人の管理栄養士等が、全国で、乳児期から高齢者までの食育を推進していくための活動を実施しています。
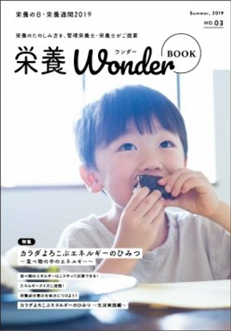
栄養ワンダーブック
公益社団法人日本栄養士会は、平成28(2016)年に全ての人々の健康の保持・増進を実現するために、「栄養の日(8月4日)」、「栄養週間(8月1日~8月7日)」を制定しました。「栄養の日・栄養週間2019」では、「栄養を楽しむ―栄養障害の二重負荷(Double burden of malnutrition)の解決をめざす―」を統一テーマとして様々な事業を実施しました。「2019年度全国栄養士大会」では、管理栄養士と栄養士が一致して取り組むべき課題を協議し、対応や実践の方法を共有しました。また、「栄養ワンダー2019」では、全国各地で講話や栄養相談などのイベントを開催しました。国民20万人を対象に、栄養の重要性と管理栄養士等の職能の認知・普及を目的として、対象者に応じて「栄養の楽しみ方」や「若年女性のやせと高齢者の低栄養、中年男性の肥満」の解決に向けたプレゼンテーションを行い、栄養ワンダーブックを配布しました。
また、「健康日本21(第二次)」で取り上げている身体活動・運動は、生活習慣病の予防のほか、社会生活機能の維持及び向上並びに生活の質の向上の観点で重要であることから、ジュニアアスリートの保護者と指導者を対象とした研修会を、平成28(2016)年度から開催しており、最終年度である令和元(2019)年度は11か所で開催しました。また、野菜をたくさん食べて健康で生き生きとした生活を送るための支援として、都道府県栄養士会と協力して、各地で栄養相談・食生活相談事業を行っています。
さらに、食育推進や特定健康診査・特定保健指導、介護予防などの活動拠点として、全都道府県栄養士会に設置している「栄養ケア・ステーション」の更なる機能充実を図るとともに、拠点数の拡大に向け、平成30(2018)年度に「栄養ケア・ステーション認定制度」をスタートさせ、管理栄養士による地域の在宅医療・健康・栄養・食育等の問題に対する取組を進めています。
加えて、管理栄養士等のキャリア支援を目的として生涯教育を実施し、到達度に応じた認定を行っています。その中では、関連学会等と共同で、特定・専門的な種類の業務に必要とされる高度の専門的知識・技能を身に付けた管理栄養士等を認定しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974





