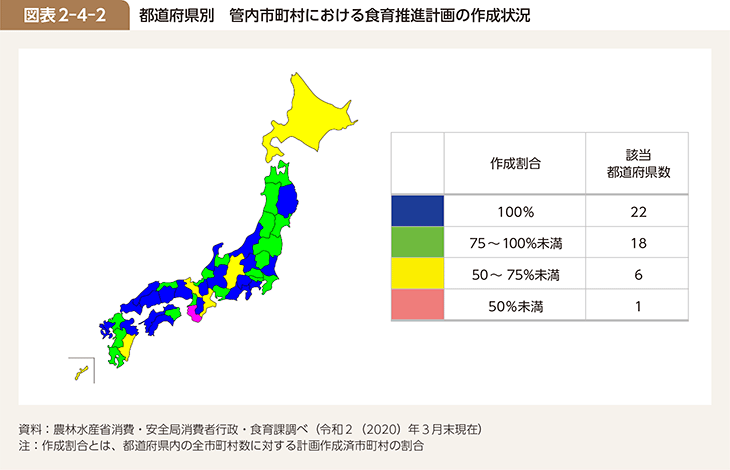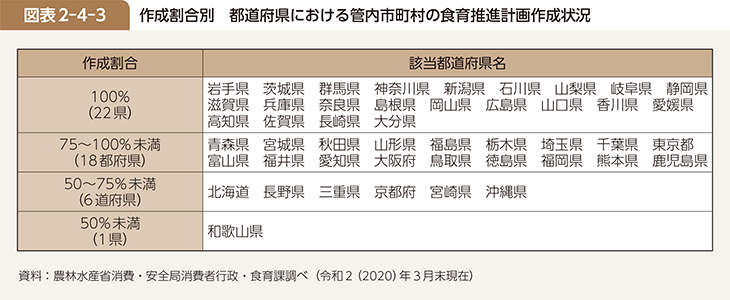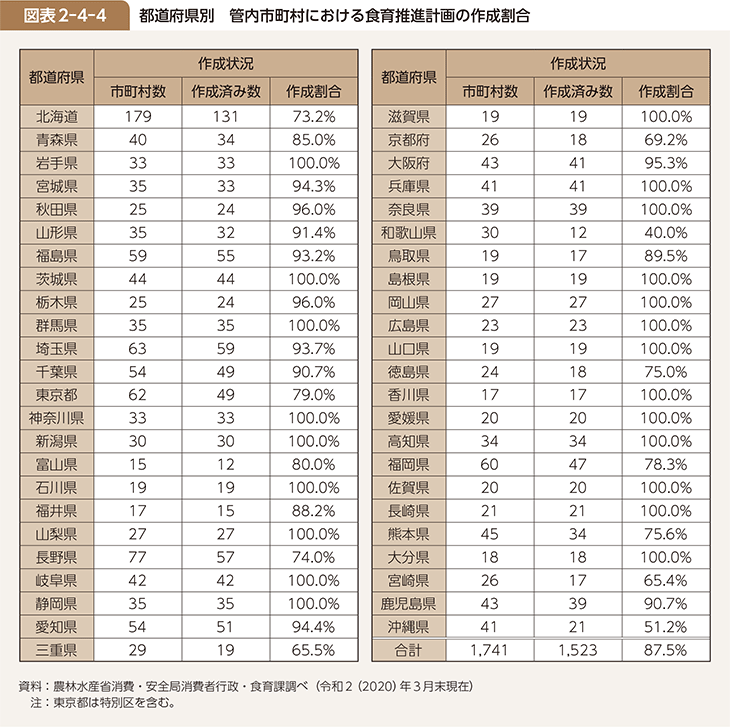3 市町村食育推進計画の状況
令和2(2020)年3月末現在、1,741市町村のうち1,523市町村で食育推進計画が作成され、全国における作成市町村の割合は87.5%となりました。また、市町村食育推進計画の作成割合が100%の都道府県は22県でした。さらに、作成割合が50%に満たない都道府県は2県から1県に減り、目標達成に向けた対応が進んでいます(図表2-4-2、2-4-3、2-4-4)。
農林水産省では、平成30(2018)年9月に市町村食育推進計画の作成・見直しに当たっての留意事項や参考となる情報を取りまとめたほか、情報提供や研修会等へ講師を派遣するなど、都道府県と連携して市町村計画作成の支援を進めています。
事例:地域の連携による食育推進活動~食でつながる みんなのさばえ~
(第3回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞)
元気さばえ食育推進会議(福井県)
「元気さばえ食育推進会議」は、「食でつながる みんなのさばえ」を基本理念に、鯖江市(さばえし)の食育推進計画「元気さばえ食育推進プラン」を踏まえ、食に関わる各種団体や個人が連携して鯖江市(さばえし)の食育を総合的に推進することを目的として、平成23(2011)年7月に結成されました。消費生活アドバイザーや学校・保育所関係者、料理店や菓子店、農家、JA、野菜ソムリエ等、市内在住の各委員と行政が連携して、包括的な体制で成長過程にある子供たちへの食育や、若い世代への情報発信を中心に食育事業の推進に取り組んでいます。
取組のうち、学校給食畑活動では、児童が農家ボランティアの指導の下、学校の授業と連携した野菜の植付けや収穫体験を行います。また、「地場産学校給食の日」等に農家ボランティアと一緒に給食を食べ、感謝の気持ちを伝え、交流しています。
さらに、市内の全小学校において、栄養教諭が各委員とのつなぎ役となり、様々な体験を取り入れた食育授業も開催しています。授業では、講師が鯖江(さばえ)産の食材を実際に持ち込み、児童に間近で見て触れてもらいます。自分たちが暮らしているまちでは、どのようなものが収穫できるのか、児童がふるさとを知り、郷土愛を育むことにつながるよう工夫しています。低学年では地場産食材で菓子を作る「お菓子の授業」、中学年では五味(甘味、酸味、塩味、苦味、うま味)について学ぶ「味覚の授業」、高学年では和食や出汁について学ぶ「うま味の授業」を行っています。普段の授業とは違った体験型の取組を行うことで子供の記憶に残るようにするとともに、家庭での会話を通じた食育にもつながるようにしています。また、市内の全小学校で、鯖江市(さばえし)の地場産業である越前(えちぜん)漆器を給食用食器として取り入れています。
さらに、小中学校での食育の取組を、義務教育が終了した高校生にもつなげていくため、市内の高校と連携し、高校生に対する食育も推進しています。高校生自らが農家の指導の下、農作業を行い、収穫した農産物を使用した献立を作成し、実際の飲食店で提供する「高校生カフェ」の取組等を通して、食への意識や関心を高めています。
事例:「宮崎の豊かな食で育む「健康長寿日本一」」を目指した食育・
地産地消活動
みやざきの食と農を考える県民会議(宮崎県)
宮崎県では、県民の豊かな食生活を実現するため、平成13(2001)年に農林水産業に関する幅広い関係機関・団体が集い、「みやざきの食と農を考える県民会議」(以下「県民会議」という。)を設立しました。県民会議では、自然の恵みや生産者への感謝の心を育む「食育」と、宮崎県の豊かな食材を生かした「地産地消」の取組を行っており、毎月16日を「ひむか(*1)地産地消の日」と定め、家庭や学校、生産や流通の現場における地産地消及び食育の普及、定着に取り組んでいます。
県民会議では、平成18(2006)年度から、これらの活動に取り組んでもらう人(「食育ティーチャー」という。)を登録しており、現在、126人が登録されています。食育ティーチャーは、農業者や漁業者をはじめ、管理栄養士、食生活改善推進員、調理師、野菜ソムリエ、グリーンツーリズム実践者等、多彩な顔ぶれで、県内各地域で食育活動や地産地消の実践活動に取り組んでいます。
具体的な活動内容としては、子供たちを対象とした地元食材を活用した料理教室、子育て世代・高齢世代等ライフステージに応じた料理教室や若い世代への郷土料理教室等を行っており、近年は食品ロス削減に向けた料理教室にも取り組み始めています。
また、平成27(2015)年度から、県内の料理人等を講師として味の基本となる五味(甘味、酸味、塩味、苦味、うま味)について学び、味わうことの楽しみに触れる体験型学習「味覚の授業」に取り組んでおり、令和元(2019)年度は、県内小学校44校、1,927人の児童が授業を受けました。
さらに、直売所は、新鮮な農産物等を消費者が身近に購入できる地産地消推進の拠点としての重要な役割を果たしていることから、県内の農林水産物直売所の運営支援にも取り組んでいます。直売所アドバイザーを交えた店舗巡回で商品陳列や販促方法のアドバイスを行うとともに、テーマを設定した課題解決セミナーの開催等により、店舗の魅力を向上させるための後押しを行っています。
*1 「みやざきの食と農を考える県民会議」では、毎月16日を、「1」ひ、「6」む、「日」か、「ひむか地産地消の日」とし、「地産地消」と「食育」を実践する日と定めている。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974