4 農林漁業や食生活、食料の生産、流通、消費に関する統計調査等の実施・公表
農林水産省は、食育を推進する上で必要となる農林漁業の姿や食料の生産、流通、消費に関する基礎的な統計データを広く国民に提供し、食育に対する国民の理解増進を図っています。主なものとしては、米や野菜など主要な農畜産物の生産や流通に関する調査、魚介などの水産物の生産や流通に関する調査を実施し、公表しています。
また、食育に関する国民の意識を把握するために、「食育に関する意識調査(*1)」や「食生活及び農林漁業体験に関する調査(*2)」を実施し、調査結果を公表しています。
環境省では、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)(*3)」として、化学物質のばく露が子供の健康に与える影響を明らかにするため、平成22(2010)年度から10万組の親子を対象に、子供が13歳に達するまで質問票によるフォローアップ等を行っています。その一環として食生活を含めた生活環境についても調査しており、その研究結果を公表しています。
*1 食育に関する意識調査(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki.html
*2 食生活及び農林漁業体験に関する調査(農林水産省):https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taiken_tyosa/jissen-datesyu.html
*3 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)(環境省):https://www.env.go.jp/chemi/ceh/index.html(外部リンク)
コラム:「平成30年国民健康・栄養調査」結果の概要
「国民健康・栄養調査」は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、毎年実施しています。
平成25(2013)年度から開始している「健康日本21(第二次)」では、国民の健康の増進の推進に関する基本的方向の1つとして、「栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善」を盛り込み、ライフステージや性差、社会経済状況等の違いに着目し、対象集団ごとの特性やニーズ、健康課題等の把握を行っています。
平成30(2018)年の国民健康・栄養調査は、所得等社会経済状況を重点項目として実施しました(*1)。
世帯の所得別(200万円未満、200万円以上400万円未満、400万円以上600万円未満、600万円以上)に世帯員の生活習慣等の状況を比較した結果は、以下のとおりです(図表1)。
<所得と食生活の状況について>
・食塩摂取量は、世帯の所得が600万円以上の世帯員に比較して、男性では200万円未満の世帯員で有意に少なかった。
・野菜摂取量は、世帯の所得が600万円以上の世帯員に比較して、男性では200万円未満及び200万円以上400万円未満の世帯員で有意に少なかった。
・果物摂取量が100g未満の者の割合は、世帯の所得が600万円以上の世帯員に比較して、女性では200万円未満の世帯員で有意に高かった。
<所得とその他の生活習慣の状況について>
・喫煙者、健診未受診者、歯の本数が20歯未満の者の割合は、世帯所得が200万円未満の世帯員で高い一方、歩数の平均値は、200万円未満の世帯員では少なかった。
「国民健康・栄養調査」では、引き続き実態の把握を行い、様々な取組の推進に役立つデータを発信していきます。
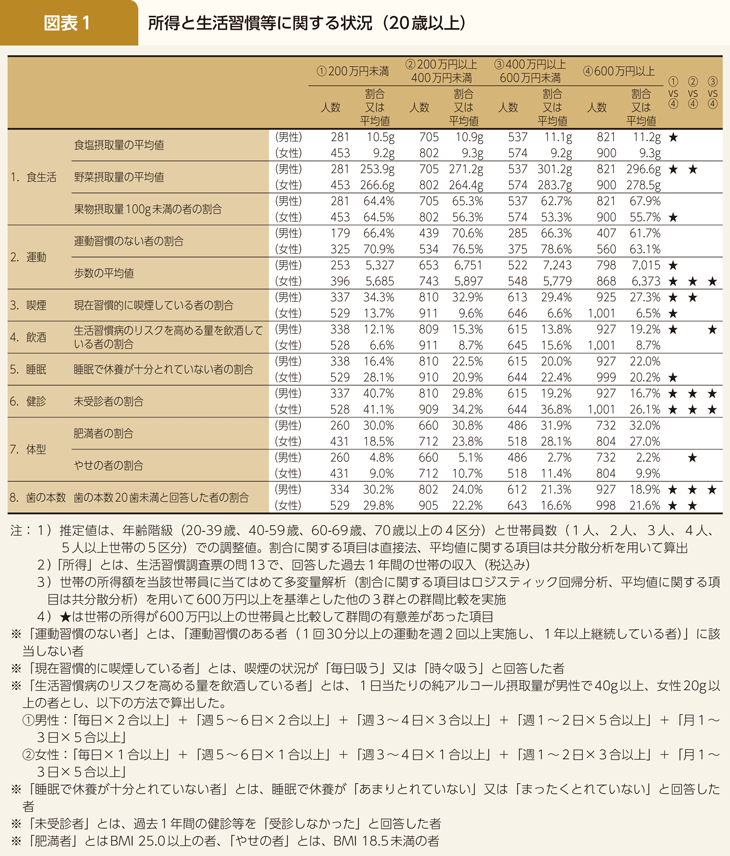
*1 平成30年「国民健康・栄養調査」の結果(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08789.html(外部リンク)
事例:私たちの食品選択で持続可能な社会づくりを
-「食の窒素フットプリント」に着目した研究成果から
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究センター(茨城県)
全ての生物は窒素を摂取せずに生きることはできず、私たちも毎日、たくさんの窒素(たんぱく質)を摂取しています。その一方、摂取量の何倍もの窒素が、食料が生産から加工を経て人間の口に入るまでの過程(フードチェーン)で、環境中に排出されています(図表1)。排出された窒素は、水圏の汚染・富栄養化や地球温暖化、オゾン層の破壊など世界各地で深刻化する環境汚染の原因となります。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究センター(以下「センター」という。)では、日本の食料消費に伴う「食の窒素フットプリント」の長期変遷を推計しました。「食の窒素フットプリント」とは、食料の消費など、食事に関わる様々な人間活動により、どのくらいの窒素が使われ、環境に負荷を与えたかを知ることができる指標です。「食の窒素フットプリント」の値は食品によって異なり、畜肉では高く、植物性食品では低い傾向があります。
センターの行った推計によると、供給された窒素量が同じ平成27(2015)年と昭和45(1970)年の「食の窒素フットプリント」を比較してみると、昭和45(1970)年の方が19%低いことがわかりました(図表2)。昭和45(1970)年の方が、植物性食品によるたんぱく質の供給量が多く、かつ、バランスよく供給されていました。さらに、食品ロスの削減で11%、必要以上のたんぱく質の摂取を抑制する(食べ過ぎない)ことによって22%の窒素負荷の削減につながることも示唆されました。すなわち、食品ロスを減らすこと、そして健康的でバランスの良い食事をすることで、食事によって排出される窒素の大幅な削減につなげることができ、環境問題解決の一助になると考えられます。
このように、「食の窒素フットプリント」を使えば、食品ごとの環境負荷を評価でき、消費者が食品を選ぶ際に役立てることができます。国連の持続可能な開発目標(SDGs)の目標12で「つくる責任つかう責任」と示されているように、持続可能な生産と消費のパターンを確立するためには、生産から消費の各段階における努力や工夫が求められています。
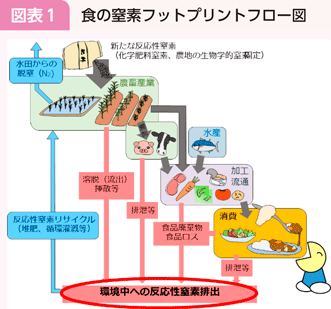
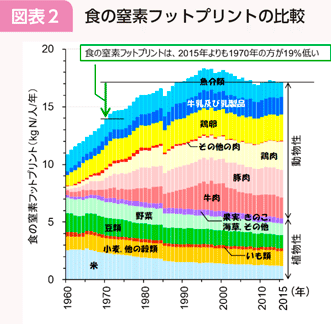
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974




