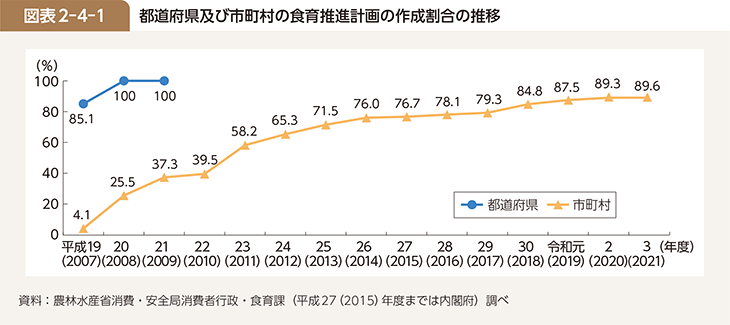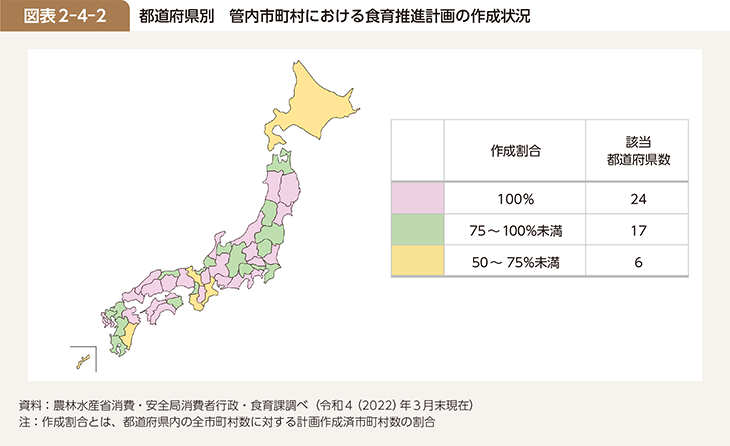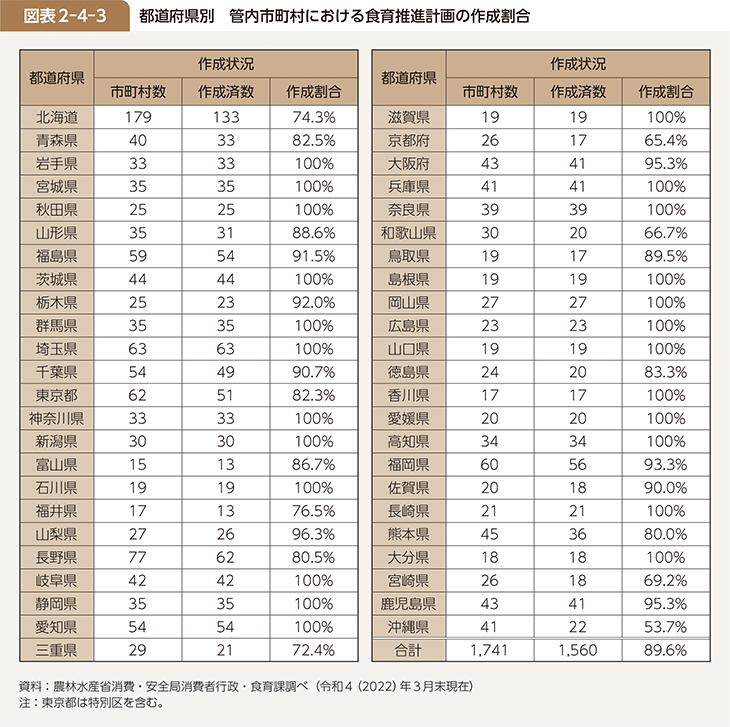2 食育推進計画の作成状況
基本計画の作成時、食育推進計画の作成割合を、平成22(2010)年度までに、都道府県は100%、市町村は50%以上とすることを目指して取組を始めました。その結果、都道府県の食育推進計画の作成割合は、目標設定当時の85.1%(47都道府県中40都道府県)から、平成20(2008)年度調査において100%に到達し、目標を達成しました。
一方、市町村における食育推進計画の作成割合は、目標設定当時の4.1%(1,834市町村中75市町村)から、令和4(2022)年3月末現在では、89.6%(1,741市町村中1,560市町村)となっています(図表2-4-1)。
また、市町村食育推進計画の作成割合が100%の都道府県は24県でした。目標達成に向けて更なる対応が必要です(図表2-4-2、2-4-3)。
農林水産省では、平成30(2018)年9月に市町村食育推進計画の作成・見直しに当たっての留意事項や参考となる情報を取りまとめたほか、情報提供や研修会等へ講師を派遣するなど、都道府県と連携して市町村計画作成の支援を進めています。
事例:スマホでも・紙面でも・お店でも
いつでもどこでも健康な食に触れることができるまちづくり
(第5回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞)
東松島市(ひがしまつしまし)食育推進協議会(宮城県)
東松島市食育推進協議会は、令和3(2021)年3月に策定された第3期東松島市食育推進計画の下、多様な関係者と連携し、様々な媒体を用いて取組を行っています。
同計画は、「新しい生活様式」に対応した食育にも言及しており、情報発信のデジタル化の推進として、市の公式YouTubeチャンネルにおける動画の配信や、市の防災メールを活用した食育に関する情報発信、民間の料理レシピサイトへの地元の食材を用いたレシピの掲載等を実施しています。これらの実施に当たっては、動画の企画は食育関係団体や薬剤師会等から、動画の編集作業は地域おこし協力隊や地元中学校のコンピューター部の生徒から、レシピの掲載は病院や福祉施設から協力を得るなど、様々な関係者と連携しながら取組を進めています。
また、オンラインで情報発信を行うだけでなく、幅広い世代に情報を届けられるよう、世代ごとにその特性を踏まえて作成したテキスト「東松島食べる学校」を地域の健康づくり活動等で配布するなどし、「食」を学ぶ機会を作っています。
さらに、情報発信だけにとどまらず、市内の飲食店と連携し、「スマートミール(*1)」を外食又は持ち帰りの弁当として提供することで、住んでいるだけで、そして滞在しているだけで健康な食を営める環境づくりに取り組んでいます。
こうした取組により、市民が意識せずとも自然と健康になれる食環境づくりを進めていき、これからも、郷土の恵みを生かしながら、地域ぐるみで食育を推進していきたいと考えています。
*1 「健康な食事・食環境」コンソーシアムから認証を受けた、科学的根拠に基づく、健康に資する要素を含む、栄養バランスのとれた食事、すなわち主食・主菜・副菜がそろい、減塩にも配慮した食事の通称
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974