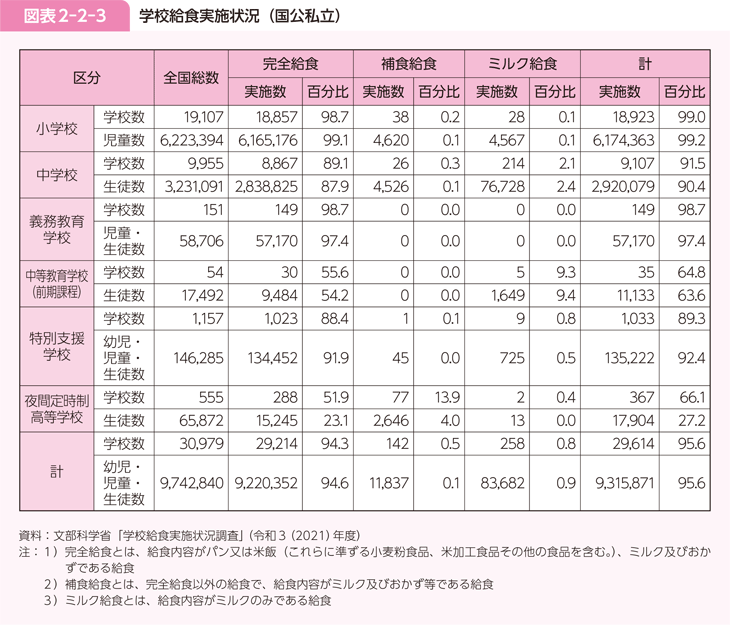1 学校給食の現状
学校給食は、栄養バランスのとれた食事を提供することにより、子供の健康の保持・増進を図ること等を目的に実施されています。また、食に関する指導を効果的に進めるために、給食の時間はもとより、各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における教材としても活用することができるものであり、大きな教育的意義を有しています。
学校給食は、令和3(2021)年5月現在、小学校では18,923校(全小学校数の99.0%)、中学校では9,107校(全中学校数の91.5%)、特別支援学校等も含め全体で29,614校において行われており、約930万人の子供が給食を食べています(図表2-2-3)。学校給食実施校は着実に増加しており、引き続き学校給食の普及・充実が求められます。なお、文部科学省では、学校給食の意義、役割等について児童生徒や教職員、保護者、地域住民等の理解と関心を高め、学校給食の一層の充実と発展を図ることを目的に、毎年1月24日から30日までの1週間を「全国学校給食週間」と定め、文部科学省及び各学校等で様々な取組が行われています。また、全国学校給食週間広報動画の日本語版と英語版を作成し、広く普及・啓発を図っています。令和4(2022)年度は、文部科学省ウェブサイトやTwitter等のSNSを活用し、教育委員会等における取組を発信しました。
また、食物アレルギーを有する児童生徒は増加傾向にあり(*1)、学校給食における食物アレルギー対応について、文部科学省では、平成24(2012)年に発生した死亡事故を受けて開催した有識者会議の最終報告を踏まえ、学校におけるアレルギー対応の改善・充実のための資料として、「学校給食における食物アレルギー対応指針」、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン・要約版」及び「学校におけるアレルギー疾患対応資料(DVD)映像資料及び研修資料」を作成しました。全国の教育委員会や学校等への配布等を通じ、食物アレルギー等を有する子供に対する、きめ細かな取組を推進しています。
新型コロナウイルス感染症に対応するため、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~」等を作成し、学校給食の場面において、座席配置の工夫や適切な換気の確保等の措置を講じた上で、児童生徒等の間で会話を行うことも可能であることを令和4(2022)年11月に改めて示すなど、地域の実情に応じた取組を促しています。
今般の学校給食における食材費高騰に対しては、令和4(2022)年4月に「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が取りまとめられ、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充により創設された「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」及び9月に政府の物価高騰に対する追加策として地方創生臨時交付金に創設された「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を積極的に活用し、保護者負担の軽減に向けた取組を進めるよう、各地方公共団体へ促しました。なお、令和4(2022)年7月末時点の保護者負担軽減に向けた取組状況では、実施又は実施を予定している地方公共団体が1,491(83.2%)、実施を予定していない地方公共団体のうち給食費の値上げを行う予定がない地方公共団体との合計は1,775(99.0%)との結果を得ました。
*1 公益財団法人日本学校保健会ウェブサイト(学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(令和元年度改訂P3))https://www.gakkohoken.jp/books/archives/226(外部リンク)
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125