漁業経営統計調査の概要
調査の目的
漁業経営統計調査は、漁業経営体の財産状況、収支状況、操業状況等、漁業経営体の経営実態を明らかにし、水産行政等を推進するための資料を整備することを目的としている。
調査の沿革
漁業経営体の安定的発展を図る各種水産施策推進の基礎資料を得るため、漁業を営む経営体の経営収支等を把握することを目的として、昭和26年に「漁家経済調査」を開始した。
調査開始時点では、10トン未満の漁船漁業を営む経営体のうち、漁業経営が中心である漁家から有意選定された490戸を対象とした。
昭和31年に漁業センサス結果を母集団とした任意抽出手法の導入、調査対象に第2種兼業漁家及び漁業企業体を追加するといった見直しを行い、平成13年に調査体系を家族型経営調査、雇用型経営調査、会社経営体調査及び共同経営体調査に再編し、名称を「漁業経営調査」に変更した。
平成18年には、調査対象を「漁業を主業とした経営体」に絞り込むため第2種兼業漁家を除外するとともに、家族型経営調査及び雇用型経営調査を統合して個人経営体調査とした。
平成28年には、共同経営体調査を廃止するとともに、個人経営体調査における海面養殖業の対象水産物を見直し、会社経営体調査における大型定置網漁業及びさけ定置網漁業を廃止した。
令和元年には、個人経営体調査及び会社経営体調査の全ての漁業種類について大規模階層を細分化するなどの見直しを行い、名称を「漁業経営統計調査」に変更した。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査として実施している。
調査体系

調査の対象
- 個人経営体調査
全国の漁業経営体(注1)のうち、個人(第2種兼業(注2)を除く。)であり、以下に該当する経営体を対象としている。
(1)漁船漁業
海面において主として動力漁船(船外機付き漁船を含む。)を用いて漁船漁業を営む経営体(漁船非使用、無動力船使用の経営体は除く。)。
(2)小型定置網漁業
海面において主として小型定置網漁業を営む経営体。
(3)海面養殖業
主としてそれぞれの対象水産物(ぶり類、まだい、ほたてがい、かき類、のり類)の海面養殖業を営む経営体。
注1:漁業経営体とは、過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を営む世帯又は事業所をいう。
ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。
注2:第2種兼業とは、個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいるもので、自営漁業以外の年間収入が自営漁業の年間収入を上回るものをいう。 - 会社経営体調査
全国の漁業経営体のうち、会社(会社法(平成17年法律第86号)に基づき設立された株式会社(旧有限会社は株式会社に含む。)、合名会社、合資会社及び合同会社)であり、以下に該当する経営体を対象としている。
(1)漁船漁業
海面において主として漁船漁業を営むもので、かつ、使用する動力漁船の合計トン数が10トン以上の経営体。
(2)海面養殖業
主としてそれぞれの対象水産物(ぶり類、まだい)の海面養殖業を営む経営体。
抽出(選定)方法
- 漁業経営体リストの作成
直近の漁業センサス結果に基づいて、調査の対象に該当する海面漁業経営体(母集団)のリストを調査の種類別、経営体階層別及び都道府県別(個人経営体調査のうちの漁船漁業については大海区別都道府県別)に作成している。 - 標本の大きさ
個人経営体調査については1経営体当たり漁労収入(全国平均。ただし、海面養殖業においては主産地平均。)、会社経営体調査については1経営体当たり漁労売上高(全国平均)を指標とする目標精度(標準誤差率)を下表のとおり設定し、必要な標本の大きさ(調査対象経営体数)を算出している。
なお、ぶり類養殖業及びまだい養殖業については目標精度を設定せず、調査対象経営体数を15経営体としている。
注:「主産地」とは、直近の漁業センサス結果で経営体数の多い都道府県から累積して8割を占めるまでの都道府県とする(以下同じ。)。
- 標本の配分
(1)個人経営体調査
ア 漁船漁業については、標本を各経営体階層(使用する動力漁船の合計トン数で区分した3トン未満、3~5トン、5~10トン、10~20トン、20~30トン、30~50トン、50~100トン、100~200トン及び200トン以上の9階層)に最適配分している。さらに、大海区別都道府県別の経営体数に応じて比例配分している。
イ 小型定置網漁業については、標本を各経営体階層(使用する動力漁船の合計トン数で区分した3トン未満、3~5トン、5~10トン、10~20トン及び20トン以上の5階層)に最適配分している。さらに、都道府県別の経営体数に応じて比例配分している。
ウ 海面養殖業については、標本を以下に示す各養殖業の経営体階層(養殖施設面積で区分)に最適配分している。
(ア)ぶり類養殖業:1,000m²未満、1,000~2,000m²、2,000~3,000m²、3,000m²以上の4階層
(イ)まだい養殖業:1,000m²未満、1,000~2,000m²、2,000~3,000m²、3,000m²以上の4階層
(ウ)ほたてがい養殖業:5,000m²未満、5,000~10,000m²、10,000~20,000m²、20,000m²以上の4階層
(エ)かき類養殖業:5,000m²未満、5,000~10,000m²、10,000~20,000m²、20,000m²以上の4階層
(オ)のり類養殖業:5,000m²未満、5,000~10,000m²、10,000~20,000m²、20,000m²以上の4階層
さらに、各養殖業の主産地に限定し、当該都道府県別の経営体数に応じて比例配分している。
なお、各養殖業に係る主産地及びその主産地を構成する都道府県(かっこ内に表示)は次のとおりである。
(ア)ぶり類養殖業:四国(愛媛県及び高知県)及び九州(長崎県及び鹿児島県)
(イ)まだい養殖業:東海(三重県)及び四国(愛媛県及び高知県)
(ウ)ほたてがい養殖業:北海道及び東北(青森県)
(エ)かき類養殖業:北海道、三陸(岩手県及び宮城県)、東海(三重県)、瀬戸内(兵庫県、岡山県及び広島県)及び九州(福岡県及び長崎県)
(オ)のり類養殖業:東京湾(千葉県)、東海(愛知県及び三重県)及び有明海(福岡県、佐賀県及び熊本県)
(2)会社経営体調査
ア 漁船漁業については、標本を各経営体階層(使用する動力漁船の合計トン数で区分した10~20トン未満、20~50トン、50~100トン、100~200トン、200~500トン、500~1,000トン、1,000~3,000トン及び3,000トン以上の8階層)に最適配分している。さらに、都道府県別の経営体数に応じて比例配分している。
イ 海面養殖業(ぶり類、まだい)については、以下に示す各養殖業の経営体階層(養殖施設面積で区分)に最適配分している。
(ア)ぶり類養殖業:2,000m²未満、2,000~3,000m²、3,000~5,000m²、5,000~20,000m²、20,000m²以上の5階層
(イ)まだい養殖業:2,000m²未満、2,000~3,000m²、3,000~5,000m²、5,000~10,000m²、10,000m²以上の5階層
さらに、各養殖業の主産地に限定し、当該主産地に属する都道府県別の経営体数に応じて比例配分している。
なお、各養殖業に係る主産地及び主産地を構成する都道府県(かっこ内に表示)は次のとおりである。
(ア)ぶり類養殖業:四国(香川県)及び九州(長崎県、大分県、宮崎県及び鹿児島県)
(イ)まだい養殖業:四国(愛媛県及び高知県)及び九州(長崎県及び熊本県) - 標本の抽出
1で作成したリストを経営体階層別及び都道府県別の区分ごとに、次の条件に従って並び替え、3により配分した当該区分ごとの調査対象経営体数で等分したそれぞれの区分から各1経営体ずつ無作為に抽出している。
(1)漁船漁業:使用する動力漁船の合計トン数の降順
(2)小型定置網漁業:使用する動力漁船の合計トン数の降順
(3)海面養殖業:養殖施設面積の降順
調査事項
- 個人経営体調査
経営主の年齢、基幹的漁業従事者の年齢、家族員数、漁業操業状況、財産及び損益 - 会社経営体調査
漁業操業状況、使用漁船、漁業投下固定資本、財産、損益及び法人番号
調査の時期
- 調査期間
(1)個人経営体調査は、毎年1月1日~12月31日までの1年間
(2)会社経営体調査は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に到来した決算日前1年間
(例)会社経営体の調査期間
- 調査票の提出期限
調査対象経営体の決算書作成後2か月間
調査の方法
調査は、農林水産省-地方農政局等(注)-調査対象経営体の調査系統で実施している。
職員又は統計調査員が調査対象経営体に「個人経営体調査票」又は「会社経営体調査票」を配布し、調査対象経営体が記入した調査票を郵送してもらう自計報告により行っている。
なお、調査対象経営体の協力が得られる場合は、オンラインによる報告により行っている。
ただし、郵送又はオンラインにより調査票を回収できない場合には、職員又は調査員による回収(必要に応じて調査票を再度配布し、自計申告の方法により記載を求めている。)、又は職員又は調査員による調査対象経営体に対する面接又は電話聞き取りにより行っている。
注:「地方農政局等」とは、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局(農林水産センターを含む。)をいう。
集計・推計方法
本調査の集計は、農林水産省大臣官房統計部 経営・構造統計課において行っている。
集計は、調査期間中に漁業種類を変更した調査対象経営体及び廃業等により調査中止となった調査対象経営体を除いた調査対象経営体により行っている。
- 全国平均、大海区別平均
集計対象とする区分ごとに加重平均法を用いて次の式により算出している。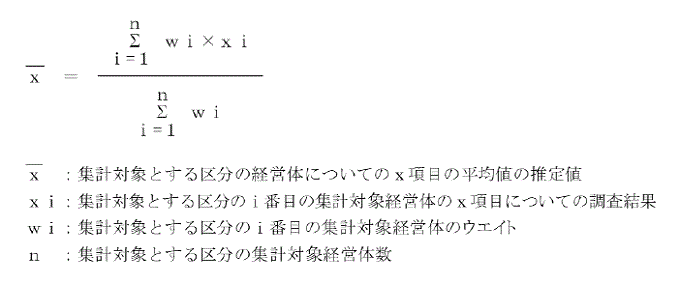
ウエイトは、次により全国の経営体階層別に算出した標本抽出率の逆数としている。
ただし、養殖部門別の全国平均については、総和平均により算出している。 - 1以外の平均
総和平均により算出している。
用語の解説
- 個人経営体調査
(1)養殖施設面積、収獲量及び養殖業生産物収入のうち、主とする養殖業には、各養殖業の当該養殖業種のみの養殖施設面積、収獲量、収入(例えば、ぶり類養殖業の場合はぶり類の生産物収入のみ)を計上している。
(2)漁労収入とは、調査期間1年間の自家漁業及び自家養殖業による漁獲物、収獲物の販売収入(直売所での販売又は自家販売による収入を含む。)、現物処理(自家消費、物々交換等を行った漁獲物及び収獲物)の評価額である。なお、現物処理の評価は、調査地における市場卸売価格による。
なお、制度受取金等(注)のうち、漁業・養殖業に関わるものを漁労収入に含めている。
また、養殖業生産物収入には、調査対象経営体が営んだすべての養殖業の生産物収入を含めている。
注:制度受取金等(漁業)とは、漁業に関わる保険金の受取金、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づき支払われた共済金の受取金、各種の損害補償金、補助・助成金等である。
(3)漁労外事業収入とは、調査期間1年間に漁業経営以外に経営体が兼営する水産加工業、遊漁船業、民宿及び農業等の事業によって得られた収入のほか、漁業用生産手段の一時的賃貸料のような漁業経営にとって付随的な収入も含めている。
なお、制度受取金等のうち、漁業・養殖業に関わるもの以外を漁労外事業収入に含めている。
(4)漁労支出とは、調査期間1年間の自家漁業及び自家養殖業による漁獲、養殖生産物の育成、収獲、販売等に要した費用及び当年に負担すべき固定資産の減価償却費の合計としている。
(5)漁労外事業支出とは、調査期間1年間に漁業経営以外に経営体が兼営する水産加工業、遊漁船業、民宿及び農業等の事業に要した費用のほか、漁業用生産手段の一時的賃借料等に係る経費も含めている。
(6)分析指標の算出方法は、次式のとおりである。
ア. 漁労所得率=漁労所得÷漁労収入×100
イ. 漁業固定資本装備率=漁業投下固定資本÷最盛期の漁業従事者数 - 会社経営体調査
(1)漁労売上高とは、調査期間1年間の漁業経営によって得られた売上高の総額であり、漁獲物及び収獲物の販売収入、現物処理(漁船の乗組員等の労賃部分としての現物支給及び船内の食料消費に充てた漁獲物)の評価額である。なお、現物処理の評価は、調査地における市場卸売価格による。
(2)漁労支出とは、調査期間1年間に漁業経営に要した費用の総額であって、当年に発生した費用及び当年に負担すべき固定資産の減価償却費の合計であり、漁労売上原価と漁労販売費及び一般管理費の合計としている。
(3)労務費とは、漁船の乗組員に支払った賃金、航海中食料費、福利厚生費等であり、給料手当・役員報酬とは、役員報酬、事務職員給与・手当、事務職員福利厚生費等である。
(4)諸利益の算出方法は、以下のとおりである。
ア. 漁労利益=漁労売上高-(漁労売上原価+漁労販売費及び一般管理費)
イ. 漁労外利益=漁労外売上高-(漁労外売上原価+漁労外販売費及び一般管理費)
ウ. 営業利益=漁労利益+漁労外利益
エ. 経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用
オ. 当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失-法人税、住民税及び事業税
調査票
利用上の注意
- 消費税の取扱いについて
漁業経営統計調査は、漁業経営体が作成している税務申告資料を参照しており、収入、支出の金額に関する調査結果には税抜きと税込み金額が混在している。 - 平成17年以前の結果は、調査体系の見直しを行ったため平成18年以降とは接続しない。
- 記号
統計表中に使用した記号は、次のとおりである。
「0」 :単位に満たないもの(例:0.4千円→0千円)
「0.0」:単位に満たないもの(例:0.04隻→0.0隻)
「-」 :事実のないもの
「x」 :個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」 :負数又は減少したもの
「nc」 :計算不能 - 秘匿措置について
統計調査結果について、集計対象経営体数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
利活用事例
- 漁業経営体の所得政策、評価等の資料。
- 「水産白書」における漁業経営の分析資料。
Q&A
Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?
A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。
Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A. 公表日時については、こちらを確認してください。
Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A. この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合の罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。
お問合せ先
大臣官房統計部経営・構造統計課
担当者:林業・漁業経営統計班
代表:03-3502-8111(内線3637)
ダイヤルイン:03-3502-0954




