SDGs×生物多様性シンポジウム「未来を創る食農ビジネス」(令和2年2月)

開催概要
2020年秋に、生物多様性について今後10年間に達成すべき新たな世界目標(ポスト2020目標)が決定される予定です。このため、農林水産省は「農林水産省生物多様性戦略」(2012年改訂)の見直しを行うこととし、有識者による研究会において、見直しにかかる論点について検討を進めてきました。
この研究会の成果を伝え、持続可能な生産・消費を実現するためのヒントになる先進的な事例を紹介するほか、生物多様性保全を重視した食農ビジネスについて知り、それらを推進することを目的として、本シンポジウムを開催しました。
- 日時:令和2年2月17日(月曜日)13時30分~17時00分(開場13時00分)
- 本会場:農林水産省本館 7階講堂(東京都千代田区霞が関1-2-1)
サテライト会場:長野県立大学 三輪キャンパス(長野県長野市三輪8‑49‑7)
プログラム
本シンポジウムは、講演パートとトークセッションパートの2部構成です。
前半の講演パートでは、後半のトークセッションパートを理解する上で必要な背景情報を御提供いただきました。
後半のトークセッションパートでは、テーマ別に、先進的な事例の御報告に続いて、議論をしていただきました。
最後に、各トークセッションの代表者と主催者を交えて、本シンポジウムの総括となる議論をしていただきました。
以下に、各プログラムの概要、講演資料および講演の様子を映した動画を掲載しました。
各プログラムの詳細については、報告書を併せてご覧下さい。
- 13時30分 開会挨拶 末松 広行(農林水産事務次官)

農業によって生産される農作物は生物多様性の恵みそのものであり、農山漁村で見られる地域特有の景観や文化も生物多様性が生み出してきたものと言える。
しかし、農林水産業が生物多様性にどのような影響を与えているのかという点については、これまでも議論があったところだが、近年では、我々が日常的に消費する食料も、世界の生物多様性との関わりがあるとの認識が広がりつつある。
生物多様性を最大限尊重しながらビジネスにもつなげていき、人々が健康で豊かな生活を送ることにもプラスになる道がきっとあるはずだと思っている。
- 13時35分 特別講演 「食の未来図~継承すべき自然の恵みと文化~」
寺島 実郎氏(一般財団法人日本総合研究所 会長、多摩大学 学長)
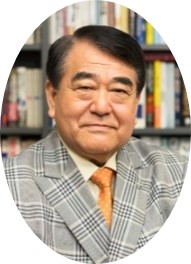
戦後、日本は工業力生産モデルの優等生として外貨を稼いできた一方で、食料自給率を落としてきた。1988年に世界GDPの16%のシェアだったのが平成には6%にまで落ち込み「日本の埋没」が世界の議論の前提となっている。
日本の異次元の高齢化、特に都市郊外型の高齢化により、文化を創り出す「食と農」に対する感受性が失われている。また、昨年は「台風19号」による河川の氾濫により、川の上流地域の山林や農地が疲弊したことによる保水力の低下が水害につながるという教訓を得た。
日本再生の基軸は「食と農」の復権にある。IoT、デジタルトランスフォーメーション、あるいは工業生産力モデルで培った技術を駆使して取り組む必要がある。
講演資料:全体版(PDF : 3,513KB)
【分割版】
分割版1(PDF : 1,824KB)
分割版2(PDF : 1,884KB)
分割版3(PDF : 1,881KB)
- 13時55分 基調講演 「農林水産業による生物多様性保全への貢献」
橋本 禅氏(東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授)

「農林水産省生物多様性戦略の見直しに関する有識者研究会」の座長として、研究会からの提言を紹介。
農林水産業や農山漁村には、食料供給・洪水防止・景観の形成などの「正の影響」がある一方で、プラスチックごみ、食品ロスの発生、農産物輸入を通じた生産地への環境負荷などの「負の影響」もあること。サプライチェーン全体における生物多様性の影響を理解した上で「持続可能な生産と消費」を促進すべきであること。SDGsや気候変動との関係性を整理すること。また、それらを実施する体制の強化が必要であること等を説明した。
講演資料:全体版(PDF : 2,006KB)
【分割版】
分割版1(PDF : 1,381KB)
分割版2(PDF : 1,418KB)
- 14時15分 SDGsダイアログとは
【ファシリテーター】 但馬 武氏(fascinate株式会社 代表取締役社長)

トークセッションパートのファシリテーターとして、後半パートへの導入として、本シンポジウムの目的、構成、進め方を説明。
大きな問題に関して1人のヒーロー、ヒロインが変えられる時代ではないとして、SDGs目標17である「パートナーシップ」を培う時間にしたいとして、参加者同士の交流を促した。
- 14時20分 トークセッション1 「ESG経営生物多様性に配慮した経営とは」
自社の経営を通じてSDGs達成に貢献し、投資家にも評価されるためには、何を知り、何をすべきか。
グローバルな視点を踏まえて議論いただきました。
【スピーカー】 橋本 禅氏(東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授)
河口 真理子氏(株式会社大和総研調査本部研究主幹)
阿部 純一氏(ネスレ日本株式会社マーケティング&コミュニケーションズ本部,
コーポレートアフェアーズ統括部, コーポレートコミュニケーション室室長)
事例紹介1 「企業や投資家の生物多様性戦略」
河口 真理子氏(株式会社大和総研調査本部研究主幹)

金融は今SDGsに積極的に取り組むようになっている。ESG投資(サステナブル投資)は世界で投資の主流になりつつあり、日本でも2019年で総運用資産の56%と2015年から12倍に拡大している。
ESGのE(環境)の要素としての「自然資本(ストック)」は「生態系サービス(フロー)」を生み出す原資である。金融は気候変動の次のリスクとして生物多様性や自然資本を認識し始めており、投資判断に森林破壊等のリスクを組み込むことが求められている。
TEEBにも出ているが「経済こそが最も自然をリスペクトしなければならない」。また「それ以上にわれわれは自然界に対して、謙虚な気持ちを取り戻さなければいけない」。
講演資料:全体版(PDF : 1,831KB)
事例紹介2 「ネスレのパーパス(存在意義)とCSVの実践」
阿部 純一氏(ネスレ日本株式会社マーケティング&コミュニケーションズ本部,
コーポレートアフェアーズ統括部, コーポレートコミュニケーション室室長)

CSV(共通価値の創造)は、2005年に当時のネスレ会長が提唱した言葉であり、株主と社会全体のために価値を創造することがネスレの長期的な成功につながるという考え方である。
また、「ネスレは、生活の質を高め、さらに健康な未来づくりに貢献します。」を活動の原点とし、3つの社会領域ごとに数的目標を設け、CSVを通じて問題解決に取り組むことでSDGsの達成に貢献すると考えている。
サプライチェーン管理は重要な課題であり、ネスレとして「責任ある調達」基準をつくり、農村開発と貧困緩和を両立するネスレカカオプランやネスカフェプラン等を進めている。
講演資料:全体版(PDF : 1,379KB)
トークセッション1 「ESG経営生物多様性に配慮した経営とは」

(但馬氏)今回のシンポジウムは見えなくなった課題を見えるようにして危機感を醸成する試みだと捉えている。
(河口氏)日本は企業が顧客を大事にし過ぎて、不愉快な思いをさせないように、サプライチェーン上の課題を隠して考えなくていいようにしてしまったことが、SDGsやESGの理解が遅れている一因だと思われる。
(橋本氏)生物多様性の損失がわれわれの社会や経済に与える影響に関するレポートが出てきており、生物多様性の価値を評価し、課題を見える化するための努力が行われている。
(阿部氏)ネスレは、社外からの厳しい声を受け止めて、一緒に改善に向けて取り組んでおり、その姿勢がメディアで報道されることで、努力が消費者に伝わっている。また、現地のNPO、NGO、サプライヤーの協力を得て農地までさかのぼる原料のトレーサビリティを実現するなど、コンプライアンスをきちんとやって信頼を得ることで、消費者から選ばれる会社になると考えている。
- 15時25分 トークセッション2 「SDGs×生物多様性 ビジネスリスクをチャンスへ」
環境課題への対応をチャンスと捉え、一歩先に進むための方法とは。具体的な取組の紹介とともに、
そのヒントについて議論いただきました。
【スピーカー】 大津 愛梨氏(O2Farm 6次化担当、NPO法人田舎のヒロインズ理事長)
菊池 紳氏(いきもの株式会社 創業者・代表取締役)
鈴木 淳一氏(株式会社電通 電通イノベーションイニシアティブ プロデューサ―)
事例紹介1 「小さな家族経営農家の飽くなき挑戦~RE100農家を目指して~」
大津 愛梨氏(O2Farm 6次化担当、NPO法人田舎のヒロインズ理事長)

世界の食糧生産を担う農家の約8割は私たちO2Farmと同じ家族経営の小中規模農家であり、農家が農業を続けているから農村の景観が維持できていることを就農してようやく気付いた。
再生エネルギー100%のRE100農家を目指しており、バイオディーゼルの使用に取り組んでいるほか、ソーラーシェアリングや小水力発電も検討中(SDGs目標7、13)。
ランドスケープ農家を名乗り、野焼きにより陸の生物多様性保全に取り組むほか、水を汚さず海を守る啓蒙プロジェクトもおこなった。(SDGs目標14、15)
今日はSDGs17のゴールに沿って、私たちの取組を紹介したが、皆さんの何かのヒントになったらいいと思う。
講演資料:全体版(PDF : 4,342KB)
【分割版】
分割版1(PDF : 1,963KB)
分割版2(PDF : 1,798KB)
分割版3(PDF : 1,795KB)
事例紹介2 「chiQ(チキュウ)が手がけるサステナブル・イノベーション」
菊池 紳氏(いきもの株式会社 創業者・代表取締役)

生産者の所得を上げるには流通コストを下げることが必要との思いから、中小零細の農家と首都圏のレストランを直接繋ぐサービス「SEND」を作った。しかし、全ての資材を海外から購入する高コストの構造に問題があると分かった。
地域資源を活用することでコストを見直すことは生態系サービスを活用するということ。しかし、私たちはそれを奪うばかりで対価を払っていないのではないか。 生物多様性が損なわれると生態系サービスが失われるとは、つまり原材料の調達コストが上がるというビジネスリスクが生じるということ。
CSRや広告を超えて、本業と両立する取組を行うため、企業と一緒に新しいものを生み出して行けたらと思っている。
事例紹介3 「ブロックチェーン技術が導くエシカル消費マーケット」
鈴木 淳一氏(株式会社電通 電通イノベーションイニシアティブ プロデューサ―)

情報の流れが、有名グルメガイドのようなマスマーケティングを中心とした中央集権型から、消費者が評価した星の数などで価値を判断するように変化しているが、情報の信頼性に課題がある。
ブロックチェーン技術を使うことで、情報の信頼性を確保するとともに、多様でニッチな価値観を持つ消費者をつなげてファンのコミュニティを形成し、第3者認証では実現が難しい価値を生むことが可能だと考えている。
宮崎県綾町の自然生態系農業を対象に実証実験をしているが、顧客同士が綾町野菜を扱う店を自発的に相互に行き来しだしており、こうしたことは今後どんどん起こると思う。
講演資料:全体版(PDF : 6,650KB)
【分割版】
分割版1(PDF : 1,979KB)
分割版2(PDF : 1,682KB)
分割版3(PDF : 1,623KB)
分割版4(PDF : 1,843KB)
トークセッション2 「SDGs×生物多様性 ビジネスリスクをチャンスへ」

(但馬氏)僕らの社会が効率的にやりすぎたために多様性がなくなったことによって引き起こされている問題がここで話されていると感じる。
(菊池氏)伝えるべき人に透明性のある情報を実態が伴う形で伝えることでビジネスリスクをチャンスに変えることができる。農家のビジネスユニットを小さくしてそれを繋げる適地適作リレー出荷のようなモデルは、分散投資の観点からも、生産者や地域資源のサステナビリティの観点からも最適かと思う。
(鈴木氏)実態を伴う情報を届けるのに「就業体験」や「民泊」があるがマスベースには広がらない。大多数の消費者に届けるには、都市部の小売の現場において、生産の現場である地方のランドスケープを想起させる工夫が必要。いつも高い定価で売ることではなく、生産者と消費者の間に信頼を形成し、いつもは安いけど不作の時は高く買って支えてくれるファンがいるというのが新しい付加価値のあり方だと思う。
(大津氏)一部の裕福な人に高付加価値のものを届けるのではなく、都市部の一般市民に普通の金額で国産農産物を届けるには、企業レベルで流通のあり方を工夫してもらう必要がある。日本の人口も農業後継者も減り続けており、生産量も消費量も減っていく。生態系サービスを守り、食料を確保するにはどうしたらいいかバックキャスティングしなければいけない。 - 16時40分 ラップアップセッション 「未来を創る食農ビジネス」
シンポジウムのまとめとして、各セッションの代表者と主催者を交えて、全体の感想を伺うとともに、
参加者に持ち帰って欲しい「想い」をお聞きしました。
【スピーカー】 橋本 禅氏(東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授)
河口 真理子氏(株式会社大和総研調査本部研究主幹)
大津 愛梨氏(O2Farm 6次化担当、NPO法人田舎のヒロインズ理事長)

(但馬氏)生物多様性のリスクを可視化する必要があり、リスクを知ることで、それをビジネスチャンスと捉える人が出てきて、その際にテクノロジーを活用するという構図がある。「死んだ地球にはどんなビジネスも成立しない」。1人や1社では解決できないテーマであり、みんなで一緒に解決していける取組にしたい。
(橋本氏)今、気候変動で起きていることは、いずれ生物多様性やビジネスにも起きると確信している。ぜひとも、何か新しい行動につなげていただきたい。
(河口氏)人間は地球が46億年かけて作ってくれた生物多様性の恩恵を受けて生きられている。食はビジネスだがすべての人間にとっての基本であり大地の恵み。儲けの手段だけではなく、食のありがたさを最初に考えると、いろんな技術や戦術的な話がもっといい方向にいくと思う。
(大津氏)農村の生物多様性を支えているのは農家だが、それを意識している農家は少ない。自然界の大原則として「変われるものしか生き残れない」というのがある。生物としての種だろうが、企業だろうが、農家だろうが、その時の状況に応じて変わっていくだけのことなのかなというのが個人的な感想。
(久保)生物多様性は今後チャンスになると信じているが、伝えることの難しさがある。農林水産業、食品産業の基盤である生物多様性を豊かにしながら、食農ビジネスも豊かになる図式を目指していきたい。
報告書
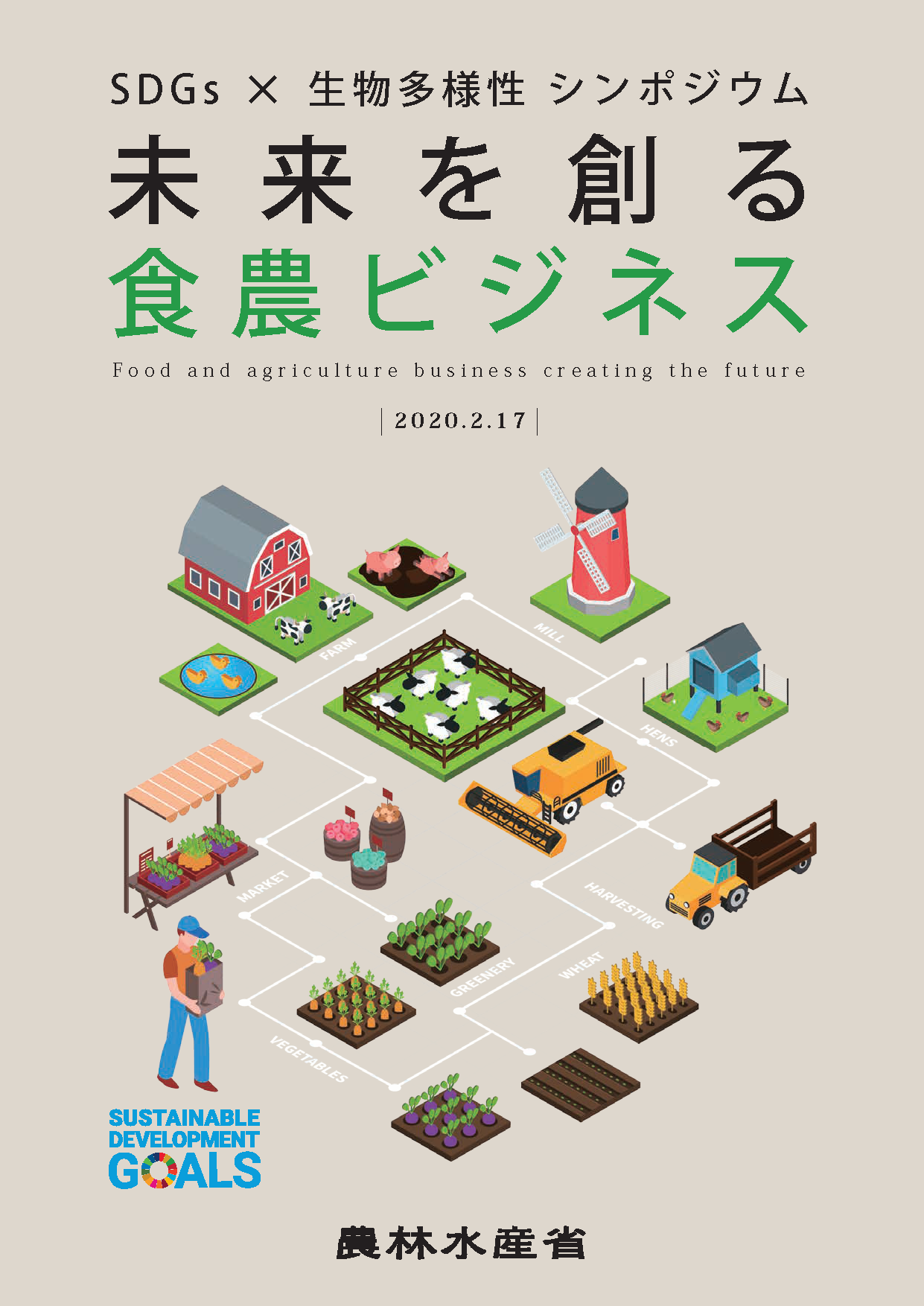 |
全体版(PDF : 12,463KB) |
お問合せ先
大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室
代表:03-3502-8111(内線3292)
ダイヤルイン:03-3502-8056




