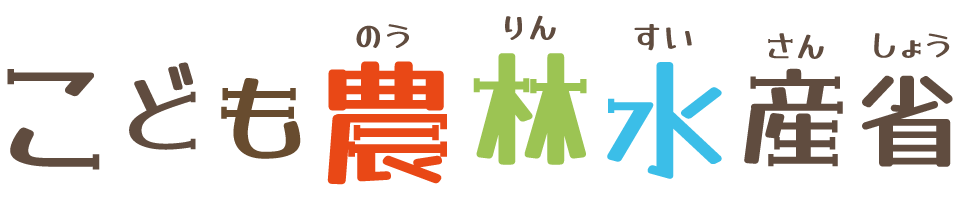日本の陸地の約7割が森です。森には、強い雨が降った時に山崩れや洪水を防ぐ、雨が降らない時にたくわえた水を川に流す、地球の温暖化を防止する、野生の動物や植物の生きる場になる、人が住む家の材料となる木材を生産するといったさまざまな働きがあります。
そのような大切な日本の森の約4割は、おじいちゃんの世代が植えたスギやヒノキなどの林で、それらの多くが植えてから50年以上がたち、十分に成長していて、今では豊かな森林資源になっています。ところが、ながい年月がたち、森がある山村には住む人が少なくなり、まだ若く手入れが十分にできていない林もあります。
豊かな森林資源を守り、子どもたちやそのまた子どもたちの世代に受け渡していくためには、森を「伐って、使って、植えて、育てる」という循環を絶やさないことが大切です。そのためには、林のお世話をする人が山村で生活できるように木材を売ったり、少ない人数で林のお世話ができるように工夫したりすることが必要です。
また、山の奥の方には木材の生産に向かない急峻な森や水源地域があり、それらの多くは国が直接管理している国有林です。
さまざまな大切な働きをする豊かな森を守り、将来の世代に受け渡していけるよう、林野庁は、山村に住み森の手入れをする人たちの支援や、山崩れを防ぐ工事、木材がたくさん売れるような調査のほか、山奥にある国有林の管理などさまざまなことに取り組んでいます。