水稲有機栽培における作業の「機械化」と「標準化」
~栽培面積拡大を目指して~
農林水産省では、「環境負荷低減技術」と「省力化技術」を取り入れた「グリーンな栽培体系」への転換を推進しています。
今回は、水稲の有機栽培に取り組んでいる、三重県津市の農業者の辻 武史(つじ たけし)さんと三重県の担当者にお話を伺いました。
- グリーンな栽培体系の詳細は こちら
検証農家プロフィール
- つじ農園のHPは こちら(外部リンク)
目次
インタビュー
航空宇宙のエンジニアから地域に根差した農家へ
元々エンジニアだったとのことですが、農業を始められた理由はなんですか?
辻 さん
大学卒業後、20年くらい地元を離れて航空宇宙産業関連の品質管理エンジニアをしていたのですが、40歳を前にして、「『食』や『地域』に携わる仕事をしたい」と思い、平成28年に地元に戻って農業を始めました。農業も航空宇宙産業も「ものづくり」という点で共通するものがあり、エンジニアとしての経験も活きるのではないかという気持ちもありましたね。
さらに、農業者としては後発になるので、「人と同じことをしてもつまらない」と思い、平成29年に有機米の栽培を20aから始めました。消費者と直接的な関係を作るためにECサイトで販売していますが、ありがたいことにたくさんのお客様にご購入いただいており、現在は栽培面積を5haまで拡大しています。
雑草防除体系を確立し、有機農業の勝率を上げる
今回、乗用除草機による機械除草を検証していますが、取り組まれた理由は何ですか?
辻 さん
有機米は県内の酒蔵や卸売業者から需要があるので、今の倍くらいに面積を増やしても良いかなと思っています。しかし、化学農薬・化学肥料を使わない有機栽培は、生育・収量や品質がその年の気象条件に大きく左右されやすいと感じています。特に、有機栽培の成否を決める「雑草防除」は、うまくいかないときの要因をまだ掴み切れていないので、 「雑草防除体系の手順書」を作りたいという思いがあります。また、有機栽培の面積拡大には機械化による省力化が絶対に必要になると考えており、今回は、乗用除草機による機械除草の検証に取り組みました。雑草防除の機械化によって、省力化を図るとともに、作業を標準化して有機栽培がうまくいく確率を上げたいと考えています。

乗用除草機の省力化効果はどうでしたか?
辻 さん
既存の田植機にアタッチメントを取り付けて使用するものですが、省力化効果はすごく高いと感じましたね。有機栽培の面積が2haくらいの時は手押し除草機を使っていて、10aあたり2時間かかっていたのが、乗用除草機だと30分になりました。作業時間が減ったことに加えて、機械に乗りながら作業ができて身体的にも楽なので、感覚的には1000分の1くらいの労力になった感覚です(笑)。何より使い方さえ覚えれば誰でも同じように除草できることが、有機栽培の面積を拡大していく上で非常に意味の大きいことだと考えています。
また、効果を十分に発揮するため、ほ場や雑草の状況に応じて、作業の時期や水位、機械のヒッチを調整するなど工夫しています。ただ、十分に除草するためには中干しまでに3回(週1回程度)入りたいので、もう1式導入して計2式にしても良いのかなと考えています。
(辻さんが代表を務める東睦合地区有機稲作協議会が作成した有機栽培の手順動画 )
営農管理システムによるデータ共有で、ほ場管理を効率化!
辻さんのところでは営農管理システムも導入されていますが、導入の経緯は何ですか?
辻 さん
うちは面積が小さい割にほ場が散らばっており、関わる方も多いので、情報をデータ化して共有するシステムがないと仕事にならないんですよね。例えば、ほ場作業をする際に、地元の昔からの農業者なら「川向いのあそこのほ場」で通じますが、地元じゃない人からしたら分からないですよね。営農管理システムはほ場を番号で管理することができるので、誰が作業の担当になってもほ場の場所がすぐに分かるようにできて便利だと感じています。
また、こういうシステムは、社員や農繁期に手伝いに来てくれる人など、 みんなが使いこなせないと意味がないと思っています。私もまだまだ使いこなせていないんですが、最終的にはみんなが使いこなせるよう、社員教育もやっていきたいですね。
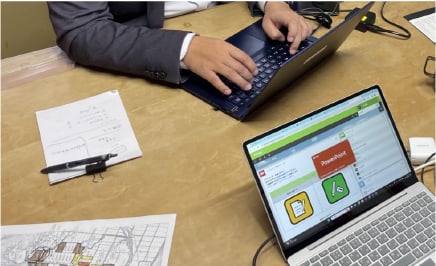 営農管理システムを用いて
営農管理システムを用いて ほ場の作業状況を確認している様子
現在、ほ場の見回りにはクラウドシステムを利用されているそうですね。
辻 さん
今年から地域の福祉事業所と連携し、クラウドシステムを活用したほ場の見回りを行ってもらいました。福祉事業所から来てもらった方に、システムに表示されている番号のほ場に行き、草丈・水位の測定とほ場の撮影を行い、そのデータをシステムに入れてもらう作業をお願いしたところ、ゲーム感覚で楽しんで作業できたようで、非常に良かったです。
既存の農業用システムではなく、基幹システムを活用してご自身で構築した営農管理システムを活用されているそうですが、理由を教えてください。
辻 さん
基幹システムを活用してオリジナルのシステムを作ることは、他産業では既に行われていることなので、農業でもできるだろうと思ったんです。うちは農業機械の種類も多いので、自分たちの使いたいように機能を拡張できるところが気に入っています。今は有機栽培のプレイヤーが少ないのでアイデアも少ないですが、これから有機農業が拡大してプレイヤーも増えれば、必然的にアイデアも増え、いろんなシステムを活用する人が出てくると思います。
作業の「標準化」で有機栽培の面積拡大を目指す
有機栽培の今後の展望をお聞かせください。
辻 さん
有機栽培の生産性を向上させたり規模拡大したりするには、今までのやり方の延長では限界があると思っています。「自分一人が作業できれば良い」と思っていたときもありますが、今は、 作業を「標準化」して、誰でも同じように作業できる環境を整えていくことが必要だと考えています。
そのため、「標準化」の最たるものである「機械化」を進めていくとともに、「標準化」に必要な有機栽培のデータやノウハウの蓄積、新たな技術の導入に積極的に取り組んでいきたいです。
三重県 担当者
三重県では、みどりの食料システム法に基づく基本計画を策定し、有機栽培の取組面積を令和2年度の238haから、令和9年度に300haにする目標を立てており、目標達成のために、年に1回有機栽培の講習会を実施しています。これからも辻さんの取り組んでこられた先進的技術とそのノウハウの普及を進めていきたいです。
 辻さん(中央)と三重県の担当者の皆さん
辻さん(中央)と三重県の担当者の皆さん- 取材日:令和6年10月25日
- 本事例の取組内容については、三重県農産園芸課(電話059-224-2808)までお問合せください。
- 参考:辻さんの取組について、「令和6年度第1回グリーンな栽培体系の取組報告会」で発表いただきました。詳しくは こちら
(YouTubeに移動します。1時間03分44秒から辻さんの発表です。)
今回は、三重県の有機水稲栽培の事例を紹介しました。全国でも、「グリーンな栽培体系への転換サポート」を活用して、有機農業の取組面積拡大の検証が行われており、既に検証を終えた地区では、検証結果を踏まえた「栽培マニュアル」が策定され、各自治体等のHPに掲載されています。
農林水産省HPでは、「栽培マニュアル」掲載ページのURLをまとめて公表していますので、ぜひご参考ください。
お問合せ先
農産局技術普及課
担当者:みどりユニット
ダイヤルイン:03-6744-2107





