突撃!お砂糖会社にインターン学生がインタビュー!【第1回:日本甜菜製糖(株)石栗秀社長】

砂糖の生産振興を支えている各製糖工場や精製糖企業の社長や社員の方に、インターンシップ生から砂糖を製造する企業として大切にしている思い、人生のターニングポイントから学生に向けたメッセージまで様々な内容をインタビュー!
記念すべき第1回は、砂糖事業を筆頭に食品事業や飼料事業など、様々な事業を展開する「日本甜菜製糖(株)」の石栗 秀社長!
今回、北海道における砂糖産業の広がりや、企業として大切にしていることなどのお話はもちろん、社長の人生に対する考え方まで、大変興味深いお話が聞けました!
大学卒業後の進路を考えている方、若いうちに何をしたらいいのか悩んでいる方も要チェック!
(インタビュー実施日:2022年8月29日)
会社の概要及び社長のプロフィール
会社の概要
社名:日本甜菜製糖株式会社
創立:1919(大正8)年6月11日
従業員数:765名 ※2022年3月末
事業内容:ビート糖、精糖、飼料(配合飼料、ビートパルプ)、紙筒、イースト、種子、オリゴ糖等機能性食品の製造・販売、農業機材の販売および不動産賃貸事業
製糖工場としては、芽室製糖所、美幌製糖所、士別製糖所の3工場を運営。
社長のプロフィール
北海道函館市出身、北海道大学卒業。東北大学大学院修士・博士課程を経て、1986年に日本甜菜製糖(株)に入社。その後研究職から営業の統括業務など多岐にわたる業務を担当し、2022年6月に社長に就任。
インターン生によるインタビュー

今回のインターン生は、北海道・帯広出身の大学3年生(写真左)。祖父の家に行く途中に芽室製糖所があり、よくそのそばを通っていて、製糖工場にはなじみがあったとのこと。インターンシップでこの課を選んだ理由のひとつでもあるそう!
――いつ入社したか、社長に就任するまでどんなお仕事をしていたのか教えてください。
日甜(日本甜菜製糖株式会社)に入ったのは27歳の時です。なぜ日甜だったのかというと、当時、東北大学の大学院ではマイナーな研究室に在籍していたのであまり就職先がなく、北海道大学時代の研究室の先生にどこに入ったらいいか聞いたら「日甜にいったら?」と返ってきたからです。
最初は微生物の研究職として入社し、その後はイースト工場で製造・品質管理業務、本社で砂糖販売の統括業務、イーストとオリゴ糖の販売関係、製糖所での砂糖製造業務、技術部長、本社の経営部門などを経験して、2022年6月から社長になりました。
――色々なことを経験されていてすごいです。
すごくはないですよ。農水省でも2~3年で部署が変わると思います。いかにコツを覚えるかだと思います。だいたい1年でコツを覚えてしまえば2年目は楽になります。
――砂糖を製造する企業として大切にしていることを教えてください。
皆さんの口に入る食品なので、安全であることを大事にしています。
また、高品質なものを供給することも非常に重要です。安心・安全・高品質に尽きます。
――パッケージの北海道産というところからも、国産という安心・安全感が伝わってきます。
北海道産てん菜100%、国産というのをきちんと提示することは大事にしているところですね。
――砂糖の製造・販売を通じた社会への関わり、貢献について、どのように考えているのか教えてください。
北海道の畑と日本の食卓をつなぐこと、北海道という地場を大事にしています。
日甜の砂糖は、関東では主に30kgの業務用サイズがパン、お菓子、飲料などに供給されており、意外と皆さんも日常で摂取されています。国内での自給が重要になっている中、食料自給率への貢献は今後も大事にしていきたいところです。また、てん菜は加工して初めて商品価値が生まれます。我々が加工をすることで、砂糖やオリゴ糖などができ、皆さんの食卓に繋がっていく。食料をめぐる流れの中の一翼を担っているのかなと思います。
てん菜は収穫開始の10月から製糖所に運び込まれ、ビート糖が製造されますが、例えば芽室製糖所では1シーズンに100万トンのてん菜が運び込まれます。運搬トラックが延べ10万台走る計算となります。搬入期間は約3ヵ月あり、1日あたり延べ1,000台以上のトラックが往来します。そこで物流関係など多くの方が関わります。工場の操業には修理をする方々も必要ですし、美幌製糖所では夏に約100人、冬の工場操業時には約300人が製糖作業に従事しており、地域の人々の力が欠かせない地場に根付いた工場になっています。
――美幌町の人口を考えると、そのうちの100人って結構大きいですよね。
そうですね。今の美幌町は人口2万人くらいかな。そう考えると大きいですね。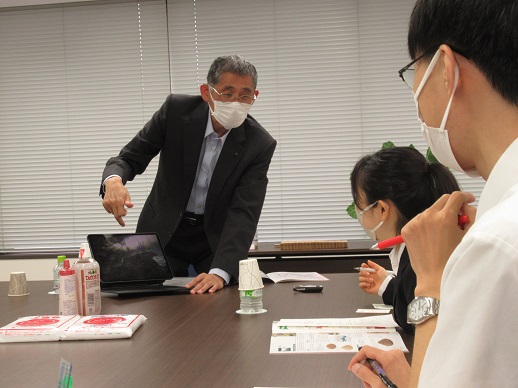
――人生のターニングポイントは何ですか。新人時代に苦労したことはありますか。
大学を卒業して、就職せずに大学院に進んだことです。普通はマスター(修士課程)の2年、それがドクター(博士課程)も合わせて5年いた。ターニングポイントというより、大きな道草であったなと。でも、私にとっての一番大きな5年でした。マスターの2年目で研究室の先輩が出払ってしまって、研究室のトップになってしまい、下には後輩たち、その中には留学生もいてその対応もしなくてはいけない。一番しんどい時でもありました。
――留学生とは英語で話されていたのですか?
ドクターの3年間はコスタリカやタイの留学生と英語で話していました。ドクター時代はさらに大変なことが続き、他部門の研究助手の人たちと議論すると色々研究について言われ返され、どうやったら理解してくれるだろうと苦労したり、ドクター1年の時には教授が退官したり……この5年間で色々経験しました。
逆に日甜に入ってからは苦労とは思わなかったです。部署は色々変わって、それもターニングポイントではあったけど、大きなギャップは感じていませんでした。
――大学卒業後にすぐ就職するのと、大学院で博士課程まで5年いるのではどちらの方がいいと思いますか?
私の場合は5年いてよかったと思っています。大学出てすぐ会社に入っていたら、あの経験はできなかった。あの経験がなかったら今の自分はないと思っています。それだけキツイ経験であったというのは間違いないです(笑)。もちろん社会人の方が楽かと言われればそういう訳ではありませんが。
――座右の銘を教えてください。
あまり座右の銘というのはないですが、最近、若手社員と面談を行っている時に20代の社員から「今の時期は何をしたらいいのか」と聞かれ、その時は「会社以外の人と付き合うのがいい」と言いました。
同じ組織に属している人間は、どうしても同じ考え方の人ばかりになります。色々な幅広い人とお話して、考え方を吸収しておけば将来役に立つのではないかと思います。私は大学院の5年間で海外の人たちとたくさんディスカッションしてきて、考え方の明らかな違いを実感してきました。そして、それは今も役立っていると感じています。
――これまでで、とても強く興味を抱いたこと、お仕事以外に没頭したことがあれば教えてください。
中学生の頃から吹奏楽でサックスをやっていて、30代半ばまで続けていました。
そして、50歳すぎてからはスキューバダイビングを始めました。家族に内緒でライセンスを取って、北海道から沖縄、カリブ海などにも行きました。突然一人で海外に潜りに行った時があって、妻からは「何を考えているんだ」と大不評でした(笑)。その代わり、家族で海外旅行する時は計画・予約・案内まで私が全てアテンドしています。
――全てお任せで旅行できるのはとてもいいですね(笑)。今まで潜った中で一番綺麗な場所はどこでしたか?
メキシコのセノーテ(鍾乳洞が雨水で水没しているところ)を潜ったのが、一番綺麗というか神秘的でした。
(写真は石栗社長がセノーテに潜り、水面に向かって撮影したもの。水中から撮ったとは思えない透明度で、光がはしごのように降り注いでいます!)
――本当に綺麗ですね!石栗社長は海外で自分からアポ取りしたりしていますが、何か国語話せるのでしょうか?
日本語、英語、スペイン語、ロシア語、昔はハングルも勉強していました。海外では基本どこに行っても英語で済ませていました。
ある意味、趣味の方が一所懸命かもしれません(笑)。でも、仕事には色々な資格が必要になってくるので、勉強して資格取得も行っていますよ。
――ここでありが糖運動としての軽い質問をさせてください。コーヒーに砂糖は入れますか?
正直に言うと、家で飲むときは砂糖入れませんが、外で飲むときはお砂糖たっぷり入れます(笑)。
――続いて、普段お菓子は食べられますか?また、和菓子派ですか?洋菓子派ですか?
お菓子よりお酒の方が正直好きかな(笑)。でも、どちらかというと洋菓子派です。コーヒーをよく飲むので、コーヒーに合うのは洋菓子かなと思います。
――お砂糖に対する想いと今後の将来像について、どのように描いているのか教えてください。
人口減少や高齢化で多くの食品産業の市場が小さくなっています。その中であっても、砂糖の重要性は変わらないと思います。ただ、北海道に話を戻すと、砂糖の消費量が減っているからてん菜を作らなくていいのか?と言われれば、単純にそうとも言えないかなと。
我々が今やっていかなければならないのは、「てん菜糖業」から「てん菜産業」への転換です。てん菜から従来の白いお砂糖以外のものも作っていこうというもので、今はオリゴ糖などを作っていますが、これからはてん菜からジェット燃料ができないか、また白い砂糖とは違う砂糖を作れないかなど様々な方向性を模索しています。
そうすることで、てん菜の生産量を維持できるのではないかと考えています。北海道農業、砂糖の将来の両方を考えていくことに日甜の会社としての将来があると思っています。
――最後に学生に向けたメッセージ等がありましたらお願いします。
自分は意外と自分のことを分かっていません。人を通すことで、自分がどう見られているかが分かります。もちろんそれを気にしすぎることはないですが、先ほども話したように色んな人と接することで、ものの考え方・見え方がしっかりと形成されていくのではないかなと思います。若いうちに色んな人と意見交換して、自分の中のブレない考えを1本作る。この軸は一生使えるのではないかと思います。
また、若い頃に想像していた人生って大抵その通りにはならないです。私もこんなに様々な部署を経験するとは思っていませんでしたし、社長になる人生設計もありませんでした。ですが、振り返ってみて思い残すことはありません。それなりに一所懸命やっていたんだと思います。その時々で一所懸命やる、というのはどの時代でも変わらないと思います。
インターンシップ生後記
インタビューの中で、てん菜糖業は地域にかかわる裾野が広いとおっしゃっていたことがとても印象的でした。工場で働く人だけでなく、てん菜を運搬するトラック、農家さんなどを合わせるとかなりの数の人々が関わっていることを初めて知りました。私の地元が北海道なのですが、気づかぬうちに生活を支えられていたのだと思いました。
お問合せ先
農産局地域作物課
担当:価格調整班、企画班
代表:03-3502-8111(内線4844)
ダイヤルイン:03-6744-2116
↓↓「ありが糖運動」公式SNS ↓↓
【X(旧Twitter)】![]() @maff_arigatou (外部リンク)
@maff_arigatou (外部リンク)
【Facebook】 @maff.arigatou (外部リンク)
【Facebook】![]() @maff_arigatou (外部リンク)
@maff_arigatou (外部リンク)




