食品企業等向けの取組|フェアプライスプロジェクト
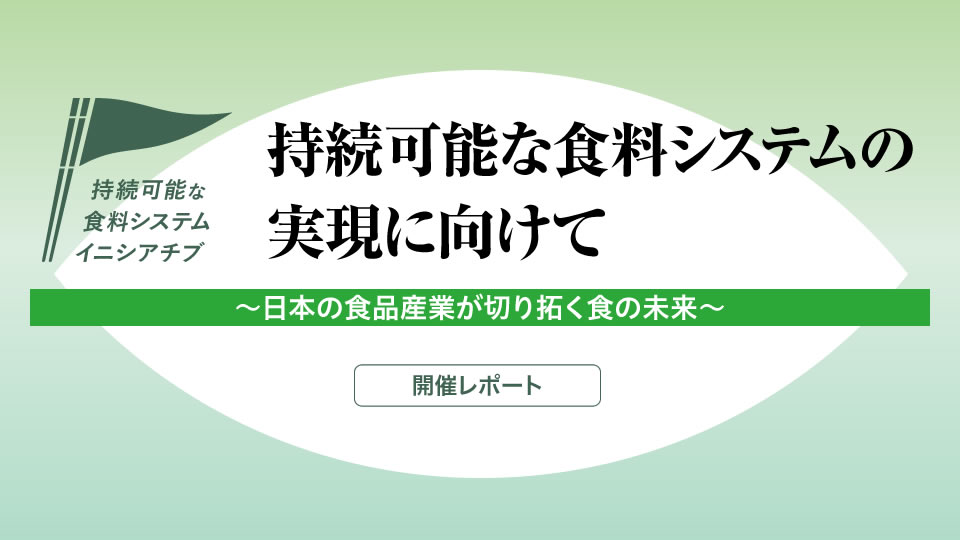
持続可能な食料システムの実現に向けて
~日本の食品産業が切り拓く食の未来~
~日本の食品産業が切り拓く食の未来~
開催レポート
食料⾃給率の低下、円安の影響、国際情勢の変動⸺。こうした要因が日本の食品産業に大きな影響を与え、持続可能な食料供給のあり方が問われています。こうした背景を踏まえ、2025年2⽉10日、東京‧大手町の日経カンファレンスルームにて、「持続可能な食料システムの実現に向けて~日本の食品産業が切り拓く食の未来~」と題したシンポジウムが開催されました。本シンポジウムは農林水産省と日本経済新聞社の共催で行われ、生産から消費に関わる多様な関係者が集い、食の未来をどのように守っていくべきかが議論されました。
日本の食品産業が直面する課題
日本の食品産業はGDPの約10.2%を占め、約819万人が従事する重要な産業です。しかし、食料自給率の低下や輸入コストの増加、農業の高齢化などの課題に直面しています。これらの問題に対処するため、持続可能な食料システムの確立が求められています。

講演の様子
環境改善と増産の両立を
東京大学大学院の中嶋康博教授からは、これからの食料システムについて、システム全体を包摂的改革によって効率化し、環境対策技術を向上させて環境改善と食料の増産を両立させることの重要性や、消費者の理解を深めながら食ビジネスを改革していくことで、持続可能な食料システムの構築が進むことへの期待が述べられました。

東京大学大学院 農学生命科学研究科 研究科長
中嶋康博氏
中嶋康博氏
業界一丸となり共創実現
食品産業センターの荒川隆理事長からは、食品産業の個社での取組には限界があることなどから、持続可能な食料システムの移行には、農業との連携や業界としての協調など、食料システム全体が一丸となった共創実現の必要性について説明がありました。

食品産業センター 理事長
荒川隆氏
荒川隆氏
食料システム法案を検討
農林水産省からは、改正食料・農業・農村基本法を踏まえて、合理的な費用を考慮した価格形成と食品企業の発展により、持続的な食料システムを確立することを目的とする法案の検討状況について情報提供しました。

農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 企画グループ長
木村崇之氏
木村崇之氏
企業による持続可能な食料供給への取り組み
プログラムの後半では、国内の食品企業による持続可能な食料供給への取り組みが紹介されました。例えば、明治ホールディングスは「持続可能な調達活動」を推進し、カルビーはじゃがいも調達の安定化に向けて農家と協力しています。日清食品は環境負荷の低減を目指し、省エネルギーの取り組みを強化しています。また、味の素は食品ロス削減に積極的に取り組み、より持続可能な食料供給の実現を目指しています。
それぞれの強みを活かしながら、持続可能な食料システムの確⽴に向けて重ねられた努力を知ることができました。
それぞれの強みを活かしながら、持続可能な食料システムの確⽴に向けて重ねられた努力を知ることができました。

明治ホールディングス 常務執行役員CSO
松岡伸次氏
松岡氏は、持続可能な生乳とカカオの調達活動について講演しました。明治グループの事業規模やサステナビリティ活動の概要が説明され、特に環境負荷の低減やサプライチェーン全体での持続可能な取り組みが重要であることが強調されました。松岡伸次氏
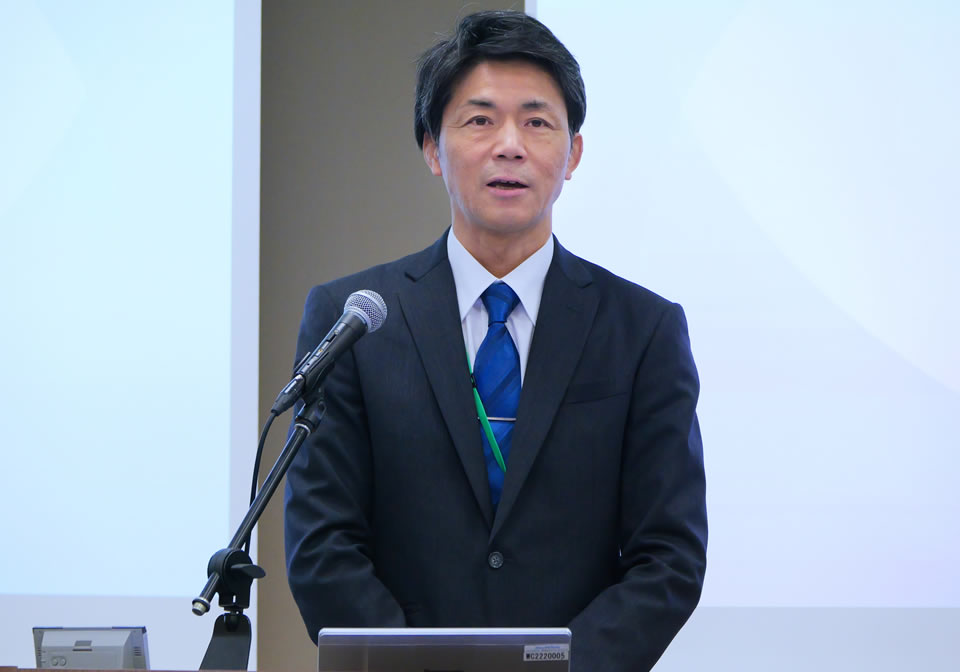
カルビー グローバル調達本部 馬鈴薯調達部 部長
小川省吾氏
小川氏は、持続可能な馬鈴薯(じゃがいも)調達の取り組みを紹介。契約栽培の仕組みや、農家との協力を通じた品質向上の工夫が説明されました。また、国内の生産量減少に対する対策として、機械化‧効率化を進めることで、安定的な調達を目指すと語りました。小川省吾氏

⽩ハト食品工業 代表取締役社長
永尾俊⼀氏
永尾氏は、さつまいもを活用した6次産業化の取り組みについて講演しました。農家の自給自足を進める農業経営対策や、地域活性化のための観光型農業の推進が紹介されました。また、数々の課題に対応するための技術開発や地域との協⼒の重要性が語られました。永尾俊⼀氏

日清食品ホールディングス
取締役‧CSO 兼 常務執行役員
横山之雄氏
横⼭氏は、持続可能な食料システムの実現に向けた取り組みについて説明しました。環境負荷の低減や食品ロス削減のための施策が紹介され、EARTHFOODチャレンジといった環境戦略の⼀環として、原料調達や製造過程の持続可能性を高める工夫が語られました。取締役‧CSO 兼 常務執行役員
横山之雄氏

サントリーホールディングス
サステナビリティ経営推進本部
シニアアドバイザー
北村暢康氏
北村氏は、水のサステナビリティをテーマに講演し、企業理念ならびにサステナビリティ経営の考え方のもと、自然環境への取り組み、中でも「水と生きる」企業として水資源の持続可能性に向け、専門家や地域社会との連携・協働を通じた森林保全活動の重要性について語られました。サステナビリティ経営推進本部
シニアアドバイザー
北村暢康氏

味の素
コーポレート本部 グローバル‧コミュニケーション部
サイエンスグループ シニアスペシャリスト
畝山寿之氏
畝山氏は、栄養とサステナビリティに関する取り組みを発表しています。世界的な栄養課題に対して、食品の栄養価向上や健康的な食生活を支援する活動が紹介されました。また、エシカル消費の推進や、社会貢献を意識した食品開発の重要性についても説明がありました。コーポレート本部 グローバル‧コミュニケーション部
サイエンスグループ シニアスペシャリスト
畝山寿之氏
持続可能な食の未来に向けて
今回のシンポジウムを通じて、日本の食品産業が直面する課題と、その解決に向けた具体的な方策が示されました。持続可能な食料システムの確立は、生産から消費までの各段階の関係者が一体となって取り組むべき重要なテーマです。
「合理的な費用を考慮した価格形成」と「付加価値向上」を実現させ、消費者を含めた関係者全員が納得できる価格を考えていくことが必要です。
「合理的な費用を考慮した価格形成」と「付加価値向上」を実現させ、消費者を含めた関係者全員が納得できる価格を考えていくことが必要です。
- 当サイト「フェアプライスプロジェクト」は令和4年度円滑な価格転嫁に向けた消費者理解醸成対策委託事業のうち広報事業で作成したものです。




