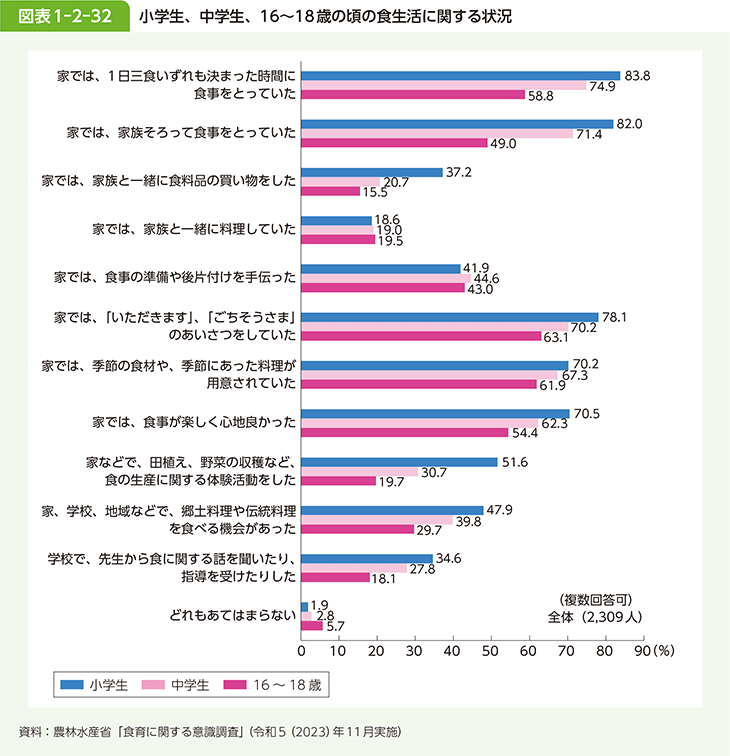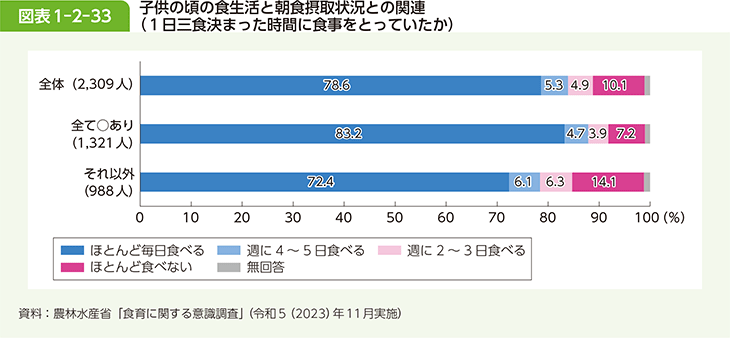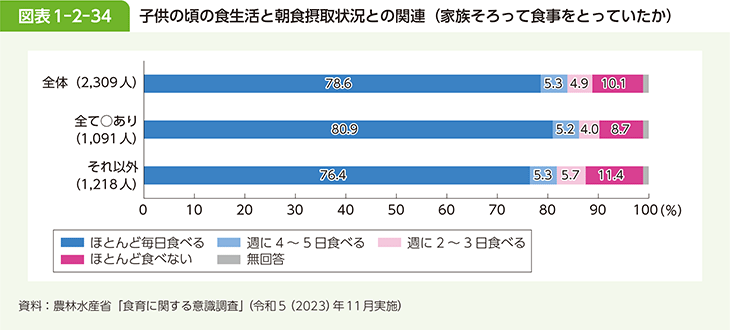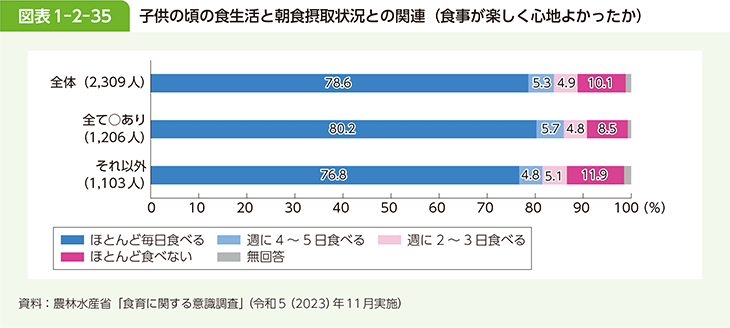3 子供・若い世代における食育の必要性
(1)子供の頃の食生活
小学生、中学生、16~18歳の頃の食生活について、「家では、家族と一緒に料理をしていた」又は「家では、食事の準備や後片付けを手伝った」以外の項目で、年代があがるにつれて「あてはまる」と回答した人の割合が減少しました(図表1-2-32)。
(2)子供の頃の食生活と朝食摂取との関連
「家では、1日三食決まった時間に食事をとっていた」について小学生、中学生、16~18歳のどの年代においても「あてはまる」人は、朝食をほとんど毎日食べる割合が高く、「あてはまる」以外の人は朝食を食べない割合が高い傾向がみられました。また、「家族そろって食事をとっていた」、「食事が楽しく心地よかった」についても、同様の関連がみられました(図表1-2-33、図表1-2-34、図表1-2-35)。
(3)子供・若い世代における食育の必要性
食育に関する意識調査の結果では、若い世代で食育に関心がある人の割合が低く、健全な食生活を送るための食品の選択や調理に必要な知識についても「あまりないと思う」又は「まったくないと思う」と回答した人の割合が高かったです。若い世代と重なり、また、乳幼児や小中学生の食育にも関わる世代である、子供と同居している世帯では、食育に関心がある人の割合が高い一方で、食品の選択や調理の知識については、「あまりないと思う」人の割合が高い状況でした。
家族と一緒に食事を食べる共食の頻度については、男性において「ほとんどない」の割合が高く、子供の年齢が高くなるほど、家族と食事を取る頻度が低くなる傾向がみられました。我が国において平均的には労働時間の短縮が進んでいるものの、男性の労働時間は依然として長いといった状況にあります。一方、平日で仕事があった日(出張・研修等の日を除く。)の有業者について、生活時間を年齢階級別にみると、25~34歳、35~44歳、45~54歳のいずれも、テレワーク(在宅勤務)をしていた人が、していなかった人に比べて長くなっている行動の種類の上位3位までに、食事の時間が入っていました(*1)。柔軟な働き方等により、共食の時間や食事を楽しむゆとりを創出することも食育を進めていく上で必要な視点であると言えます。
朝食の欠食や主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度について、若い世代で依然として課題がみられ、その理由としては「時間がないこと」、「食費に余裕がないこと」等が挙げられました。子供と同居している世帯については、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の回数を増やすために必要なこととして、特に乳幼児がいる世帯では「自分で用意することができること」の割合が低いという結果でした。さらに、普段の食事の準備について、男性と女性で異なる傾向がみられることに加え、乳幼児がいる世帯では、全体と比べて「一部市販食品を取り入れて、食事を準備している」の割合が高かったです。一方、若い世代では、今後、実践したいこととして、「栄養バランスのとれた食生活」又は「自分で調理すること」が挙げられており、栄養バランスに配慮して自分で料理もしたいが、時間がないこと等により、実践が難しいといった側面もうかがえました。
このような状況を踏まえると、若い世代が健全な食生活を実践するに当たっては、国、地方公共団体、関係団体、食品関連事業者等が協力し、健全な食生活の実践に必要となる食品、料理、食事等を入手しやすい環境を整備していくことが必要です。くわえて、自分で調理したいと思う人が手軽に料理に取り組むことができる場の提供や情報を発信し、実践につなげる機会を創出していくことも必要であると考えられます。健全な食生活を自ら実践していけるように、食に関する知識、食品の選び方等も含めた判断力を一人一人が備え、自ら食を選択する力を身に付けていくことも食育の目指すところです。健全な食生活に必要な知識や判断力は、年齢や健康状態、更には生活環境によっても異なってくるため、そのことへの配慮も必要です。
また、子供の頃の食生活について、「家では、家族と一緒に料理をしていた」及び「家では、食事の準備や後片付けを手伝った」以外の項目については、年代があがるにつれて「あてはまる」と回答した人の割合が減少していました。
子供の頃に健全な食生活を確立することは、生涯にわたり健全な心身を培い、豊かな人間性を育んでいく基礎となります。さらに、学校、保育所等で様々な学習や体験活動を通し、食料の生産から消費等に至るまでの食の循環を知り、自然の恩恵として命をいただくことや食べ物が食卓に届くまでの全ての人に感謝する気持ちを育むことも重要であり、引き続き、農林漁業体験の機会の提供等を通じた食育の推進に努める必要があります。
今後も、子供や若い世代の食育について、個々の家庭や個人の問題として見過ごすことなく、社会全体の問題として捉え、取り組んでいく必要があります。
*1 総務省「令和3年社会生活基本調査」
コラム:子供向けの減塩の取組
厚生労働省は、「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」において、活力ある持続可能な社会の構築を目指し、我が国の栄養課題の1つである「食塩の過剰摂取」の解決に向けて、健康的で持続可能な食環境づくりに取り組んでいます。その活動の1つとして、令和5(2023)年11月に、こども家庭庁及び消費者庁の協力の下、子供(主な対象は小学5・6年生)向けの減塩普及啓発資料「知っていますか?食塩のとりすぎ問題」を作成し、福岡、大阪、東京で本資料を活用したワークショップを開催しました。
ワークショップでは、料理に含まれる食塩量のクイズや、適切な食塩量の献立作成、食塩をとりすぎないための工夫や減塩に向けて自分自身や家族と一緒に取り組みたいことなどを発表し合いました。開催後のアンケートでは、約9割の子供が「食塩を減らす工夫をして、できるだけとりすぎに気を付けようと思った。」と回答しました。また、減塩に向けて取り組みたいことの記載では、「買物のときに食塩相当量を確認する。」や「減塩のことを発表する。みんなに興味をもってもらう。」などの意見があり、子供たちは「食塩の過剰摂取」の問題があることを学び、自ら次のアクションにつなげようと、意欲的に取り組んでいました。会場の保護者からは、「大変分かりやすかったので大人向けにも同じ内容でやってほしい。」、「知らなかったことが多く、勉強になった。」といった感想が聞かれ、ワークショップ中も積極的にメモを取る方も多くいました。

減塩普及啓発資料 表紙

減塩普及啓発資料 裏表紙

減塩普及啓発資料
「知っていますか?食塩のとりすぎ問題」
URL:https://sustainable-nutrition.mhlw.go.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/initiative_texta.pdf
(外部リンク)

ワークショップ開催レポート
URL:https://sustainable-nutrition.mhlw.go.jp/contents/workshopreport
(外部リンク)
コラム:牛乳を飲もう!こども食堂での取組
牛乳は豊富なカルシウムを含むだけではなく、良質なたんぱく質や脂質等がバランスよく手軽に摂取できる優れた食品であり、特に子供の発育期においては、発育に必要な栄養を摂取する上で欠かせない食品となっています。
このことからも、学校給食において広く牛乳が提供されているところですが、学校給食のない夏休みや冬休み等の長期休暇期間においては、子供たちの栄養バランスが崩れがちになり、特に牛乳に多く含まれるカルシウムについては摂取量が足りていないという調査結果も報告されています。
また、こども食堂については、子供たちが栄養のある食事を共にするよい機会であり、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止措置である行動制限が緩和されたことに伴い、活動が徐々に再開され始めてきたところです。
このような状況の中、農林水産省では、学校給食のない長期休暇期間にも、子供たちに栄養豊富な牛乳を飲む機会が得やすくなるようにするために、こども食堂において無償配布や割引クーポン(「冬休みも毎日牛乳を飲もう!クーポン」等)の配布などを行いました。
このような牛乳等の提供を通じて、子供たちの発育に必要な栄養の摂取を支援するとともに、食育活動を通じて、牛乳の栄養や機能性、また、食や生命、これらを支える酪農家の大切さを丁寧に分かりやすく伝えながら、食生活における牛乳の価値の向上と我が国の酪農に対する理解醸成に努めています。
事例:食事の提供を軸とした、学生寮・社員寮での取組
株式会社共立(きょうりつ)メンテナンス(東京都)
株式会社共立メンテナンスは、創業時から学生寮・社員寮を運営しており、「おいしいものをお腹いっぱい食べてほしい。」という想いから、手作りの料理の提供を寮の運営の軸としています。
管理栄養士が考案した朝夕の食事は、それぞれの寮で一食一食を手作りしており、おいしい食事の提供を行っています。食堂はコミュニケーションの場でもあり、学生たちがグループで食べる際には、共食の場にもなっています。提供される食事は、行事食や郷土料理を取り入れたり、国産の米や旬の野菜を取り入れたりするなど、季節のおいしいものを食べてもらえるよう心掛けています。近年は寮の食事の要・不要を管理できるアプリ「ドミコ」で、提供された料理ごとに付く「いいね」のマークでの反応も参考にして献立を検討したり、各寮の寮母さんによる「アイディア料理のコンテスト」を実施し様々な地域の料理を全国で展開したりしています。現在は、健康や栄養バランスに配慮した食事をとりたい、といった社会の動きも踏まえ、野菜摂取の増加に向けた取組も進めています。
寮での食事の利用状況は学生寮と社員寮では状況が異なっており、社員寮での利用が低いことが課題です。このため、社員寮では、寮の食事をサブスクリプションで提供するといった工夫も行っています。学生は保護者の意向で入寮することも多いですが、退寮後に「自分自身で食事を用意する大変さを感じ、寮での食事の提供のありがたさを再認識した。」といった声が聞かれています。
また、学生寮では寮長・寮母さんとの橋渡しや寮の運営等を担うレジデント・アシスタント(以下「RA」という。)プログラムを導入しており、RAの発信により学生寮で「こども食堂」を開設する取組も行われました。これがきっかけとなり、他大学の学生寮でも、こども食堂が開設されるなど、学生寮が地域づくりの場にもなってきています。
今後は、寮が「生活の場」としてだけではなく、地域に住む様々な世代の方々が寮に食事に来て、コミュニケーションを取れる、地域の憩いの場のような機能も持つ場づくりとしても地域に貢献しつつ、食育の取組を進めていきたいと考えています。
事例:子育て世帯が無理なく気軽に取り組める食育に向けて~子育て世帯を食生活の面から応援~
新潟県
新潟県では、すべての世代が生き生きと暮らせる「健康立県」を実現するため、「生きがい・幸福度」を軸に「食生活」、「運動」等の5つのテーマで取組を進めています。テーマの1つである「食生活」では、本県の主食・主菜・副菜をそろえた食事をする人の割合が少ないという課題から、キャッチフレーズを「からだがよろこぶ、一皿を足そう。」とし、特に食環境の整備に力を入れ、自然に健康な食事ができる環境づくり事業に取り組んでいます。本事業では、県内スーパーマーケット等と連携し、エネルギーや食塩相当量等、県独自の基準を満たした惣菜・弁当「からだがよろこぶデリ」を販売し、県民が健康に配慮した食事を手に取りやすい環境づくりを進めています。
また、令和5(2023)年度の食育月間には子育て世帯に向けた「無理なく気軽に食育!」のリーフレットを作成し、市町村等を通じて配布しました。仕事や家事・育児に忙しい子育て世帯が無理なく気軽に取り組める食育等について、管理栄養士からの具体的なアドバイスや、「からだがよろこぶデリ」を活用することで、家事時間の短縮と手軽にバランスのよい食事ができること等を紹介しています。
県内の南魚沼(みなみうおぬま)保健所では、本リーフレットを活用した取組が行われています。令和5(2023)年度の月間の取組の1つとして管内全保育所・認定こども園(26施設)と連携し、食事作りや準備を担っている保護者約1,500人を対象とした食育に関するアンケートを行いました。その結果、子育て世帯の食事の担当者は同年代と比較して、食育に対する関心が高く、「野菜を食べる」、「3食を食べる」、「家族そろって食べるよう心掛ける」ことを大切にしている一方、「野菜不足」、「栄養バランス」、「塩分や濃い味」を心配しており、「減塩」については「時間がない」、「調理技術の不足」等から難しく感じていることが伺えました。また、中食の利用頻度は同年代と比較して高い傾向があり、「時間がない」ことや核家族の増加が影響していることが考えられました。乳幼児期から学齢期までのこどもとその保護者は、保健所、市町村、保育所・こども園、学校等が連携することで、継続的かつ効果的に食育に関わることができる貴重な年代であるため、本保健所では横断的かつ効果的な情報発信や栄養ケアを実施するため「乳幼児期から学齢期までのシームレスな栄養ケアや食育を考える研修会」を定期的に開催しています。
今後もアンケート結果や地域課題を踏まえ、こどもや保護者に関わる機関や職種が連携し、子育て世帯が無理なく気軽に取り組める食育を進め、適塩やバランスの良い食事の定着につなげていきます。
事例:「朝」を応援する「HYOGO アサ@プロジェクト」で朝食欠食の減少を目指す
~産官学連携による食環境づくり~
兵庫県

プロジェクトのロゴマーク
兵庫県では県内の若い世代の朝食欠食がなかなか改善されない状況の中、朝食の摂取率を上げることを目指し、第4次兵庫県食育推進計画の開始をきっかけにHYOGOアサ@プロジェクトを立ち上げました。
本プロジェクトは、「朝」という時間帯に着目したプロジェクトです。プロジェクトの趣旨に賛同する企業・団体と一緒に、朝食欠食だけでなく、早寝早起き・良質な睡眠など、生活習慣改善の気付きの機会となるような様々な取組を実行しています。
また、従来から健康づくり部局が行ってきた子供たちへのアプローチのみならず、朝の時間を気軽に楽しんで過ごせるようなコンテンツを企業と連携して作りながら課題の解決を図ることをねらいとしています。
食は身近なテーマであり、企業の特色を生かした様々なアプローチが可能です。朝ごはんのレシピブックの作成、ラジオ番組の放送や県立の農業高校と協働した若い世代向けの商品開発等パートナー企業と県の関係課がアイディアを出し合い、プロジェクトを展開しています。
商品開発では、健康福祉事務所(保健所)の管理栄養士と連携し、朝食摂取の大切さ等の授業を行い、自分たちが大人になった時を想像して、どういうものだったら食べられるのか等、ターゲットとする層の気持ちになって商品を考えてもらいました。授業を踏まえて生徒自身が思い描いた商品を、試作を重ねながら作っていきました。
また、米を食べることを推進する県のプロジェクト「おいしいごはんを食べよう県民運動」との協働で兵庫県民農林漁業祭にブースを出展し、県内のスポーツチームの選手の朝ごはんを紹介する動画の放映とパネルの展示を行いました。動画はSNSでも発信し、若い世代への関心につなげています。朝ごはんに米を食べることをテーマとし、朝にしっかり食べることの大切さを伝えました。
本プロジェクトのウェブサイトは、「朝を楽しむところから始めませんか。」というコンセプトのもと、ポップなデザインに仕上げています。多様性の時代において、前向きに、楽しんで食べてもらえるよう、引き続き、関係者と連携しながら食育を推進していきます。
事例:地元企業の新入社員研修での食育の取組
~講話と調理体験を組み合わせ、自らの食生活に手軽に取り入れられる朝食を~
栃木県
栃木県では、県民一人一人が、楽しく健全な食生活を実践することにより、食に対する感謝の気持ちを深め、心身の健康と豊かな人間性を育むことを基本理念とした食育を推進しています。豊かな食に感謝し、親しむ機会を増やすため、食育ボランティア「とちぎ食育応援団」による、地域と連携した取組を進めています。「とちぎ食育応援団」の活動の一環として、平成23(2011)年10月から、就学前の子供とその保護者等を対象とした「食育出前講座(以下「講座」という。)」を公益財団法人栃木県農業振興公社に委託し、実施してきましたが、進学や就職で生活環境が変化することによって食生活が乱れがちになる若い世代に対しても食育を行う必要があるのではないかと考え、令和5(2023)年度から大学や企業を対象とした講座を開始しました。
令和5(2023)年度は県内企業である栃木トヨタ自動車株式会社(以下「栃木トヨタ」という。)の新入社員研修の中で講座を実施しました。栃木トヨタと協議の上、仕事をする上での朝食の重要性や、県産農作物への理解促進を盛り込み、食に関する専門的な知識も学べる内容としました。今回のポイントは、若い世代が食に関する講話で朝食の大切さを学び、くわえて県産の米や味噌を用いた調理体験を実施することで、食や食材としての農産物への理解が深めやすい点にあります。食事にかける時間が短い傾向が見られる新社会人や大学生が、日々の食生活に取り入れやすいミニおにぎり作りやみそ玉を用いたみそ汁作りといった調理体験を研修プログラムの中に組み込みました。
講座後のアンケートでは、「食と農についてよく理解できた。」、「県産の農作物について愛着がもっと湧いた。」、「朝、ジュースを飲むだけでなく、食事をとることの必要性を理解できた。」という声が聞かれました。アンケートの結果から、参加者の理解が進み、栃木トヨタの人事担当者からも有意義な研修が実施できたとの感想をいただきました。
本取組が地元のメディアで紹介されたことによる講座の反響が少しずつ出ており、他の企業からも新入社員を対象とした講座を実施したいとの希望が上がっています。この取組を通じ、若い世代を対象とした食育の重要性が改めて明らかになりました。
栃木県ではこれまでと同様に子供の頃から食の大切さを学んでもらう活動を継続するとともに、SNS等の若い世代が興味を持てるツールの活用も検討していきたいと考えています。今後も地域の声を捉えながら、食と農の理解を深めてもらえるような食育の取組を進めていきます。
事例:学校給食を中心に、食と農の持続可能な資源循環を学ぶ
横浜(よこはま)国立大学教育学部附属鎌倉(かまくら)小学校(神奈川県)
横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校では、生命を尊重し、健康の保持増進や持続可能な社会の実現に向けて、自ら実践する能力や態度を育てるための食育を推進しています。
食育活動の1つとして、給食の残渣(ざんさ)等を活用して堆肥を作り、その堆肥を使って農薬を使わずに野菜を栽培・収穫する取組があります。校内の生ごみを削減するため、令和2(2020)年から中庭にコンポストを設置し、年間約4トンの調理残渣や残菜を堆肥化しています。4年生の総合的な学習の時間では「究極の小松菜を育てよう」を目標に、有機野菜を栽培している生産者の畑へ見学に行き、栽培方法や小松菜に適した土等について教えていただきました。その学びを生かし、コンポストでできた堆肥を利用して小松菜の栽培を行いました。収穫した小松菜は、検品・包装して校門前で販売し、収益は、児童から「ユニセフへ募金したい。」と希望があり全額寄付しました。このほか、有志保護者によるPTA活動では、コンポストの堆肥を使用して農薬を使わずに野菜を栽培し、収穫した野菜を給食の食材として使っています。このように、給食の残渣等を堆肥化し、育てた野菜を生きた教材として給食に提供することを通じて、児童は食と農の持続可能な資源の循環を学んでいます。
また、栄養教諭による各教科と連携した食育の授業も積極的に行っています。例えば、国語科の教科書に出てくる食材である大豆を取り上げ、大豆を使った食品がどのようにできるか、どのような種類の加工品があるのかなど、実物の食品を用いて授業を行ったり、給食に大豆や大豆製品を使用したりすることで、机上の学びから五感で味わう食体験ができる取組を行っています。授業後には児童から「教科書に載っていない食品もあって楽しかった。」、「こんなにたくさんの種類があるのはすごい。」などの声が上がるなど、児童の食への興味や食の選択の幅を広げることができたのではないかと考えています。
さらに、令和3(2021)年には、総合的な学習の時間を活用し、和食文化について学ぶ授業を行いました。児童は、和食の基本を学んだり、鎌倉の郷土料理である「けんちん汁」と関わりの深い建長寺(けんちょうじ)の方に由来などを伺ったりした後、郷土料理「けんちん汁」を含む給食を食べました。こうした取組を通じて、児童は家庭でも和食や伝統的な行事食を作ったり、調理方法を調べたりするようになり、和食への興味・関心が高まる様子がみられました。
今後も、様々な食育活動を通して、望ましい食習慣を理解し実践できる力を育てていきたいです。
事例:農業体験を通じて命を大切にする心を育む(第7回食育活動表彰 審査委員特別賞受賞)
富士文化(ふじぶんか)幼稚園(愛知県)
富士文化幼稚園では、毎年、JA(農業協同組合)、地域のボランティア、園の給食担当の事業者とともに、食育の年間計画、目標を立て、園児や親子で種まき、植え付け、収穫等の農業体験や行事食のイベントを提供する取組を行っています。園内外で子供たちが自ら米や野菜の栽培に関わり、収穫し、食べる体験をすることで、生きものは全て、他の命をいただいて生きていることを知り、命を大切にする心を育んでいます。野菜等の生長を見守る中で、昆虫等の命についても学んでいます。親子で体験する機会も作ることで、一緒に命をいただくことの意味を考えることができ、より深い学びにつなげています。命の恵みを工夫して生活に取り入れる取組として、玉ねぎの皮を使った染物体験も行っています。
実際に体験することで、子供たちに「楽しい」や「おいしい」を感じてもらうことに加え、絵本の読み聞かせで生き物の命の大切さを伝えています。このような取組を、園の広報で保護者に情報発信することで、保護者からは「野菜を栽培・収穫することで子供が食への関心が高くなった。」、「好き嫌いが少なくなった。」、「食べられなかった野菜や食材を食べるようになった。」などの感想が寄せられています。園での様々な活動を通して園児や保護者の食育への関心が高まっています。
今後は、栽培の品目を増やすこと、育てた米を給食で使用すること等も予定しています。食べ物となった生き物に、「命をくれてありがとう。」、「いただきます。」、「ごちそうさま。」と、感謝する言葉の意味を、子供たちに伝えるとともに、命を大切にする心を育む、食育活動を進めていきます。
事例:調理体験を通じて、次世代を担う高校生たちにふるさとの味をつなぐ
(第7回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞)
熊本(くまもと)市食生活改善推進員協議会(熊本県)
熊本市食生活改善推進員協議会は、地域の高校生に対する郷土の食材や郷土料理の伝承活動を中心とした食育活動を継続的に展開しています。平成17(2005)年から次世代を担う高校生を対象に「思春期の食育推進事業」として、熊本の食文化の理解と自身の健康を守るスキルを身に着けることを目的として開始しました。現在では家庭科授業の年間行事として定着しています。
調理体験を通して、ひご野菜である春日(かすが)ぼうぶら等の地元の農産物や、南関(なんかん)あげ、海苔、大豆等の地元の食材への理解と、地産地消の重要性を伝えています。高校の教諭との打合せを綿密に行い、参加者に合わせた内容を実施することで再現性を高め、1度きりにならない食文化の伝承を目指しています。さらに、食生活改善推進員が生徒に積極的に声を掛け、気軽に質問をできる雰囲気を作り、生徒が等しく調理を体験できるように工夫しています。生徒からは「教えてもらった郷土料理を将来、自分の子供に伝えたい。」といった声も聞かれています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響下では、行政と協働で動画を作成配信し、再生回数は4.1万回を超え、新たな日常に対応した食文化の継承にも力を入れています。
今後は、若い世代に対して、料理を作る楽しさを通した、心に残る食体験を継続して提供するとともに、新たな動画の作成等により、より多くの方に郷土料理を伝承していきます。
事例:地域における食農教育・農業教育の取組
食育の推進は、学校教育の現場においても学校給食や関連する教科学習、農業体験等を通じて積極的に行われています。
埼玉県熊谷(くまがや)市立妻沼(めぬま)小学校では、平成27(2015)年度に、学校の花壇で給食に使用する野菜の栽培を始め、現在では学校の敷地内にある畑でも野菜を栽培・収穫し、給食として提供して食べる、「エディブル・スクールヤード」の取組を行っています。給食に必要な食材が思うように購入できなかったことをきっかけに、栄養教諭の発案で、自分たちで野菜を作ろうと考えたところからこの取組が始まりました。現在では、栄養教諭が畑の栽培計画を作成し、玉ねぎやキャベツ、米や大豆等、1年間で約20種類の作物を栽培しています。畑の管理は食育担当の教員と3年生の児童が主担当となり、地元の農家や種苗(しゅびょう)会社、障害者支援を行っている農業団体の方の協力を得ながら行っています。農業体験は畑の栽培計画に基づき、各学年の年間の学習計画にも盛り込まれており、「大好き!妻沼の野菜」をテーマに、1・2年生は生活科、3・4年生は社会科・総合、5・6年生は社会科・理科・家庭科と関連付けて授業を行っています。このように子供たちが授業で収穫した野菜のほか、地域の農家から提供される地元産のにんじんや長ねぎ等を給食に活用しています。さらに、令和2(2020)年からは障害者支援を行う農業団体が所有する学校の近くの水田で3年生と5年生の児童が米作りも行っており、農業団体のスタッフのサポートを受けながらみんなで一緒に田植えや稲刈りをします。米の収穫後、全校児童が昔ながらの足踏み式脱穀機で脱穀し、その米でおにぎりを作り、収穫祭でふるまい、地域の方々へ感謝の気持ちを伝えます。この取組を通して、子供たちからは「自分たちや他の学年が作った野菜だから、残さず食べよう。」といった声や、「もしかしたら、農業は僕の将来の職業選択のひとつになるかもしれない。」という声があがっています。今後も、農業体験を通じて食への感謝や農業への興味を引き出し、将来、地域の農業を支えていけるような心を育む活動に取り組んでいきます。
また、令和5(2023)年4月に徳島県神山町(かみやまちょう)でテクノロジーやデザインを学びながら起業家精神を養うことを目的に開校した神山まるごと高専では、学生自ら「まるごとファームクラブ」を立ち上げ、地元の農家や食農教育を推進する民間団体等と協力しながら、野菜の栽培や収穫に勤しんでいます。
まるごとファームクラブは、開校後初めて立ち上がった、30人規模の学生が所属する学内最大の部活動です。発起人の学生は当初、個人の活動として農作物を育てられればと考えていましたが、日常の風景の中に田んぼや畑がある神山町での生活を通して自ずと多くの学生たちが農業に興味を持ったことで、たくさんの学生たちが集まり、正式な部活動となりました。
活動としては、基本的には学生たちが話し合いながら、自分たちで植えたいものや地域の方々から頂いたものを中心に、ジャガイモなど数種類の作物を栽培しています。また、春から秋にかけては地域の方から指導・助言を得ながら、田んぼでの米作りも行いました。活動に当たっては、技術的な指導から農具の提供まで、地域の農家の方々やJA、NPOなど、様々な地域の方々からの理解・協力を得ながら日々の農作業を行っています。
農作業の協力を行っているNPOや学校側としても、高専生が農業に従事することは、我が国の未来を担う若者たちが農業への理解・関心を高め、持続可能な農業の発展にもつながるのではないかと好意的に捉えています。中山間地にある神山町での農業は、大型機械を導入することが難しく、決して効率的に行えるわけではありません。しかし、こうした農作業を通じて、学生自身が農業をめぐる様々な問題を痛感し、今後の農業にとってどのようなモノ・コトが必要なのか、また、神山まるごと高専生として、テクノロジーやデザインの視点からどうやって解決できるかといったことを考えるきっかけとなることが期待されています。また、雑草取りや畝(うね)づくりといった一つ一つの手作業を通して、1つのモノをつくる達成感を得られたり、日々の作業の中でトライ&エラーを繰り返し、課題に対してどのようなアプローチをすれば効率的かつ持続可能な形で解決できるかを学んだりする貴重な機会となっています。
今後は、収穫した野菜について、全寮制の学生の食を支える学生食堂で提供することや、道の駅で販売することも視野に入れながら、「神山まるごと高専×農業」という新しい取組を更に進めていきます。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4551)
ダイヤルイン:03-3502-1320