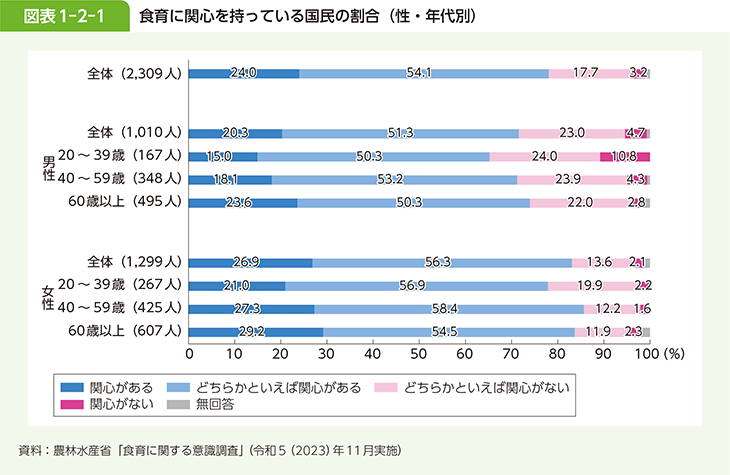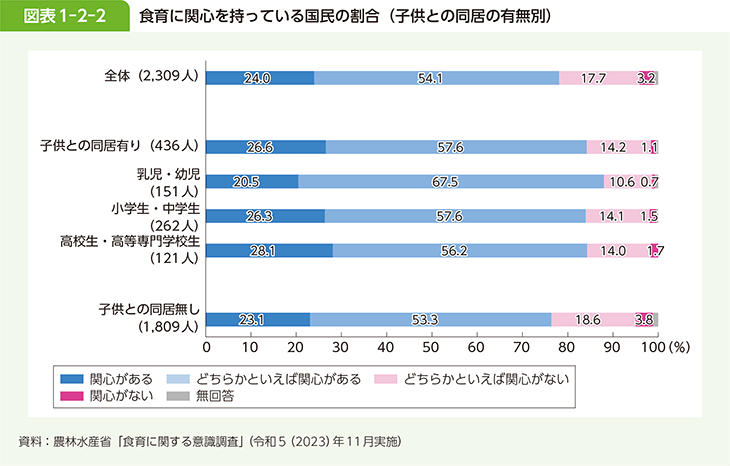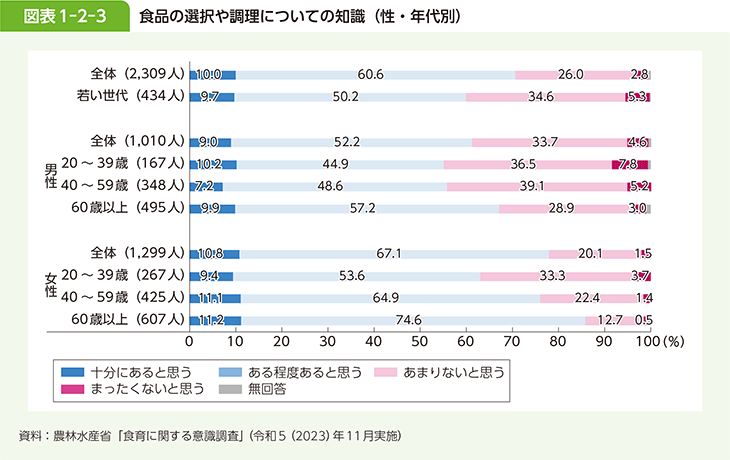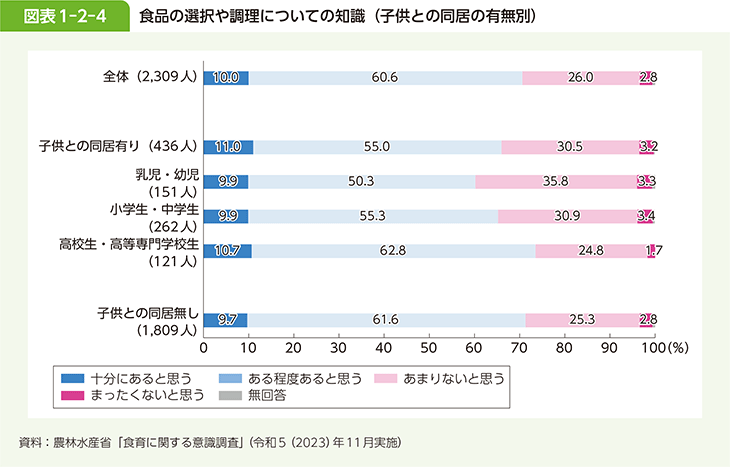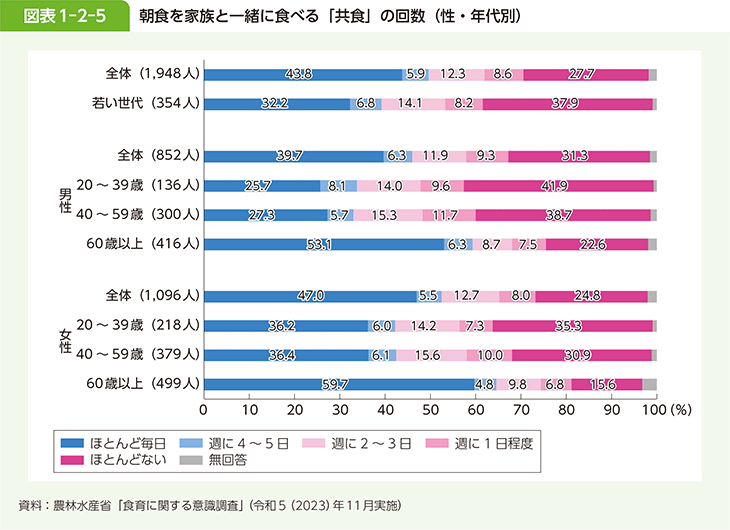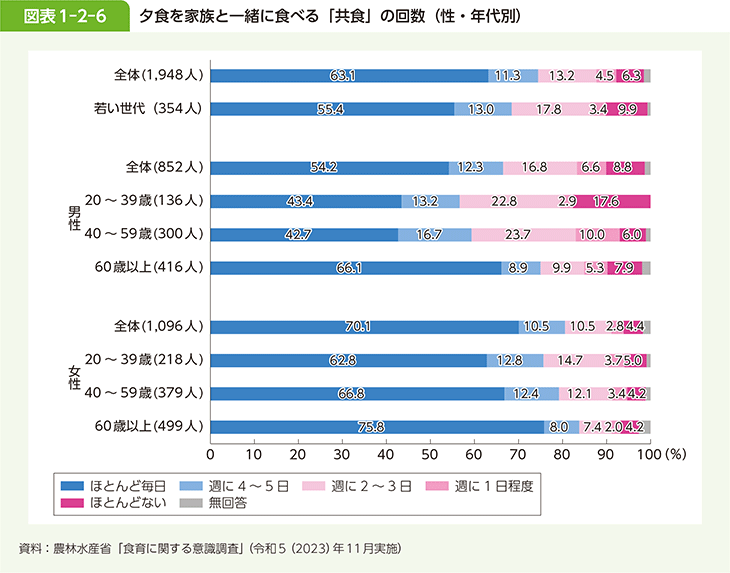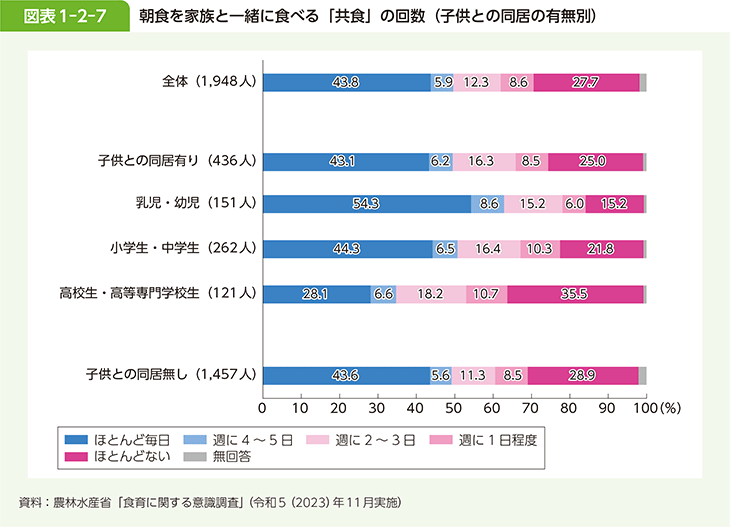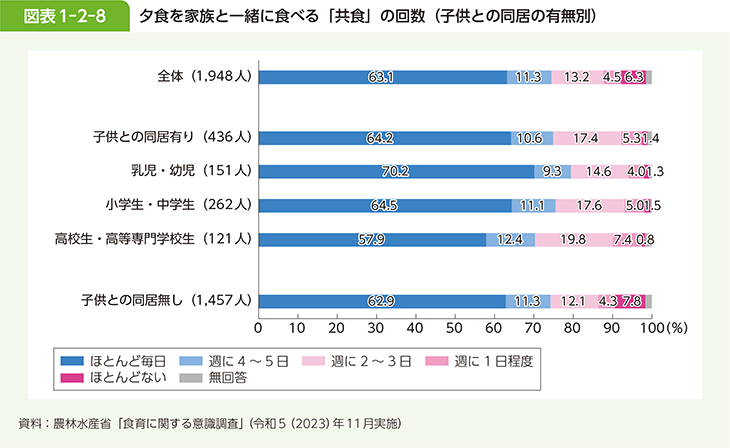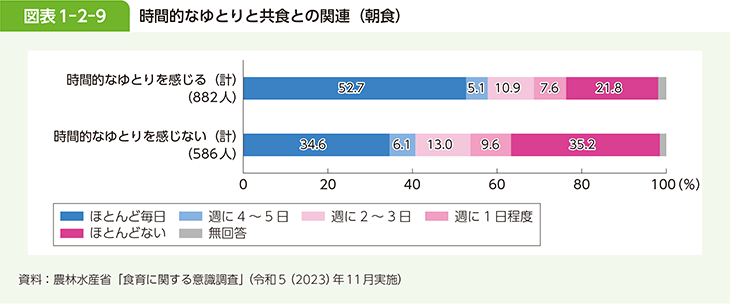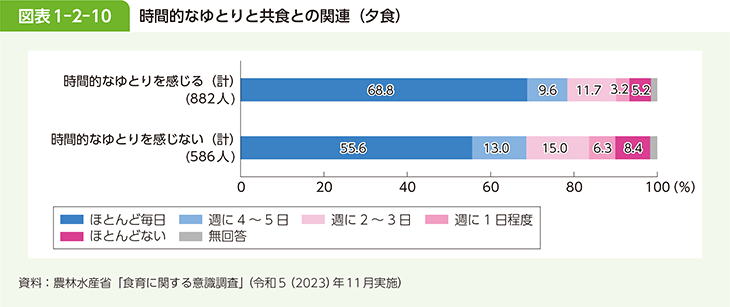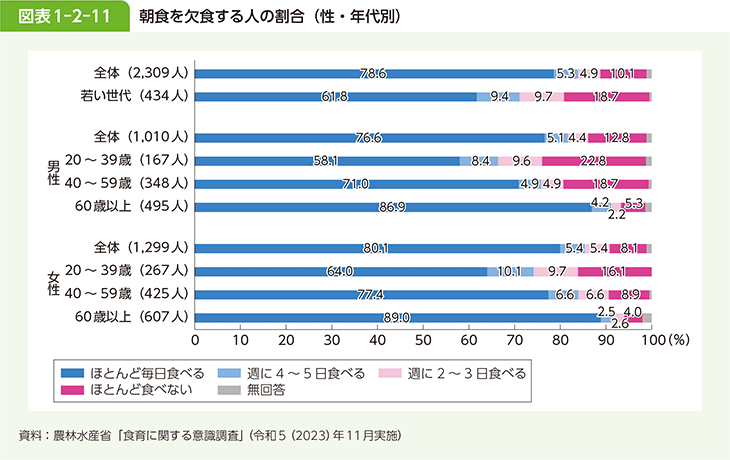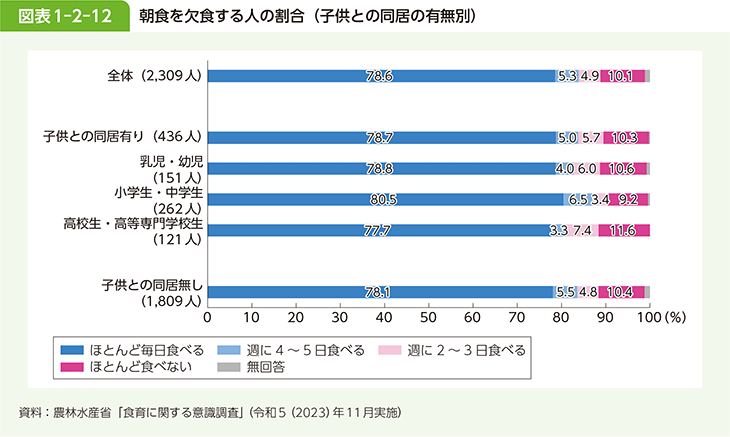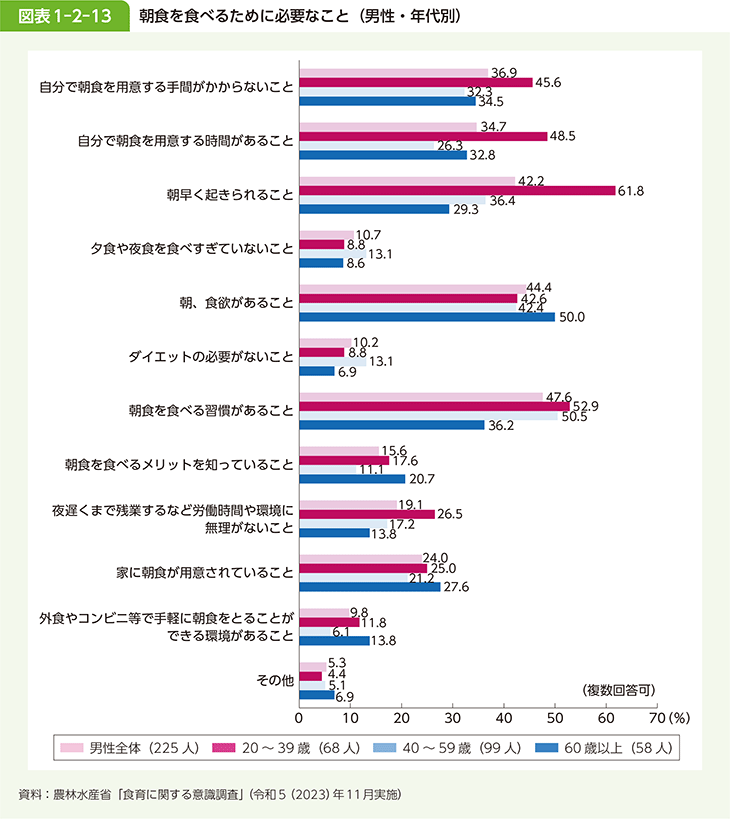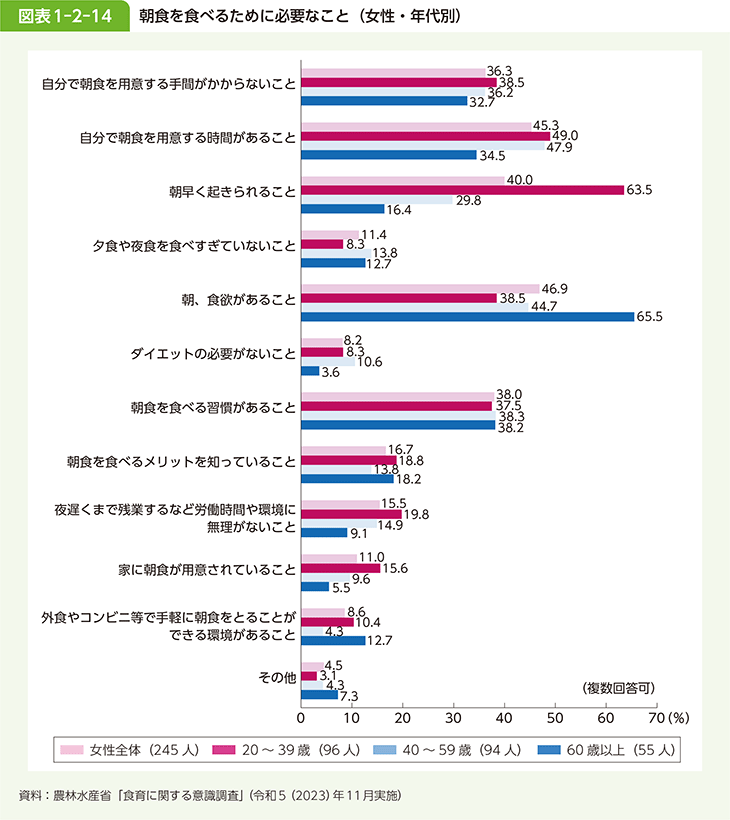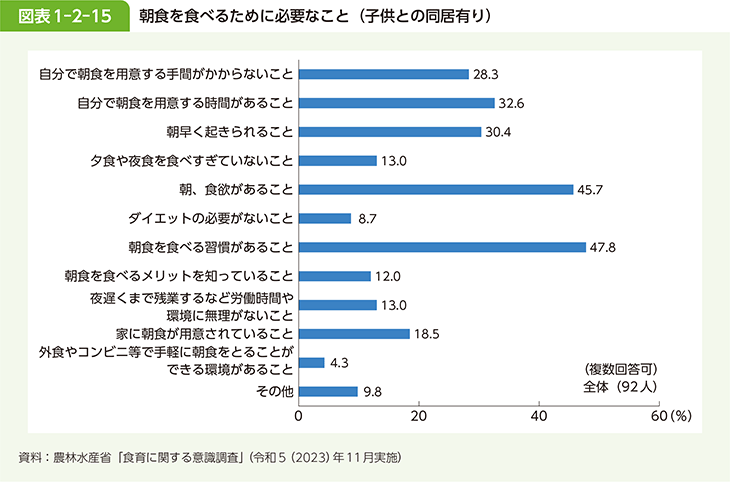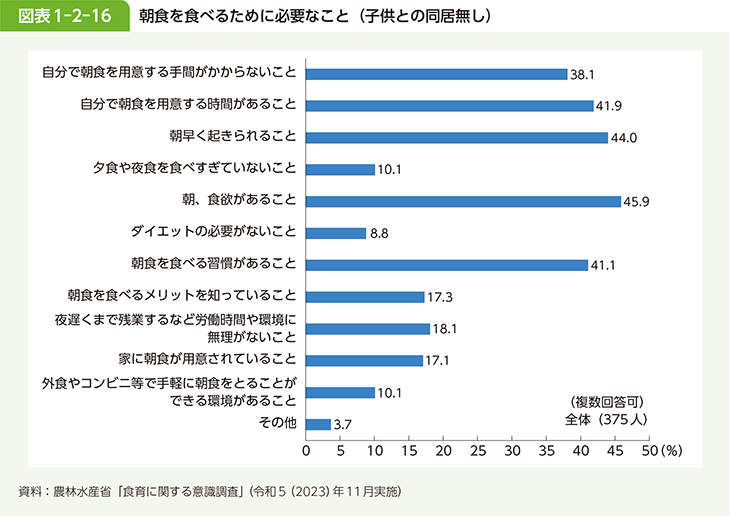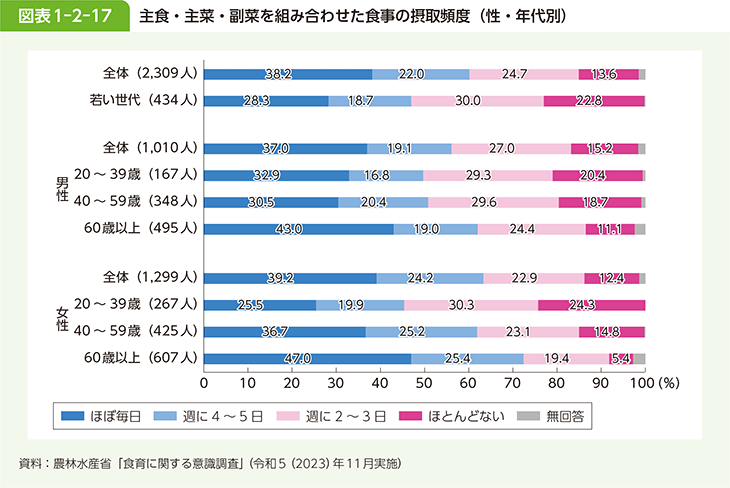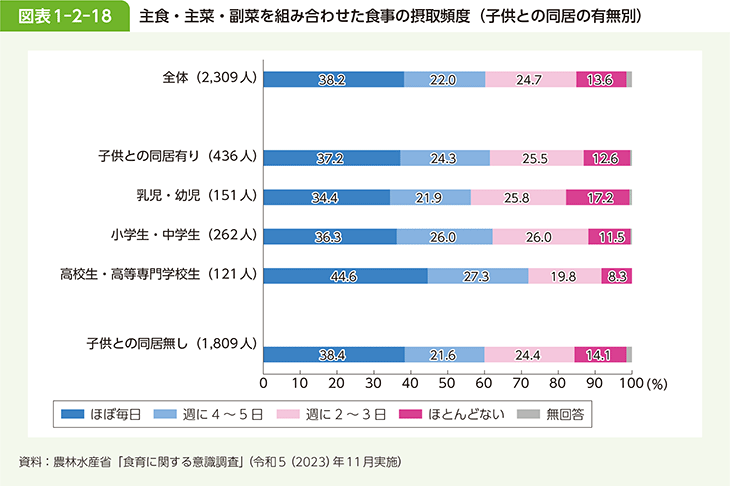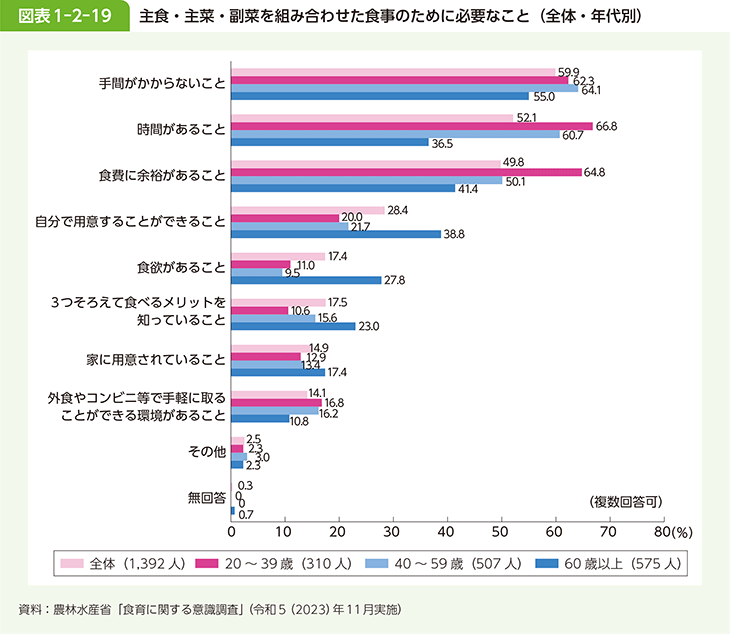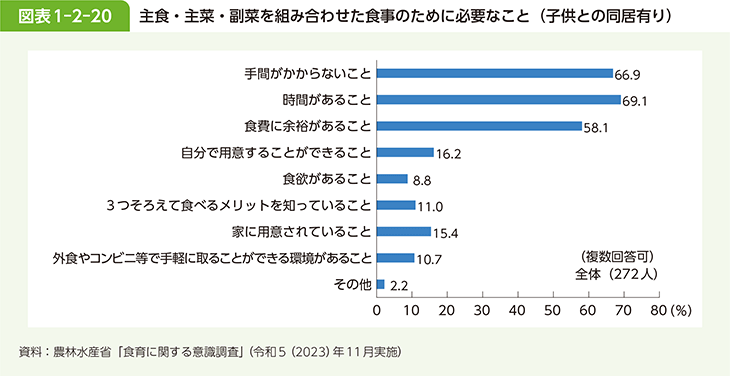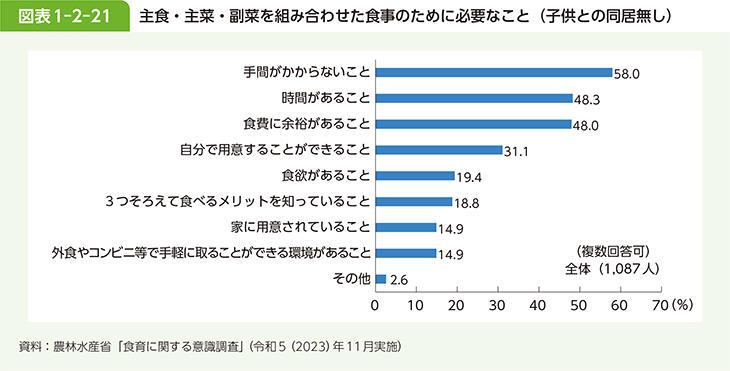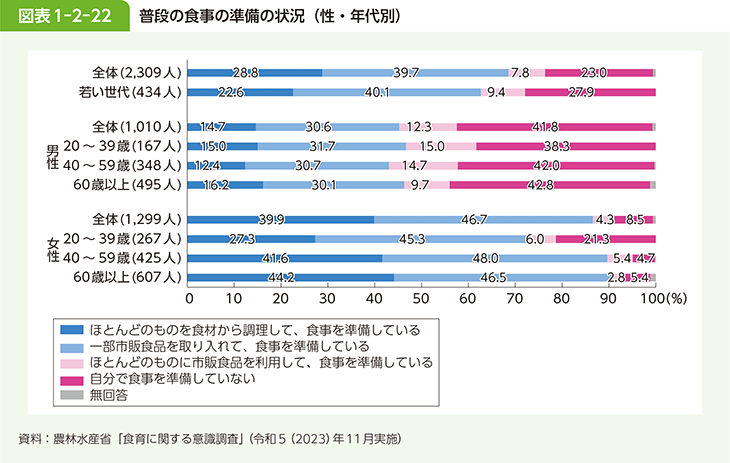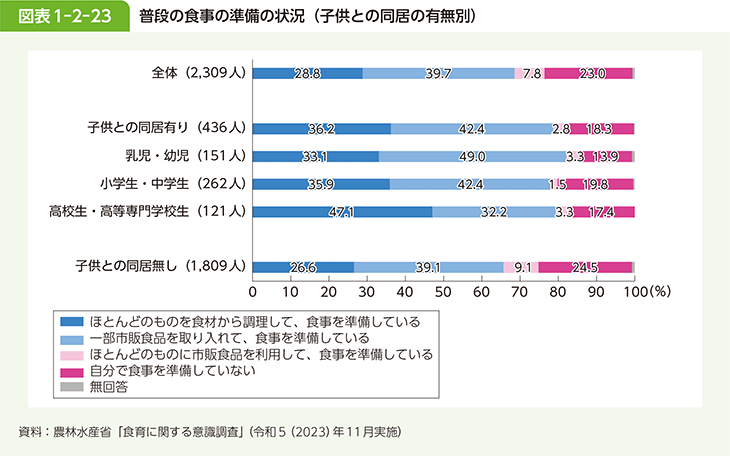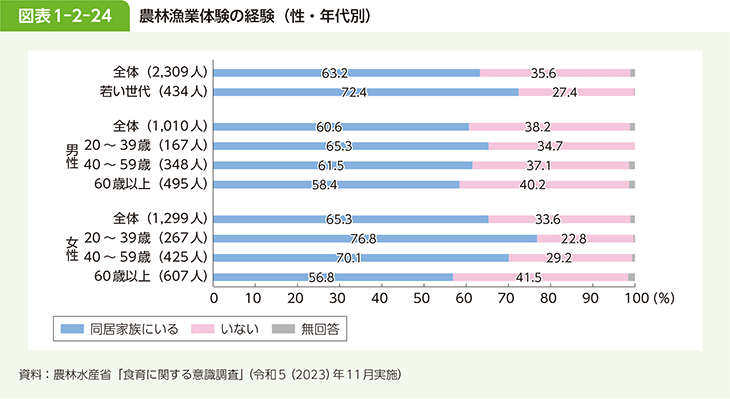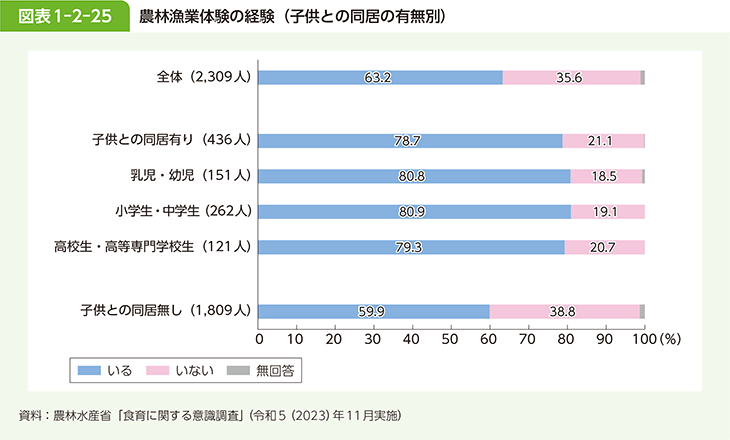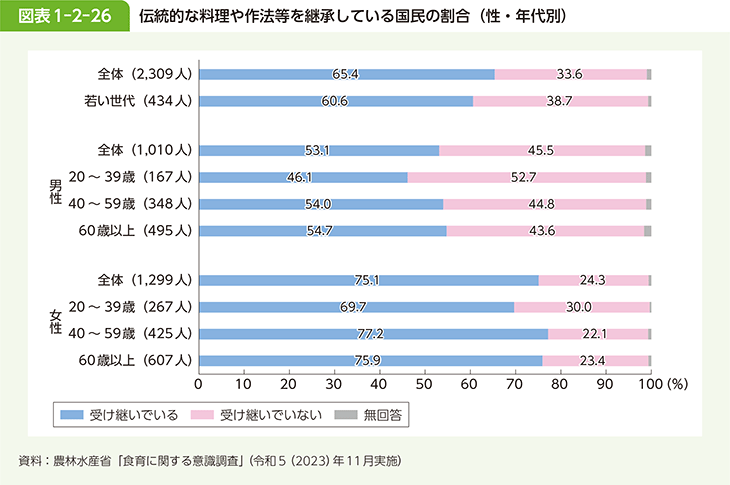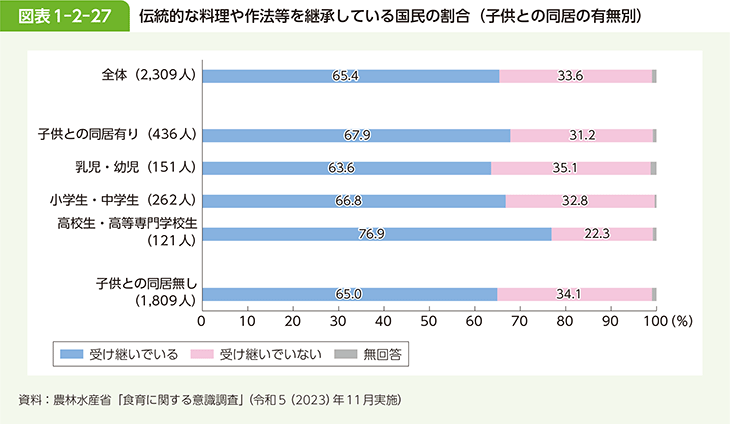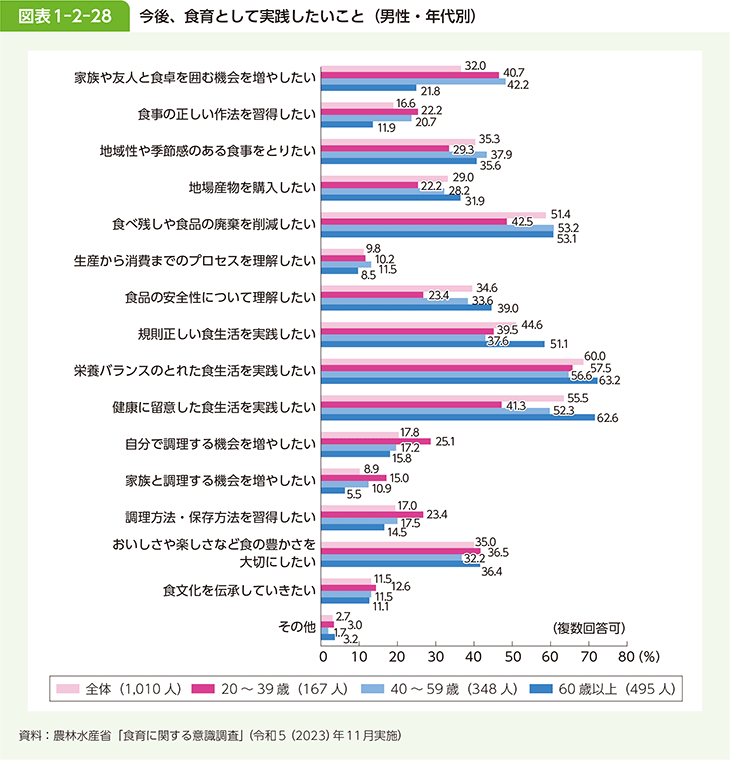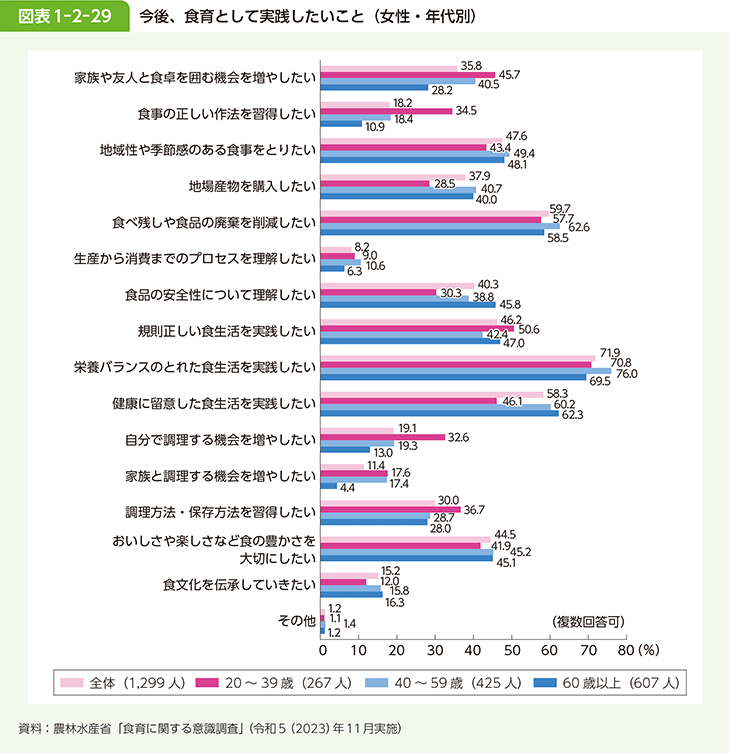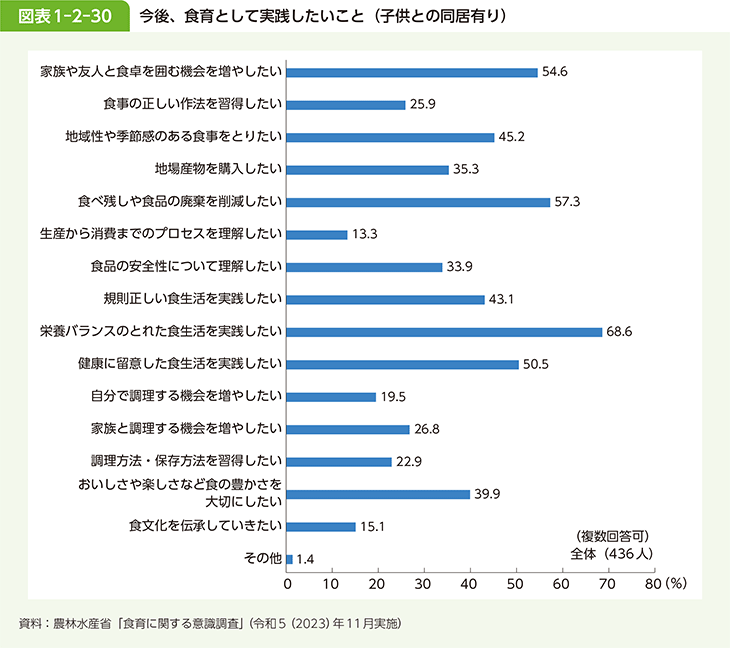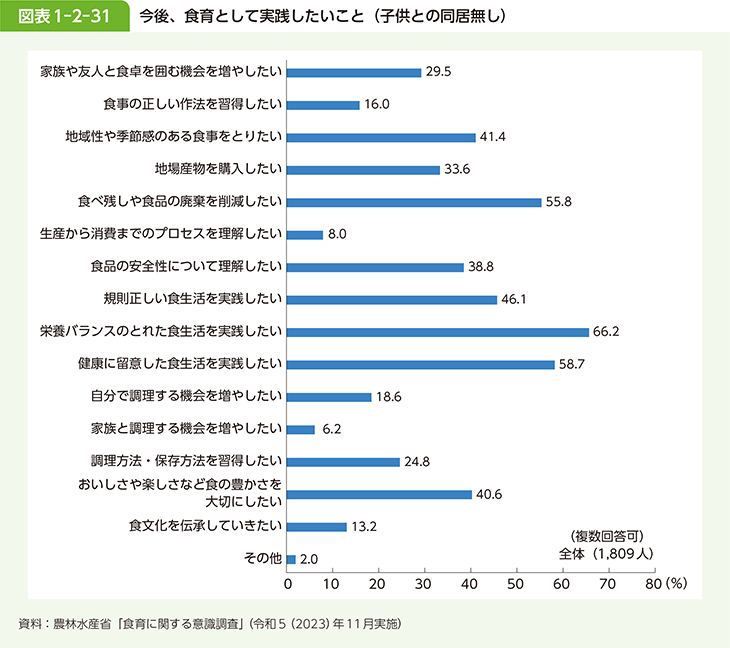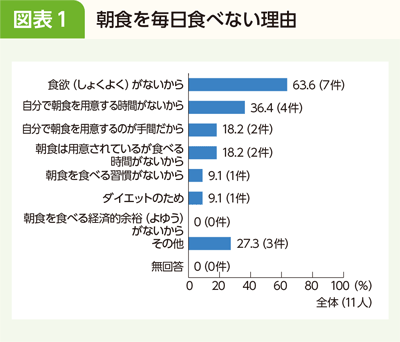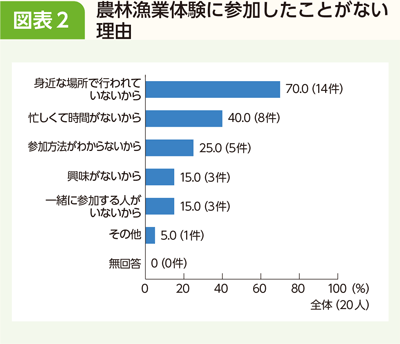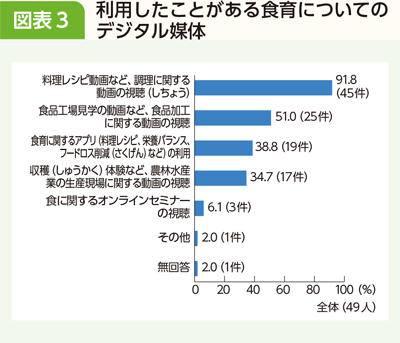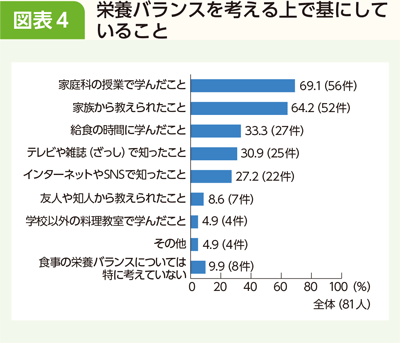2 子供・若い世代における食育への関心や食生活等の現状
ここでは、子供や若い世代、子供(18歳未満)と同居している世帯(*1)における食育への関心や食生活等の現状について、令和5(2023)年度「食育に関する意識調査」(*2)の結果等から示します。
*1 乳児、幼児、小学生、中学生、高校生、高等専門学校生の子供と同居している世帯(孫と同居している世帯を除く。)
*2 全国20歳以上を対象に、令和5(2023)年11月に、郵送及びインターネットを用いた自記式で実施
(1)食育への関心
食育に関心を持っている(「関心がある」及び「どちらかといえば関心がある」)人の割合について、若い世代では男性65.3%、女性77.9%でした。男性では「関心がない」と回答した人の割合が高く(図表1-2-1)、子供(18歳未満)と同居している世帯(以下「子供と同居している世帯」という。)では、食育に関心を持っている人の割合は84.2%であり、全体と比較して高いという結果でした(図表1-2-2)。
(2)食品の選択や調理についての知識
健全な食生活を送るために必要な食品の選択や調理の知識について、若い世代では「あまりないと思う」及び「まったくないと思う」と回答した人が39.9%で、全体と比べて高いという結果でした(図表1-2-3)。子供と同居している世帯でも同様の傾向がみられました(図表1-2-4)。
(3)家族と一緒に食べる「共食」の頻度
朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数について、若い世代で「ほとんどない」と回答した割合は、朝食で37.9%、夕食で9.9%と高い結果でした(図表1-2-5、図表1-2-6)。また、子供の年齢が高くなるほど、共食の頻度が低くなる傾向がみられました(図表1-2-7、図表1-2-8)。
共食の頻度と時間的なゆとりの関連について、「時間的なゆとりを感じる」と回答した人では朝食や夕食の共食の回数が「ほとんど毎日」と回答した割合が高く、「時間的なゆとりがない」と感じている人では朝食や夕食の共食の回数が「ほとんどない」と回答した割合が高い状況でした(図表1-2-9、図表1-2-10)。
(4)朝食を食べる頻度
朝食を欠食する人(「週に2~3日食べる」及び「ほとんど食べない」)の割合について、若い世代では28.3%と全体と比べて高い状況で、特に男性では「ほとんど食べない」と回答した人が22.8%となっています(図表1-2-11)。子供との同居の有無別でみると、全体と比べて大きく異なる状況はみられませんでした(図表1-2-12)。
(5)朝食を食べるために必要なこと
朝食を食べていない人(「週に4~5日食べる」、「週に2~3日食べる」及び「ほとんど食べない」)に、朝食を食べるために必要なことについて聞いたところ、若い世代では「朝早く起きられること」が最も多かったです。また、男性では「朝食を食べる習慣があること」、女性では「自分で朝食を用意する時間があること」が全体と比べて多くなっており、年代や男女によっても特徴が異なりました(図表1-2-13、図表1-2-14、図表1-2-16)。一方、子供と同居している世帯では、「朝早く起きられること」と回答した人は少なかったです(図表1-2-15)。
(6)主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の摂取頻度
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている人の割合について、若い世代では、28.3%で全体と比べて低い結果でした(図表1-2-17)。子供と同居している世帯では、高校生・高等専門学校生がいる世帯で高い傾向がみられました(図表1-2-18)。
(7)主食・主菜・副菜を組み合わせた食事のために必要なこと
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べていない人(「週に4~5日」、「週に2~3日」又は「ほとんどない」に回答)に、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を食べる回数を増やすために必要なことについて聞いたところ、若い世代では「時間があること」又は「食費に余裕があること」が多いという結果でした(図表1-2-19)。子供と同居している世帯でも、「時間があること」、「手間がかからないこと」又は「食費に余裕があること」が多いという結果でした(図表1-2-20、図表1-2-21)。
(8)普段の食事の準備の状況
普段の食事の準備について、若い世代では「自分で食事を準備していない」と回答した人の割合が27.9%で全体と比べて高い結果でした。女性では「ほとんどのものを食材から調理して、食事を準備している」又は「一部市販食品を取り入れて、食事を準備している」と回答した人の割合が高く、男性では「自分で食事を準備していない」と回答した人の割合が高いなど、男女で異なる状況がみられました(図表1-2-22)。乳幼児がいる世帯では、全体と比べて「一部市販食品を取り入れて、食事を準備している」の割合が高いという結果でした(図表1-2-23)。
(9)農林漁業体験の経験
農林漁業体験を経験した人の割合(本人又は家族の中に、農林漁業体験に参加した人がいる割合)は、若い世代では72.4%、子供と同居している世帯では78.7%でした(図表1-2-24、図表1-2-25)。
(10)地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等の継承
地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承している人の割合について、若い世代では60.6%、子供と同居している世帯では67.9%でした(図表1-2-26、図表1-2-27)。
(11)今後、食育として実践したいこと
今後、1年間にどのようなことを食育として実践したいか尋ねたところ、男女ともに、また子供との同居の有無にかかわらず、「栄養バランスのとれた食生活を実践したい」を挙げた人が最も多く、ほかの世代に比べて若い世代では「自分で調理する機会」又は「家族と調理する機会」等を増やしたいと考えている人が多い傾向がみられました。また、男性と女性でみると、男性は全体的に低く、女性は全体的に高い傾向でした(図表1-2-28、図表1-2-29、図表1-2-30、図表1-2-31)。
コラム:こども若者★いけんぷらす「いけんひろば」~こども・若者への食育の推進について~
平成17(2005)年に施行された「食育基本法」には、こどもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには「食」が重要であること、また、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができるよう食育を推進することが掲げられています。
より良い食育を推進するためには、当事者である世代の意見を聴くことが重要です。こども家庭庁では、こどもや若者が様々な方法で自分の意見を表明し、社会に参加することができる新しい取組として、令和5(2023)年度に「こども・若者意見反映推進事業(こども若者★いけんぷらす)」を開始しました。農林水産省では、当該世代の課題やニーズを把握するため、「こども若者★いけんぷらす」の中で、「こども・若者への食育の推進について」をテーマとした意見交換等を行いました。本テーマでは、こども・若者に関わる様々なテーマについて広く意見を伝えてくれる「ぷらすメンバー」のうち、小学5年生~高校3年生世代を対象として、ウェブ上でアンケートを実施し(回答数:81件)、実態を把握しました。その後、希望者に集まってもらい、「朝食欠食」、「農林漁業体験」、「デジタル技術を活用した食育」及び「栄養バランスのよい食事を組み立てる力」のグループに分かれ、それぞれの取組を実施するに当たっての課題や必要だと思う支援について意見交換を行いました(参加者数:22人)。
【ウェブアンケート結果の概要】
- 朝食を「ほとんど毎日食べる」又は「週に4~5回食べる」と回答した人の割合は93.8%。朝食を毎日食べない理由として、「食欲がないから」、「自分で朝食を用意する時間がないから」等が挙げられた(図表1)。
- 農林漁業体験に参加したことが「ある」と回答した人の割合は75.3%。参加したことがない理由として、「身近な場所で行われていないから」、「忙しくて時間がないから」等が挙げられた(図表2)。
- これまで食育を扱ったデジタル媒体を利用したことが「ある」と回答した人の割合は60.5%。食育についてのデジタル媒体のうち、利用したことがあるものは「料理レシピ動画など、調理に関する動画の視聴」、「食品工場見学の動画など、食品加工に関する動画の視聴」等が挙げられた(図表3)。
- 食事の栄養バランスについて何を基に考えているか尋ねたところ、「家庭科の授業で学んだこと」、「家族から教えられたこと」等が挙げられた(図表4)。
【対面での意見交換の概要】
- 朝食欠食について、毎日朝食を摂取しているこどもがいる一方、「食事で考えることは、栄養よりも値段である」、「家族も朝食を食べる習慣がない」等の、必ずしも朝食摂取を必要と認識していないという意見が挙げられた。
- 農林漁業体験についてより多くのこどもに農林漁業体験に参加してもらうアイディアとして「身近な場所で体験ができること」、「テレビやラジオ、SNSでの積極的な情報発信」等が挙げられた。農林漁業体験を通じて考えたことについては、「一工程だけではなく、(田植や稲刈りまでなど)様々な工程に関われると感動できると思う」又は「1週間くらい(農林漁業の現場で)一緒に働いてみたい」といった、より踏み込んだ体験活動に参加したいという意見が挙げられた。
- デジタル技術を活用した食育について、食育に関して使ってみたいデジタル技術やアプリについて、「自分の食生活を管理するアプリ」「食に関する相談サイト」という意見があった一方、「食育に関するアプリは見ないし、調べたこともないので広告にも出てこない」といった意見が挙げられた。
- 栄養バランスのよい食事を組み立てる力に関する質問について、栄養バランスについてより身近に感じられるツールとして、アプリやSNSの活用が挙げられた。また、参加者自身が健康のために気を付けていることとして、不足している栄養素を食事で補うという意見が多く挙げられた。
ウェブアンケート及び対面の意見交換では、普段から自分の食生活について積極的に考えているという意見や、関心や知識はあるものの、実践したり取り入れたりする機会がないという意見が得られました。それぞれのグループで、参加者自身の生活や経験から、取組に参加するための工夫や課題について活発な意見交換が行われました。
ここで得られた意見は、関係府省庁で共有し、今後の施策への反映を検討していきます。また、本事業の詳細は、こども家庭庁ウェブサイトに掲載しています。

こども・若者意見反映推進事業 いけんひろば
~こども・若者への食育の推進について~
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/iken-plus/hiroba/shokuiku/(外部リンク)
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4551)
ダイヤルイン:03-3502-1320