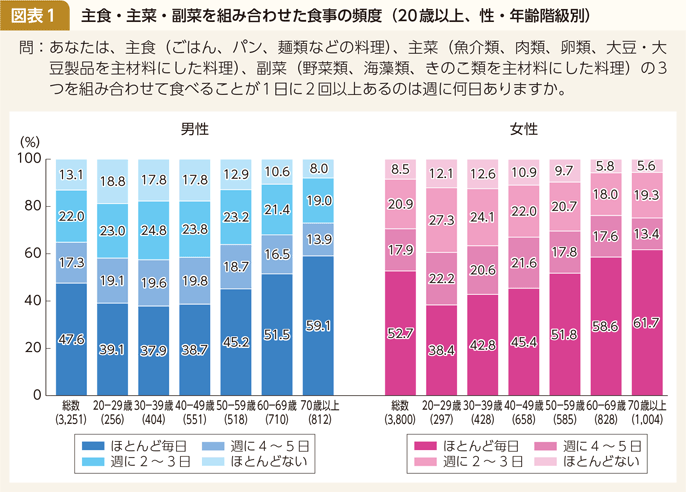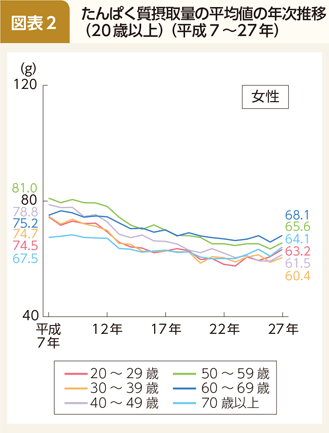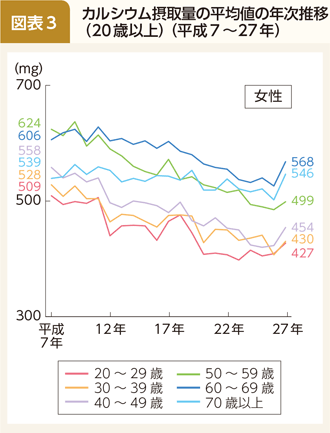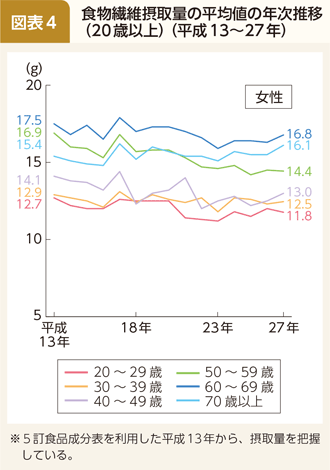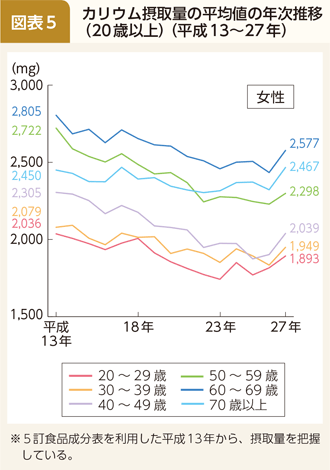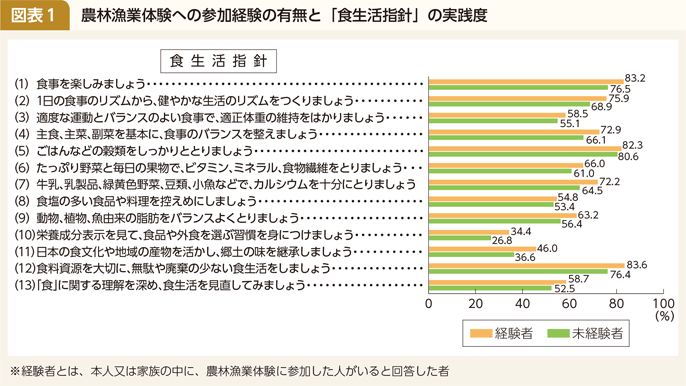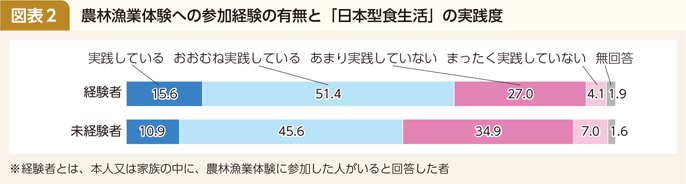4 農林漁業や食料の生産、流通、消費に関する統計調査等の実施・公表
農林水産省は、食育を推進する上で必要となる農林漁業の姿や食料の生産、流通、消費に関する基礎的な統計データを広く国民に提供し、食育に対する国民の理解増進を図っています。主なものとしては、米や野菜など主要な農畜産物の生産や流通に関する調査、魚介などの水産物の生産や流通に関する調査を実施・公表しています。
また、「食育に関する意識調査」や「食生活及び農林漁業体験に関する調査」を実施し、食育に関する国民の意識の把握に資するとともに、調査結果を公表しています(コラム:「食生活及び農林漁業体験に関する調査」について 参照)。
コラム:平成27(2015)年国民健康・栄養調査結果の概要
「国民健康・栄養調査」は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、毎年実施しています。
平成25(2013)年度から開始している「健康日本21(第二次)」では、基本的方向の1つとして、新たに「社会環境の整備」を盛り込み、生活の質の向上と社会環境の質の向上を図ることで、健康寿命の延伸・健康格差の縮小を実現するものとしています。平成27(2015)年の国民健康・栄養調査は、重点項目として、社会環境の整備の状況について把握しており、本頁では、その中でも食、食生活に関する調査結果についてまとめました。
〈若い世代ほど栄養バランスに課題〉
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日に2回以上食べることが「ほとんど毎日」の割合は、男性47.6%、女性52.7%であり、年代別にみると、男女ともに若い世代ほどその割合が低い傾向にありました。
また、特に20~30歳代の女性では、たんぱく質、カルシウム、食物繊維及びカリウムなどの摂取量が60歳以上に比べて少ない傾向であるという特徴が見られました。
国民健康・栄養調査では、引き続き実態の把握を行い、様々な取組の推進に役立つデータを発信していきます。
エネルギー及び主食・主菜・副菜に関連した栄養素摂取量の年次推移(平成7年~27年)
※調査方法の変更により個人の摂取量を把握する事が可能となった平成7年から平成27年までの性別・年齢階級別の栄養素摂取量
コラム:「食生活及び農林漁業体験に関する調査」について
「食生活及び農林漁業体験に関する調査」は、「食生活指針」や「日本型食生活」の認知度・実践度、農林漁業体験への参加経験割合等について全国の20歳以上を対象に調査を行い、今後の施策展開に向けての基礎資料とするために実施しているものです。ここでは、農林漁業体験への参加経験の有無と、「食生活指針」及び「日本型食生活」の実践度との関連について紹介します。
1.農林漁業体験への参加経験の有無と「食生活指針」の実践度
平成28(2016)年度に実施した本調査の結果では、農林漁業体験を経験した国民(本人又は家族)の割合は30.6%でした(第1部特集1第2節 参照)。農林漁業体験への参加経験の有無と、「食生活指針」の実践度について調べたところ、「食生活指針」に掲げられた項目全てにおいて、農林漁業体験への参加経験があると回答した人の方が、実践度(「実践している」又は「おおむね実践している」と回答した人の割合)が高くなっています。
2.農林漁業体験への参加経験の有無と「日本型食生活」の実践度
日本型食生活の実践度は、経験者が66.9%、未経験者が56.4%でした。日本型食生活の実践度については、経験者と未経験者で10%以上の差が出ています。上記1の結果も踏まえれば、健全な食生活の実現に向けて、より多くの人に農林漁業体験の機会を持ってもらうことは有効であると示唆されます。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974