特集1 食育をめぐる生産や消費、食生活の動向と食育の推進
1 食生活をめぐる現状と食育実践
「主食、主菜、副菜」を組み合わせた食生活の実践は、多様な食品を組み合わせ、必要な栄養素をバランスよくとることができる食生活の基本形。
栄養バランスに配慮した食生活を実践している人は、男性で53.0%、女性で64.9%(平成28年度調査結果)。特にここ2年の結果を見ると、男女ともにその割合はやや低下傾向。
主食・主菜・副菜を組み合わせて食べる頻度が低い人に聞いた、組み合わせて食べられないものは、男女ともに「副菜」が最も高い状況。
「食事バランスガイド」に沿った食生活を送る人ほど健康長寿であるという研究も報告。
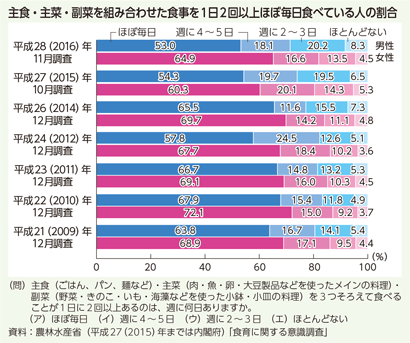
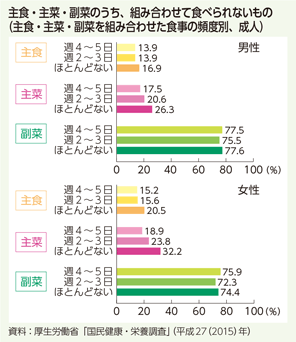
コラム:「食事バランスガイド」に沿った食生活で健康長寿
「食事バランスガイド」に沿った食生活の見直しにより健康寿命のさらなる延伸が期待。
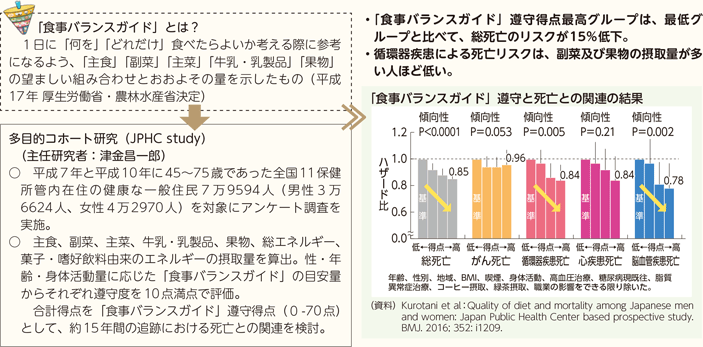
「食事バランスガイド」に沿った食事の人ほど、総死亡や循環器疾患による死亡リスクが低い。
不足しがちな野菜や果物を積極的に摂取し、「食事バランスガイド」に沿った食事をすることが長寿につながることが示唆。
副菜を構成する野菜類の摂取量について、目標とされている1日当たり350gの野菜を摂取する人の割合は約3割で、ここ10年で大きな変化はなし。
栄養バランスに配慮した食生活を進めるためには、時間や手間が関係。また、「自分で用意できること」や「メリットを知っていること」と回答した人が3人~4人に1人存在。
朝食欠食について、中学生、高校生の頃から習慣化している人は2割程度存在。また、20歳以降に朝食を欠食し始めた人は男女とも半数。
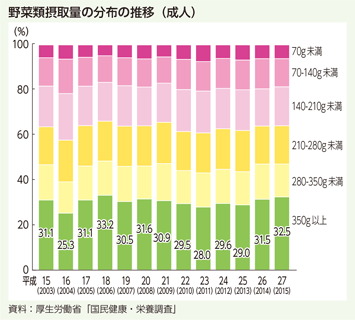
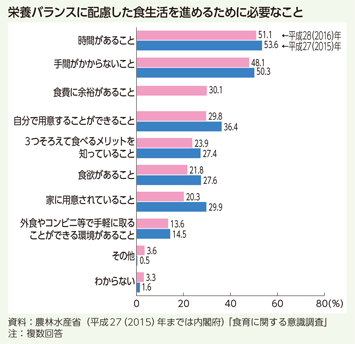
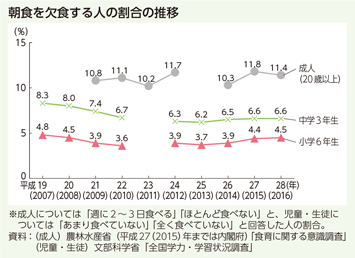
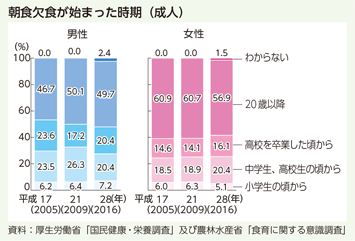
事例:~明日を美しく健康に働く~「まるのうち保健室」
Will Conscious Marunouchi 実行委員会では、平成26年から東京・丸の内で『まるのうち保健室』を開催し、働く女性の健康支援を展開中。
丸の内界隈のカフェ等で、食生活調査等を実施するとともに、その結果を用いた保健室公認カウンセラーによる、妊娠や出産等のライフイベントに向けた食生活や生活改善の提案を受けることができる枠組みを構築。
また、忙しい毎日の中でも健康的な生活を送ることができるよう、『まるのうち保健室』では、働く女性の健康をサポートするメニューを開発し丸ビル1階のカフェで、期間限定として提供。
この他、丸の内で朝食や健康的なメニューを食べることのできるお店や婦人科等の医療機関の場所を掲載した「Eat + Act Map」を作成し配布。
平成28年度からは、新たな試みとして、パートナー企業とともに、参加者の健康に対する知識が高まっている『まるのうち保健室』で測定後に「まるのうち部活動」と称する講座やセミナーも開催中。
今後は、働く女性がパフォーマンス良く健康的に過ごすことができるように、働く人が気軽に健康的な生活を送れる街づくりを進めていく予定。
2 生産から消費に至る食の循環への理解増進と食育実践
「第3次食育推進基本計画」の重点課題のひとつとして、「食の循環や環境を意識した食育の推進」を位置付け、「食に対する感謝の念を深めていくためには、食料の生産から消費に至る食の循環を意識し、生産者を始めとして多くの関係者により食が支えられていることを理解することが大切」と明記。農林漁業に関する体験活動は、そうした理解を深める上で重要。
農林漁業体験を経験した国民(本人または家族)の割合は30.6%。「学校の取組に参加」と回答した人の割合が61.4%と最も高く、次いで「地方自治体や地域の取組に参加」(22.8%)、「民間ツアーなどに参加」(9.0%)の順。
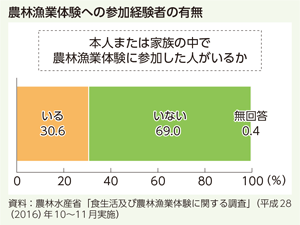
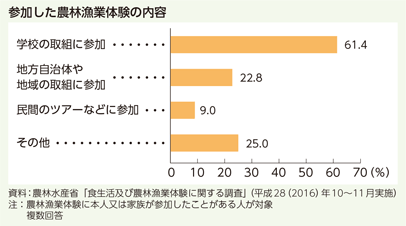
体験の際に農林漁業に携わる者から直接、指導を受けた人は83.0%。
農林漁業体験に参加して変化したことは、「自然の恩恵や生産者への感謝を感じられるようになった」が最も高く、次いで「地元産や国産の食材を積極的に選ぶようになった」が続く。農林漁業に携わる者の積極的な関与があるかどうかで結果に違い。
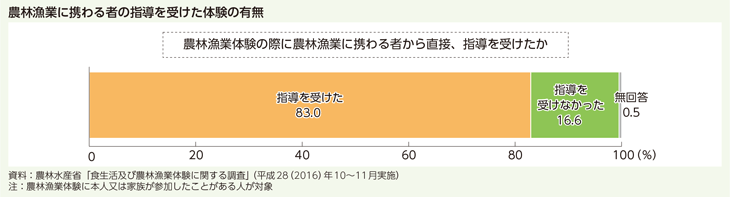
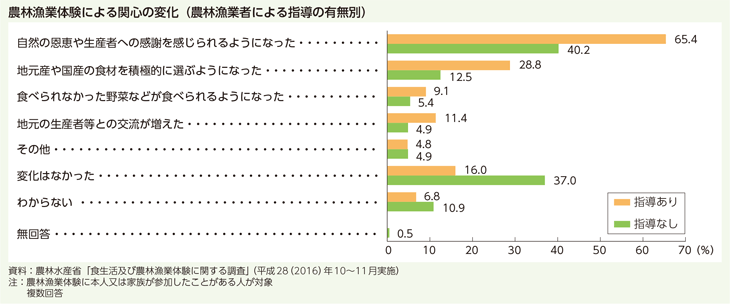
食品ロスについては、事業系が330万トンであるのに対し、家庭系は302万トン(平成25年度推計)。
食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合は76.4%。
「食育に関する意識調査」において、購入した食品を食べないまま、捨ててしまうことがあるか聞いたところ、『ある』(「よくある」と「ときどきある」の計)が33.1%、『ない』(「ほとんどない」と「まったくない」の計)が66.2%。
『ある』と回答した者の捨ててしまった原因は、「消費・賞味期限内に食べられなかった」、「購入後、冷蔵庫や保管場所に入れたまま存在を忘れてしまった」等であり、必要以上に在庫を抱えている状況。
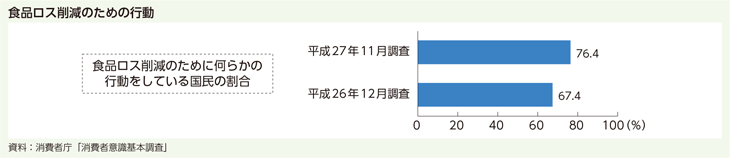
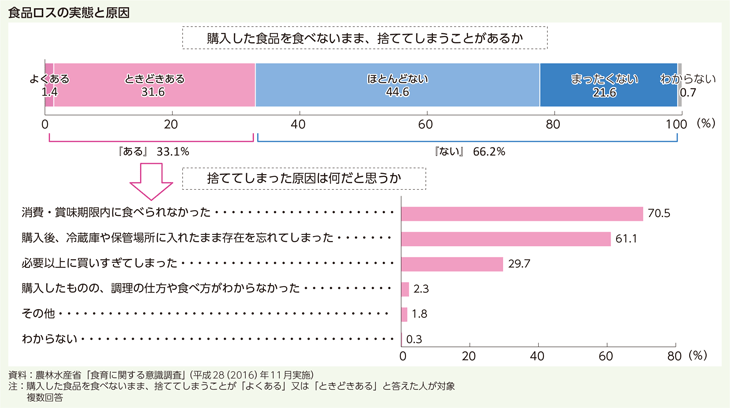
事例:地産地消から農業体験活動への展開
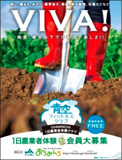
「青空フィットネスクラブ」
会員募集広告
おうみ冨士農業協同組合は、平成20年に地産地消の拠点として直売所「ファーマーズ・マーケットおうみんち」を開設。主に店頭が品薄になる午後、直売所近隣の畑で農産物の収穫を楽しんでもらい、持ち帰り袋のサイズ(大・中・小)に応じた価格で購入してもらう「畑の直売所」を実施。これが評判を呼び、「定期的に開催してほしい」などの声が出てきたことから、収穫だけでなく、種まき、雑草抜き、施肥等、時期に応じて農作業を支援する「援農」をしてもらい、代わりに収穫物の一部を持ち帰ってもらう仕組みを平成22年度から開始。
これを後に「青空フィットネスクラブ」と名付け、農業体験をしながら青空の下で汗を流す楽しさを気軽に味わってもらう取組とした。登録会員数は、開始当初の50名程度から現在は約350名に、体験の場を提供する農業者の生産意欲向上にもつながっている。
本取組は、直売所の利用者に参加してもらうだけでなく、地元である守山市の地域資源を活用する取組「もりやま食のまちづくりプロジェクト」における「食と農の体験ツアー」との連携プログラムとしても実施。また、企業や団体等からも参加があり、特に「生活協同組合コープしが」においては、本取組への参加をきっかけとして組合員が地元の農家と直接交流する活動へと発展し、食育・農業体験組織「ファーマーチャレンジ隊」が結成され、さらにコープしがの農業体験活動を県全体に波及するべく、おうみ冨士に加えて県下の3農協が連携した活動へと交流が拡大。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974






