地域での食育の推進
企業・生産者団体・ボランティア等による食育
近年、地域住民等による自主的な取組として、無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供する子供食堂等が増えており、家庭における共食等が難しい子供たちに対し、共食等の機会を提供する取組が広まっています。
(事例)子供や地域の人々の居場所としての子供食堂
(埼玉県)NPO法人SK人権ネット
- 「熊谷(くまがや)なないろ食堂」は、中学生以下と70歳以上は無料、その他は200円で利用できる子供食堂です。
- 開始当初は月1回でしたが、週3回に回数を増やし、様々な世代が集まる地域交流の場となりました。
- 地域の農家や企業から寄附された食材を利用しており、くまがや農業協同組合の直売所では、食堂のための専用ボックスを設置しています。
- 2020年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、週3回、希望者に弁当を配布しました。

食事の様子

活動内容などをまとめた
「熊谷なないろ食堂通信」
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P110
野菜、食べていますか?
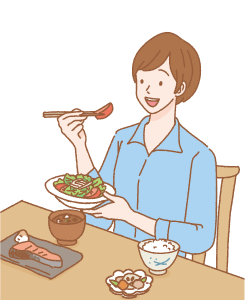
- 「令和元年国民健康・栄養調査」では、1日当たりの野菜類摂取量の平均値は280.5gでした。
- 年齢階級別に見ると、若い世代ほど野菜類摂取量が少なくなっていることが分かります。
- 摂取量増加のため、これからも、消費者への普及・啓発を続けていくことが重要です。
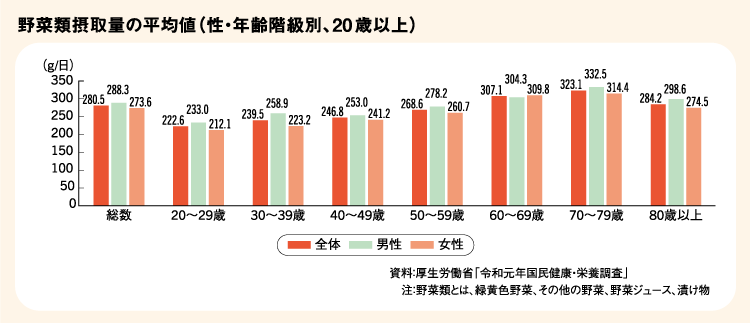
(事例)第2のふるさとで食の大切さを学ぶ
~南島原市(みなみしまばらし)農林漁業体験民泊~
(長崎県)南島原(みなみしまばら)ひまわり村
- 南島原ひまわり村には約160軒が所属し、国内外の修学旅行生を中心に受入れを行っています。
- 参加者は、農林漁業を体験し、自分で収穫した野菜や地元で採れた食材を一緒に調理し、食卓を囲むことで、食の楽しさや家族の大切さを体感します。
- 定期的に受入れ家庭同士で意見交換を行うことで、同等の受入れができるようにしています。また、新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを策定し、「ウィズコロナ時代」に対応した受入れ体制の整備を図っています。

受入れ家庭と食卓を囲んで「だんらん」

たまねぎ収穫体験
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P159
[column]食品ロスの削減に関する取組
- 消費者庁では「「賞味期限」の愛称・通称コンテスト」を実施し、「おいしいめやす」が内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞を受賞しました。
- あわせて、「私の食品ロス削減スローガン&フォトコンテスト」も実施し、「でこぼこやさいに魔法をかけて」が内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞を受賞しました。
- 環境省では、消費者庁、農林水産省、ドギーバッグ普及委員会と共催し、飲食店等での食べ残し持ち帰り行為の名称等を公募する「Newドギーバッグアイデアコンテスト」を実施し、「mottECO(モッテコ)」が大賞に選ばれました。

「賞味期限」の
愛称・通称コンテスト
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)賞

私の食品ロス削減
スローガン&フォトコンテスト
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)賞

コンテストでネーミングの大賞を
受賞した「mottECO」のロゴマーク
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P173
東日本大震災からの復興における取組
東日本大震災の発生から10年、各地で行政や企業、ボランティア等による被災地の復興や人々の暮らしを応援する活動が進められてきました。
(事例)東日本大震災被災地での共食の場づくりや食生活改善の取組
- 宮城県女川町(おながわちょう)では、仮設住宅で開催した「栄養相談会」において、食生活に関する相談に応じるだけでなく、町の管理栄養士や食生活改善推進員、大学の栄養学の教員や学生が連携し、仮設住宅で実際に食事を作り、一緒に食べることで、健康づくりや食育の推進につなげていくことを目指しました。
- 岩手県釜石市(かまいしし)食生活改善推進員協議会では、地元の大学、県栄養士会、市の地域包括支援センター等と連携し、「減塩クッキング教室」を実施し、仮設住宅でも手軽に、簡単にできるメニューを伝えるなどの取組を行いました。

みんなで食卓を囲んだ食事

地域住民向けの講演会の様子
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P142~143
(事例)大震災を契機として注目される防災への備え
- ローリングストック法とは、普段から少し多めに食料を買っておき、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法のことです。
- 一般財団法人日本気象協会は、神戸学院大学防災女子と連携し、備蓄した食料を用いて、普段からおいしく食べることができるレシピを考案するなどの活動もしています。
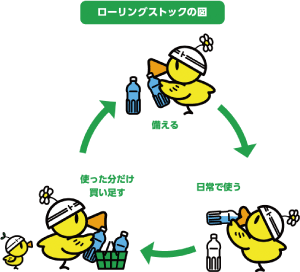
ローリングストックの図
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P144
食育推進運動の展開
食育の取組が全国で展開していくことを目的として、「食育活動表彰」を始め、各種の表彰を実施しています。
第4回 食育活動表彰 受賞事例
1.生活協同組合コープおきなわ(沖縄県)
- 生活協同組合コープおきなわでは、地産地消の促進や食文化の継承に関する取組を実施しています。
- 中学校を対象にした取組では、地域の特産品を活用した商品開発を支援し、開発した商品は、生徒自らがコープおきなわの店舗で販売しました。
- 「親子米づくりスクール」や「定置網体験ツアー」を開催し、生産から消費までの一連の流れを体験することで、食の循環について学ぶ機会を提供しています。

中学校での授業の様子

定置網漁体験の様子
2.岡崎市(おかざきし)食育推進会議
- 第3次岡崎市食育推進計画を踏まえ、「食育の環プロジェクト(8→∞)」の下、多角的な食育活動を展開しています。
- 給食事業者や企業・団体等との協働により、いつでも(日常)、だれでも(幅広い年齢層)、どこでも(家、学校・保育所、お店等)、市民が食育に参画できる仕組みづくりを行っています。

「給食センター探検隊」での大釜調理疑似体験

店頭でPR「野菜を食べよう大作戦!」
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」1はP130、2はP156
その他の受賞事例を知りたいときは「第4回食育活動表彰事例集」(PDF)
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班
電話:03-3502-8111(内線4578)
FAX:03-6744-1974




