学校・保育所等での食育の推進
学校における食育
- 学校給食を活用しつつ、給食の時間を始め、各教科、特別活動、総合的な学習の時間等における食に関する指導を中心として行われています。
- 公立小・中学校等の栄養教諭の配置数は年々増加しています。(全都道府県で6,652人が配置されています(2020年5月1日現在)。)
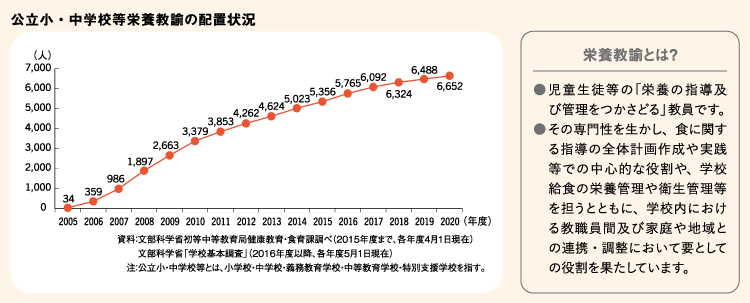
(事例)子供たちの自己管理能力の育成を目指して
奈良県教育委員会

【広陵北小学校】朝ごはん指導の様子
- 奈良県では、文部科学省のモデル事業を受託し、2020年度は広陵(こうりょうきた)北小学校と広陵(こうりょう)中学校を実践校としました。
- 広陵北小学校では、コロナ下で学校での調理実習ができない代わりに、家庭科の先生と栄養教諭が調理実習の様子を収録したDVDを配布し、家庭で実習を行うようにしたことで、保護者を巻き込んだ取組とすることができ、朝食を自分で作ることができる子供が増えました。
- 広陵中学校では、給食センター勤務の栄養教諭が学級担任等と連携し、教科等の学習やICTを活用した食に関する指導を行い、作成した動画教材には常に栄養教諭の姿が映し出されるように工夫するなど、子供たちが栄養教諭や給食センターを身近に感じられるようにしました。
- 学校長のリーダーシップの下、全校体制で食に関する指導に取り組むことにより、結果として学校給食の残食率低下にもつなげることができました。
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P90
学校給食
- 学校給食は、全小学校数の99.1%、全中学校数の89.9%で実施しています。
(出典:文部科学省「学校給食実施状況調査」(2018年度)) - 栄養バランスの取れた食事を提供することにより、子供の健康の保持・増進を図るために実施しています。
- 食に関する指導を効果的に進めるために、給食の時間はもとより、各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における教材としても活用することができるものであり、大きな教育的意義を有しています。
- 地場産物を学校給食に活用し、食に関する指導の教材として用いることにより、子供が、より身近に、実感を持って地域の食や食文化等について理解を深め、食料の生産、流通に関わる人々に対する感謝の気持ちを抱くことができます。
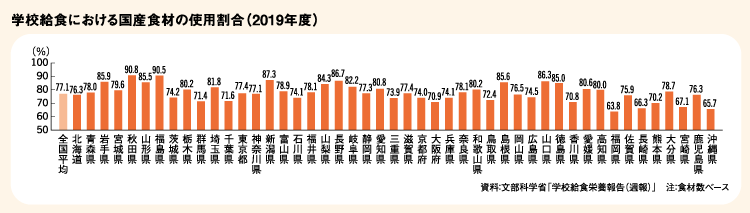
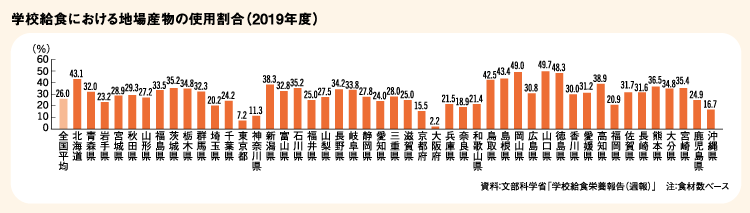
(事例)17万人で静岡県産の鯖を味わおう!「ふじっぴー給食」
静岡県教育委員会

「ふじっぴー給食」モデル献立
- 静岡県教育委員会では、2020年度、文部科学省の事業の委託を受け、学校給食を活用した「食品ロスの削減」と「地産地消の推進」に取り組みました。
- 学校給食での地場産物の活用率を高め、子供たちの静岡県への愛着を育むために、県内産の地場産物を45%以上使用した「ふじっぴー給食」のモデル献立を作成しました。県内の小中学校、特別支援学校約500校で、約17万食が提供されました。
- 「鯖」をテーマ食材とし、緑茶まぜごはん、鯖のねぎソースがけ等を提供しました。この取組は、県内の水産関係者と流通についての課題を共有し、連携する体制作りにもつながりました。
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P95
保育所における食育

保育所における食育の取組
(収穫した野菜でクッキング)
- 保育所における食育は、「保育所保育指針」において、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標としています。
- そして、子供が毎日の生活と遊びの中で、食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子供に成長していくこと等に留意して実施しなければならないとしています。
幼稚園における食育
- 幼稚園における食育は、2018年度から実施されている「幼稚園教育要領」において、「先生や友達と食べることを楽しみ、食べ物への興味や関心をもつ」ことが指導する内容として示されています。
認定こども園における食育

- 認定こども園における食育は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき、各園において食育の計画を策定し、教育・保育活動の一環として計画的に行うこととされています。
(事例)豆づくりから始まった食育活動の展開~子供の一言でつながって~
(神奈川県)社会福祉法人横浜YMCA福祉会YMCAオベリン保育園

コロナ下でも地域の農家の方と交流
- 子供たちが、卒園児の保護者から寄贈された味噌の木樽に興味を持ったことをきっかけに、味噌の材料となる大豆の栽培に取り組むとともに、様々な味噌の種類があることについても学びました。
- 地域の大豆農家から大豆の栽培方法を教えてもらうなど、地域に根付いた食育の取組を行っています。
- 自然の恵みとしての食材に触れる機会を通して、子供たちが生産から消費までの一連の食の循環や、食べ物を無駄にしないことへの気付きが生まれています。
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P100
(事例)地域の人と共に郷土食に触れ、食べることを楽しみながら
感謝の気持ちや食べ物への興味や関心をもつ取組
(山形県)南陽市(なんようし)立赤湯(あかゆ)幼稚園
- 赤湯幼稚園では、核家族世帯の幼児が全体の6割と多く、家庭で伝統文化に触れる機会が少なくなっていました。
- そこで、幼児の祖父母や地域の方が先生になり、地域の郷土食「笹巻き・干し柿」を一緒に作る取組を行いました。
- 笹巻き作りでは、笹に入れるもち米の量やいぐさの巻き方を、干し柿作りでは、柿の剥き方のコツ、干し柿が保存食になること等を教えてもらいました。
- 取組を通して、お世話になった方への感謝の気持ちが育まれ、さらに食べ物への興味、関心が広がっています。

干し柿作りの様子

笹巻き作りの様子
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P101
(事例)みんなで食べるとおいしいね
(鹿児島県)認定こども園阿久根(あくね)めぐみこども園
- 「みんなで食べるとおいしいね」という食育への思いを形にするために、昼食は3歳以上の子供たちがランチルームで毎日一緒に食事をしています。(なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、グループに分かれて時間をずらして食べるよう工夫しています。)
- 昔から食べられてきたものの、食生活の変化で家庭で食べる機会が減ったイワシの丸干しを地元の生産者の協力の下、定期的に給食で提供しています。また、柑橘類の栽培が盛んなことから、冬には職員や保護者が持ち寄った柑橘類を大きさ順に並べて「柑橘列車」を作り、しばらく飾った後にみんなで皮をむいて食べるなど、子供たちが地域の味に触れる機会を作るように工夫しています。

イワシの丸干しを食べる園児

柑橘列車
もっと詳しく知りたいときは令和2年度「食育白書」P102
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班
電話:03-3502-8111(内線4578)
FAX:03-6744-1974




