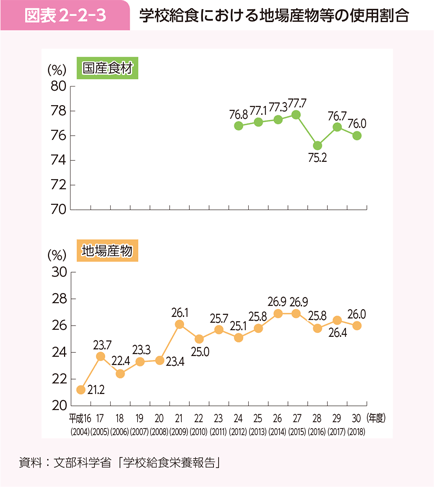2 地場産物等の活用の推進
地場産物を学校給食に活用し、食に関する指導の教材として用いることにより、子供が、より身近に、実感を持って地域の食や食文化等について理解を深め、食料の生産、流通に関わる人々に対する感謝の気持ちを抱くことができます。また、流通に要するエネルギーや経費の節減、包装の簡素化等により、環境保護に貢献することもできます。さらに、地域の生産者等の学校給食を始めとする学校教育に対する理解が深まることにより、学校と地域との連携・協力関係の構築にも寄与していることから、学校や地域において、地場産物を学校給食で活用する取組が積極的に進められています。一方で、地域によっては、県内産農産物の入手が困難であったり、価格が高い、一定の規格を満たした農産物を不足なく安定的に納入することの難しさなどにより使用量・使用品目の確保が困難になってきているといった現状もあります。
平成30(2018)年度の学校給食における地場産物の使用割合は、全国平均で26.0%(食材数ベース)となっています。また、国産食材の使用割合は、76.0%(食材数ベース)となっています(図表2-2-3)。
文部科学省においては、平成28(2016)年度より、「社会的課題に対応するための学校給食の活用事業」を実施し、学校給食において地場産物が一層活用されるよう、教育委員会などの学校設置者と生産・流通に係る農水部局や事業者とが連携し、食品の生産・加工・流通等における新たな手法等を開発するとともに、全国的な普及を図っています。また、関係府省庁とも連携を図りながら、地場産物の活用を推進しています。
農林水産省では、地産地消及び国産農林水産物・食品の消費拡大を推進する様々な取組を表彰する「地産地消等優良活動表彰」を実施しています。
また、学校給食等の食材として、地場産物を安定的に生産・供給する体制を構築するため、地場産物の生産量等の調査・分析、新しい献立・加工品の開発・導入実証等の取組への支援、生産者と学校等の双方のニーズや課題を調整する地産地消コーディネーターの育成や派遣を行っています。
各都道府県の現行食育推進計画の約8割において、学校給食における地場産物の活用に関する目標値が設定されています。目標値の算出方法やその値は様々ですが、食材数ベースで目標を設定している場合、目標値を30~40%としている府県が多くなっており、中には70%以上としている県(*1)もあります。また、令和2(2020)年3月末現在で、約6割において目標を達成又は計画作成時より数値が増加していた一方、約4割において数値が減少していました(*2)。
*1 70%以上としている県は、食材数ベースでは鳥取県、山口県、重量ベースでは長崎県、大分県、鹿児島県
*2 農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課調べ
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974