2 バイオマス利用と食品リサイクルの推進
バイオマスは、動植物由来の再生可能な資源であり、家庭やレストラン等から出る食品廃棄物や家畜排せつ物など私たちの身近に豊富に存在しています。バイオマスを利用することは、循環型社会の形成や地球温暖化の防止に寄与するほか、新たな産業の創出や農山漁村の活性化につながるものです。
政府は、「バイオマス活用推進基本法」(平成21年法律第52号)及びこれに基づく「バイオマス活用推進基本計画」(平成28(2016)年9月16日閣議決定)の下で、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進しています。
食品廃棄物については、食品関連事業者による飼料や肥料等への再生利用の取組が進められているものの、消費者に近い食品流通の川下や家庭での廃棄物については、分別が難しく、それらの取組は必ずしも十分とはいえない状況にあります。このため、食品流通の川下においても比較的、分別が容易で取り組みやすいメタン化を促進しています。具体的には、下水処理施設の混合利用による食品廃棄物のメタン化の取組の支援や、メタン化に伴い発生する消化液の肥料利用に向けた取組に対する支援など、地域の実情に応じた食品廃棄物の再生利用を推進しています。
我が国では、環境負荷の少ない、循環を基調とした経済社会システムを構築するため、「食品リサイクル法」に基づき、食品の売れ残りや食べ残し、食品の製造過程において発生している食品廃棄物等について、発生抑制により廃棄物として排出される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料とするリサイクル等を推進しています。
令和元(2019)年7月には「食品リサイクル法」に基づく新たな基本方針を策定し、再生利用等実施率の数値目標の見直しを行うなど、食品循環資源の再生利用等の更なる促進を図ることとしました。リサイクルの推進のための取組の一例として、平成26(2014)年度から平成30(2018)年度まで「食品リサイクル飼料化事業進出セミナー」を開催し、令和元(2019)年度には「エコフィード全国セミナー(CSF(*1)・ASF(*2)対策)」を開催しました。また、平成27(2015)年度から「食品リサイクル推進マッチングセミナー」を、平成29(2017)年度から「食品リサイクル肥料の利用促進に向けた意見交換会」を開催しています。この結果、食品関連事業者の再生利用等実施率は、平成29(2017)年度には84%になりました。「食品リサイクル法」の再生利用事業計画(食品リサイクル・ループ)の認定制度の活用等により、食品関連事業者、再生利用事業者及び農林漁業者等の3者が連携し、地域で発生した食品循環資源を肥料や飼料として再生利用し、これにより生産された農産物を地域において利用する取組も進んでおり、令和元(2019)年10月末現在で50の計画が認定されています(図表2-5-4)。
さらに、令和2(2020)年3月には、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策として、食品関連事業者等に対して、やむを得ず廃棄することとなる学校給食向けの未利用食品を飼料や肥料等に再生利用する際に要する輸配送費及び処理費を支援しました。
*1 Classical Swine Feverの略。豚熱。ウイルスが豚やイノシシに感染することで起こる家畜伝染病
*2 African Swine Feverの略。アフリカ豚熱。CSFに酷似するが、より病原性が強い家畜伝染病
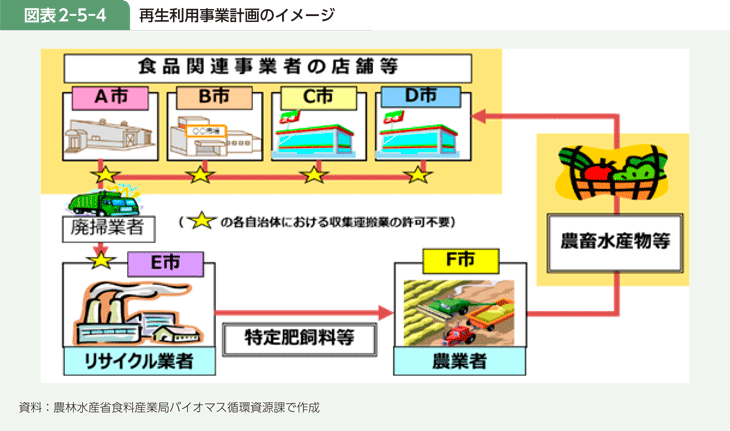
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4576)
ダイヤルイン:03-6744-1971
FAX番号:03-6744-1974




