2 「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進
(1)子供の生活習慣づくりの推進

Nara 早寝早起き朝ごはんフォーラム
~わくわく親子広場~ チラシ
朝食をとることは、栄養補給だけでなく、よく噛んで食べることで、脳や消化器官を目覚めさせ、早寝早起きのリズムをつけることにつながります。
文部科学省では、子供の健やかな成長に必要となる、十分な睡眠、バランスのとれた食事、適切な運動等、規則正しい生活習慣づくりを社会全体の取組として推進しています。
令和2(2020)年度は、独立行政法人国立青少年教育振興機構と連携・協力し、「早寝早起き朝ごはん」国民運動を促進するための「早寝早起き朝ごはん」フォーラム事業を全国5か所で実施するとともに、中学生の基本的な生活習慣の維持・定着・向上を図るための「早寝早起き朝ごはん」推進校事業を全国10 か所で実施しました(図表2-1-9、2-1-10)。
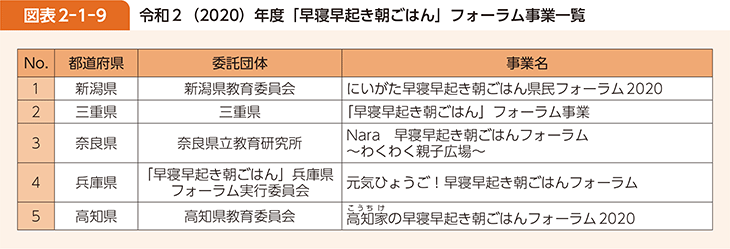
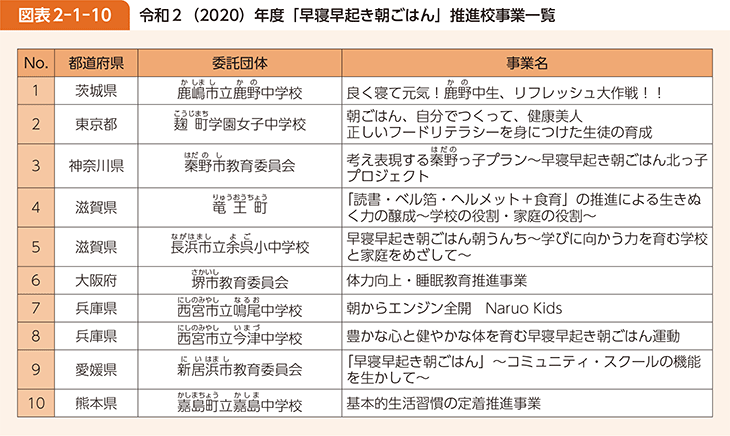
(2)「早寝早起き朝ごはん」全国協議会との連携による運動の推進
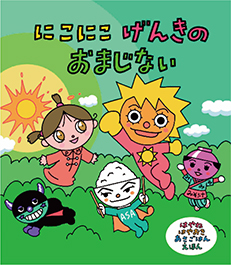
大型絵本「にこにこ げんきの おまじ
ない」©やなせスタジオ
「早寝早起き朝ごはん」全国協議会は、平成18(2006)年に発足し、幅広い関係団体や企業等の参加を得て、「早寝早起き朝ごはん」国民運動を文部科学省と連携して推進しています。令和3(2021)年3月現在、全国協議会の会員団体数は336で、様々な年齢層の子供や保護者に向けたガイドブックの作成・配布、全国フォーラム・総会の企画・運営等、子供の基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上につながる取組を展開しています。令和2(2020)年度は、「早寝早起き朝ごはん」の効果に関する調査研究の中間まとめを作成・発表し、新聞等で取り上げられました。中間まとめでは、子供の頃「早寝早起き朝ごはん」をよく実践していた人ほど、大人になった現在の資質・能力(*1)が高い等の調査結果が出ており、「早寝早起き朝ごはん」の重要性を、広く普及啓発しました。また、これまで作成した絵本の内容を大型絵本にして、各都道府県立図書館等に配布しました。
また、専門家による講演やトークセッション等を通し、子供の生活リズムについての知識や理解を深めるために、毎年3月に全国フォーラムを開催しています。なお、令和2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、全国フォーラムは中止となりました。
*1 自尊感情、共生感、意欲・関心、規範意識、人間関係能力、職業意識、文化的作法・教養、へこたれない力の8項目
事例:西合志(にしごうし)中学校区 「早寝早起き朝ごはん」運動
(「早寝早起き朝ごはん」推進校事業)
熊本県合志市(こうしし)立西合志(にしごうし)中学校

「早寝早起き朝ごはん」通信
西合志(にしごうし)中学校では、生徒の学習面や運動面の力を向上させるとともに、生活リズムの乱れが一因として挙げられる不登校の未然防止対策の強化を目的として、「早寝早起き朝ごはん」推進校事業の取組を実施しました。「早寝早起き朝ごはん」を中心とした基本的生活習慣の重要性を教職員の共通理解とし、研究の推進と活動の実践を進めました。
取組を実施するに当たり、生徒の実態を把握するために、アンケートの実施等を行いました。その結果、全く朝食をとらない生徒はいませんでしたが、週に1~2日食べるという生徒が2.3%いることや、スマートフォンの利用やゲームに関して家庭での監督が行き届かない状況があることを把握できました。
取組の計画においては、生徒の基本的な生活習慣の定着を図るため、「生徒への啓発による意識向上及び主体的な活動の活性化」、「保護者や地域への啓発による意識の向上」、「教職員の意識の向上及び実践の手立てのための研究」の3点に配慮しました。
「生徒への啓発による意識向上及び主体的な活動の活性化」として、PTA主催の講演会を開催しました。講演会では、生活チェックを行い、生活習慣病と睡眠、朝食の関係について話を聞き、生徒に自らの生活習慣を見直すきっかけを与えました。また、「早寝早起き朝ごはん」通信を発行し、早寝早起き朝ごはんに関する〇×クイズ、生徒の生活習慣調査の結果、教職員が参加した研修の内容や調査結果等を掲載し、生徒・保護者への周知・啓発を図りました。夏休みには、睡眠時間や朝食の摂取、スマートフォンの使用について記録し、生活習慣を振り返るようにしました。また、夏休み中の朝食を自分で作り、家族の感想をもらうという宿題を活用し、提出されたものの中から栄養バランスのとれた朝食の写真やレシピについては校内に掲示して紹介しました。
「保護者や地域への啓発による意識の向上」として、保護者や地域へ学校からの通信を配布することや、地域の人も参加できるよう講演会の開放などの啓発を行いました。地域の人や保護者が参加し、協働して学校づくりを進める学校運営協議会でも取組内容を発表し、保育所や小学校との意見交換を行いました。
「教職員の意識の向上及び実践の手立てのための研究」として、久留米(くるめ)大学医学部教授による教職員向け教育講演会の開催や、「弁当の日(*1)」の取組、食に関する取組が防災教育にもつながる視点等を、先進校視察により学びました。
例年2学期以降に新規の不登校生徒が急増しますが、令和元(2019)年度はほとんど発生せず、この取組の大きな成果といえると考えます。さらに、取組を推進することで教職員の意識が上がり、保護者の協力も例年になく高まり、学校全体が1つのテーマに向かって進むことができました。特に生徒会執行部での朝のあいさつ運動や保健委員会でのレシピの掲示等の活動によって引き出された生徒の主体的な活動は、生徒の達成感や自己肯定感の向上に大きく貢献しました。
今後も、生徒や保護者、地域と協力して活動を展開し、更なる取組を進めていこうと考えています。
*1 香川県の小学校から始まった、子供が年に数回、自分で弁当を作って学校に持ってくるという取組https://bentounohi.jp/about/(外部リンク)
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974






