第2節 学校における食に関する指導内容の充実
学校における食に関する指導は、子供が食に関する正しい知識を身に付け、望ましい食習慣を実践することができることを目指し、学校給食を活用しつつ、学校の教育活動全体を通じて行われています。
(1)栄養教諭による取組
栄養教諭は、学校における食育推進の要として、食に関する指導と献立作成や衛生管理などの学校給食の管理を一体的に展開することにより、教育上の高い相乗効果をもたらしています。
ア 食に関する指導の連携・調整
食は、各教科等で学習する内容に幅広く関わっており、食に関する指導は、学校の教育活動全体を通して行うことが重要です。栄養教諭は、各教科等において指導に携わるだけでなく、学校における食に関する全体的な指導計画の策定に中心的に携わるなど、教職員間の連携・調整の要としての役割を果たしています。そして、栄養教諭のみならず関係教職員が食に関する指導の重要性を理解し、必要な知識や指導方法を身に付けるとともに、十分な連携・協力を行うことにより、体系的・継続的に効果的な指導を行うことができます。
イ 各教科等における教育指導
食に関する指導は、学校の教育活動全体の中で体系的・継続的に行われるものであり、その中で、栄養教諭は、その専門性を生かして、各学級担任や教科担任等との連携を図りながら積極的に指導を行っています。また、栄養教諭は、学校給食の管理業務を担っていることから、各教科等の授業内容と関連させた献立を作成し、学校給食を生きた教材として活用するなど、効果的な指導を行っています。
平成29(2017)年3月には幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を、同年4月には特別支援学校幼稚部教育要領及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を、平成30(2018)年3月には高等学校学習指導要領を、平成31(2019)年2月には特別支援学校高等部学習指導要領を改訂しました。各学習指導要領においては、引き続き、学校における食育の推進について、各教科等のそれぞれの特質に応じて適切に行うように努めることや、指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮することとしています。幼稚園教育要領においては、その基礎として、食の大切さに気付き、進んで食べようとする気持ちを育むようにすることとしています。また、教育課程の編成及び実施に当たっては、食に関する指導の全体計画を含む各分野における学校の全体計画等と関連付けながら、効果的な指導が行われるよう留意することも新たに明記しました。
ウ 学校・家庭・地域における栄養教諭を中核とした取組
子供の望ましい食生活の実践を目指して、栄養教諭等には、学校教育活動の中で体系的・継続的な指導を実施するとともに、家庭や地域と連携した取組を行うことについても特に大きな成果が期待されています。
具体的取組としては、保護者会等を通じた食に関する指導、給食便りやパンフレットの配布等、家庭と連携した取組、農作業体験などの体験活動、料理教室、給食試食会など地域と連携した取組、PTAの積極的な取組を促すための働き掛け等が挙げられます。
文部科学省では、平成29(2017)年度から栄養教諭と養護教諭等が連携した家庭へのアプローチや、体験活動を通した食への理解促進等、学校を核として家庭を巻き込んだ取組を推進することで、子供の日常生活の基盤である家庭における食に関する理解を深め、効果的に子供の食に関する自己管理能力の育成を目指す「つながる食育推進事業」を実施しています。令和2(2020)年度は、全国で5事業、実施校10校で取組を行い、共通の指標によってその取組を検証しました。
共同調理場を担当する栄養教諭もおり、その地域の給食を管理していることを生かし、献立計画だけでなく各学校の食に関する指導の全体計画を作成しています。地域の児童生徒の食生活や生活習慣等の実態を把握し児童生徒や各学校が抱える課題と食育推進のための方策を明らかにし、栄養教諭と各学校の給食主任が連携するための組織を構築することで、地域全体の食育を推進しています。
(2)食に関する学習教材等の作成
文部科学省は、各教科等における食に関する指導において使用する教材等を作成しています。平成28(2016)年2月には、様々な教科等に分散している食育に関する内容を集約し、「小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」」を作成するとともに、学級担任等が授業の時間に食に関する指導を効果的に行うことができるよう、指導上のポイント等をまとめた指導者用資料を作成し、全国の小学校等に配布しました。また、同年12月には編集可能な媒体でこれらの教材等をウェブサイトに掲載し、その活用を促進しています。
(3)食育を通じた健康状態の改善等の推進
近年、子供の食を取り巻く社会環境が変化し、摂取する栄養の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満ややせ、生活習慣病等の増加が指摘されています。
令和3(2021)年2月には、「学校給食実施基準」(平成21年文部科学省告示第61号)を一部改正しました。食品構成については、児童生徒1人1回当たりの栄養量の摂取基準である「学校給食摂取基準」を踏まえ、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバランス良く摂取しつつ、様々な食に触れることができるようにすることとし、「食に関する指導の手引」や食育教材を活用しながら、児童生徒の望ましい食習慣の形成に向けた指導を行っています。
事例:子供たちの自己管理能力の育成を目指して
(つながる食育推進事業における取組)
奈良県教育委員会
奈良県では平成29(2017)年度から令和2(2020)年度に、文部科学省のモデル事業を受託し、令和2(2020)年度は広陵町(こうりょうちょう)を実践地域、広陵町(こうりょうちょう)立広陵北(こうりょうきた)小学校と広陵町(こうりょうちょう)立広陵(こうりょう)中学校を実践校として、望ましい食習慣の形成を目指し、児童生徒が朝食を自分で作ることができる力の育成に取り組んできました。
また、奈良県の課題である学校給食における地場産物の活用割合の増加もテーマの一つとし、地域の生産者と相談しながら学校給食に使用する野菜の計画栽培を行うなど、積極的に地場産物を取り入れ、地域や食に関する理解を深めてきました。そして、児童が家庭でも地場産物を使った料理を作ることができるようになることを目的に、フードコーディネーターと連携してレシピを開発し、チラシを配付しました。
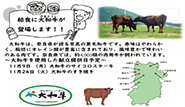
【広陵町(こうりょうちょう)
・香芝市(かしばし)
共同中学校給食センター】
11月生徒配付用献立表より
「大和牛の紹介」
広陵北(こうりょうきた)小学校ではコロナ下における対応のため、学校での調理実習の代替として、家庭科担当教諭と栄養教諭が調理実習の様子を収録したDVDを配付し、児童が家庭で実習を行うようにしたことで、保護者を巻き込んだ取組とすることができ、自分で作ることができる児童が増えるとともに、自分で作ることができるメニューも増えました。また、教科の学習や学級活動で食に関する知識を身に付けることに加え、学校全体で教職員が一丸となり、個々の児童が抱える課題の解決に向け、実態に応じたアドバイスを繰り返すことにより、「朝食を食べない」と回答する児童が減少し、大きな成果につなげることができました。
広陵(こうりょう)中学校では、給食センター勤務の栄養教諭が学級担任等と連携し、教科等の学習やICTを活用した食に関する指導を実施し、作成した動画教材には常に栄養教諭の姿が映し出されるように工夫しました。また、学校給食の食材を紹介する資料の掲示や校内放送を積極的に行ったことにより、生徒が栄養教諭や給食センターを身近に感じることができるようになりました。そのほか、管理栄養士を目指す県内の大学生と連携して、毎月19日の「食育の日」に新献立の開発を行いました。東京オリンピックの開催に向けて、令和2(2020)年度は「世界の料理」をテーマにし、多様な食文化に触れ、世界の料理に興味を持ち、給食時間を楽しく過ごせるように工夫しました。
学校長のリーダーシップの下、栄養教諭を中核とし、全校体制で食に関する指導に取り組むことにより、教職員の意識が向上し、生産者・調理員・栄養教諭等、学校給食に関わる多くの方の思いが児童生徒に伝えられ、結果として学校給食の残食率の低下にもつなげることができました。これらの結果から、児童生徒が自分自身の将来の健康について考え、食事をする、食の自己管理能力の育成につながったのではないかと考えています。
今後は、4年間取り組んできた事業の成果を生かし、学校・家庭・地域がつながり、次世代を担う子供たちが楽しみながら食に関する知識と実践力を養うことができる食育の推進に努めていきたいと考えています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974







