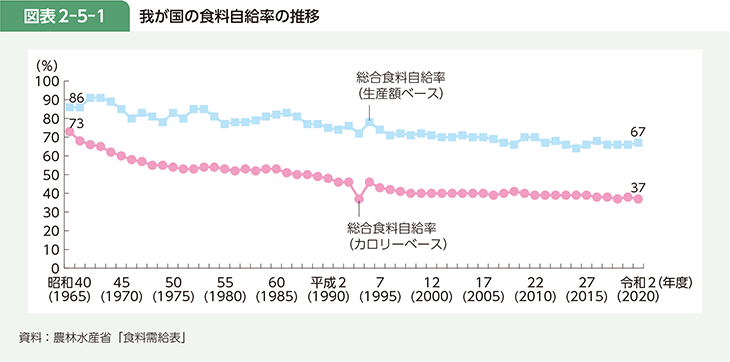1 農林漁業者等による食育の推進
我が国の令和2(2020)年度の食料自給率は、カロリーベースで37%、生産額ベースで67%であり(図表2-5-1)、食料及び飼料等の多くを海外からの輸入に頼っています。我が国の農業・農村をめぐる状況として、農業者の一層の高齢化・減少や農地等の生産基盤の脆弱化により食料自給力(*1)も長期的に低下しています。くわえて、地域コミュニティの衰退や大規模自然災害の頻発といった課題にも直面しています。また、世界の人口増加や経済発展に伴う食料需要の増加、気候変動や家畜疾病等の発生などにより、我が国の食料の安定供給に関するリスクは顕在化しています。このような中、将来にわたって食料の安定供給を確保するためには、食料自給力の構成要素でもある農地、農業者等を確保していくことの重要性について国民の理解を促していくとともに、食料自給率は食料消費の在り方等にも左右されるものであることを踏まえ、できるだけ多くの国民が、我が国の食料・農業・農村の持つ役割や食料自給率向上の意義を理解する機会を持ち、自らの課題として将来を考え、それぞれの立場から主体的に支え合う行動を引き出していくことが重要です。農林水産省では、消費者が農業・農村を知り、触れる機会を拡大するために、生産者と消費者との交流の促進、地産地消の推進等、様々な施策を講じています。その一つとして、食や農林水産業への理解の増進を図るためだけでなく、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや食に関わる人々の様々な活動に支えられていることなどに関する理解を深めるために、農林漁業者等による農林漁業に関する体験の取組を推進しています。
1 国内農林水産業生産による食料の潜在生産能力を示す概念。その構成要素は、農産物は農地・農業用水等の農業資源、農業技術、農業就業者、水産物は潜在的生産量と漁業就業者。現在の食生活に比較的近い「米・小麦中心の作付け」と供給熱量を重視した「いも類中心の作付け」の2パターンで国内生産のみで最大限供給可能な熱量を試算しており、その際、農地の制約に加えて、生産に必要な労働力の充足率を反映した供給可能熱量も試算
教育ファームなどの農林漁業体験は、自然と向き合いながら仕事をする農林漁業者が生産現場等に消費者を招き、一連の農作業等の体験機会を提供する取組です。自然の恩恵を感じるとともに、食に関わる人々の活動の重要性と地域の農林水産物に対する理解の向上や、健全な食生活への意識の向上など、様々な効果が期待されます。
例えば消費者に酪農のことを理解してもらいたいという酪農家の願いと、酪農を通じて子供たちに食や仕事、生命の大切さを学ばせたいという教育関係者の期待が一致し、各地で酪農教育ファームの取組が行われています。新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じつつ、受入れ可能な牧場においては、子供たちが乳牛との触れ合い、餌やりや掃除といった牛の世話などをする酪農体験の学習を行っています。そのほか、オンラインを活用した酪農体験の提供を行う酪農家もいます。
また、苗植え、収穫体験から食材を身近に感じてもらい、自ら調理しおいしく食べられることを実感してもらう取組もあります。このほか、漁業体験では、漁業協同組合の職員や水産加工業者が中心となり、とれたての魚介類を使った料理教室や、生産現場の見学会などを行い、林業体験では、「木育(*2)」の一環として、親たちが地元の木材を用いて離乳食用のスプーン(「ファーストスプーン」)を製作するなど、農林水産業の様々な分野で関係者が連携しながら体験活動を進めています。このような体験活動の参加者からは、「命の大切さを感じるとともに、その命をいただいている感謝の気持ちを実感できた。」などの感想が寄せられ、農林水産業の良き理解者となっていることがうかがわれます。
農林水産省は、これらの取組を広く普及するため、補助事業による教育ファームなどの農林漁業体験活動への交付金による支援のほか、どこでどのような体験ができるかについて、情報を一元化した「教育ファーム等の全国農林漁業体験スポット一覧」、タイムリーな情報を発信する「食育メールマガジン」等を提供しています。
2 子供から大人までを対象に、木材や木製品との触れ合いを通じて木材への親しみや木の文化への理解を深めて、木材の良さや利用の意義について学んでもらうための活動
事例:子供たちに残したい漁業集落
~アジやトラフグの魚食普及を通じて~
新松浦(しんまつうら)漁業協同組合(長崎県)
長崎県松浦市(まつうらし)は、多種多様な漁業及び養殖業が営まれ、全国でも有数のアジの水揚量及びトラフグの養殖業生産量を誇る水産業が盛んな地域です。新松浦漁業協同組合では、そうした松浦市の水産業を子供たちに知ってもらい、地域を活性化することで、後世に漁業集落を残していこうと、様々な魚食普及の取組を行ってきました。
例えば新松浦漁業協同組合女性部は、平成15(2003)年から、県外の中学生及び高校生の民泊受入れと、地元の子供向けの魚料理教室を実施しています。魚料理教室では、地元で水揚げされたアジを使い、三枚おろしやアジフライ作りに挑戦してもらうことで、子供たちに地元の魚に対する親しみを持ってもらいます。
平成25(2013)年からは、「いいフグの日」(11月29日)にちなみ、学校給食でトラフグの唐揚げを提供する取組を行っており、現在では市内全ての小・中学校でこの取組が実施されています。食材を提供するだけでなく、養殖業者が学校を訪問し、トラフグの特徴や養殖の方法について説明したり、子供たちにも分かりやすい資料を配布することで、地元の水産業への関心を醸成します。
新松浦漁業協同組合では、今後もこうした取組を通じて、魅力ある漁業集落を子供たちに残していくことにつなげていきたいと考えています。
事例:地域に根ざした自然養鶏から学ぶ命の食育活動
(第5回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞)
ささえたまご農園(福井県)
ささえたまご農園では、平飼い養鶏を行いながら、鶏との触れ合いや卵料理作りを通して、生き物と自然環境とのつながり、生き物の命を頂くことの尊さや食べ物の大切さを伝える体験プログラムを実施しています。
体験プログラムは、子供たちの食育への理解が深まるように次の順序で構成しています。
<1> 鶏との触れ合いと卵拾い体験で、産みたてのまだ温かい卵に触れ、鶏から生きている卵を分けてもらうことを体感してもらう。
<2> 拾った卵でプリンなどを作る。
<3> 試食中に、卵の黄身の真ん中にある白い点が命の源の胚盤で、20日間温めるとヒヨコになることを説明する。
こうした体験を通して、子供たちは命と食のつながりを学んでいます。中には「ごはんを残さず食べられるようになった。」という子供もいます。
また、園内には一般社団法人全国料理学校協会加盟の料理学校が併設されており、大人向けの料理教室を実施しています。レシピや調理方法などの料理作りの基本を教えるだけでなく、食材に含まれる栄養素に関する情報や、農業が資源の循環に果たす役割なども伝えています。
農園だからこそできる特色ある食育活動を、より一層進めていきたいと考えています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974