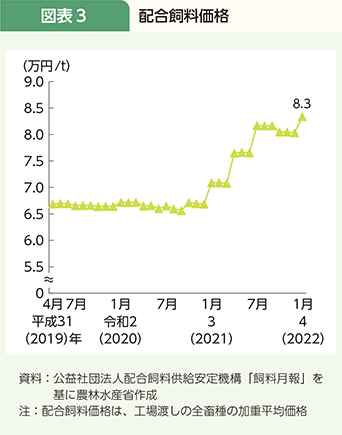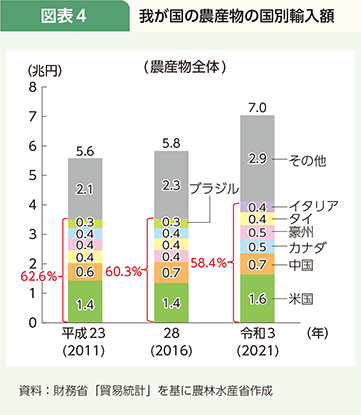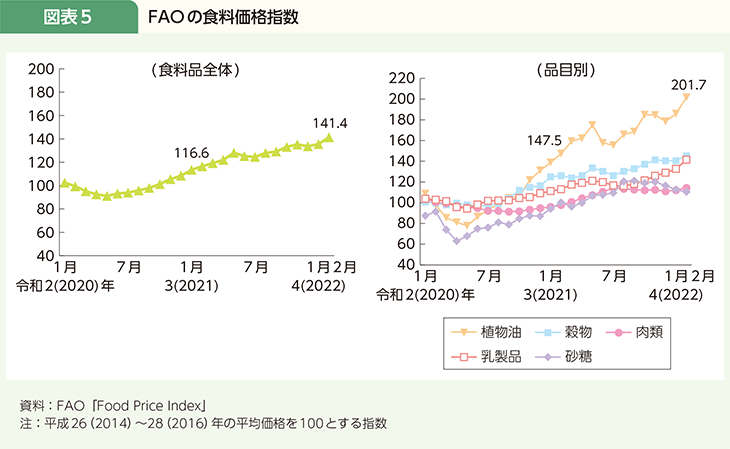1 地産地消の推進
地域で生産したものを地域で消費する地産地消の取組は、消費者に「顔が見え、話ができる」関係で地場産物を購入する機会を提供し、農山漁村の活性化を図る上で重要な取組です。また、農山漁村の6次産業化(生産・加工・販売の一体化等)にもつながる取組です。
直売所や量販店での地場産物の販売、学校や病院・福祉施設の給食、外食・中食産業や食品加工業での地場産物の利用等により、消費者は身近な場所で作られた新鮮な地場産物を入手できるだけでなく、地場産物を使った料理や地域の伝統料理を食べることができます。また、農林水産業を身近に感じる機会が得られ、食や食文化についての理解を深められることが期待されます。さらに、直売所は、地場産物の販売だけでなく、地場産物の特徴や食べ方等の情報提供を行っており、消費者と生産者とのコミュニケーションを生かした食育の場にもなっています。
なお、地産地消については、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(平成22年法律第67号)に基づく「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針」(平成23年農林水産省告示第607号)において、地場産物の使用の促進の目標として、<1>令和7(2025)年度までに年間販売額が1億円以上の直売所の割合を50%以上とすること、<2>令和7(2025)年度までに学校給食において地場産物を使用する割合(金額ベース)を現状値(令和元(2019)年度)から維持・向上した都道府県の割合を90%以上とすること、<3>令和7(2025)年度にグリーン・ツーリズム施設の年間延べ宿泊者数及び訪日外国人旅行者数のうち農山漁村体験等を行った人数の合計を1,540万人とすること等を設定しています。同法及び同基本方針に基づく地方公共団体による促進計画の取組が進められていくこと等により、地産地消の一層の促進が図られることが期待されます。
農林水産省では、地産地消の取組を一層促進するため、地産地消や国産農林水産物の消費拡大に資する地域の創意工夫ある取組の表彰を行うほか、地域資源を活用した新商品の開発等を進める地域ぐるみの6次産業化としての直売所の売上げ向上に向けた取組や施設整備への支援、産品の名称を知的財産として保護する「地理的表示(GI)保護制度」への申請の支援等を行いました。また、学校給食等におけるメニュー開発・導入実証等への支援や、学校給食等への地場産物の利用拡大を促進するため、専門的知見を持つ人材育成の研修や安定供給システムの構築を進めるため地産地消コーディネーターの派遣への支援を行いました。さらに、直売所の売上げ向上に向け、インバウンド等需要向けの新商品の開発、消費者評価会の開催、直売所と観光事業者等とのツアー等の企画、集出荷システムの構築などの取組への支援を行っています。
我が国は、多種多様な農畜水産物・加工食品を多くの国・地域から輸入しています。食料の輸送量に輸送距離を乗じた指標として「フード・マイレージ」があります。これは、1990年代からイギリスで行われている「Food Miles(フードマイルズ)運動」を基にした概念であり、「生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろう」という仮説を前提として考え出されたものです。国内生産・国内消費の拡大、地産地消の推進等の取組は、環境負荷の低減に資することも期待されます。
また、「食料・農業・農村基本計画」(令和2(2020)年3月31日閣議決定)において、食と農とのつながりの深化に着目した官民協働の新たな国民運動が位置付けられており、令和3(2021)年7月から、我が国の食と農をめぐる課題を消費者、生産者、食品関連事業者等と行政が一体となって考え、議論し、行動する新たな国民運動として「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」を開始しています。特に「Z世代(*1)」と呼ばれる未来を担うべき若者たちを重点的なターゲットに、共感や応援につなげる情報を発信することで国産農産物の積極的な選択などの具体的な行動変容を促していきます。
1 1990年代後半から2000年代に生まれた世代のこと
コラム:我が国の食料安全保障をめぐる状況
世界の食料需給は、人口の増加や経済発展に伴う畜産物等の需要増加等が進む一方、気候変動や、家畜の伝染性疾病・植物病害虫の発生等が食料生産に影響を及ぼす可能性があり、中長期的には逼迫が懸念されます。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やロシアによるウクライナ侵略等による食料供給に対する懸念も生じています。
(農業資材の価格高騰について)
食料の安定供給に向けては、生産活動に必要な肥料や飼料といった農業資材を安定的に確保することも重要です。農業資材については、原材料やその原料の大部分を輸入に頼っていることから、偏在性がある鉱石や穀物等の国際相場や為替相場の変動等の国際情勢の影響を受けるという特徴があります。
近年の価格変動を示す農業資材の物価指数は、全体的には上昇基調で推移しています。特に飼料や燃油等の光熱動力等の価格指数は、令和3(2021)年4月以降、原料価格の上昇等を要因として上昇しており、令和4(2022)年2月には、基準年である平成27(2015)年の水準から飼料は20ポイント、光熱動力は24ポイント、肥料は9ポイント上昇しています(図表1)。さらに、令和4(2022)年2月以降も、ウクライナ情勢を背景に、原油等の国際相場は高い水準で推移しつつ、不安定な動きを見せていることから、今後の市場の動向を注視し、必要な資材の確保に万全を期する必要があります。
農産物の生育に不可欠な肥料については、化学肥料原料の大半を限られた相手国からの輸入に依存しています。貿易統計及び肥料関係団体からの報告によると、りん酸アンモニウムや塩化加里はほぼ全量を、尿素は96%を輸入に依存しています(図表2)。輸入原料の安定調達を進めるとともに、輸入原料からの転換を図るため、農山漁村に賦存する地域・国内資源を一層活用し、循環利用を促進する必要があります。
(配合飼料の価格高騰について)
家畜の餌となる配合飼料は、その原料使用量のうち5割がとうもろこし、1割が大豆油かすとなっており、我が国はその大部分を輸入に頼っていることから、穀物等の国際相場の変動に価格が左右されます。令和2(2020)年9月以降、米国におけるとうもろこしの中国向け輸出成約が増加したことや、南米産とうもろこしの作況への懸念等からとうもろこしの国際価格は上昇しており、配合飼料の工場渡し価格は、令和4(2022)年1月には8万3,381円/tと、前年同月の7万902円/tより17.6%上昇しています(図表3)。引き続き、とうもろこしのバイオエタノール向け需要の拡大やウクライナ情勢等を背景に、国際相場は高い水準で推移しつつ、不安定な動きを見せていることから、今後の動向を注視する必要があります。
(主要農産物の輸入状況について)
令和3(2021)年の我が国の農産物輸入額は7兆388億円となりました。国別の輸入額を見ると、米国が1兆6,411億円、次いで中国が7,112億円で、カナダ、豪州、タイ、イタリアと続いており、上位6か国が占める輸入割合は6割程度で推移しています(図表4)。一部の品目では輸入先の多角化が進みつつあるものの、我が国の農産物の輸入構造は、依然として米国を始めとした少数の特定の国への依存度が高いという特徴があります。
(食料価格の上昇について)
令和3(2021)年以降の穀物等の国際価格については、北米での高温乾燥による不作や主要な穀物輸入国の需要増加、肥料等の農業資材や海上運賃の上昇等により上昇し、国連食糧農業機関(FAO(*1))が公表している食料価格指数は、令和4(2022)年2月に食料品全体で141.4を記録し、前年同月比で21.3%上昇しました(*2)。また、これにロシアによるウクライナ侵略が重なったことで、両国が主要輸出国となっている小麦の国際価格は、令和4(2022)年3月に過去最高値を記録しました。その後も食料の国際相場は、高い水準で推移しつつ不安定な動きを見せており、国内における食料の消費者物価指数も、令和3(2021)年後半以降上昇傾向で推移しています(図表6)。
1 Food and Agriculture Organization of the United Nationsの略
2 令和4(2022)年3月4日公表時点
こうした情勢を踏まえ、政府は、原材料費等の上昇分を適切に価格に転嫁し、中小企業等が賃上げの原資を確保する環境を整備するため、令和3(2021)年12月27日に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を決定し、公正取引委員会や事業所管省庁等が連携して適正な取引を推進しています。
(国民の理解の増進について)
食料の安定供給は、国の最も基本的な責務の一つであり、「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)においては、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄を適切に組み合わせることにより、食料の安定的な供給を確保することとしており、国内の農業生産の増大に向け、生産基盤の強化や国産への切替え等の取組を着実に推進しています。
農林水産物・食品の価格は天候や季節などの状況だけでなく、輸入原材料や農業資材、配合飼料の価格等にも影響を受けることから、食料安全保障の確立には国民の理解の増進が不可欠です。令和3(2021)年度に農林水産省が実施した「食生活・ライフスタイル調査(*3)」によると、食に関して重視していることとして、「できるだけ日本産の商品であること」を挙げた人が40.1%と最も多かった一方、「同じような商品であれば出来るだけ価格が安いこと」を挙げた人が38.3%でした。消費者の価値観やライフスタイルは様々ですが、農林水産省では、食料安全保障の確立への理解を深めるよう、食料需給に関する情報の収集・分析と消費者等への情報発信を強化しています。また、国民運動である「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」等を通して、国産農産物の積極的な選択などの行動変容を促しています。
3 全国15~74歳を対象にしたインターネット調査(モニターに対して実施)
事例:学校給食への地場産農産物供給を起点とした「食べて学んで体験する」食育活動(第5回食育活動表彰農林水産大臣賞受賞)
JA東京むさし小平(こだいら)地区(東京都)
東京都小平市(こだいらし)は、地場産農産物を使った「地場産学校給食」の取組を積極的に進めており、市内の全ての公立小・中学校への出荷調整を、JA東京むさし小平地区が担っています。学校給食における地場産農産物の使用割合30%という目標を掲げ、取組を行ってきた結果、平成18(2006)年度時点で、小学校5.5%、中学校6.0%だったものが、令和2(2020)年度にはそれぞれ、30.1%、32.8%となり、現在ではほぼ毎日、学校給食に地場産農産物を供給できるようになりました。
さらに、JA東京むさし小平地区は、学校給食の出荷調整だけでなく、生産者による出張授業や、「学童農園」による体験学習等、多角的に食育活動を実施しています。出張授業では、生産者が教壇に立ち、給食で使われる地場産農産物や、生産者の思いについて授業を行った後、児童と一緒に給食を食べます。また、「学童農園」は、市内の全ての公立小学校で実施しており、農家が畑を貸し、農業体験を児童に提供することにより、農業に対する理解の深化や、給食の食べ残しの減少へとつなげています。
地元住民の理解を得て、市内の農地を未来に残していくため、子供の頃から食べて、学んで、触れて、農業を体験してもらうための活動を、今後も続けていきます。
事例:「ふるさと納税」を活用した「ふるさと給食」
宮崎県都城市(みやこのじょうし)
平成20(2008)年に始まった「ふるさと納税」は、都道府県、市区町村への「寄附」であり、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。
都城市では、ふるさと納税申告時に寄附金の使途について8つのメニューから選択してもらいます。そのうち、子育て支援への寄附額が最も多く、全体の約半分を占めます。
寄附金を活用して実施した子育て支援に関連した事業のうち、平成29(2017)年度から開始した地場産物「ふるさと給食」提供事業では、地場産物を活用した学校給食を提供しています。令和3(2021)年度は都城産のブランド豚肉を使用した「幸せ上々(あげあげ)竜田揚げ」を市立の小・中学校で提供しました。竜田揚げに添えた野菜やごはんなども都城産です。また、「ふるさと給食」に合わせて、生産者による講話で生産者の声を伝えるとともに、ふるさと納税、地産地消の授業も行っています。
このように、生きた教材として「ふるさと給食」を活用することにより食育の推進を図るとともに、子供たちにふるさと都城の魅力を伝えています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
担当者:食育計画班
代表:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125
FAX番号:03-6744-1974