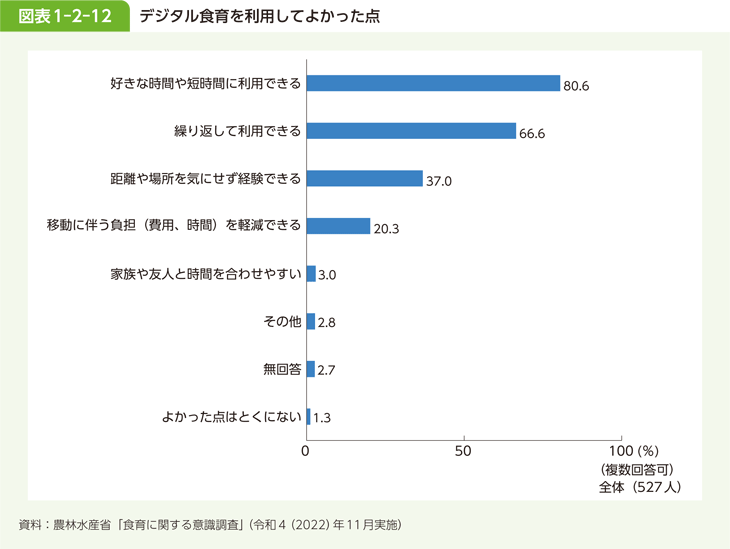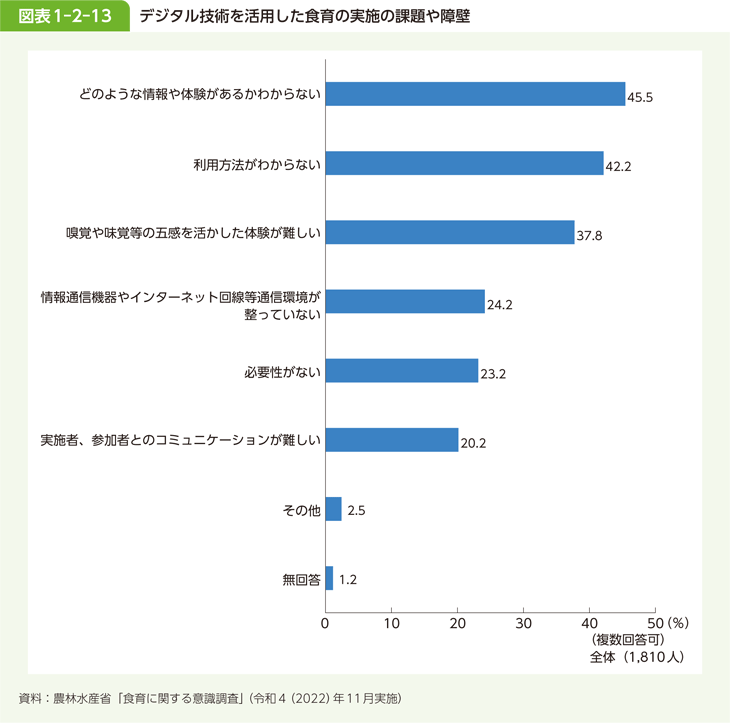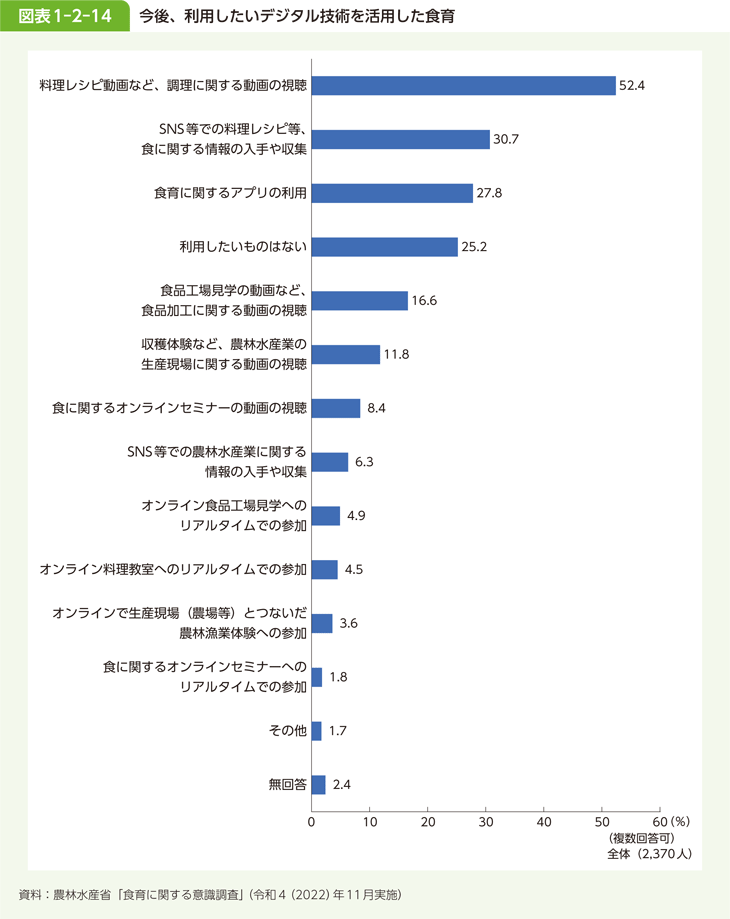4 ポストコロナ、ウィズコロナ時代における食育の推進
ここでは、令和4(2022)年度「食育に関する意識調査」の結果から見えてきた、デジタル技術を活用した食育の利点や課題等を示すとともに、農林水産省や食育関係者によるデジタル技術を活用した食育の取組を紹介します。
(1)デジタル技術を活用した食育を経験してよかったところ
家族の中でデジタル技術を活用した食育を「利用したことがある」と回答した人に、デジタル技術を活用した食育を経験してよかった点を聞いたところ、「好きな時間や短時間に利用できる」を挙げた人の割合が80.6%と最も高く、次いで、「繰り返して利用できる」(66.6%)となっていました(図表1-2-12)。
(2)デジタル技術を活用した食育を利用する場合の課題や障壁
家族の中でデジタル技術を活用した食育を「利用したことがない」と回答した人に、デジタル技術を活用した食育を利用する場合に、どのような課題や障壁があるか聞いたところ、「どのような情報や体験があるかわからない」を挙げた人の割合が45.5%と最も高く、次いで、「利用方法がわからない」(42.2%)、「嗅覚や味覚等の五感を活かした体験が難しい」(37.8%)となりました(図表1-2-13)。
(3)今後利用したいデジタル技術を活用した食育
新型コロナウイルス感染症の拡大が収まった後、利用したいデジタル技術を活用した食育を聞いたところ、「料理レシピ動画など、調理に関する動画の視聴」を挙げた人の割合が52.4%と最も高く、次いで、「SNS等での料理レシピ等、食に関する情報の入手や収集」(30.7%)、「食育に関するアプリ(料理レシピ、栄養バランス、フードロス削減など)の利用」(27.8%)となりました(図表1-2-14)。
農林水産省では、「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進に向けて、令和3(2021)年度に「デジタル食育ガイドブック(以下本項において「ガイドブック」という。)」を作成しました。ガイドブックは、新型コロナウイルス感染症の影響下で対面での食育活動が困難となった人や、デジタル化に対応した食育を今後実践してみたいと考えている個人、グループをターゲットとし、これからデジタル技術を活用した食育の推進を目指す農林漁業者、各種団体、企業等が行う「デジタル食育」の実践に役立つ内容としました。令和4(2022)年度には、ガイドブックを活用し、デジタル化に対応した食育を推進するため、地方公共団体職員等を対象にしたセミナー等を行いました。
また、「新たな日常」における食育体験やオンライン体験の可能性について考えるセミナーとして、令和5(2023)年2月に「食育推進フォーラム2023~食育キーパーソンに学ぶ!これからの食育とその実践~」を開催し、オンラインでの配信を実施しました。また、「こども霞が関見学デー」のウェブサイト「マフ塾」にて、乳牛の暮らしや煮干しの解剖など、食べ物・いのち・環境について学べる動画コンテンツを掲載しました。
令和4(2022)年度「食育に関する意識調査」の結果から、デジタル技術を活用した食育を利用したことがある人は2割程度にとどまっていることが明らかとなりました。その課題や障壁として「どのような情報や体験があるかわからない」、「利用方法がわからない」ことが挙げられています。このことは、デジタル技術を活用した食育の更なる普及啓発の必要性を示しており、今後、好事例の横展開等を含めた情報発信を行っていくことが重要であると考えられます。また、課題や障壁として「嗅覚や味覚等の五感を活かした体験が難しい」ことが挙げられており、これまでのリアルでの食育により得られる体験の重要性も示唆されています。
一方、デジタル技術を活用した食育の良かった点として「好きな時間や短時間に利用できる」、「繰り返して利用できる」ことが挙げられており、広がりのある食育活動を展開していくに当たって、これらの結果が参考になると考えられます。
新型コロナウイルス感染症の影響下では、接触機会や対面の機会が減少し、共食の機会等も減少しましたが、自宅で食事をする機会や自宅で料理を作ることが増えたこと等、食育への関心が高まるきっかけとなることが期待されます。健全な食生活の実践には、科学的知見に基づき合理的な判断を行う能力を身に付けた上で、食生活や健康に関する正しい知識を持ち、自ら食を選択していく必要があります。そのためには、消費者に的確な情報を分かりやすく提供することが重要です。
デジタル化された情報は、情報伝達が容易である反面、偽情報等も瞬時に流通することで社会的混乱を招くこともあり、情報の発信者・利用者双方が情報の真偽を見極めるリテラシーを向上させることが必要となります。
ポストコロナ、ウィズコロナ時代においては、これまでの対面での食育の取組に加え、デジタル技術を活用した食育の取組を効果的に組み合わせながら実施することにより、多様で広がりのある食育を推進していくことが望まれます。
事例:デジタル技術を活用した魚をおろす疑似体験(第6回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞)
愛南町(あいなんちょう)ぎょしょく普及推進協議会(愛媛県)
愛南町ぎょしょく普及推進協議会は、魚の生産から消費、生活文化までを含む幅広い内容を広めるために、町全体で7つの「ぎょしょく教育」を実施しています。ぎょしょく教育とは、「魚食」へ到達することを目指し、魚に触れる「魚触」、魚の生態や栄養を学ぶ「魚色」、獲る漁業を学ぶ「魚職」、育てる漁業を学ぶ「魚殖」、伝統的な魚文化を学ぶ「魚飾」、魚を取り巻く環境を学ぶ「魚植」の一連の取組です。本取組は、平成17(2005)年度に開始し、平成22(2010)年度には町内の全ての保育所、小・中学校で実施しています。
新型コロナウイルス感染症の拡大前は、出前授業、養殖現場の見学、調理実習を中心に活動してきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2(2020)年度は遠隔授業、魚のおろし方や調理に関する動画の配信を開始しました。さらに、令和3(2021)年度には、デジタルトランスフォーメーション(DX)のひとつとして、魚の三枚おろしを疑似体験できるアプリを制作しました。愛南町内の小中学校では、一人に一台の情報端末が導入されており、動画やアプリを効果的に使用することができます。アプリは、魚をおろした回数や時間によって、習熟度を自動で判定するようになっているため、一人で何回も疑似体験を行うことが可能です。子供たちの「本物の鯛をおろしてみたい」という興味を引き出したり、実物の魚をおろす体験へのハードルを下げたりすることで、魚を調理したり、食べたりすることへの関心を高めています。
アプリは、時間や場所の制約を受けることがなく、学校等の団体以外でも活用できます。今後も、社会環境の変化等に合わせて、ぎょしょく教育の普及を行うとともに、楽しみながら食育を学べる活動を進めていきます。
コラム:野菜摂取量の「見える化」の取組
第4次基本計画では、健康寿命の延伸を目指す「健康日本21(第二次)」の趣旨を踏まえ、令和7(2025)年度までに、1日当たりの野菜摂取量の平均値を350g 以上とすることを新たに目標として設定しています。一方、現状は平均280g程度と約7割の人が目標量に達しておらず、これは日頃の食生活において、自分自身が摂取している野菜の量や不足している野菜の量を正しく把握できていないことが原因の一つと考えられます。
そこで、「野菜の日(8月31日)」の特別企画として、日頃の野菜摂取状況が把握できる測定機器を、令和4(2022)年8月中旬から9月末まで農林水産省内に設置し、職員及び来庁者に対して日頃の食生活に適量の野菜を取り入れることが習慣となるような機会を作りました(*1)。
職員向けの取組結果を見ると、1回目の測定結果の平均が野菜摂取量の推定で305g程度であったのに対し、2回目以降の平均(*2)は340g程度と35g程度上昇しました(*3)。また、取組前・取組後のアンケート結果を比較すると、野菜を摂取するよう心がけているかという質問に対し、「とてもそう思う」又は「そう思う」と回答した人の割合は、取組前は51.5%だったのに対し、取組後は61.6%と、約10ポイント増加しました(*4)。さらに、1回目の測定後に2回目の測定時における目標値の設定を促したグループ(<1>)と促さなかったグループ(<2>)で2回目の測定結果の平均を比較すると、<1>では平均25.4ポイント有意に上昇したのに対し、<2>では平均9.5ポイント上昇したものの有意差は認められませんでした。
この取組結果から、野菜摂取状況を数値で「見える化」することで、日頃の食生活を見直す機会となり行動変容を促すことにつながったと推測されるとともに、目標値の設定を促すことは更なる意識改革と行動変容に寄与する可能性が示唆されました。
なお、来庁者向けの取組結果を見ると、測定結果の平均が野菜摂取量の推定で280g程度となり、約7割の人が目標量に達しておらず、一般の20歳以上の平均とほぼ同じ結果でした。
*1 農林水産省の職員には期間中に複数回の測定を前提として、その結果の推移を個人ごとに記録するため、ID等の個人情報の入力が可能なベジメータを使用し、来庁者には個人情報の入力が不要なベジチェックを使用
*2 期間中に2回以上測定した人の場合は、最も高い値を採用
*3 1回目(1,239人)に比べて2回目(281人)は有効なデータが少ないことに留意する必要がある。
*4 取組前(1,121人)に比べて取組後(413人)のアンケートの回答者が少ないことに留意する必要がある。
事例:地元の食材や食文化の魅力とともに、料理人の立場から進める、
オンラインも活用した楽しく学ぶ食育活動
(第6回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞)
長田 勇久(おさだ はやひさ)さん(愛知県)
自ら経営する日本料理店を拠点として、持続可能な食につながる地域の食材と発酵文化の魅力、旬の大切さを料理人の立場から多くの人に伝えています。また、生産者や食品事業者と協力した公開講座の開催、伝統野菜や醸造文化の研究と発信、小中学校での栄養教諭等への料理講座の開催等、オンラインを活用しながら多彩な活動を展開しています。
料理人として生産と消費をつなぐことができる立場を生かし、地域の生産者や醸造文化の継承者たちの思いをくみ取るとともに、地産地消の推進など、食の循環を担う多様な主体とのつながりを深めています。
国内外の多くの方に活動の内容が伝わるように、日常の食事の振り返りや旬の食材に関する内容等のオンライン講座を行っているほか、SNS等のウェブ媒体を活用し、調理のイベントの様子などを情報発信しています。オンラインイベントでは参加者と意見交換を行うことにより、分かりやすく楽しい学びとなるよう工夫するとともに、アーカイブを残すことで振り返りができるようにしています。また、地元の食材や食文化に関する団体等に主体的に関わる中で、生産者や食品事業者との交流を行い生産物の知識を深めるとともに、自身が経営する日本料理店では、会話を通じて五感に直接訴えるようにするなど、食材、調理方法、食文化、旬の説明に時間をかけています。さらに、公開講座では、「愛知の食を学ぶ・楽しむ」をテーマに野菜の農家、畜産や水産加工業者、醸造業など多様な生産者を迎え、地元の食材の良さを伝える講座を実施しています。生産者の話を直接聞き、その食材を使ったお弁当を食べてもらうことで学生が地産地消を学ぶ機会を提供しています。
新型コロナウイルス感染症の影響下においては、早くからオンラインでの活動を取り入れてきましたが、今後は新型コロナウイルス感染症の収束も見据え、リアルとオンラインの取組の融合や、多様な分野と積極的に交流を進めていきます。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125