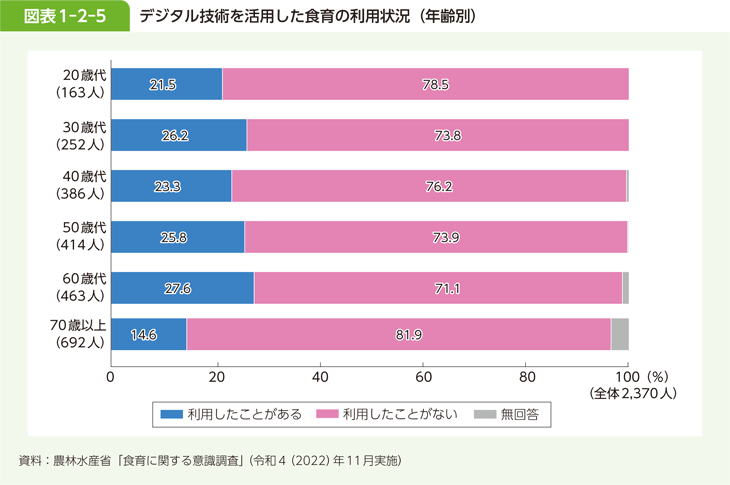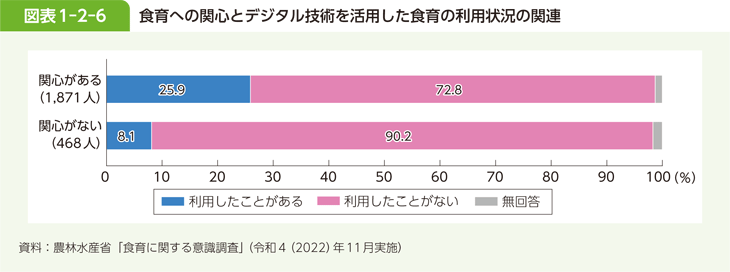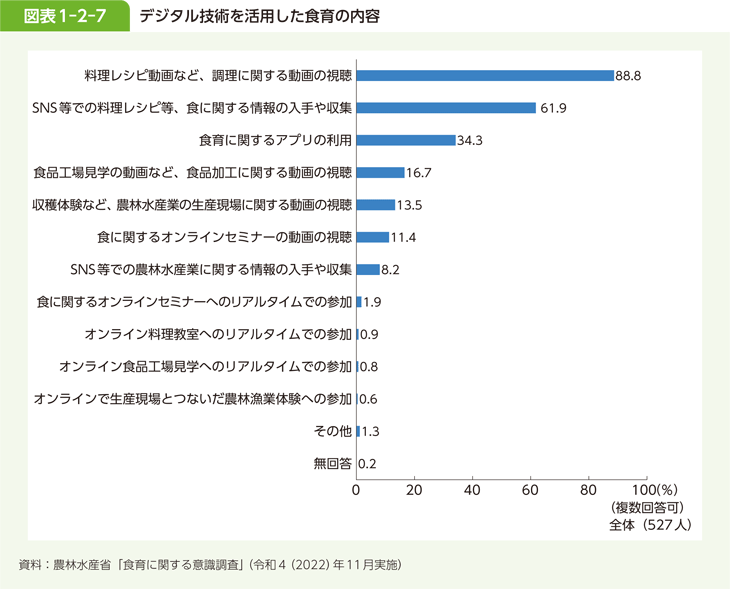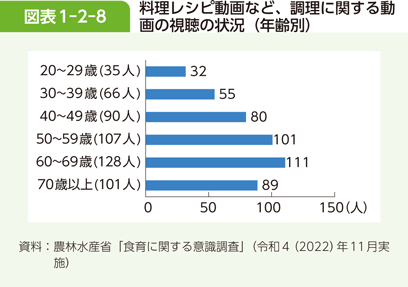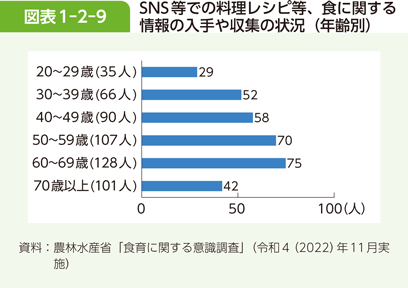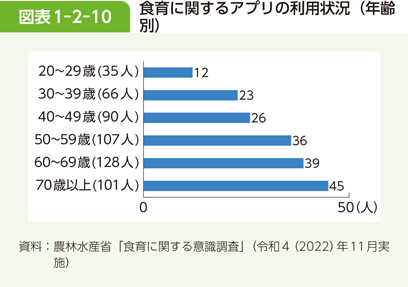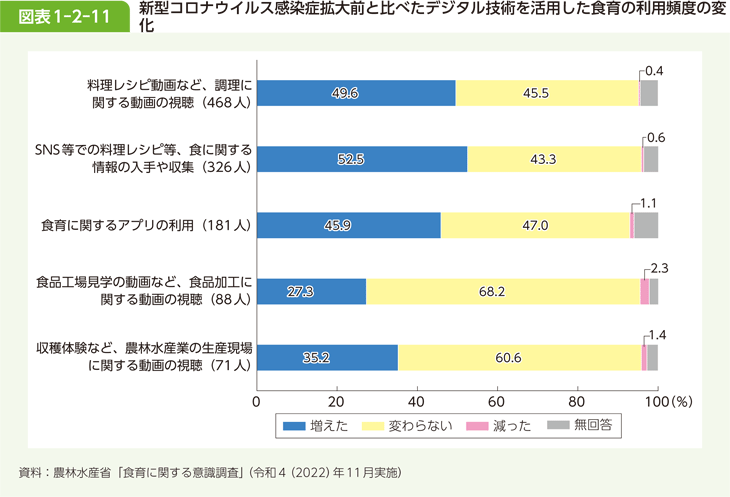3 デジタル技術を活用した食育に関する国民の実践の状況
令和4(2022)年度「食育に関する意識調査」で示されたデジタル技術を活用した食育(*1)についての国民の実践の状況は以下のとおりです。
*1 本調査において「デジタル技術を活用した食育」とは、インターネット等を通して食育に関する情報等を収集、視聴、活用、学習、体験することをいう。
(1)デジタル技術を活用した食育の実践の状況
家族の中でデジタル技術を活用した食育を利用したことがあるか尋ねたところ、「利用したことがある」と回答した人の割合は22.2%で、利用したことがある人を年齢別に見ると、20~60歳代のいずれの世代においても2割程度でした(図表1-2-5)。
食育について「関心がある」(「関心がある」又は「どちらかといえば関心がある」)と回答した人の25.9%がデジタル技術を活用した食育を利用していました(図表1-2-6)。
(2)デジタル技術を活用した食育の内容
家族の中でデジタル技術を活用した食育を「利用したことがある」と回答した人に、利用したことがある内容を聞いたところ、「料理レシピ動画など、調理に関する動画の視聴」を挙げた人の割合が88.8%と最も高く、次いで、「SNS等での料理レシピ等、食に関する情報の入手や収集」(61.9%)、「食育に関するアプリ(*1)(料理レシピ、栄養バランス、フードロス削減など)の利用」(34.3%)でした(図表1-2-7)。
*1 アプリケーションの略。スマートフォンの上で動くソフトウェアのこと。アプリをインストールすることで、スマートフォンに機能を追加できる。
「料理レシピ動画など、調理に関する動画の視聴」、「SNS等での料理レシピ等、食に関する情報の入手や収集」、「食育に関するアプリ(料理レシピ、栄養バランス、フードロス削減など)の利用」について、いずれの年代においても利用されています(図表1-2-8~1-2-10)。
(3)新型コロナウイルス感染症拡大前と比べたデジタル技術を活用した食育の利用頻度の変化
家族の中でデジタル技術を活用した食育を「利用したことがある」と回答した人に、新型コロナウイルス感染症拡大前と比べたデジタル技術を活用した食育の利用頻度の変化について、デジタル技術を活用した食育の利用状況の上位5つを見てみると、いずれも「増えた」と回答した人の割合が「減った」と回答した人の割合を上回っていました。「料理レシピ動画など、調理に関する動画の視聴」、「SNS等での料理レシピ等、食に関する情報の入手や収集」、「食育に関するアプリ(料理レシピ、栄養バランス、フードロス削減など)の利用」については、いずれも5割程度の人が「増えた」と回答しています(図表1-2-11)。
コラム:スマートフォンのアプリを活用した食育の取組

食生活改善アプリ
スマートフォンのアプリを使って、健康管理を実践したり、食品ロスの削減に協力したりすることで取り組む食育について紹介します。
健康管理に関するアプリでは、毎日の食事を記録すると栄養バランスを考えた献立が提案されたり、歩数等の生活習慣が記録されたりすることで、健康増進に役立てられます。
株式会社asken(アスケン)では、日々の食事を記録することで栄養バランスがとれた食事を自ら選ぶ力を育むことにつなげる、食生活改善のアプリを提供しています。何をどれくらい食べたかを記録すると、摂取したエネルギーや栄養素量等が算出され、目標量に対する過不足がアプリの画面にグラフで表示されます。また、記録された食事内容に対して管理栄養士の助言が自動でスマートフォンに届き、食事の改善に生かすことができます。食べた料理や食材は、アプリ内にある15万件以上のデータから選択できるほか、スマートフォンで撮影した食事の写真や市販食品のバーコードからも登録可能で、簡単に食事記録が続けられる工夫がされています。新型コロナウイルス感染症の影響下ではアプリの利用者も大幅に増加し、生活時間の変化等についても把握することができました。引き続き、食を通じて人々の健康に貢献できるような活動を展開していきます。
株式会社コークッキングでは、中食や外食の店舗において、美味しく安全に食べることができるにもかかわらず廃棄される食品を、消費者とつなげるアプリを平成30(2018)年から提供しています。
消費者が食品ロスの発生する店舗をアプリで検索し食べたい物を見つけたら、受け取る時間を決めて店舗に行き、アプリの画面を提示することで食料を受け取る仕組みとなっています。アプリ内では「購入する」、「買う」という言葉を使用せずに「レスキューする」という表現を用いて、食品ロスを削減したいお店や余った食料を「助けに行く」という意識を利用者が持てるように工夫されています。アプリを利用している人たちが、日々の行動の中で環境配慮や持続可能性、エシカルといったことに少しでも関心を持ち、消費に関する行動や体験が積み上がっていくことで社会全体に広がっていくことが期待されます。
事例:デジタルツールを活用した、果物の遠隔収穫体験
株式会社パーシテック(京都府)
株式会社パーシテックは、センサーシステムによる温度・日照量等のデータ収集、ドローンによる農作物の育成状態の確認、遠隔作業支援システムとスマートグラスを用いた遠隔操作による農業技術の伝承等、スマート農業の機器を導入した取組を行っています。また、平成29(2017)年からは遠隔操作技術を用いて、農園と消費者を結ぶ遠隔収穫体験を実施しています。
遠隔収穫体験は、実家の果樹園を継ぐに当たって父親から収穫の作業に関する指導を受けるため、スマートグラス等の遠隔操作ができるツールを活用したことがきっかけで始まりました。
遠隔収穫体験では、参加者はパソコンの画面を見ながら収穫の指示を出し、農家の方がスマートグラスを着けて農園で果物を収穫し、農園での収穫の映像を通して参加者は自分が指示した果物が目の前に現れるような視覚的な面白さを感じることができます。収穫された果物は参加者に送付されるため、参加者は自分が収穫した果物を実際に食べることができ、楽しさと美味しさを感じることができる仕組みとなっています。子供たちからは「柿はこんなに密に実がなるんだ。」、「りんごってこんな風に実がつくんだ。」と驚く声が聞かれます。
今後も、子供たちが農業やデジタル技術に興味を持つきっかけを作るとともに、デジタルツールを活用して子供たちが楽しいと感じる体験を提供していきます。
事例:リモートを活用した工場見学、出前授業、体験型の食育の取組
一般財団法人 食品産業センター(東京都)
一般財団法人食品産業センターは、食品産業(食料品・飲料製造業)や関連する業界を網羅する116団体、食品事業者等約124社、地方食品産業協議会等約31団体を会員とする業種横断的組織ですが、国民(特に子供たち)への食品に関する理解醸成等の観点から、各事業者の食育を支援しています。
新型コロナウイルス感染症の影響下において、これまで行ってきた対面での様々な食育活動に制約が生じる中、令和2(2020)年から令和3(2021)年にかけて、各事業者は工場見学、出前授業、体験型食育等はオンラインに切り替えて実施しました。オンラインでの食育の取組の実施に当たっては、年齢に応じた食育プログラム、学習用教材を事前に送付し、体験しつつ学ぶコンテンツ等を作成するなど、事業者ごとに創意工夫がされています。
多くの参加者から「実際の工場見学では入れない所をオンラインで見ることができて嬉しかった。」、「オンラインにもかかわらず、臨場感がよく伝わり、実際に工場見学をしているように参加できた。」等の感想が聞かれました。
オンラインでの食育は、場所にとらわれずに参加できるという良さがあり、対面での食育と並行して、画面を通して「体験」、「体感」を得られるコンテンツの作成に取り組んでいく予定です。今後も、食品事業者における食育に対する意識の向上を図るとともに、行政を始めとした様々な機関と連携して食育の活動に取り組んでいきます。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125