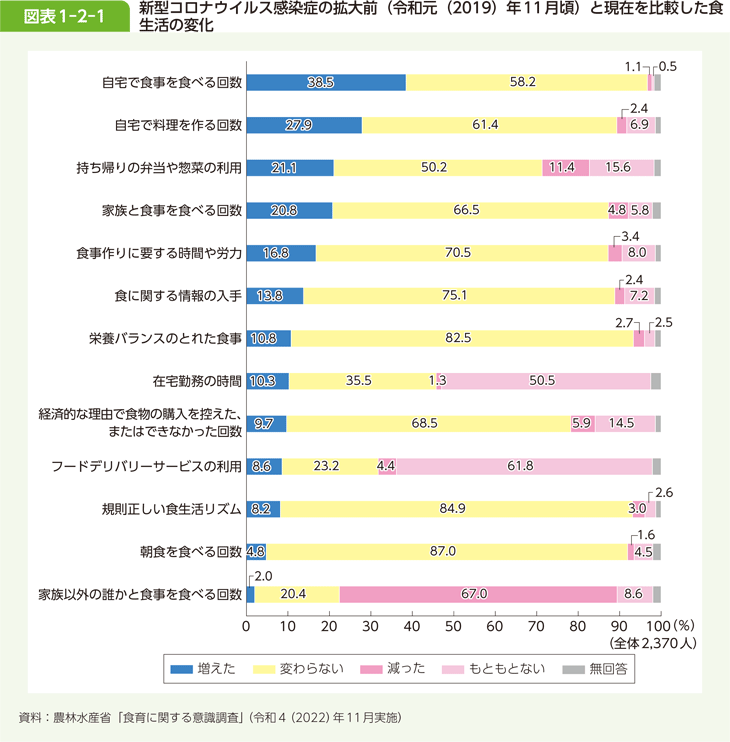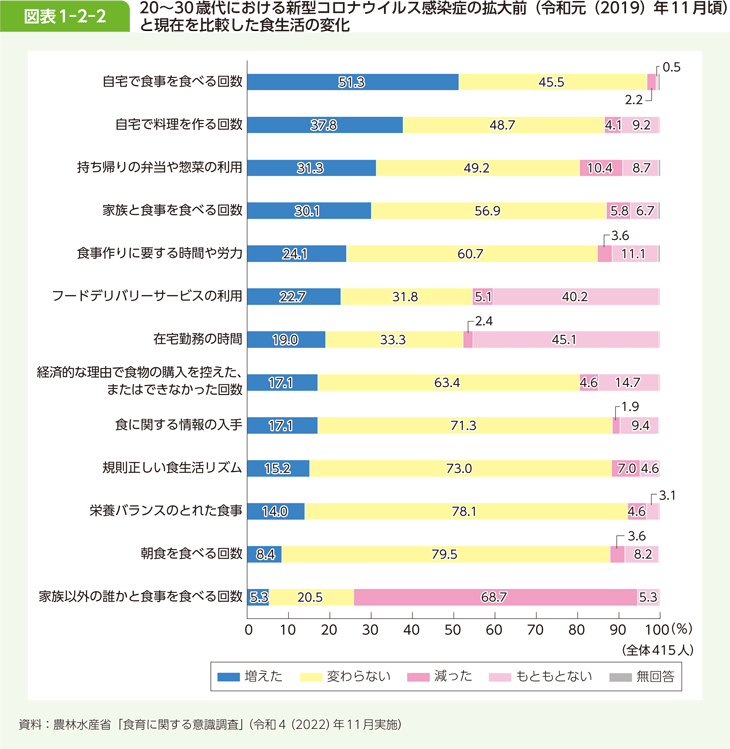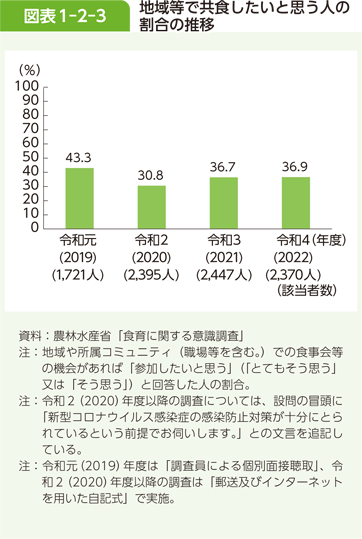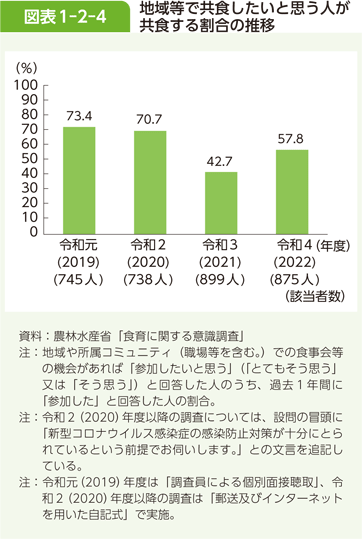2 新型コロナウイルス感染症の影響下における食生活等の変化
ここでは、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中での、国民の意識等の変化について、令和4(2022)年度「食育に関する意識調査(*1)」結果を示します。
*1 全国20歳以上を対象に、令和4(2022)年11月に、郵送及びインターネットを用いた自記式で実施
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大前と現在を比較した食生活の変化
新型コロナウイルス感染症の拡大前(令和元(2019)年11月頃)に比べて、現在の食生活が変化したかについて13の内容を挙げ、それぞれについて尋ねたところ、「増えた」と回答した人の割合が最も高いのは、「自宅で食事を食べる回数」(38.5%)で、次いで「自宅で料理を作る回数」(27.9%)、「持ち帰りの弁当や惣菜の利用」(21.1%)でした。
「減った」と回答した人の割合が最も高いのは、「家族以外の誰かと食事を食べる回数」(67.0%)で、次いで「持ち帰りの弁当や惣菜の利用」(11.4%)でした。「変わらない」と回答した人の割合が最も高いのは、「朝食を食べる回数」(87.0%)で、次いで「規則正しい食生活リズム」(84.9%)、「栄養バランスのとれた食事」(82.5%)でした(図表1-2-1)。
新型コロナウイルス感染症の拡大前(令和元(2019)年11月頃)に比べて、現在の食生活が変化したかについて、若い世代(20~30歳代)で見ると、「自宅で食事を食べる回数」(51.3%)、「自宅で料理を作る回数」(37.8%)が「増えた」と回答した人の割合が高くなっています(図表1-2-2)。
若い世代については、第4次基本計画において、栄養バランスに配慮した食生活の実践について、その他の世代よりも割合が低く、男性は将来の肥満が懸念されることや女性はやせの者が多いことなど、食生活に起因する課題が多いとされており、若い世代が食育に関心を持ち、自ら食生活の改善等に取り組んでいけるよう、効果的に情報を提供すること等を行うこととしています。新型コロナウイルス感染症の影響により、自宅で料理を作ったり自宅で食事を食べたりする機会が増えたことで、若い世代を含めた幅広い世代が食育に関心を持ち、自ら食生活の改善等に取り組むきっかけになることが期待されることから、効果的な情報提供を一層進めることが重要です。
(2)共食に対する考え方や行動の変化
共食は、会話やコミュニケーションが増えること、食事がおいしく楽しく感じられること等のメリットがあり、共食により食を通じたコミュニケーション等を図りたい人にとって、地域や所属するコミュニティ(職場等を含む。)等を通じて、様々な人と共食する機会を持つことは重要です。地域や所属コミュニティ(職場等を含む。)での食事会等の機会があれば「参加したいと思う」(「とてもそう思う」又は「そう思う」)と回答した人の割合は、令和元(2019)年度は43.3%であったのに対して、令和2(2020)年度は30.8%に減少し、令和3(2021)年度は36.7%、令和4(2022)年度は36.9%にやや増加しました(図表1-2-3)。また、「参加したいと思う」と回答した人のうち、過去1年間に食事会等に「参加した」と回答した人の割合は、令和元(2019)年度は73.4%、令和2(2020)年度は70.7%であったのに対して、令和3(2021)年度は42.7%と大幅に減少しましたが、令和4(2022)年度は57.8%となり、令和3(2021)年度より増加しました(図表1-2-4)。
新型コロナウイルス感染症の影響下における食生活等について、新型コロナウイルス感染症の拡大前と現在の食生活等を比較した場合、「減った」と回答した人の割合が最も高いのは「家族以外の誰かと食事を食べる回数」(67.0%)でした。また、地域や所属コミュニティ(職場等を含む。)での食事会等に「参加したいと思う」と回答した人の割合は令和2(2020)年度に減少した後、増加しており、「参加したいと思う」と回答した人のうち、過去1年間に食事会等に「参加した」と回答した人の割合は、令和3(2021)年度に大きく減少した後、増加しており、新型コロナウイルス感染症の影響下で、人々の共食に対する考え方や行動が変化していることがうかがえます(*1)。
*1 共食に対する考え方や行動について、令和2(2020)年度から調査方法を変更したため、単純に比較することはできない。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
消費・安全局
消費者行政・食育課
代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)
ダイヤルイン:03-6744-2125