食品産業動向調査の概要
調査の目的
食品産業動向調査は、毎年、食品産業に係る課題(テーマ)を定め、食品産業のおかれている状況と当面の課題を把握し、各種食品産業関連施策の推進に資することを目的とする。
調査対象
1.HACCP手法による食の安全性確保対策の実態
(1)調査対象は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示139号)による食品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業(製氷業、たばこ製造業及び飼料・有機質肥料製造業を除く)を営む企業で従業者数のうち常用雇用者が5人以上の企業とした。
(2)標本数の算出に当たっては、平成12年度調査結果から予想したHACCP手法の導入率を基準に標準誤差率(目標精度)が7.0%になるように標本を定め、業種別・従業者別規模別に配分している。
(3)平成18年度(HACCP手法による食の安全性確保対策の実態)の調査対象数は2,600企業である。
2.「食の安全・安心システム」の導入状況
(1) 調査対象は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示139号)による各種商品小売業及び飲食料品小売業を営む企業とした。
(2) 標本数の算出に当たっては、平成18年度調査における食品小売業の調査結果から「食の安全・安心システム」の導入率(トレーサービリティ・システムを導入し、同システムで記録・保管している情報について、仕入先から「二次元コード」や「電子タグ」等により伝達されている企業の割合)を基準に標準誤差率(目標精度)が7.0%になるように標本を定め、業種別・従業者別規模別に配分している。
調査事項
1.HACCP手法による食の安全性確保対策の実態
(1) 食品の販売総額規模、従業者規模
(2) 製造している食品のうち販売金額が多い上位3品目
(3) HACCP手法の導入状況
(4) HACCP手法の導入方式
(5) HACCP手法の導入予定時期
(6) HACCP手法の一層の充実を図る方法
(7) HACCP手法の導入に当たっての問題点
(8) HACCP手法の導入による効果
(9) HACCP手法の導入に当たって役立った支援策
(10) HACCP手法を導入する予定がない理由
2.「食の安全・安心システム」の導入状況
(1) 企業の従業者規模
(2) トレーサビリティ・システムの導入状況
(3) 同システムにおける情報の記録内容
(4) IT機器の活用状況
(5) ロット管理の単位
(6) ロット番号の伝達方法
(7) 生産者等の特定(遡及)の可能性と生産者等の特定(遡及)に要する時間 等
調査の時期
1.HACCP手法による食の安全性確保対策の実態
調査対象期間は平成18年6月1日現在とし、平成18年7月に調査を行った。
2.「食の安全・安心システム」の導入状況
調査対象期間は平成20年1月1日現在とし、平成20年1月21日から2月20日の間に調査を行った。
調査の方法
食品産業動向調査は、農林水産省統計部→地方農政局(地方農政事務所)→ 統計・情報センター→調査対象の流れにより行う。具体的には次のとおりである。
調査対象企業に対して調査票を郵送により送付・回収する自計調査の方法
集計・推計方法
調査対象全体、業種別及び従業者規模別に集計を行う。なお、各階層区分の平均値は、次の計算式により推定している。
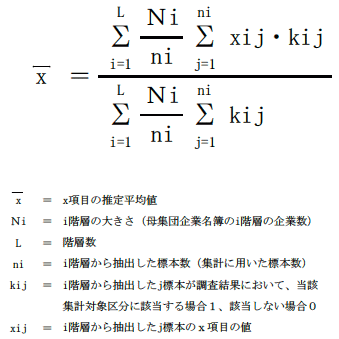
用語の解説
1.HACCP手法による食の安全性確保対策の実態
(1) HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)手法
食品の安全性を高度に保証する衛生管理手法の1つで、食品の製造業者が原材料から加工・包装・出荷に至る一連の工程の各段階で危害防止につながる重要管理点をリアルタイムに監視し記録することにより製品の安全を確保しようとする管理方式をいう。
(2) 食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程承認制度
食品衛生法に基づくHACCP手法による食品衛生管理の認証制度で、厚生労働大臣が食品の製造又は加工施設ごとに承認するものをいう。
(3) HACCP手法支援法に基づく高度化計画の認定
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(HACCP手法支援法)に基づき、食品の製造業者が作成した高度化計画について、食品ごとの事業者団体が指定認定機関となり、高度化基準(農林水産省と厚生労働省の両大臣が認定)に則っているかを確認し、工場ごとに認定することをいう。
(4) 対米・対EU輸出水産食品の登録施設アメリカ、欧州連合域内へ輸出する水産食品については、当該国が規定した衛生管理基準に適合することが必要なことから、厚生労働省が定めた取扱要領により都道府県等が審査・登録を行うもののほか、民間登録機関(大日本水産会等)が審査・登録を行うものをいう。
(5) 地方自治体が独自に設定した食品衛生管理認定制度等
食品事業者の自主的な衛生管理を積極的に評価する制度として、HACCP手法による衛生管理を基本とした基準を設け、その基準を満たしている施設を認証する地方自治体独自の制度をいう。
(6) ISO22000
食品の安全の確保をより確実なものにするため、農家等の一次生産者、飼料生産者、食品製造業者、輸送・保管業者、小売業者、食品サービス事業者等のフードチェーンに関係したあらゆる組織の事業者を対象として、相互コミュニケーション、食品安全マネジメントシステム、一般的衛生管理プログラム及びHACCP手法の実施を行うシステムをいう。
(7) 食品の販売金額
企業全体の平成17年度(平成17年4月1日~平成18年3月31日)1年間の食品の販売金額とした。
なお上記期間での記入が困難な場合には直近の決算期間(1年間)とした。
(8) 従業者数
雇用期間を定めずに雇用されている者、もしくは1か月を超える期間を定めて雇用されている者(常用雇用者)の人数とした。
2. 「食の安全・安心システム」の導入状況
(1) トレーサビリティ(追跡可能性)
生産、処理・加工、流通・販売のフードチェーンの各段階で、食品とその情報を追跡し遡及できることをいう。
(2) トレーサビリティ・システム
いつ、どこから、仕入れし、(いつ、どこで製造し)、いつ、どこへ出荷(販売)したか特定できる仕組みをいい、本調査では、(ア)店舗(企業)内において、食品のロット管理ができており、(イ)食品の仕入先を特定(遡及)することができることをいう。なお、パソコンなどのIT機器を利用したシステムのみを指すものではない。
(3) ロット(荷姿)
同一条件の下で加工又は包装された食品の各段階での取り扱い単位のことをいう。品目により何をロットとするかは異なる。
(4) ロット管理
一定のまとまり(ロット)ごとに、店舗内での商品を把握(管理)することをいう。
(5) JANコード
POSシステムなどに利用されるもので、バーコードで表すための一般的な共通商品コードをいう。
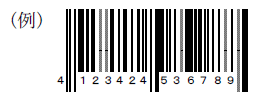
(6) UCC/EAN-128(EAN/UCC-128、GS1-129)
ロット番号や商品情報など複数の情報を1つのバーコードで表すためのコードをいう。
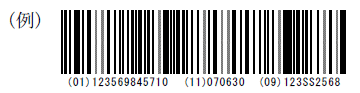
(7) バーコード
太さや間隔の異なる棒を並べ合わせて表示する符号をいう。
(8) 二次元コード
水平、垂直方向に情報を持つ符合をいう。二次元方向に情報を持つことから、一方向の情報しか持たないバーコードの数十倍から数百倍のデータ表現が可能なコードである。
(9) 電子タング
情報を記録する小さな集積回路(IC)チップとアンテナが組み込まれたタグ(荷札)をいう。非接触でデータを読みとり又は書き込みできるRFID(Radio frequency Identification)とも呼ばれる。
(10) 従業者数
雇用期間を定めずに雇用されている者、もしくは1か月を超える期間を定めて雇用されている者(常用雇用者)の人数をいう。
その他
食品産業動向調査の年度別テーマ
15~17年度トレーサービリティ・システムの導入・実施状況等の実態
18年度HACCP手法による食の安全性確保対策の実態
食の安全・安心システムの導入状況
19年度食の安全・安心システムの導入状況
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室
担当者:食品産業動向班
代表:03-3502-8111(内線3717)
ダイヤルイン:03-3591-0783




