(1)これまでの食料・農業・農村基本計画
(前基本計画までの目標と施策)
平成11(1999)年7月に、食料・農業・農村に関する施策の基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めた、食料・農業・農村基本法(以下「基本法」という。)が制定され、以降、基本法が掲げる食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的発展及び農村の振興という4つの基本理念を具体化するための施策が推進されてきました。
食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)は、基本法に掲げる基本理念に沿った具体的な施策展開のプログラムであり、食料・農業・農村をめぐる情勢の変化等を踏まえ、おおむね5年ごとに変更することとされています。
最初の基本計画は、平成12(2000)年に策定され、食生活指針の策定、不測時における食料安全保障(*1)マニュアルの策定、効率的かつ安定的な農業経営が相当部分を担う農業構造の確立、価格政策から所得政策への転換、中山間地域等直接支払制度の導入等が位置付けられました(図表特1-1)。次に平成17(2005)年基本計画では、食の安全と消費者の信頼の確保、食事バランスガイドの策定等食育の推進、地産地消(*2)の推進、担い手を対象とした水田・畑作経営所得安定対策の導入、農地・水・環境保全向上対策の導入、バイオマス(*3)利活用等自然循環機能の維持増進、農林水産物・食品の輸出促進等の施策を展開することとされました。さらに、平成22(2010)年基本計画では、食の安全と消費者の信頼の確保、総合的な食料安全保障の確立、戸別所得補償制度の導入、生産・加工・販売の一体化や輸出促進等による農業・農村の6次産業化(*4)等の推進等が位置付けられました。その後、平成27(2015)年基本計画では、国産農産物の消費拡大、「和食」の保護・継承、農地中間管理機構のフル稼働、米政策改革の着実な推進、多面的機能支払制度等の着実な推進、東日本大震災からの復旧・復興、農協改革や農業委員会改革の推進等の施策を展開することとされました。
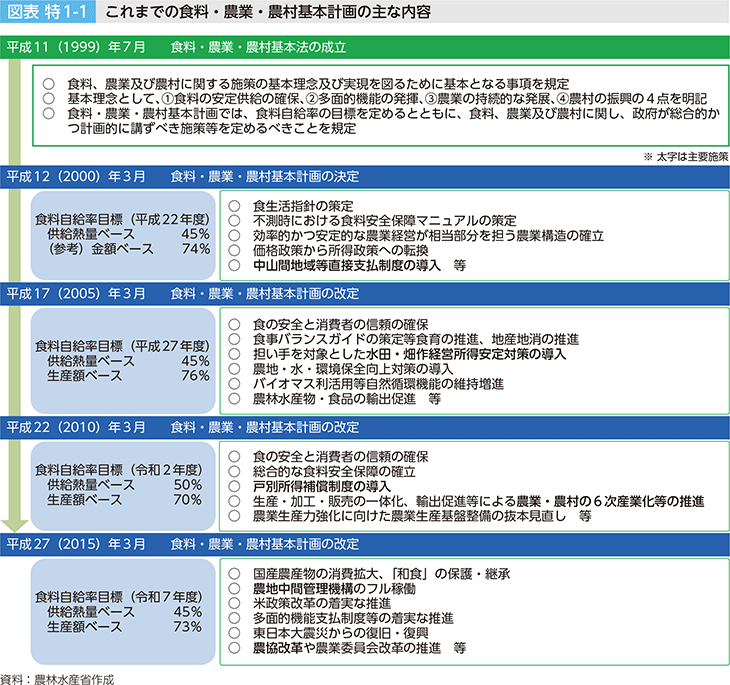
また、基本法第15条において、「食料自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、国内の農業生産及び食料消費に関する指針として定める」こととされており、それぞれの基本計画に総合食料自給率の目標が設定されています。
平成12(2000)年基本計画では、計画期間内における実現可能性を考慮し、平成22(2010)年度に供給熱量(*5)ベースで45%とする目標が定められました。次の平成17(2005)年基本計画では、平成27(2015)年度に供給熱量ベースで45%とすることに加え、比較的低カロリーである野菜、果実等の生産活動をより適切に反映する観点から、前回は参考として示されていた生産額ベースについて、76%とする目標が定められました。さらに平成22(2010)年基本計画では、「我が国が持てる資源をすべて投入した時にはじめて可能となる高い目標」として、令和2(2020)年度に供給熱量ベースで50%、生産額ベースで70%とする目標が定められました。その後の平成27(2015)年基本計画では、平成22(2010)年基本計画における目標の検証を踏まえ、令和7(2025)年度に供給熱量ベースで45%、生産額ベースで73%とする目標が定められました。
*1~5 用語の解説3(1)を参照
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526




