第8節 農福連携の推進
近年、農業分野と福祉分野が連携して、障害者や生活困窮者、高齢者等の農業分野への雇用・就労を促進する農福連携の取組が各地で盛んになっています。農福連携は、障害者等の自信や生きがいを創出するとともに、農業分野においても働き手の確保のみならず、生産の効率化や高品質な農産物生産につながる効果が期待される、両分野にとって利点のある取組です(図表3-8-1)。
(農福連携は農業者の収益性向上や障害者の工賃向上に効果)
農福連携により、障害者等の農業分野への雇用・就労を通じて、障害者等の活躍の場が拡大し、農産物の付加価値の向上、障害者等の自立支援にもつながります。
一般社団法人日本(にっぽん)基金の調査によれば、障害者を受け入れた農業者の78%は5年前と比較して年間売上額が上がったと回答しています(図表3-8-2)。また、障害者が人材として貴重な戦力となっていること、営業等に充てる時間の増加、作業の見直しによる効率向上といった副次的な効果があると回答しています(図表3-8-3)。
また、農業に取り組んだ福祉事業所の89%は農業への取組によるプラスの効果があったと回答し、58%が農産物(加工品)の年間売上高が5年前と比較して上がったと回答しています(図表3-8-4、図表3-8-5)。また、79%が体力がついた、62%が表情が明るくなったと回答しており、精神面、身体面への効果もうかがえます。さらに、過去5年間の障害者の賃金・工賃についても、「増えてきている」と回答している事業所が全体の7割以上を占めていることから、農業に参入することが障害者の工賃向上の一助になっていることがうかがえます(図表3-8-6)。
このように、働き手の不足に悩む農業者側と、安定した雇用の場や、それに伴う賃金や生活の質の向上を求める障害者側のニーズが一致し、農業生産・農業経営の効率化が可能となり、収益の向上につながっていると言えます。
(障害者とのコミュニケーションや作業時間の調整に課題)
一方で、障害者を雇用している農業者のうち、63%が障害者とのコミュニケーションに課題があると回答していますが、その課題に対して、多くの農業者が、関係者からの情報収集が重要である、日々障害者と接する中で徐々に理解が深まると回答しています(図表3-8-7)。また、農閑期は作業が少なく、安定的な通年雇用にも課題が見られますが、作業工程の細分化や販売・加工等への事業拡大等によって通年で作業を確保するなどの取組が行われています。
さらに、福祉事業所に農作業を委託している農業者のうち67%は、農作業の時間と福祉側の時間が合わない、福祉側が急な仕事に対応できないなど、スケジュール調整や人手の確保に関して課題を感じていると回答しており、福祉事業所と直接相談し調整することで課題解決に取り組んでいます(図表3-8-8)。
(農福連携に取り組む農業者には拡大の意向あり)
このような課題はあるものの、全体として効果が大きいことから、障害者を雇用している農業者の59%が雇用を拡大したいという意向を持っており、また、福祉事業所に農作業を委託している農業者の63%が委託を拡大したいという意向を持っています(図表3-8-9、図表3-8-10)。
(農福連携等推進ビジョンを決定)
平成31(2019)年4月、議長を内閣官房長官、副議長を厚生労働大臣、農林水産大臣とし、構成員として、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省の関係局長等、また有識者として、先進的に農福連携に取り組まれている方、経済団体、農業団体、歌手グループのTOKIO(トキオ)の城島茂(じょうしましげる)さんも出席する農福連携等推進会議の第1回会議を開催しました。この会議では、農福連携による農山漁村の再生への取組推進について、実効性のある方策を検討しました。
令和元(2019)年6月に開催された第2回会議では、農福連携等推進ビジョンを決定しました。このビジョンでは、農福連携を全国的に広く展開するため、農林水産省を始めとする関係省庁等の連携の下、定量的なデータ収集・解析による農福連携のメリットの客観的な提示、国民全体に訴え掛ける戦略的プロモーション、ワンストップで相談できる窓口体制の整備、農業経営体と障害者就労施設のニーズをつなぐマッチングの仕組みの構築、障害者が働きやすい環境の整備と専門人材の育成、各界の関係者が参加するコンソーシアムの設置等の取組を促進することとしています。また、令和6(2024)年度までに農福連携に取り組む主体を新たに3千主体創出することを目標としています。これを踏まえ、経済団体等、幅広い関係者が参加する「農福連携等応援コンソーシアム」が令和2(2020)年3月に設立され、今後、優良事例の表彰、横展開等を推進していく予定です。
(農福連携推進に向けた政府等の取組)
このように、農福連携の取組への関心が高まる中、農林水産省及び厚生労働省 では、平成31(2019)年3月に農業側と福祉側のマッチングをテーマとした農福連携推進フォーラムを開催しました。また、一般社団法人日本(にほん)農福連携協会は、令和元(2019)年9月、持続可能な共生社会の実現に向けて、多分野の関係者を招き、基調講演、プレゼンテーション、トークセッションを行うノウフクフォーラム2019を開催しました。こうした機会は、農福連携に関心のある農業者や、これから農福連携に取り組みたい事業者にとって、農福連携の現状や課題を知る場となり、農福連携の更なる推進が期待されます。
また、農林水産省では、農山漁村振興交付金の農福連携対策により、障害者等の雇用・就労を目的とした農業用ハウスや加工施設の整備、障害者を受け入れる際に必要となる休憩所や手すり等の安全施設の整備等、農福連携のために必要となる環境整備の取組を支援しています。
さらに、地域活性化に取り組む多様な方々に農福連携の価値を知っていただき、地域の方々がつながる場として農福連携推進ブロックセミナーを全国7か所で開催しました。
コラム:農福連携の推進の鍵となる専門人材
障害者が農作業を円滑に行うためには、障害者の特性を理解した上で、作業指示を分かりやすく障害者に伝えることが必要です。
そのため、農業者、福祉事業所の指導員、障害者の間を取り持ち、障害者への分かりやすい指示の方法を農業者に助言するとともに、農業者に代わって障害者に具体的に作業指示を行うことにより、障害者の職場定着を支援する専門人材の育成が重要です。
農林水産省では、令和2(2020)年度からそのような専門人材を農福連携技術支援者と呼び、育成のためのガイドラインを設け、農林水産研修所水戸ほ場等で育成研修を実施することとしています。
また、農山漁村振興交付金(農福連携対策)により、都道府県による農福連携技術支援者の育成等の取組に対して支援をしています。
三重県では、一般社団法人と連携し、障害者が農園で働けるよう支援する専門人材を農業ジョブトレーナーと称して、養成研修を実施し、農業者へのトレーナーの派遣等の取組を展開しています。
コラム:ノウフクJASの認証
平成31(2019)年3月に、障害者が主要な生産行程に携わって生産した農林水産物及びこれらを原材料とした加工食品について、その生産方法及び表示の基準を規格化した「ノウフクJAS」が制定されました。
ノウフクJASは、障害者が携わった食品への信頼性を高め、人や社会・環境に配慮した消費行動を望む購買層に訴求するとともに、「農福連携(ノウフク)」の普及を後押しすることで、農業・福祉双方の課題解決のツールになるものです。
令和元(2019)年11月1日、登録認証機関(一般社団法人日本基金)により、「ノウフクJAS」第1号として4事業者が認証され、その後、令和2(2020)年3月までに10事業者が認証されました。
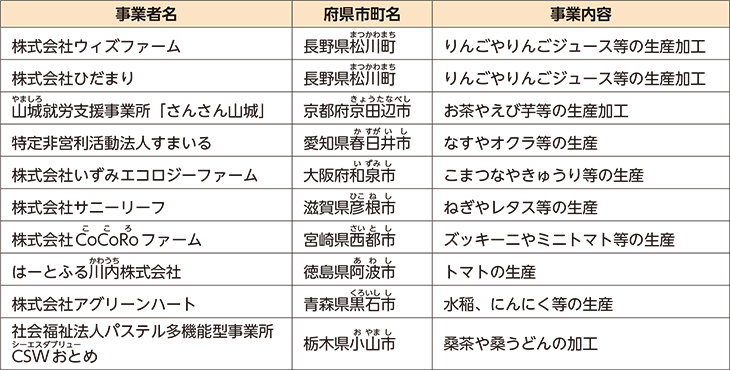
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883
FAX番号:03-6744-1526


















