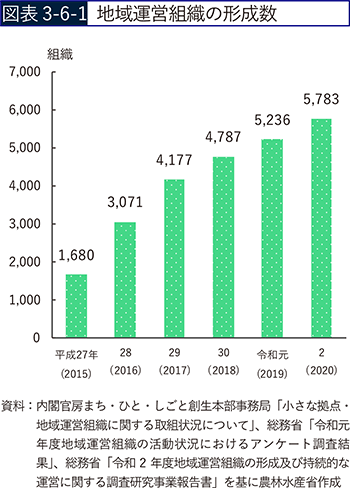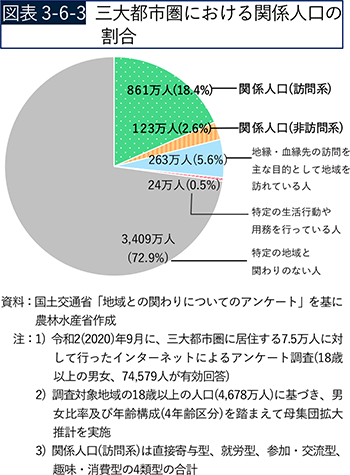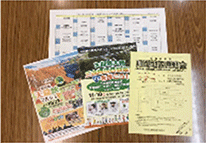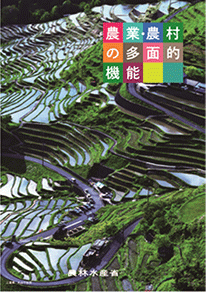第6節 農村を支える新たな動きや活力の創出

「田園回帰」による人の流れが全国的に広がりつつある中で、本節では、農村における新たな動きや農村の活力の創出に向けた体制・人材づくり、棚田地域の振興、多面的機能に関する理解の促進等の様々な取組について紹介します。
(1)地域を支える体制と人材づくり
ア 地域づくりに向けた体制整備の進展
(地域運営組織による地域づくりの取組が進展)
地域課題の解決に取り組む地域運営組織(RMO)(*1)は、公共施設の維持管理といった行政の代行事業や地域イベントの運営といった多様な活動を行っており、近年、その形成数は増加しています(図表3-6-1)。
農林水産省は、農林漁業の振興と併せて買物・子育て等の地域のコミュニティの維持に資するサービスの提供や、地域内外の若者等の呼び込みを行う事業体の形成等を支援しています。
また、リーダーの世代交代等に関係なく地域を持続的に支えることができる体制を構築し、地域を維持していくため、中山間地域等直接支払制度における地域の集落戦略作成を推進すること等を通じて、地域運営組織の形成と地域づくりの取組を推進しています。
さらに、令和2(2020)年5月から「新しい農村政策の在り方に関する検討会」において、集落機能の維持・強化に資する地域運営組織への支援等について議論を行っており、令和3(2021)年6月までに取りまとめることとしています。
1 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織のこと(総務省「暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書」)
(事例)地域運営組織によって地域の課題やニーズに総合的に対応(高知県)
高知県三原村(みはらむら)は、人口減少や高齢化により、地域活動の担い手不足、買い物や移動手段といった生活面での不安等の様々な課題に直面しています。このため、平成28(2016)年度に、住民が主体となって、地域運営組織、一般社団法人三原村集落活動(みはらむらしゅうらくかつどう)センターやまびこ(以下「やまびこ」という。)を設立し、村内の14地区それぞれの課題やニーズに応じ、生活、福祉、産業といった活動に取り組んでいます。
やまびこには活動内容に応じて六つの部署が設置されています。例えば、生産部では、ししとうやブランド米「水源のしずく」の栽培を行っており、店舗部が運営するレストランで提供されているほか、特産品販売促進部によって加工・販売されています。
やまびこの職員は「以前は村民が一体となって話し合う機会が少なく、村の将来に悲観的な声もあったが、やまびこを設立したことで村内14地区の多様な住民が集まる場が生まれ、質的にも量的にも地域づくりの取組を向上させることができた。住民の意識も前向きになった。」と話しています。今後は、広報誌等による住民への情報発信を続け、更に村民が一体となって活動を継続していく予定です。
(地域づくり人材の育成のための仕組みづくりを促進)
地域への「目配り」をする地方自治体職員の減少や体制の脆弱化等に対応するため、農林水産省では令和2(2020)年度において、各地域の実情に応じた地域づくりを行うコーディネーターを育成する研修のカリキュラムを作成したところであり、令和3(2021)年度から主に地方公共団体の職員を対象とした人材研修を開始することとしています。
(人口急減地域特定地域づくり推進法が施行)
人口急減地域特定地域づくり推進法(*1)が令和2(2020)年6月に施行されました。これにより、地域人口の急減に直面している地域において、地域の様々な事業者が出資し、地域内外の若者等を雇用する事業協同組合を設立し、都道府県知事の認定を受けた場合に、労働者派遣法(*2)の特例や組合の運営等に係る経費について財政上の措置を受けられるようになり、令和2(2020)年度は全国で5市町村が特定地域づくり事業推進交付金の交付対象となりました。地域内で複数の仕事を組み合わせ、年間を通じた雇用を創出することにより、安定的な雇用環境や一定の所得水準の確保が可能となり、地域内外の若者等の定住の増加や地域経済の活性化につながっていくことが期待されています。
1 正式名称は「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」
2 正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
イ 関係人口の創出・拡大や関係の深化を通じた地域の支えとなる人材の裾野の拡大
(関係人口の増加に向けた取組を実施)
農村の人口減少の下、地域の社会的・経済的活力を維持するため、これからの地域づくりの担い手として「関係人口」が注目されています(図表3-6-2)。
農林水産省は、長期的な定住人口でも短期的な交流人口でもない、地域や地域の人々と継続的に多様な形で関わる「関係人口」の増加に向けて、農山漁村と都市の交流を契機として農山漁村地域に関心を持ってもらうため、平成29(2017)年度以降、農泊に取り組む地域に対して、古民家等を活用した滞在施設の整備や体験・交流プログラムの開発を支援するなど農泊を推進しています。また、平成20(2008)年度から、子供の農山漁村体験の充実のため、体験プログラムの開発や宿泊施設の整備等を支援しているほか、平成27(2015)年度からは、都市住民の農業への理解を醸成するため、体験農園の取組を支援しています。

(事例)体験を通じた関係人口から実際の移住へ(和歌山県)
和歌山県では、平成30(2018)年度より、移住前の生活のイメージと移住後の生活のミスマッチを防ぐため、地域での「しごと」を体験しながら、ゲストハウスや農家民宿等に滞在し、「くらし」を体験することができる「わかやましごと・くらし体験」事業を実施し、関係人口の創出・拡大に取り組んでいます。
平成30(2018)年度から令和2(2020)年度までの間に、県内の130を超える事業者から受入れの登録があり、参加者は最大2泊3日の「起業・就農コース」や最大5泊6日の「就労コース」を通じて、製炭業からIT事業まで様々な業種を体験することができます。
これまでの参加者のうち、実際に移住したのは7人で、その家族も含めると移住者は計15人となります。移住者の中には地域の伝統産業である紀州備長炭の担い手となる者や、地域の様々な取組を紹介するライターとして活動する者等もおり、移住先で多様な活躍を見せています。
「わかやましごと・くらし体験」事業への参加者は、令和元(2019)年度の25人から、令和2(2020)年度には55人に増加しており、和歌山県は今後更なる関係人口の創出を目指しています。
(三大都市圏における関係人口は1千万人弱)
国土交通省の調査によると、令和2(2020)年9月時点で、三大都市圏都市部の18歳以上の居住者4,678万人のうち、18.4%にあたる861万人が関係人口(訪問系)として、日常生活圏や通勤圏等ではない特定の地域を訪問している(*1)と推計されています(図表3-6-3)。また、実際に訪問はしないものの、ふるさと納税やクラウドファンディング、地場産品等の購入、オンラインの活用等による地域との関わりのある関係人口(非訪問系)は123万人いると推計されており、地域との関わり方が多様になっていることがうかがわれます。
1 帰省等の地縁・血縁的な訪問は除く。
(事例)ふるさと納税の返礼に手紙、写真で情報を発信(長野県)
長野県飯田市(いいだし)が導入しているふるさと納税には、平成20(2008)年に開始した「ふるさと飯田応援隊」と平成29(2017)年に開始した「飯田市20地区応援隊」の2種類の仕組みがあります。「ふるさと飯田応援隊」は納税者が飯田市を対象に寄附を行い、返礼品として飯田市の特産品が届けられるものです。一方、「飯田市20地区応援隊」は、飯田市を構成する20地区のうち、応援したい地区を納税者が選択して寄附を行い、その返礼としてお礼の手紙のほか、地区の折々の行事等の案内状や写真を受け取るもので、納税者と地区との関係づくりを目指したものです。
20地区の一つ、飯田市川路(かわじ)地区では、川路(かわじ)まちづくり委員会が20地区応援隊による寄附金を基に、納税者にお礼の手紙のほか、運動会、マルシェ、祭りの開催の案内状や開催時の様子の写真、カレンダー等を発送しています。川路地区には平成30(2018)年度に3件・55万円、令和元(2019)年度には15件・24万円の寄附が集まりました。川路まちづくり委員会では、今後も春、秋の年2回、行事の案内等の情報発信、ふるさと納税への呼びかけを続けることとしています。
川路地区を含む「飯田市20地区応援隊」への寄附は、平成29(2017)年度の9件・29万円から、令和元(2019)年度には51件・215万円と増加しており、飯田市は令和3(2021)年度以降も制度を継続する予定です。
(子供の農山漁村体験を推進)
農林水産省を含む関係省庁は、平成20(2008)年度より、子供が農山漁村に宿泊し、農林漁業の体験や自然体験活動等を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」を推進しています。
子供の教育にとって、農山漁村での生活体験は、生命と自然を尊重する精神の育成や環境保全に対する意識の形成、農林漁業の意義の理解等の効果があるとされています。また、子供を受け入れる地域にとっても、地域内外の関係者同士の新たなつながりや住民の活力の創造等の効果が期待されます。
(コラム)小学生向けに農業について紹介した教材を配布
JAバンクでは、平成20(2008)年度より、小学校高学年向けに米や野菜等の生育過程や我が国の農業の概要等を紹介した教材本「農業とわたしたちのくらし」を作成し、全国2万校に130万部を配布しています。
小学校における総合的な学習の時間等の補助教材として利用されており、児童の農業や自然環境等に対する理解を醸成し、農業に関心を持つ次世代の育成に寄与しています。
実際に、児童からも、「これからの農業は後継ぎ不足でどうなるかわからないけど、今自分たちがご飯を食べられるありがたさを習い、そのことを活かすことができたらいいなあと思いました。」といった声が聞かれています。
(地元企業の認知度が高いほど出身市町村への愛着が高く、Uターンを希望)
独立行政法人労働政策研究・研修機構(ろうどうせいさくけんきゅうけんしゅうきこう)の調査(*1)によると、出身市町村への愛着を持っている割合(*2)は、高等学校卒業までに地元企業を全く知らなかったとした回答者では51.1%であるのに対し、地元企業をよく知っていたとした回答者では87.1%と高くなっています(図表3-6-4)。また、出身市町村へのUターン希望の割合(*3)についても、高等学校卒業までに地元企業を全く知らなかったとした回答者では32.5%であるのに対し、地元企業をよく知っていたとした回答者では63.8%と高くなっています。このように、高校時代までの地元企業への認知度が、出身地への愛着につながり、Uターン希望を喚起する可能性がうかがえます。
1 独立行政法人労働政策研究・研修機構「地方における雇用創出―人材環流の可能性を探る―」(平成29(2017)年3月公表)
2 「強い愛着あり」「少し愛着あり」と回答した割合の合計
3 「戻りたい」「やや戻りたい」と回答した割合の合計
ウ 多様な人材の活躍による地域課題の解決
(地域おこし協力隊員が全国で活躍)
平成21(2009)年度に総務省が開始した「地域おこし協力隊」の取組により、都市部から住民票を移した地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の定住・定着を図る取組が進められています。
隊員は、地方公共団体から委嘱され、地場産品の開発・販売や農林水産業の支援等の「地域協力活動」に従事することで、地域に定住するための準備等を行うことができます。隊員の地域協力活動を通して、受入地域や地方公共団体は、斬新な発想や新たな技術を持った人材を活用することができるようになります。令和2(2020)年度末時点で、全国1,065の地方公共団体で5,556人の隊員が受け入れられています。
令和元(2019)年度末までに任期を終了した隊員の数は延べ6,525人となっており、このうち20代が30.7%、30代が39.8%を占めています(図表3-6-5)。また、任期を終了した隊員の半分に当たる3,310人は受入地域と同一市町村内に定住し、古民家カフェの起業や地域づくり・まちづくり支援業への就業、農業法人への就職等を通じて引き続き地域で活躍しています(図表3-6-6)。
(2)農村の魅力の発信
(棚田地域振興法に基づく棚田地域の振興を推進)
棚田は、農産物の供給にとどまらず、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面的機能を有しています。しかし、地形的条件の厳しさのため、その保全には多大なコストが必要であり、地域の高齢化等が進展する中、荒廃の危機に直面している棚田も見られます。
このような背景の下、令和元(2019)年8月、棚田地域振興法が施行され、市町村や都道府県、農業者、地域住民等の多様な主体が参画する地域協議会による棚田を核とした地域振興の取組を、関係府省庁横断で総合的に支援する枠組みが構築されました。
令和2(2020)年度には、同法に基づき累計629地域を指定棚田地域に指定するとともに、指定棚田地域において地域協議会が作成した累計102計画の指定棚田地域振興活動計画を認定しました。認定された活動計画に基づき地域協議会が行う棚田の保全と地域振興の取組を、関係府省庁で連携して支援しています。
(棚田カードの作成等を通じた棚田の魅力を発信)
農林水産省では、棚田地域を盛り上げ、棚田保全の取組の一助となるよう、都道府県に呼びかけ、平成30(2018)年度に棚田カードプロジェクトチームを立ち上げました。本チームでは、「棚田に恋」をキャッチコピーに、棚田に関心を持ってもらい棚田を訪れるきっかけになるよう棚田カードを作成しており、令和2(2020)年7月には第2弾となる棚田カードの配布を開始するなど、108地区の棚田が参加する取組となっています。また、令和2(2020)年度には、「棚田コン」と表して佐賀県玄海町(げんかいちょう)の浜野浦(はまのうら)の棚田を舞台としたオンライン婚活イベントを開催したほか、「棚田で輝くおばあちゃん」を「棚田ばあ」としてスポットライトを当てた作文・フォトコンテストを開催しました。
(3)多面的機能に関する国民の理解の促進等
(日本農業遺産、世界かんがい施設遺産の認定が増加)
世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業システムをFAO(国際連合食糧農業機関)が認定する制度であり、令和2(2020)年度末時点で、我が国では11地域が認定されています。
日本農業遺産は、我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を農林水産大臣が認定する制度であり、令和2(2020)年度には新たに7地域が認定され、認定地域は22地域となりました(図表3-6-7)。

また、世界かんがい施設遺産は、歴史的・社会的・技術的価値を有し、かんがい農業の画期的な発展や食料増産に貢献してきたかんがい施設をICID(国際かんがい排水委員会)が認定する制度で、令和2(2020)年度には我が国で新たに3施設が認定され、認定施設は42施設となりました。
認定された農業遺産や世界かんがい施設遺産を将来にわたって継承していくため、各認定地域や認定施設では、認定を契機として、観光客の誘致活動や教育活動、農産物のブランド化等が行われています。
農林水産省では、農業遺産認定地域における取組の効果をより大きくするため、令和2(2020)年度にプロモーション動画を作成し、首都圏の電車内や全国4駅の構内において紹介したほか、11月には民間事業者が開催するオンラインイベントに出展を行うなど、制度に対する国民の理解と認知度の向上に取り組んでいます。
(多面的機能の普及・啓発と調査研究の推進)
農業が有する国土保全・水源涵養・景観保全等の多面的機能について国民の理解を促進するため、これらの機能を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、令和2(2020)年度は、学校や地方自治体等に約2万8千部配布し普及・啓発に取り組んでいます。また、平成13(2001)年11月の日本学術会議の答申によれば、多面的機能には機能回復リハビリテーションの機能もあることから、令和3(2021)年3月に農業者と非農業者の後期高齢者の医療費について試行的な調査を実施したところ、農業者は非農業者に比べて医療費が1人当たり年間8.6万円少ないことが分かりました(図表3-6-8)。
(「ディスカバー農山漁村の宝」に28地区と4人を選定)
農林水産省と内閣官房は、平成26(2014)年度から、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことで地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」として選定し、農村への国民の理解の促進や優良事例の横展開等に取り組んでいます。第7回目となる令和2(2020)年度は全国の28地区と4人を選定しました(図表3-6-9)。選定を機に更なる地域の活性化や所得向上が期待されます。

(4)関係府省で連携した仕組みづくり
(農山漁村地域づくりホットラインを開設)
農林水産省は、令和2(2020)年12月に、農山漁村の現場で地域づくりに取り組む団体や市町村等を対象に相談を受け付け、取組を後押しするための窓口「農山漁村地域づくりホットライン」を開設しました。
「農山漁村地域づくりホットライン」は、食料・農業・農村基本計画に基づく「しごと」、「くらし」、「活力」の三つの柱からなる農村振興を推進する仕組みの一つとして、地域の実態や要望を直接把握し、関係府省とも連携して課題の解決に取り組んでいます。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883