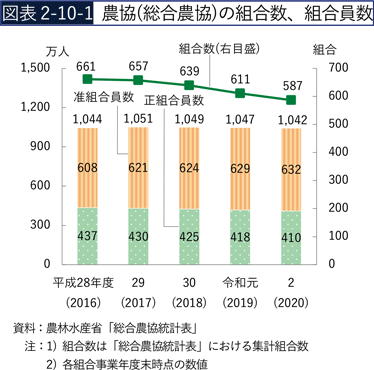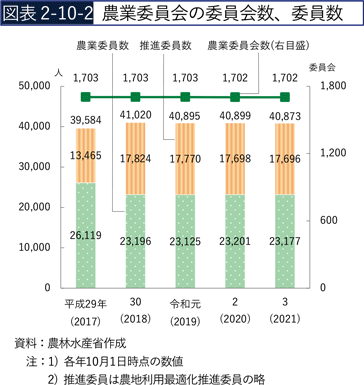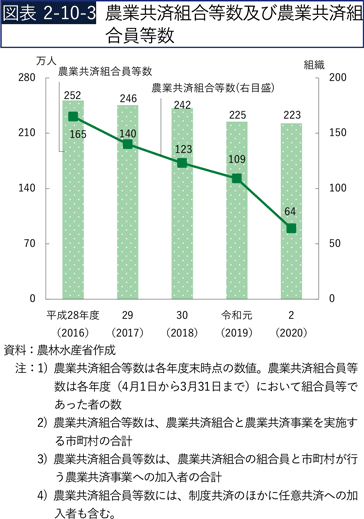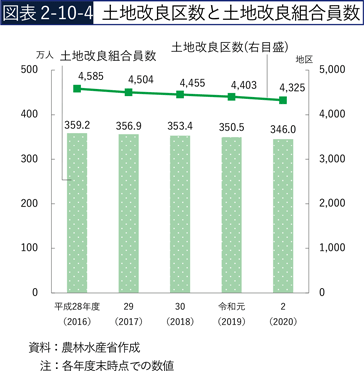第10節 農業を支える農業関連団体

各種農業関連団体については、農業経営の安定、食料の安定供給、農業の多面的機能(*1)の発揮等において重要な役割を果たしていくことが期待されています。
本節では、そのような期待の下での各種農業関連団体の取組の動向について紹介します。
1 用語の解説4を参照
(1)農業協同組合系統組織
(農業者の所得向上に向けた自己改革を実践)
農協は協同組合の一つで、農業協同組合法(以下「農協法」という。)に基づいて設立されています。農業者等の組合員により自主的に設立される相互扶助組織であり、農産物の販売や生産資材の供給、資金の貸付けや貯金の受入れ、共済、医療等の事業を行っています。
農業協同組合系統組織においては、平成28(2016)年に施行された改正農協法(*2)に基づき、農業者の所得向上に向け、農産物の有利販売や生産資材の価格引下げ等に主体的に取り組む自己改革に取り組んできました。また、令和3(2021)年6月に閣議決定した規制改革実施計画においては、それぞれの農協が組合員との対話を通じて自己改革を実践していくサイクルを構築し、これを前提として農林水産省が指導・監督等を行う仕組みを構築する、との方向性が決定されました。
1 正式名称は「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」
(事例)品質と価格の維持により、継続的に黒字を実現(静岡県)
静岡県浜松市(はままつし)の三ヶ日町(みっかびちょう)農業協同組合では、生産販売額全体の約85%を占める「三ヶ日みかん」の生産、販売に力を入れています。冷風貯蔵設備を活用した端境期での出荷や、品種の絞込みによる栽培技術の維持、マッピングシステムの活用による個別園地の管理のほか、平成27(2015)年からは機能性表示食品としての販売を行うこと等により、「三ヶ日みかん」ブランドの品質と価格の維持につなげてきました。こうした取組が功を奏し、同農協では、平成15(2003)年度から10年以上農業関連事業の黒字を実現しています。
令和3(2021)年11月には、AI(*)を搭載した新たなかんきつ選果場が稼働しました。AI画像選別システムによる高精度な選果と高速化により、従来以上に高品質な果実の出荷を実現するとともに、選果場等での労働時間の削減が可能となりました。
用語の解説3(2)を参照
(コラム)厚生連病院が新型コロナウイルス感染症拡大に対応
JAグループは、全国に33ある厚生農業協同組合連合会(以下「厚生連」という。)を通して、病院・診療所等の運営、高齢者福祉といった厚生事業も行っています。全国に105の厚生連病院、61の診療所(令和4(2022)年3月末時点)を運営し、令和2(2020)年以降は、猛威を振るう新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応として、感染者の受入れや、職域・地域におけるワクチン接種を行い、地域医療の基幹施設としての役割を果たしています。
厚生連病院において、新型コロナウイルス感染症の発生当初から令和3(2021)年11月末までに感染者の受入実績のある病院数は80、受入患者の累計は12,270人に上ります。感染者が更に急増した場合に備え、病床の増床、入院受入者数の増加も進めました。
また、感染が急拡大し、医療提供体制が逼迫(ひっぱく)した地域からの医療従事者の派遣要請にも、積極的に対応してきました。令和3(2021)年5~6月には大阪府及び沖縄県に、同年9~10月には東京都に看護師を派遣し、令和4(2022)年1月にも、オミクロン株による感染が広まった沖縄県に派遣するなど、計8厚生連が対応しました。
総合農協(*1)の組合数は減少傾向、組合員数は横ばいで推移しており、令和2(2020)年度の組合数は587組合、組合員数は1,042万人となっています(図表2-10-1)。組合員数の内訳を見ると、農業者である正組合員数は減少傾向ですが、非農業者である准組合員数は増加傾向です。
1 農協法に基づき設立された農協のうち、販売事業、購買事業、信用事業、共済事業等を総合的に行う農協
(2)農業委員会系統組織
(農地利用の最適化に向けて活動の「見える化」等を推進)
農業委員会は、農地法等の法令業務及び農地利用の最適化業務を行う行政委員会で、全国の市町村に設置されています。農業委員は農地の権利移動の許可等を審議し、農地利用最適化推進委員は現場で農地の利用集積や遊休農地(*1)の解消、新規参入の促進等の農地利用の最適化活動を担当しています。
農業委員会が実施する農地利用の最適化活動の内容と成果は、地域の農業者に対して「見える化」することが重要であり、農業委員会系統組織においては、地域内の農地の利用集積、遊休農地の解消等に係る具体的な目標を定め、その目標達成に向けて最適化活動を行う農業委員及び農地利用最適化推進委員が活動内容を記録し、それを基に活動実績と目標達成状況を点検・評価、公表することとしています。
令和3(2021)年における農業委員数は23,177人、推進委員数は17,696人で、合わせて40,873人となっています(図表2-10-2)。
1 用語の解説3(1)を参照
(3)農業共済団体
(1県1組合化等による業務効率化の取組を推進)
農業共済制度は、農業保険法の下、農業共済組合及び農業共済事業を実施する市町村(以下「農業共済組合等」という。)、県単位の農業共済組合連合会、国の3段階で運営されてきました。
近年、農業共済団体においては、業務効率化のため、農業共済組合の合併により県単位の農業共済組合を設立するとともに、農業共済組合連合会の機能を県単位の農業共済組合が担うことにより、農業共済組合と国との2段階で運営できるよう、1県1組合化を推進しています。令和3(2021)年4月1日時点では、前年から4県で1県1組合化が進み、45都府県で1県1組合化が実現しています。残る2道県の農業共済組合等においては、引き続き1県1組合化等による業務の効率化を進めることとしています。
令和2(2020)年度における農業共済組合等数は64組織、農業共済組合員等数は223万人となっています(図表2-10-3)。
(4)土地改良区
(土地改良事業の円滑な実施を更に支援するための改正土地改良法が成立)
土地改良区は、圃場(ほじょう)整備等の土地改良事業を実施するとともに、農業用用排水施設等の土地改良施設の維持・管理等の業務を行っています。
豪雨災害の頻発化・激甚化、耐用年数を超過する土地改良施設の突発事故等による施設の維持管理に係る負担の増大や、土地改良区の技術者不足等の課題によって、土地改良区の運営は厳しさを増しています。小規模な土地改良区では、技術者の雇用や業務の実施が困難な場合もあることから、農林水産省は土地改良事業団体連合会等関係機関と連携して技術的な助言を行うなど、土地改良区が事業を円滑に実施できるよう取り組んでいます。さらに、令和4(2022)年3月に成立した「土地改良法の一部を改正する法律」では、土地改良事業団体連合会への工事委託制度が創設され、土地改良区はこれら制度を活用して事業を円滑に推進することが期待されます。
令和2(2020)年度末時点で土地改良区は4,325地区となっており、近年減少傾向が続いています。土地改良区の組合員数も減少傾向にあり、令和2(2020)年度は前年度と比べて4万5千人減少し、346万人となりました(図表2-10-4)。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883