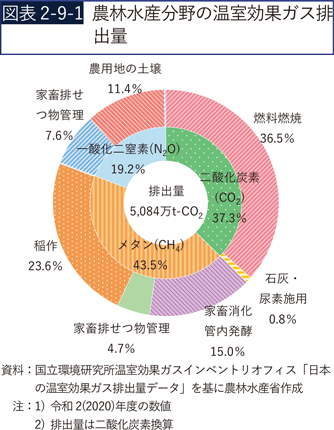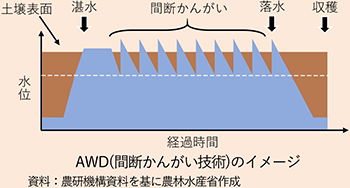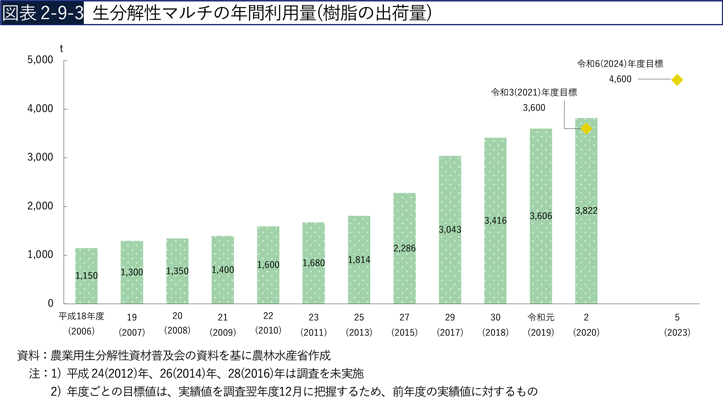第9節 気候変動への対応等の環境政策の推進
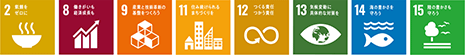
気候変動対策において、我が国は、令和32(2050)年までにカーボンニュートラルの実現を目指しており、あらゆる分野ででき得る限りの取組を進めることとしています。また、生物多様性条約第15回締約国会議(CBD COP15)での議論等を背景に、生物多様性の保全等の環境政策も推進しています。本節では、食料・農業・農村分野における気候変動に対する緩和・適応策の取組や生物多様性の保全に向けた取組等を紹介します。
(1)地球温暖化対策の推進
(2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて)
我が国の温室効果ガス(*1)の総排出量は令和2(2020)年度に11億5,000万t-CO2となっているところ、政府は、令和32(2050)年までに温室効果ガスの総排出量を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの実現に向け、令和3(2021)年4月の米国主催気候サミットで、令和12(2030)年度において温室効果ガス排出量を平成25(2013)年度比で46%削減することを目指し、更に50%の高みに向けて挑戦を続けることを宣言しました。
さらに、令和3(2021)年10月、政府は、令和12(2030)年度の温室効果ガス削減目標等の実現に向け、内閣総理大臣を本部長とする地球温暖化対策推進本部において「日本のNDC(*2)(国が決定する貢献)」を決定するとともに、新たな令和12(2030)年度削減目標の裏付けとなる対策・施策を記載して新目標実現への道筋を描く「地球温暖化対策計画」、令和32(2050)年カーボンニュートラルに向けた基本的考え方等を示した「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定しました。あわせて、気候変動の適応策を示した「気候変動適応計画」を閣議決定しました。
農林水産分野での気候変動に対する緩和・適応策の推進に向け、農林水産省は、「みどりの食料システム戦略(*3)」(以下「みどり戦略」という。)を踏まえ、令和3(2021)年10月に「農林水産省地球温暖化対策計画」と「農林水産省気候変動適応計画」を改定しました。令和12(2030)年度の温室効果ガス削減目標として、平成25(2013)年度の我が国の総排出量に対し、農林水産分野における排出削減対策と吸収源対策により3.5%相当分を削減(排出削減量303万t-CO2、吸収量4,650万t-CO2)することを目指しています。
我が国の農林水産分野における令和2(2020)年度の温室効果ガスの排出量は、前年度から42万t-CO2増加し、5,084万t-CO2となりました(図表2-9-1)。今後、地球温暖化対策計画や、みどり戦略に沿って、更なる温室効果ガスの排出削減に資する新技術の開発・普及を推進していきます。
1 用語の解説3(1)を参照
2 Nationally Determined Contributionの略
(炭素貯留の取組を推進)
温室効果ガスの吸収源対策の一つとして、農林水産省は、改定後の農林水産省地球温暖化対策計画に基づき、堆肥や緑肥等の有機物やバイオ炭(*1)の施用を通じ、農地や草地における炭素貯留の取組を推進しています。具体的には、堆肥の高品質化、広域的な供給に必要なペレット堆肥製造施設等の環境整備、実証的な堆肥の施用による有効性の周知や、堆肥・緑肥等の有機物やバイオ炭について、産地に適した施用技術の検証の支援などを行っています。
1 燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物
(コラム)果樹の剪定枝を利用したバイオ炭の取組を推進
山梨県では、令和2(2020)年4月から、光合成の働きによって多くの炭素が蓄積した果樹園での剪定(せんてい)枝を炭化することで「バイオ炭」として活用し、長期間炭素を土壌中に貯留する取組を推進しています。
簡易な炭化器を活用することで、簡単にバイオ炭づくりができることから、今後、消費者への浸透も図りながら、「環境に優しいくだもの」として山梨の新しいブランドを目指していきます。
(世界的な気候変動対策の推進に向け国際的な枠組みに参加)
令和3(2021)年10月から11月にかけて英国のグラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)においては、パリ協定下の市場メカニズムの実施指針等が採択され、パリ協定の実施指針が完成しました。議長国英国の主導で実施された会合等においては、我が国からみどり戦略を世界に向けて発信しました。
また、COP26においては、二酸化炭素よりも高い温室効果を有するメタンについて、令和12(2030)年までに世界全体の排出量を令和2(2020)年比で30%削減することを目標に、各国で協働するための国際的な枠組みである「グローバル・メタン・プレッジ」が発足し、我が国も参加しています。我が国は、メタン発生の少ないイネの品種開発や、水田の土壌内に存在するメタン生成菌の活動を抑制する中干し技術、牛のげっぷとして排出されるメタンガス削減の研究開発等に強みを持っています。今後も農業分野におけるメタン排出削減に向けた研究開発を推進していきます。
(コラム)農地土壌由来のメタン削減を可能とする水稲栽培技術の開発
農研機構、JIRCAS等の研究グループは、農業分野における温室効果ガス排出削減技術の開発に向け、平成24(2012)年度から東南アジアの国々と連携し、水稲の総合的栽培管理技術の研究に取り組んでいます。
湛水(たんすい)が続く水田では、土壌中の酸素が減少し、温室効果ガスであるメタンの発生が増えることが知られています。そこで研究グループでは、IRRI(国際稲研究所)が開発した節水のための間断かんがい技術AWD(Alternate Wetting and Drying)を応用し、湛水と落水を繰り返すことでメタンの発生を抑制できるのかについて、フィリピン、インドネシア、ベトナム、タイ等の圃場(ほじょう)で検証を行ってきました。また、稲作農家にとっては生産の安定や、そのための土壌保全も重要であることから、AWDによる水管理のみではなく、肥料や有機物の効率的な利用法も研究してきました。
この研究では、水田からのメタン等の温室効果ガスの排出量を30%以上削減し、地球温暖化の緩和に資するとともに、有機物管理等を組み合わせて土壌保全と生産の安定化を実現することを目標としており、令和4(2022)年度までに、そのような総合的栽培管理技術を開発する予定です。この技術は費用・労力が比較的に軽微で、生産性の維持とも両立することから、アジア諸国での普及が期待されています。
(気候変動の影響に適応するための品種・技術の導入が進展)
農業生産は気候変動の影響を受けやすい中で、近年では、気温の上昇による栽培地域の拡大を活用し、熊本県における、うんしゅうみかんよりも温暖な気候を好む中晩柑「しらぬひ」への転換や、青森県におけるももの生産、愛媛県におけるアボカドの生産等、新しい作物の導入が進展しています。
また、水稲における白未熟粒(しろみじゅくりゅう)(*1)や、りんご、ぶどう、トマトの着色・着果不良等、各品目で生育障害や品質低下等の影響が現れていることから、この影響を回避・軽減するための品種や技術の開発、普及も進展しています。
1 胚乳の一部又は全部が白濁した玄米のことで、登熟期の高温によりデンプンの蓄積が阻害されて細胞内に空気の隙間が生じ、これが光を乱反射して白く見える。精米しても白濁はなくならず、米の検査等級の下落や食味の低下の原因となる。
(2)生物多様性の保全と利用の推進
(次期生物多様性国家戦略等を策定し環境と経済の向上を両立)
農林水産業は、人間の生存に必要な食料や生活資材を供給する活動であるとともに、その営みは、人々にとって身近な自然環境を形成し、多様な生物種の生育・生息に重要な役割を果たしています。また、農林水産業と生物多様性との関わりは、農山漁村の文化や景観を形づくり、農山漁村に活力を与え、地域経済の発展や健康的で豊かな生活基盤となっています。
令和3(2021)年10月、中国・昆明(こんめい)でCBD COP15第一部が開催され、ハイレベルセグメントにおいては、生物多様性の世界目標である「ポスト2020生物多様性枠組」の採択に向けて生物多様性の損失を食い止めること等の決意が記載された「昆明宣言」が採択されました。我が国からは日本の取組の説明や国際支援の表明を行いました。令和4(2022)年に中国・昆明で開催が予定されているCBD COP15第二部では、「ポスト2020生物多様性枠組」が採択される予定であり、今後この採択を受け、我が国でも令和4(2022)年度に次期生物多様性国家戦略を策定する予定です。
これに先立ち農林水産省は、「ポスト2020生物多様性枠組」についての議論や、みどり戦略を踏まえ、「農林水産省生物多様性戦略」を見直すため、有識者による検討を行いました。新たな農林水産省生物多様性戦略では、環境と経済の向上の両立を目指していく旨を記載することとしています。
(3)廃プラスチック対策の推進
(農業分野における廃プラスチック対策を推進)
一般社団法人プラスチック循環利用協会(じゅんかんりようきょうかい)の調査によると、令和2(2020)年の我が国全体のプラスチック廃棄量は822万tとなっています。このうち農林水産分野の廃プラスチック排出量は11万tで、我が国全体の総排出量の1.4%を占めています。
農業分野の廃プラスチックには農業用ハウスの被覆資材やマルチ(*1)等が含まれます。被覆資材の耐久性向上や耕地面積の減少等により、その排出量は、平成5(1993)年度をピークに減少傾向にあります。農業分野の廃プラスチックの再生処理の割合は上昇傾向で推移しており、平成30(2018)年度では74.5%となっています(図表2-9-2)。今後も各地域においてブロック協議会や都道府県協議会を中心に、情報や地域課題の共有、法令の周知徹底を図り、この割合を令和8(2026)年度に80%とすることを目標としています。
また、徐々に肥料成分が溶け出す緩効性肥料の一つであるプラスチックを使用した被覆肥料については、使用後に被膜殻(ひまくがら)が圃場から流出することで海洋汚染等の要因となることが指摘されています。このため、肥料メーカー等は、令和4(2022)年1月に「緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の海洋流出防止に向けた取組方針」を公表しました。令和12(2030)年までにプラスチックを使用した被覆肥料に頼らない農業を掲げ、農業者に被膜殻の流出防止対策の徹底や代替となる施肥方法の提案等を進めることとしています。農林水産省においても、生産現場におけるプラスチック被膜殻流出防止等の取組を推進しています。
農業分野においては、農業者、農業者団体、地方公共団体による廃プラスチック対策の排出抑制と適正処理の推進を徹底しており、農業用ハウスでは、耐久性を強化したフィルムの使用を推進しています。また、マルチについては、廃プラスチックの排出量削減の取組として、農林水産省は、従来のポリマルチの利用から、使用後にすき込むことで土壌中の微生物により水や炭酸ガスに分解される生分解性マルチの利用への転換を推進しています。
農業用生分解性資材普及会(のうぎょうようせいぶんかいせいしざいふきゅうかい)の調査によると、生分解性マルチの年間利用量(樹脂の出荷量)は年々増加傾向で推移しており、令和2(2020)年度は3,600tの目標に対し、3,822tとなっています(図表2-9-3)。今後も生分解性マルチへの転換を推進し、令和5(2023)年度の年間利用量を4,600tとすることを目標としています。
1 マルチングの略で、畑の畝をビニールシートやポリエチレンフィルム、わら等で覆うこと。マルチの用途は、地温の調節、土の乾燥防止、雑草の抑制、雨による肥料の流出防止、病害虫の防止等
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883