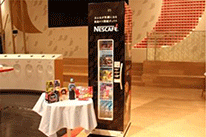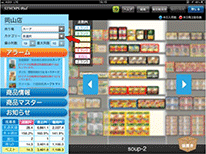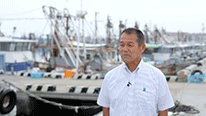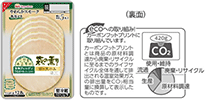第6節 みどりの食料システム戦略の推進

気候変動や生産基盤の脆弱(ぜいじゃく)化等の国内外の課題を背景に、農林水産省は、令和3(2021)年5月に「みどりの食料システム戦略(*1)」(以下「みどり戦略」という。)を策定し、令和32(2050)年までに目指す姿を示しました。本節では、みどり戦略の意義と、調達、生産、加工・流通、消費の各分野での具体的な取組の推進状況を紹介します。
1 トピックス2を参照
(1)みどりの食料システム戦略の意義
(持続可能な食料システムの構築が必要)
我が国の食料システムは、高品質・高付加価値な農林水産物・食品を消費者に提供している一方で、気候変動への対応や生産基盤の脆弱化等の克服すべき課題に直面しています(図表1-6-1)。世界的にもSDGs(*1)が広く浸透し、環境配慮に対する関心が高まってきており、諸外国では環境負荷軽減のための戦略を策定し、国際ルールに反映させようとする動きも出ています。
このような中、将来にわたり食料の安定供給と農林水産業の発展を図るためには、我が国において持続可能な食料システムを構築する必要があります。あわせて、そのシステムをアジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデルとして打ち出し、国際ルールメーキングに参画していくことも必要となっています。
1 用語の解説3(2)を参照
(生産力向上と持続性の両立に向け、中長期的な観点から行動変容とイノベーションを推進)
持続可能な食料システムの構築に向け、生産力向上と持続性の両立を実現するには、調達に始まり、生産、加工・流通、消費に至る食料システムを構成する関係者による行動変容と、これに併せ、官民を挙げたイノベーションを強力に推進することが必要です。そのため、みどり戦略では、令和32(2050)年までに目指す姿と各分野での具体的な取組を示し、中長期的な観点から、それらの取組を進めていくこととしています(図表1-6-2)。

(2)資材・エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷低減の推進
(農山漁村に賦存する地域・未利用資源の活用を推進)
みどり戦略においては、温室効果ガス(*1)削減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化、化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行、令和22(2040)年までの農林業機械・漁船の電化・水素化等技術の確立、我が国の再生可能エネルギーの導入拡大に歩調を合わせた農山漁村における再生可能エネルギーの導入に取り組むこととしています。その一環として、国内の地域資源や未利用資源を一層活用し、循環利用を促進していくこととしています。
肥料原料は資源が世界的に偏在していることから、我が国は、化学肥料原料の大部分を限られた相手国からの輸入に依存しています。貿易統計及び肥料関係団体からの報告によると、りん酸アンモニウムや塩化加里はほぼ全量を、尿素は96%を輸入に依存しています(図表1-6-3)。
そのため、農林水産省は、散布に労力が掛からず、かつ、家畜排せつ物の発生場所から離れた場所でも利用可能なペレット堆肥の活用を推進しています。ペレット堆肥の技術実証を進めるとともに、ペレット堆肥を含む高品質堆肥の生産や広域流通等の推進のために必要な機械・施設整備を支援しています。
また、国内の未利用資源の利用拡大について、例えば、下水汚泥中の窒素やりん等を含む有機物を肥料として利用する取組は、国土交通省が実施した調査によると令和元(2019)年時点で10%となっています。このような未利用資源の肥料利用を促進するため、農林水産省は、原料に汚泥や産業副産物を含む肥料の規格を大括り化するとともに、肥料に使用できる原料の種類や条件について規格を設定し明確化するなどの肥料制度の見直しを行いました。新制度は令和3(2021)年12月から施行されました。
1 用語の解説3(1)を参照
(事例)ペレット堆肥を開発し実用化に向けた取組を推進(新潟県)
新潟県阿賀野市(あがのし)のささかみ農業協同組合では、令和3(2021)年6月に堆肥製造施設「ゆうきセンター」においてペレット堆肥を試験的に開発しました。堆肥を水分調整しながら圧縮、乾燥させることで、直径5mmと小さく割れにくいペレット堆肥の製造に成功しました。また、堆肥散布機から効率良く施肥ができるよう、直径6mmでも製造しています。
また、田畑への堆肥散布は従来、専用の大型散布機や堆肥運搬用の重機等を使っていましたが、ペレット堆肥の場合、トラックで運搬し、農業者自身がトラクターに小型散布機を取り付けて散布することが可能となり、同組合の実施した試験散布では、散布時間を半減することができました。
同農協は、新潟県におけるペレット堆肥散布試験の圃場(ほじょう)の一つにも選定されており、今後、通常の施肥と比較した土壌分析を行う予定です。
(3)イノベーション等による持続的生産体制の構築
(化学農薬や化学肥料の使用量の低減に向けた取組を推進)
みどり戦略においては、環境負荷低減のため、令和32(2050)年までに目指す姿として、化学農薬使用量(リスク換算(*1))を50%低減、化学肥料使用量を30%低減することに取り組むこととしています。
このうち、化学農薬については、令和元(2019)農薬年度(平成30(2018)年10月~令和元(2019)年9月)の使用量は2万3,330(リスク換算値)となっており、低減に向けて化学農薬のみに依存しない病害虫の総合防除の取組の推進、リスクのより低い化学農薬の開発等を進めることとしています。このため、農林水産省は、土壌診断・輪作等の導入による土壌くん蒸剤の低減や、化学農薬を代替する光防除技術、天敵等の導入等、地域の実態に合った総合防除体系の実証の取組を支援しています。
また、化学肥料については、平成28(2016)肥料年度(*2)(平成28(2016)年7月~平成29(2017)年6月)の使用量は90万t(NPK総量・出荷ベース(*3))となっており、低減に向けて家畜排せつ物を始めとした様々な未利用有機性資源の循環利用による化学肥料の代替を進めているほか、ドローンによるセンシングに基づく可変施肥など土壌の性質や作物の生育に応じた施肥の効率化等を進めています。
1 個々の農家段階での単純な使用量ではなく、環境への影響が全国の総量で低減していることを、検証可能な形で示せるように算出した指標。リスク換算は、有効成分ベースの農薬出荷量に、ADI(Acceptable Daily Intake : 許容一日摂取量)を基に設定したリスク換算係数を掛けたものの総和により算出
2 化学肥料の需要実績の算定に用いている窒素質肥料の輸入量について、近年、一部が工業用に仕向けられている可能性があり、業界からの聞き取り等を通じて精査を行っているところ。このため、基準値、現状値共に現在公表されている直近のデータである2016肥料年度の数値(精査前の数値)を用いている。
3 肥料の三大成分である窒素(N)、りん酸(P)、加里(K)の全体での出荷量のこと
(コラム)少ない窒素肥料で高い生産性を示すコムギの開発に成功
国立研究開発法人国際農林水産業研究(こくさいのうりんすいさんぎょうけんきゅう)センター(JIRCAS)は、国際(こくさい)とうもろこし・小麦改良(こむぎかいりょう)センター(CIMMYT)等と共同で、少量の窒素肥料でも高い生産性を示す生物的硝化(*1)抑制(BNI(*2))強化コムギの開発に世界で初めて成功しました。本コムギは、研究において、標準より6割少ない窒素肥料でも、従来品種(育種の親系統)と同等の生産性を示しました。また硝化抑制により窒素肥料の農地での損失を軽減できるため、窒素肥料に起因する水質汚濁物質や温室効果ガス排出の削減が期待できます。
今後、世界第2位のコムギ生産国であるインドにおいて、BNI技術を用いて窒素利用効率に優れたコムギの栽培体系を確立していく予定です。将来的には、世界のコムギ農地、約2億2,500万haからの一酸化二窒素(N2O)排出削減や、窒素肥料の製造過程からの温室効果ガス排出削減等が期待されます。
1 微生物(硝化菌)がアンモニア態窒素(アンモニウム)を硝酸態窒素へと酸化する過程
2 Biological Nitrification Inhibition の略。植物自身が根から物質を分泌し、硝化を抑制する働きのこと
(有機農業の拡大に向けた取組を推進)
みどり戦略においては、令和32(2050)年までに目指す姿として、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%(100万ha)に拡大することに取り組むこととしています。有機農業については、平成30(2018)年度の取組面積は、有機JAS認証を取得しているところと、有機JAS認証を取得していないところを合わせると2万3,700ha、またその耕地面積に占める割合は0.5%となっています(図表1-6-4)。
有機農業の取組の拡大に向け、除草や病害虫の防除等の作業に多くの時間を要するという課題を解決するため、農研機構は、AI(*1)により雑草のみを物理的に除草するロボット等の先進的な技術の開発を進めるとともに、水稲や野菜等の栽培マニュアル等の普及に取り組みました。
また、農林水産省は、都道府県における指導員の育成や各地で農業者等が行う技術講習会の開催の支援を通じて、新たな栽培技術の全国的な普及を進めており、令和3(2021)年12月に持続可能性の高い農法への転換に向けての手引書を作成・公表しました。また、令和4(2022)年1月には、みどり戦略の実現に向けて、栽培暦の見直し等、生産現場でより持続性の高い農法への転換に向けた検討に活用していただくことを目的に、現場への普及が期待される技術を「みどりの食料システム戦略」技術カタログとして取りまとめ、公表しました。さらに、複数の病害に抵抗性を有する品種の育成やAIによる病害虫発生予察の実施等、様々な次世代有機農業技術の確立に取り組んでいます。
このほか、化学農薬・化学肥料を原則5割以上低減する取組と併せて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に対しては、環境保全型農業直接支払制度による支援を行っており、令和2(2020)年度の支援面積は、前年度比で約1千ha増加して約8万1千haとなりました。
これらの取組を通じ、令和12(2030)年度における有機農業の取組面積を6万3千haとすることを目標としています。

「みどりの食料システム戦略」技術カタログ
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/
seisaku/midori/catalog.html
1 用語の解説3(2)を参照
(事例)農機メーカーと連携して有機米を産地化し学校給食へ活用(千葉県)
千葉県木更津市(きさらづし)は、令和元(2019)年度から有機米の産地化に取り組んでいます。
令和3(2021)年3月には、水田での作業改善の観点から、農機メーカーの井関農機(いせきのうき)株式会社と「先端技術を活用した農業と有機農業の推進に関する連携協定」を結びました。有機農業の課題となる雑草を、水位センサーによる水管理や、条間に加え株間も除草可能な新型の水田除草機で抑制し、収量を向上させることが狙いです。
令和3(2021)年度は、学校給食に提供することを目的に約15haの水田を13人の農業者で栽培し、収穫された米のうち約50tを、令和3(2021)年11月から令和4(2022)年2月の間に市内の公立小中学校30校の学校給食に提供しました。有機米を提供した学校給食では、児童・生徒の残食率が従来の米を使用した給食より低減された学校もありました。
同市は、今後、有機米を学校給食へ安定供給することを目標としています。そのためには玄米ベースで年間147t(35ha相当)が必要となっていることから、毎年5haずつ栽培面積を増やし、令和8(2026)年に達成する計画を立てて取り組んでいます。
(4)ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立
(食品産業分野の労働生産性の向上に資する取組を推進)
みどり戦略においては、食品製造業の労働生産性を向上することに取り組むこととしています。
令和2(2020)年度における食品製造業の労働生産性は、目標値が540万1千円/人に対し、実績値は483万6千円/人となっています(図表1-6-5)。農林水産省は、ロボット、AI、IoT(*1)等の先端技術を活用した自動化・リモート化による食品産業の労働生産性の向上を推進しており、令和3(2021)年度では実際の製造等の現場における先端技術のモデル実証や、その成果の横展開を図るための情報発信の取組を支援しています。これらの取組を通じて、令和11(2029)年度までに669万4千円/人にすることを目標としています。
1 用語の解説3(2)を参照
(食品産業界全体の取組を支援することにより食品ロス発生抑制を推進)
みどり戦略においては、令和12(2030)年度までに事業系食品ロス量を平成12(2000)年度比で半減することに取り組むこととしています。
我が国の食品ロスの発生量は、近年減少傾向にあり、令和元(2019)年度においては、前年度より30万t減少し、年間570万tと推計されます(図表1-6-6)。食品ロスの発生量を場所別に見ると、一般家庭における発生(家庭系食品ロス)は261万tとなっています。また、食品産業における発生(事業系食品ロス)は309万tで、そのうち食品製造業128万t、食品卸売業14万t、食品小売業64万t、外食産業103万tとなっています。
食品ロスを更に削減するため、農林水産省は令和3(2021)年10月30日の「全国一斉商慣習見直しの日(*1)」に、食品小売事業者が賞味期間の3分の1を経過した商品の納品を受け付けない「3分の1ルール」の緩和や、食品製造事業者における賞味期限表示の大括り化(年月表示、日まとめ表示)の取組を呼び掛けました。その結果、同年10月時点で3分の1ルールの緩和に取り組む食品小売事業者は、前年同月と比べて44事業者増の186事業者、賞味期限表示の大括り化に取り組む食品製造事業者は67事業者増の223事業者となりました。
このほか、農林水産省は、食品製造事業者等による出荷量、気象等のデータやAIを活用した需給予測システム等の構築を推進しています。
また、国の災害用備蓄食品について、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から有効に活用するため、更新により災害用備蓄食品の役割を終えたものについて、原則として、フードバンク(*2)団体等への提供に取り組むこととしました。農林水産省が「国の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト」を設け、各府省庁の情報を取りまとめて公表を行っています。
1 令和元(2019)年10月に施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」において、10月が「食品ロス削減月間」、10月30日が「食品ロス削減の日」と定められている。
2 用語の解説3(1)を参照
(事例)無人販売機で食品ロスを削減
ネスレ日本(にっぽん)株式会社とみなとく株式会社は連携して、令和3(2021)年6月から、食品ロス削減を目的とした無人販売機「みんなが笑顔になる食品ロス削減ボックス」の運用を東京など全国5か所で開始しました。
飲食が可能でありながら納品期限を超過したことで出荷先が限定され、通常の流通ルートでの販売が困難になっている商品を一般の小売価格より低価格で消費者に販売するチャネルを構築することにより、食品ロス削減に取り組んでいます。各設置場所で想定を上回る売行きとなっており、一度購入した人のリピート購入が多くなっています。
この取組を通して食品ロスを削減し、コーヒー豆やカカオ豆等の原材料を可能な限り無駄にせず、持続可能な形で消費者に商品を届ける仕組みを作ることを目指しています。
(事例)AIによる自動発注や在庫管理等により食品ロスを削減(大阪府)
大阪府大阪市(おおさかし)の株式会社シノプスは、「世界中の無駄を10%削減する」ことの達成のために、同社の流通業向けAIサービスを活用した食品ロスの削減に取り組んでいます。
同社の需要予測を中心としたクラウド型AIサービスは、日配食品のほかに総菜やパン等、それぞれに特化した需要予測・自動発注を行うことが可能であり、令和3(2021)年12月時点で100社、5千以上の小売店舗等に導入されています。
同社のシステムでは、AIが天候や特売の有無による来店客数の変化や、過去の販売実績を学習し、商品ごとの売行きや値引き、欠品を加味し、売上げ・粗利を最大化する数量を自動発注します。同システムにより、食品ロスが約2割削減した店舗の事例も見られました。
同社は、食品分野に強みを持つ総合商社と提携し、小売業の需要予測データを卸売業者や食品メーカーに共有するプラットフォームを構築することを目指しています。これにより、川下から川上への情報共有を図り、サプライチェーン全体の無駄削減・物流DX(*)を目指すデマンド・チェーン・マネジメントの構築を目指しています。
用語の解説3(2)を参照
(製造・流通・販売部門における効率的な食品流通体系の構築を推進)
みどり戦略においては、令和12(2030)年度までに飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合を10%に縮減することに取り組むこととしています。
令和2(2020)年における飲食料品卸売業における売上高に占める経費の割合は、11.5%となっています。農林水産省は、食品流通事業者による、デジタル化・データ連携による業務の効率化や輸送コストの低減、コールドチェーンの整備、食料品アクセスの確保等、効率的なサプライチェーン・モデルを構築し、食品流通の合理化・高度化を推進しています。
特に、青果物流通では、遠隔産地からの長距離輸送や人力によるトラックへの青果物の積み下ろし作業が非効率であるため、共同物流拠点施設の整備や集荷場の整備・集約等による共同輸配送、船舶・鉄道輸送へのモーダルシフト等を支援しており、農産物の流通の効率化を推進しています。
(持続可能な輸入原材料調達の実現に向けた取組を推進)
みどり戦略においては、令和12(2030)年度までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現に取り組むこととしています。
海外では、小売企業等が商品を納入する企業に対して持続可能な原材料調達を求める動きが広がっていることを受け、民間団体や政府による調達の認証システムが構築されつつあります。こうした国際的な動きに対応するため、農林水産省は、原料生産国の生産の現状や国際的な認証制度の動向、食品業界の取組実態や課題等について調査・分析を進めるとともに、現地での安定供給体制の構築に対する支援を行っています。
(食品産業におけるESG投資の引き込みにつながる情報開示等を推進)
みどり戦略の下では、国際的な動向を踏まえた環境配慮経営の推進によるESG(*1)投資の引き込みと持続可能性の向上や環境保全に関するESG取組の促進を図っていくこととしています。
食品産業において持続可能な原材料調達や食品ロス削減への対応が急務となっている中、環境、人権への関心が世界的に高まっています。このような中で、機関投資家等は既に、ESGに積極的に取り組む企業に対する投資を優先しています。今後、日本の食品産業が持続的な発展を図っていくためには、情報開示等を進め、ESG投資による資金を食品企業に円滑に引き込んでいくことが不可欠です。
このような状況も踏まえ、農林水産省では、令和3(2021)年11月からESGへの先進的な取組を行う食品企業と勉強会を開催し、ESGに係る具体的な取組や取組上の課題等を企業間で共有・集約するとともに、Webサイトで公表しました。また、食品企業におけるESGへの理解の促進等を図るため、ESGに係る国内外の最新動向や、ESG投資の進展がもたらす食品企業への影響分析等の調査を実施しました。
1 環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)
(生産から消費までのデータの相互利用を可能にするシステムの構築等を推進)
みどり戦略の下では、生産から加工・流通、販売、消費までのデータの相互利用を可能とするシステムの構築等を推進しています。
内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」においては、生産から消費に至るまでのデータ連携が可能なスマートフードチェーンの研究開発が行われています。出荷・流通・販売の全ての過程において記録された時間と温度を消費者が確認できることに加え、鮮度が保証されることで農産物の高付加価値化につながる「フードチェーン情報公表JAS」をレタスのほか、メロンやブドウを対象に、令和4(2022)年度中の策定を目指して検討及び実証を行っています。
今後、スマートフードチェーンの取組を進めることで、青果物輸送での共同物流による環境負荷の低減や、需給予測による食品ロス削減も期待できます。
(5)環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進
(サプライチェーン全体における行動変容を促進)
みどり戦略の実現に向け、農林水産省は、ニッポンフードシフトに加え、関係省庁や、企業・団体が一体となって令和2(2020)年6月に立ち上げた、持続可能な生産消費を促進する「あふの環(わ)2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」(以下「あふの環プロジェクト」という。)を推進しており、本取組には令和4(2022)年3月末時点で、農業者や、食品製造事業者等の150社・団体が参画しています。
あふの環プロジェクトでは、勉強会や交流会を開催するほか、令和3(2021)年9月、「サステナウィーク」として食と農林水産業のサステナビリティについて認知を高めるため、参加メンバーが一斉に情報発信を実施しました。
(コラム)サステナアワード2021農林水産大臣賞は海底耕耘の取組
「あふの環プロジェクト」では、食と農林水産業の持続可能な取組を伝える動画を表彰する「サステナアワード2021 伝えたい日本の“サステナブル”」を開催し、令和4(2022)年2月に表彰式を行いました。
令和元(2019)年度に続き2度目となる今回は、農林水産大臣賞を新設し、全国各地から応募された92作品の中から、持続可能な海を目指す取組を表現した兵庫県の明石浦(あかしうら)漁業協同組合の「「豊かな海へ」海底耕耘(こううん)プロジェクト」が選ばれました。この取組は、海に投入した鉄製器具「耕耘桁(けた)」をロープで船に結んで引っ張り、海底を掘り起こすことで、堆積していた窒素やりんなどを栄養塩として海中に放出し、漁業環境を改善して豊かな海を目指すものです。
また、消費者庁長官賞は長崎県波佐見町(はさみちょう)の「半農半陶の里 波佐見の地域内循環の取組」が選ばれました。この取組は、陶磁器の作陶過程で廃棄された石こう型を肥料として再利用し、休耕田や畑に散布して農作物の栽培に活用したものです。
令和4(2022)年3月に東京で開催されたシンポジウムでは、上記受賞者が取組内容について講演しました。今後、その他の受賞作品も含め、在外公館で行われるレセプション等を通じて、我が国のサステナブルな取組として国内外で発信していくこととしています。
持続可能な食料システムを構築するためには、フードサプライチェーン全体で脱炭素化を推進するとともに、その取組を可視化して持続可能な消費活動を促すことが必要です。
農林水産省は、令和2(2020)年にフードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方について検討を開始し、令和3(2021)年6月、TCFD(*1)(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言の解説や、農産物、畜産物等、業種別の気候変動による重要な課題、事業インパクト等を例示した食品事業者向けの手引書を公表しました。
また、農業者等の脱炭素の努力・工夫に関する消費者の理解や脱炭素に貢献する製品への購買意欲の向上等、消費行動の変容を促すために、商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの全体を通して排出される温室効果ガスをCO2換算で算定し表示するカーボンフットプリントなどの消費者に分かりやすい伝達方法等について検討し、農産物の温室効果ガス排出削減効果を「見える化」する簡易算定ツール等の作成を進め、フードサプライチェーンを通じた脱炭素化の実践とその可視化の取組を促すこととしています。
1 Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。効率的な気候関連財務情報開示を企業等に促す、民間主導のタスクフォース。各国の中央銀行総裁及び財務大臣から成るFSB(金融安定理事会)の作業部会に位置付けられる。
(事例)生産者自らが消費者に対して環境に配慮した生産活動を推進(北海道)
北海道新篠津村(しんしのつむら)で農業を営む有限会社大塚(おおつか)ファームの大塚裕樹(おおつかひろき)さんは、平成9(1997)年から有機農業に取り組んでいます。17ha(うち有機JAS認証9.8ha)の農地にミニトマトやだいこん、ハーブ等30種類以上の有機野菜を生産するとともに、干し芋やドレッシングの開発や販売にも力を入れています。
大塚さんは、生産者の「取組の見える農業」を意識し、子供の農業体験や大学生の研修受入れを行うほか、有機野菜を使った料理を提供するイベントを開催する等、消費者と一体となって有機農業の良さを伝える活動を積極的に実践してきました。
平成21(2009)年からは、消費者との契約栽培に取り組むことで、生産した有機農産物の安定的な販路を確立しました。これにより、市場には出回らない規格外の有機野菜も、消費者のニーズに対応し有効活用することが可能になりました。
大塚さんは今後も、生産規模の拡大や新たな加工品の開発・販売等により売上増を目指し、自身が60歳になる令和15(2033)年には、経営を3人の後継者にバトンタッチする予定です。
(第4次食育推進基本計画の目標達成に向け食育活動を推進)
みどり戦略では、環境にやさしい持続可能な食育の推進に取り組むこととなっています。食育については、令和3(2021)年度からおおむね5年間を計画期間とする「第4次食育推進基本計画」で、基本的な方針や目標値を掲げるとともに、食育の総合的な促進に関する事項として取り組むべき施策等が定められています。
目標の達成に向けて、農林水産省は、農林漁業体験機会の提供、「日本型食生活」の実践を含む食文化の保護・継承等について、地域の関係者が連携し創意工夫して取り組む食育活動を推進しています。また、農林水産省、岩手県と第16回食育推進全国大会岩手県実行委員会は、令和3(2021)年6月に、「第16回食育推進全国大会inいわて」をオンラインで開催しました。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883