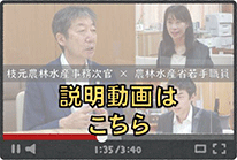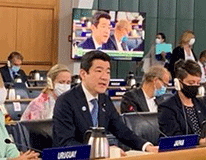トピックス2 みどりの食料システム戦略に基づく取組が本格始動
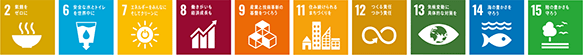
我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害、地球温暖化、農業者の減少等の生産基盤の脆弱(ぜいじゃく)化、地域コミュニティの衰退、生産・消費の変化等の、持続可能性に関する政策課題に直面しています。また、諸外国ではSDGs(持続可能な開発目標)(*1)や環境を重視する動きが加速しており、あらゆる産業に浸透しつつあることから、我が国の食料・農林水産業においても的確に対応していく必要があります。
これらを踏まえ、農林水産省は令和3(2021)年5月に「みどりの食料システム戦略」(以下「みどり戦略」という。)を策定しました。以下では、みどり戦略の目指す姿と実現に向けた取組を紹介します。
1 用語の解説3(2)を参照
(みどりの食料システム戦略を策定)
我が国の食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、農林水産省は、生産者、関係団体、食品事業者等幅広い関係者との意見交換等を経て、令和3(2021)年5月にみどり戦略を策定しました。
みどり戦略は、令和32(2050)年までに目指す姿として、農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現、化学農薬使用量(リスク換算)の50%低減、化学肥料使用量の30%低減、耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%に拡大等、14の数値目標(KPI(*1))を掲げました。その実現に向けて、調達から生産、加工・流通、消費までの各段階での課題の解決に向けた行動変容、既存技術の普及、革新的な技術・生産体系の開発と社会実装を、時間軸をもって進めていくことが重要です(図表トピ2-1)。
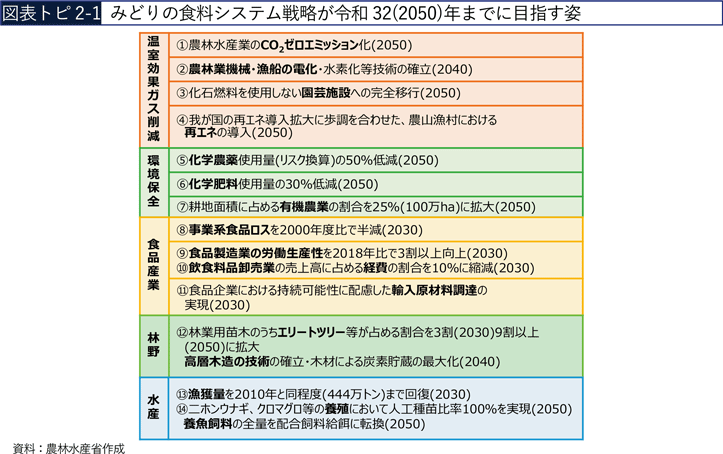
1 Key Performance Indicatorの略であり、「重要業績評価指標」。組織やチームで設定した最終的な目標を達成する上で、過程を計測・評価するための個別の指標・数値目標のこと
(多様な関係者との意見交換の実施と国連食料システムサミットでの発信)
みどり戦略は、食料システムを構築する関係者それぞれの理解と協働の上で実施していく必要があることから、取組の分野ごとの解説動画を作成して公開するほか、全国各地で意見交換を実施し、様々な機会を捉えてみどり戦略の目指す姿、取組方向等を発信しました。
また、欧米と気象条件や生産構造が異なるアジアモンスーン地域の特性に応じた持続可能な食料システムを提唱していくため、令和3(2021)年7月にイタリアのローマで開催された国連食料システム・プレサミットにおいて、みどり戦略を紹介するとともに、同年9月にオンラインで開催され150か国以上の首脳級・閣僚が参加した国連食料システムサミットにおいて、生産力の向上と持続性の両立、各国・地域の気候風土、食文化を踏まえたアプローチの重要性等について提唱し、みどり戦略を通じて持続可能な食料システムの構築を進めていく旨を発信しました。
(みどりの食料システム戦略の実現に向けて)
みどり戦略の実現に向けて、各分野の令和32(2050)年までの技術の工程表、更には現在から直近5年程度までの技術の工程表を作成しており、毎年取組の進捗管理をしていくこととしています。また、食の生産・加工・流通・消費に関わる幅広い関係者が一堂に会する場として、令和3(2021)年12月に「持続可能な食料生産・消費のための官民円卓会議」を設置しました。生産者や食品関連産業、消費者等の関係者間の対話を通じて、情報や認識を共有し、具体的な行動にコミットしていきます。
さらに、令和4(2022)年2月に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案(みどりの食料システム法案)」を国会に提出しました。また、戦略を強力に推進するため、みどりの食料システム戦略推進総合対策等の関係予算を措置しており、これらの取組により、みどり戦略の実現に資する研究開発、地域ぐるみでの環境負荷低減の取組を促進することを目指していきます。

みどりの食料システム戦略トップページ
URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883