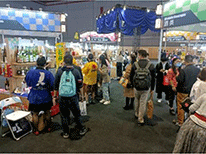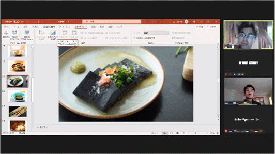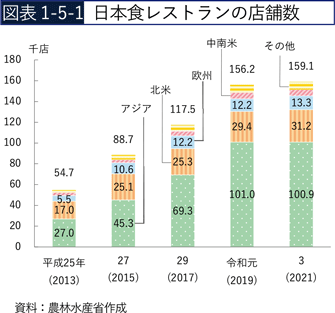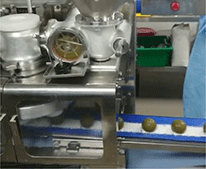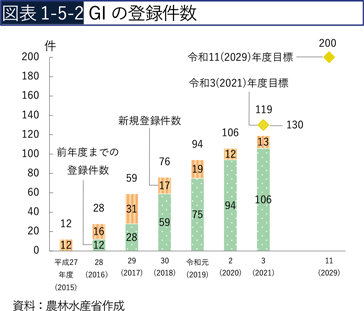第5節 グローバルマーケットの戦略的な開拓
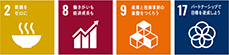
新型コロナウイルス感染症の感染が世界的に拡大する中、我が国の農林水産物・食品の輸出額は増加しており、令和3(2021)年には過去最高額を更新し、初めて1兆円を突破しました。人口減少や高齢化により農林水産物・食品の国内消費の減少が見込まれる中で、農業・農村の持続性を確保し、農業の生産基盤を維持していくためには、輸出を拡大していくことが重要です。
本節では、政府一体となっての輸出環境の整備、輸出に向けた海外への商流構築やオールジャパンのプロモーション、食産業の海外展開の促進、知的財産の保護・活用について紹介します。
(1)農林水産物・食品の輸出促進に向けた環境の整備
(輸出の関連施策を政府一体となって実施)
農林水産物・食品の輸出に関しては、マーケットインによる輸出への転換のための海外現地における情報収集や売り込み、輸入規制等に係る政府間協議、食品安全管理、知的財産管理、流通・物流整備、研究開発等、様々な関連分野において政府による環境整備が不可欠です。海外でニーズがあるにもかかわらず、我が国からの輸入が規制されている、海外の規制に対応する国内の加工施設が少ないなどの理由により輸出できない産品は、依然として多くあります。
このような課題に対応するため、農林水産物・食品輸出本部を政府全体の司令塔組織として、輸出関連施策を政府一体となって実施することとしています。
(事例)輸出拠点として成田市公設地方卸売市場を開場(千葉県)
千葉県成田市(なりたし)は、令和4(2022)年1月に成田市公設地方卸売市場(なりたしこうせつちほうおろしうりしじょう)(以下「成田市場(なりたしじょう)」という。)を開場しました。
成田市場は敷地面積が9.3haで成田国際空港(なりたこくさいくうこう)に隣接し、青果棟、水産棟のほか、各輸出証明書の交付、検疫等の輸出手続を市場内で完結できる高機能物流棟を有しています。輸出手続のワンストップ化により、輸出手続を短縮することが可能となりました。
今後は、海外からの訪日外国人旅行者等に向けて我が国の農水産物や食文化を発信する集客施設を整備し、輸出拠点と卸売市場の役割を両立させていきます。
(改正投資円滑化法が施行)
農林漁業や食品産業の分野では、輸出のための生産基盤構築・施設整備や、スマート農林水産業による生産性向上等の新たな動きに対応するための資金需要が生じています。
このことを踏まえ、農業法人だけでなくフードバリューチェーンに携わる全ての事業者を投資対象にすること等を内容とする「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」が令和3(2021)年8月に施行されました。農林漁業の生産現場から輸出に関するものも含め、フードバリューチェーン全体への資金供給を促進するための措置を講じることにより、農林漁業や食品産業の更なる成長発展を図ることとしています。
(マーケットインの発想に基づく輸出産地・事業者の育成・展開)
農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づき、農林水産省は、輸出先国のニーズや規制に対応した輸出産地の育成・展開を図るため、主として輸出向けの生産を行う輸出産地・事業者をリスト化しています。リスト化された輸出産地・事業者の数は、令和4(2022)年3月時点で1,287産地・事業者になります。リスト化された輸出産地・事業者をサポートするため、地方農政局等に輸出の専門家を「輸出産地サポーター」として配置し、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」に基づく輸出事業計画の策定と実行を支援しています。
(2)海外への商流構築等と食産業の海外展開の促進
ア 海外への商流構築、プロモーションの促進
(GFPを活用し輸出を支援)
GFP(*1)のWebサイトを通じて会員登録すると、専門家による無料の輸出診断や輸出商社の紹介、登録者同士の交流イベントへの参加等のサービスを受けることができます。登録者数は令和3(2021)年度末時点で6,105件となっており、前年度から1,533件増加しています。このうち輸出診断の対象者である農林水産物・食品事業者は3,448件となっており、農林水産省、独立行政法人日本貿易振興機構(にほんぼうえきしんこうきこう)(JETRO)、輸出の専門家等とともに、令和3(2021)年度においては、227件に輸出診断を行いました。また、輸出に取り組む商社や事業者を育成するためにセミナーやマッチングイベント、輸出相談会を行いました。

GFPコミュニティサイト
URL:https://www.gfp1.maff.go.jp/(外部リンク)

GFP 農林水産物・食品輸出プロジェクト
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/
export/gfp/gfptop.html
1 Global Farmers/Fishermen/Foresters /Food Manufacturers Project の略称
(事例)GFPの会員登録をきっかけに輸出の取組を開始(熊本県)
熊本県玉名市(たまなし)にある株式会社レッドアップは、昭和22(1947)年からトマトの栽培を開始し、現在はビニールハウス40棟でトマトとミニトマトを生産しています。
平成30(2018)年9月にGFPに会員登録し、GFPの輸出診断を活用して輸出先国や認証に関するアドバイス、商社の紹介を受け、輸出に取り組み始めました。
JETRO担当者からのサポートもあり、令和3(2021)年3月から香港の高級スーパー向けにミニトマトの輸出をすることができました。近年は、他の野菜や加工品の引き合いがあり、周辺の生産者の商材を取りまとめて輸出する体制を整備しています。
今後は、輸出量の更なる拡大と海外販路の開拓、加工品の内製化を目指しています。
(JETRO・JFOODOによる海外での販路開拓)
JETROは、国内外の商談会の開催、海外見本市への出展、セミナー開催、専門家による相談対応等により、海外販路の開拓・拡大を目指す事業者をオンラインを活用しつつ支援しました。
また、日本食品海外(にほんしょくひんかいがい)プロモーションセンター(JFOODO)は、牛肉、水産物(ブリ・ハマチ、ホタテ、タイ)、茶、米粉及び米粉製品、日本酒等について、市場分析に基づいて国・地域を設定し、売り込むべきメッセージを明確にした重点的・戦略的なプロモーションを実施したほか、品目別団体と連携したオールジャパンでのプロモーションを実施しました。
(海外において日本食・日本産食材が普及)
海外における日本食レストランの数については、令和3(2021)年は約15万9千店と、平成25(2013)年の3倍近くに増加しており、近年、海外での日本食・食文化への関心が高まっていることがうかがえます(図表1-5-1)。
農林水産省は、平成28(2016)年度から、日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店を民間が主体となって「日本産食材サポーター店」として認定する制度を創設し、日本産食材の主要な輸出拠点とすることとしています。令和3(2021)年度末時点で、前年度に比べて2,176店増加の8,245店が認定されており、JETROでは、世界各地の日本産食材サポーター店等と連携して、日本産食材等の魅力を訴求するプロモーションを実施しています。

海外における日本産食材
サポーター店認定制度
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/
syokubun/suppo.html
(訪日外国人旅行者の日本滞在時の食に関する体験を推進)
農林水産省が平成30(2018)年から実施している「食かけるプロジェクト」では、食と芸術や歴史等、異分野の活動を掛け合わせた体験を通じて、訪日外国人旅行者の日本食への関心を高めるとともに、帰国後も我が国の食を再体験できる環境の整備を推進しています。本プロジェクトの一環として、食と異分野を掛け合わせた食体験を募集・表彰する「食かけるプライズ」を実施し、令和3(2021)年9月に大賞等15件を決定しました。
イ 食産業の海外展開の促進
(輸出を後押しする食産業の海外展開を支援)
農林水産物・食品の輸出のみならず、輸出を後押しする我が国農林水産・食品事業者の戦略的な海外展開を通じて広く海外需要を獲得していくことは、国内生産者の販路や稼ぎの機会を増やしていくことにつながります。このため、農林水産省では、海外展開に際し注意すべきポイントや代表的な契約ひな形を取りまとめた海外展開ガイドラインを作成するとともに、RCEP協定、ハラール・コーシャ等、農林水産・食品事業者の関心に沿った海外展開に関するセミナーを開催しました。
(事例)製造機械等の技術も含めたフードバリューチェーン全体での海外展開
ふぁん・じゃぱん株式会社は、マレーシアを拠点に同国内の工場で同国のハラール認証(JAKIM認証)を取得した菓子類を製造、小売店への卸売販売等を行っています。近年では、大福を始めとした和菓子も製造・販売しており、マレーシアでも人気を博しています。
大福を大量生産するためには、あんを餅で包むための機械(包あん機)が必要となりますが、包あん機は我が国のメーカーが世界シェアの大部分を占めており、同社でも、マレーシアで我が国のメーカーの機械を使用して大福を製造しています。また、大福の原料として我が国で製造し、同国に輸出した抹茶を使用しています。
このように、農林水産物・食品の輸出を更に拡大していくためには、製造機械等の技術も含めたフードバリューチェーン全体で海外展開を考えることが重要です。
(3)知的財産の保護・活用
(GI保護制度の登録産品は119産品となり着実に増加)
地域ならではの特徴的な産品の名称を知的財産として保護する仕組みである地理的表示(GI)保護制度については、GIの国内登録数を令和11(2029)年度までに200産品にする目標を掲げているところ、令和3(2021)年度は、新たに13産品が登録されました。これまでに登録された産品は、同年度末時点で41都道府県と2か国の計119産品となりました(図表1-5-2)。
このほか、日EU・EPA(*1)により、日本側GI 95産品、EU側GI 106産品が相互に保護され、日英EPAにより、日本側GI 47産品、英国側GI 3産品が相互に保護されています。
1 用語の解説3(2)を参照
(改正種苗法の施行により植物新品種の海外流出を防止)
近年、我が国の登録品種(*1)が海外に流出する事例が見られたことも踏まえ、植物品種の育成者権の保護を強化し、新品種の開発を促進するために令和3(2021)年4月に施行された改正種苗法(*2)により、登録品種のうち、国立研究開発法人農業(のうぎょう)・食品産業技術総合研究機構(しょくひんさんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうきこう)(以下「農研機構」という。)や都道府県等が開発した品種約3,800品種について海外への持ち出しが制限されることとなりました。
また、令和4(2022)年4月からは、登録品種の増殖は農業者による自家増殖も含め育成者権者の許諾が必要となり、無断増殖等が把握しやすくなるとともに、育成者権侵害に対しての立証を容易にする措置が講じられることとなっています。
植物の新品種は、我が国農業の今後の発展を支える重要な要素となっている中で、これらの措置によって、育成者権者による登録品種の管理の徹底や海外流出の防止を図り、新品種の開発や、それを活用した輸出を促進することとしています。
1 種苗法に基づき品種登録を受けている品種
2 正式名称は「種苗法の一部を改正する法律」
(和牛遺伝資源の適正な流通・利用を確保)
和牛遺伝資源(*1)の適正な流通・利用を確保し、知的財産としての価値の保護を図っていくために令和2(2020)年10月に施行された改正家畜改良増殖法と家畜遺伝資源法(*2)に基づき、和牛遺伝資源の生産事業者において、その遺伝資源の譲渡先との間で、利用者の範囲等について制限を付す契約を締結するなどの取組が進展しています。
和牛は関係者が長い年月をかけて改良してきた我が国固有の貴重な財産であり、その遺伝資源は我が国畜産業における競争力の源泉の一つとなっている中で、引き続き国内生産基盤の強化を図り、和牛肉の輸出拡大につなげていくこととしています。
1 用語の解説3(1)を参照
2 正式名称は「家畜改良増殖法の一部を改正する法律」と「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」
(事例)GI登録の効果
GI制度は、登録により模倣品が排除されるほか、産品の認知度向上に伴う輸出を含む取引の増大や地域の担い手の増加等の効果が現れています。また、GI登録を機に、生産者団体が自ら産品の価値を再認識することで、品質管理の重要性を認識し、より良い産品を生産しようとする意欲が高まるといった効果も現れています。
平成28(2016)年にGI登録された長野県の市田柿(いちだがき)は、地域発祥の渋柿品種「市田柿」を用いた糖度が高く、あめ色の果肉と表面の白い粉が特徴の干し柿です。令和2(2020)年度の輸出額は、平成28(2016)年度に比べ2.2倍の1億2,500万円となりました。
また、福井県の吉川(よしかわ)ナスは、光沢のある黒紫色をした直径10cmほどの大きさの肉質が緻密な丸ナスです。栽培農家が途絶えていましたが、有志8人が研究会を立ち上げ、平成28(2016)年のGI登録を機に生産者が増加し、令和3(2021)年度末時点で21人の生産者が栽培しています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883