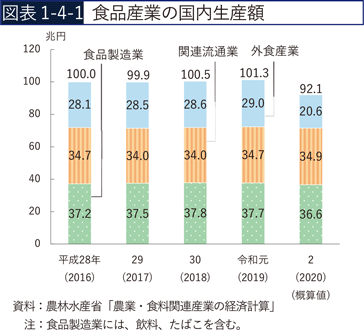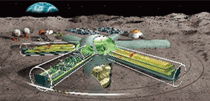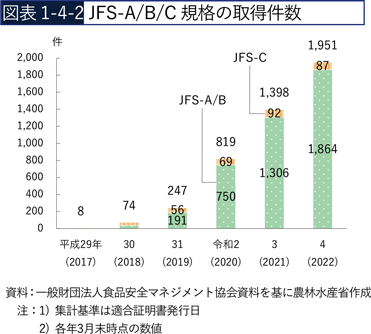第4節 新たな価値の創出による需要の開拓
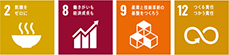
食品産業は、農業と消費者の間に位置し、食料の生産から消費までの各段階において、食品の品質と安全性を保ちつつ安定的かつ効率的に供給するとともに、消費者ニーズを生産者に伝達する役割を担っています。また、食品ロス削減等環境問題への対応にも重要な役割を果たしています。本節では、これらに係る食品産業の動向等について紹介します。
(1)食品産業の競争力の強化
ア 食品産業の動向
(食品産業の国内生産額は92.1兆円)
食品産業の国内生産額は、近年増加傾向で推移していましたが、令和2(2020)年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外食産業が大きな影響を受けたことから、前年と比べ9兆2千億円減少し、92兆1千億円となりました(図表1-4-1)。食品製造業では清涼飲料や酒類の工場出荷額が減少したこと等から前年と比べ2.8%減少の36兆6千億円となり、関連流通業はほぼ前年並の34兆9千億円となりました。また、全経済活動に占める食品産業の割合は前年と比べ0.3ポイント減少し、9.4%となりました。
(適切な価格転嫁を行うためのガイドラインを策定し取引環境を整備)
原油価格の上昇と為替相場における円安の進展があいまって、我が国が輸入に依存するエネルギーや原材料価格の上昇が懸念されていたこと等を踏まえ、令和3(2021)年12月、政府は「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」を決定しました。中小企業等が賃上げを確保できるよう支援していくことに併せて、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を価格に適切に転嫁できるように取り組んでいます。
農林水産省では、同月に「食品製造業者・小売業者間における適正取引推進ガイドライン」を策定し、食品製造業者と小売業者との取引関係において、問題となり得る事例等を示しています。また、取引上の法令違反の未然防止、食品製造業者及び小売業者の経営努力が報われる健全な取引の推進を目指し、本ガイドラインの普及を行っています。
(食に関する課題の解決や新たなビジネスの創出に向けフードテックの取組を推進)
世界的に消費者の健康志向や環境志向等、食の価値観が多様化している中で、フードテック(*1)を活用した新たなビジネスの創出に関心が高まっています。このため、農林水産省は、令和2(2020)年10月に立ち上げた「フードテック官民協議会」に設置した作業部会での専門的な議論を通じ、食に関する課題の解決や、フードテックを活用した新たなビジネスの創出に向けた官民連携の取組を推進しています。また、多様な食の需要への対応や社会課題の解決を図るため、食品事業者等の関係者が実行するフードテック等を活用した新たな商品・サービスを生み出すビジネスモデルを実証する取組を支援しています。
1 生産から流通・加工、外食、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジネスモデルのことで、我が国における取組事例としては、大豆ミートや、健康・栄養に配慮した食品、人手不足に対応する調理ロボット、昆虫を活用した環境負荷の低減に資する飼料・肥料の生産等の分野で、スタートアップ企業等が事業展開、研究開発を実施
(コラム)宇宙における食料供給システムの開発を実施
近年、国際社会において宇宙開発利用の拡大に向けた取組が活発化しています。このような中、我が国においては、宇宙における国際競争力を強化していくための重要な要素の一つとして、月や火星での持続的な有人活動で活用が期待される、QOL(Quality of Life)重視型の持続可能な食料供給システムの開発に取り組んでいます。
農林水産省では、内閣府が創設した「宇宙開発利用加速化戦略プログラム」の一環として、令和3(2021)年度から「月面等における長期滞在を支える高度資源循環型食料供給システムの開発」戦略プロジェクトを開始しました。本プロジェクトでは、将来の月面基地での食料生産を想定した閉鎖空間におけるイネ、ダイズ、イモ類などの作物を対象とした環境制御による栽培技術と発酵等を利用した資源再生技術を組み合わせた高効率な食料供給システムの開発等を目指しています。
このような取組を通じて確立された食料生産技術は、砂漠のような過酷な環境における食料生産や世界の食料問題の解決に貢献することが期待されます。
イ 卸売市場を始めとする食品流通の合理化等
(食品流通の合理化を推進)
トラックドライバーを始めとする流通分野の人手不足が深刻化する中で、国民生活や経済活動に必要不可欠な物流の安定を確保するためには、サプライチェーン全体で食品流通の合理化に取り組む必要があります。特に、野菜や果物等の青果物の輸送は、荷物の手積み、手降ろしといった手荷役作業が多い、小ロット・多頻度での輸送が多いなどの事情から、運送業者から取扱いを敬遠される事例があります。
農林水産省は、令和3(2021)年6月に閣議決定された「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」を踏まえ、青果物流通の現状と今後の対応の方向性について関係者が議論・検討する検討会を開催し、流通段階や事業者ごとに規格が一様でないパレットやコード・情報の標準化等、青果物流通の合理化に向けた取組を進めています。
生鮮食料品等を取り扱う1卸売市場当たりの取扱金額は、令和2(2020)年度に707億円の目標に対し、前年度から23億円減少し、605億円となりました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための外出自粛や飲食店への営業自粛の要請、緊急事態宣言等による飲食店への時短営業の要請等により、飲食店を始めとする業務需要が大きく落ち込み、水産物を中心に取扱金額が影響を受けたためと考えられます。
卸売市場の活性化に向け、農林水産省は、卸売市場のハブ機能の強化、コールドチェーンの確保や、パレット等の標準化、デジタル化・データ連携による業務の効率化等を推進することにより、令和6(2024)年度までに1卸売市場当たりの取扱金額を、平成28(2016)年度比で24億円増加の719億円にすることを目標としています。
ウ 規格・認証の活用
(日本発の食品安全管理に関する認証規格(JFS規格)の取得件数は年々増加)
JFS(*1)規格は、一般財団法人食品安全(しょくひんあんぜん)マネジメント協会(きょうかい)が策定した、日本発の食品安全管理に関する認証規格です。JFS規格の特徴は、生食や発酵食等の食品の認証が可能で、我が国の食文化になじむことにあります。くわえて、JFS規格の各製造セクターでは、HACCP(*2)の考え方を取り入れた衛生管理を包含するJFS-A規格や、HACCPに基づく衛生管理を包含するJFS-B規格、国際取引にも通用する高水準のJFS-C規格(*3)が設けられており、経営規模等に応じて段階的に取り組みやすい仕組みとなっています。
JFS-A/B/C規格の国内取得件数は、平成28(2016)年の運用開始以降、年々増加してきており、令和4(2022)年3月末時点で1,951件(*4)となりました(図表1-4-2)。今後、JFS規格の更なる普及により、我が国の食品安全レベルの向上や食品の輸出力強化が期待されます。
1 Japan Food Safetyの略。用語の解説3(2)を参照
2 用語の解説3(2)を参照
3 平成30(2018)年10月にGFSI(世界食品安全イニシアティブ)に国際規格として承認された。GFSIについては用語の解説3(2)を参照
4 製造セクター以外の規格を含めた国内取得総件数は2,031件
(HACCPに沿った衛生管理の実施が義務化)
農林水産省は、HACCP導入について、手引書を使ったモデルの実証やオンライン学習教材の作成等への支援を行っています。令和2(2020)年度は、HACCPに沿った衛生管理を導入済み又は導入途中の食品製造事業者の割合は、前年度から20ポイント増加し、60%となりました。これを従業者規模別に見ると、導入済み又は導入途中の事業者は、従業員数が100人以上の事業者では98%であるのに対し、50人未満の事業者では53%となっており、中小規模の事業者でHACCP導入の割合を高めることが課題となっています。
令和3(2021)年6月からは、令和2(2020)年6月に施行された食品衛生法等の一部を改正する法律により、1年間の猶予期間を経てHACCPに沿った衛生管理が完全施行され、原則全ての食品等事業者(食品製造、調理、販売等)に対して、HACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されています。このため、農林水産省は、引き続き、中小規模の事業者におけるHACCP導入を促進するためWebサイトにおける情報提供を行っています。
(多様なJASを推進)
近年、輸出の拡大や市場ニーズの多様化が進んでいることから、農林水産省では、農林水産物・食品の品質だけでなく、事業者による農林物資の取扱方法、生産方法、試験方法等について認証する新たなJAS制度を推進しており、令和3(2021)年度には、精米、大豆ミート食品類のJAS等、8規格を制定しました(図表1-4-3)。これらのJASによって、事業者や産地の創意工夫により生み出された多様な価値・特色を戦略的に活用でき、我が国の食品・農林水産分野の競争力の強化につながることが期待されています。
農林水産省は、輸出促進に向け海外との取引を円滑に進めるための環境整備として、産官学の連携により、ISO規格等の国際規格の制定・活用を進めています。
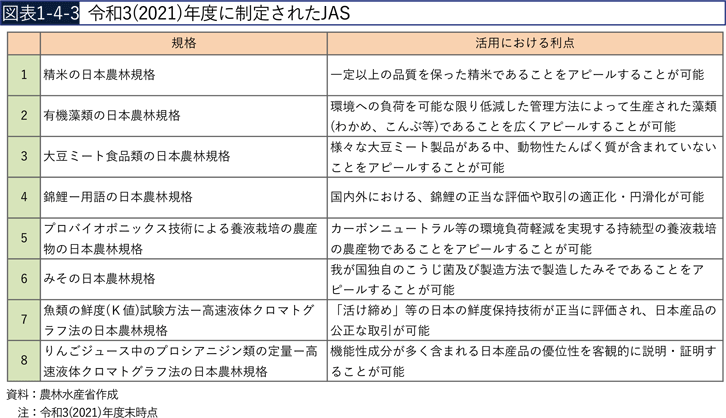
(2)食品産業における環境問題への対応
(食品産業界全体の取組により食品ロス発生を抑制)
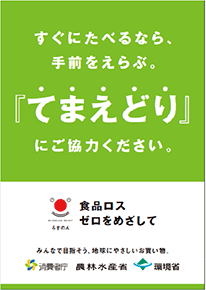
「てまえどり」を呼び掛けるポスター
食品ロスを削減するため、令和3(2021)年6月、農林水産省は一般社団法人日本(にほん)フランチャイズチェーン協会(きょうかい)、消費者庁、環境省と連携して、小売店舗が消費者に対して、商品棚の手前にある商品を選ぶ「てまえどり」を呼び掛ける取組を行いました。「てまえどり」を行うことで、販売期限が過ぎて廃棄されることによる食品ロスを削減する効果が期待されます。
(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が成立)
令和3(2021)年6月に成立した「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」では、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組を促進することとしています。令和4(2022)年4月以降、製造事業者等においては環境配慮型の製品設計に努めること、フォーク、スプーン等の使い捨てプラスチック製品の提供事業者においては使用の合理化のための取組を行うこと、排出事業者においては可能な限りプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制と再資源化を実施することなどが求められます。
このほか、飲料用PETボトルについては、令和2(2020)年度の回収率は前年度から4ポイント増加し97%となり、93%の目標を達成しました。農林水産省は、令和12(2030)年度までに100%とすることを目標としています。
ご意見・ご感想について
農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。
白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
送信フォームはこちら。
お問合せ先
大臣官房広報評価課情報分析室
代表:03-3502-8111(内線3260)
ダイヤルイン:03-3501-3883